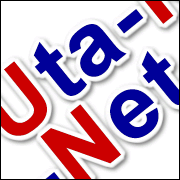天使のユリの話から『Debüt ‐α』シリーズに戻ります![]()
原作では叶わなかった卒業式。せめてこちらの世界では盛大(?)に![]()
![]() ユリの一世一代の決意より少し前の話です。詳しくは下記の二編で
ユリの一世一代の決意より少し前の話です。詳しくは下記の二編で![]()
今回の挿絵/緑(葉っぱ)縛り(意味なし)![]()
緑風が、旅立ちの季節を連れてくる──
聖ゼバスチアンの卒業式は、基本的に、誰でも参列が許されていた。
場所が礼拝堂ということもあり、毎年、卒業生や在校生の友人、知人が多数訪れる。卒業時の年齢が成人に達しているためか、どちらかといえば身内が列席する割合の方が低かった。
その日、イザークは、送辞という重大な役目を任されていた。いや、厳密に言えば、命じられた。通常、送辞は現時点での最上級生、つまり8年生がやるものだ。イザークはまだ7年生である。
答辞は、当然、ヴァイオリン科主席で寮長も務めたクラウスである。その本人からの半強制的指令であった。
どうやら、クラウスも答辞をやるのは不本意らしい。要するに、腹いせだ、とイザークは思っている。
クラウスとは、学内、学外の演奏会と、様々な場面で行動をともにしてきた。パートナーとしての相性は間違いなかったし、演奏自体も刺激になることが多く、そして何より楽しかった。
時々、いや頻繁に起こる(奔放と言う名の)暴走を止めるのには苦労したが。
恐らく相手がユリウスなら、彼もこんなことはしないに違いない。愛するが故か、或いは、(二人の練習風景に余り立ち会ったことはないが)実は彼女は意外と手厳しくて、クラウスも従わらずを得ないとか?
『クラウスってば、そこは走らないでって言ってるのに、もうっ!』
(鍵盤を叩くユリウス)
『おい、ピアノに当たるなよ。悪かった、もう一度やろう』
(機嫌を窺うように彼女の顔を覗き込むクラウス)
──いいなぁ……。
はっ!
我に返った。
というわけで、不承不承ながら、彼のために、イザークは送辞を引き受けることにした。
──ユリウスは来るだろうか。いや、来るに決まっている。何と言っても、クラウスの卒業式なんだから。
いい加減に諦めたらどうだ……? もう一人の自分が苦言を呈する。
それなのに、入口にユリウスの姿が見えた途端、胸の動悸が速まった。
ところが、ユリウスは一人ではなかった。おそらくレーゲン学院の友人だろう。同じ制服の男女が三人、彼女から少し遅れて入ってきた。
「やあ、ユリウス。三人とも学校の友達?」
「うん……。みんな行くって聞かなくて……」
ユリウスが少し困った表情をする。
「安心して、ユリウス。ここぞというときは、ちゃあんと二人っきりにしてあげるから」
最初に近寄ってきた女性が、ユリウスの肩をぽんと叩いた。
「ボクは別に、そんなこと……。あ、こちらは、リーナとハリーとアニカ」
イザークは名前を名乗り、軽く頭を下げる。
三人とも顔だけは知っていた。リーナは同級生、ハリーとアニカは一学年上らしい。
「だいたい、どうしてあなたたちまで来るわけぇ?」
リーナが、呆れた顔でアニカとハリーを交互に睨む。
「良いじゃないのぉ。私は、もちろんイイオトコの発掘に……あら、あそこに座っている彼、ナイスガイだわぁ」
持ち前の眼力を駆使して、早速、アニカは辺りを物色し始める。同じ制服なのに、彼女が着ると規律の意味が薄れて見えるのは気のせいか。
「ぼ、僕は、同じヴァイオリニストとして尊敬するクラウスの勇姿を、目に焼きつけておきたいと思ったんだ。彼は将来、絶対、素晴らしい演奏家になるに違いないからね」
ここにも一人、諦めの悪い男がいた。
「何よそれ? 偶像崇拝している暇があったら、一時間でも多く練習して、自分の腕を磨いた方が有意義じゃあないのかしら?」
リーナは何でも知っている。ちくちくちくちく……。
「いや……、だから、僕は、演奏家だけではない彼の人間性を目標に……」
「はぁ?」
捉えようによっては、アニカの方が率直で清々しいわ、とリーナは思った。
「ねえ、イザーク。クラウスから聞いたんだけど、送辞をやるんだって?」
ユリウスが訊く。
「あ、うん。参ったよ……。『俺が答辞なら、送辞はイザークだ!』って。無茶苦茶だろ?」
イザークは溜息をついた。
「ふふ、災難だったね。でも大丈夫。君なら、きっと上手くやれると思うよ」
ユリウスはにっこり微笑む。
「えっ? そ、そうかなぁ?」
「うん、楽しみにしているね。頑張って」
イザーク、急にやる気が漲る。
イザークは時間が許す限り、ユリウスの左隣で喋っていたが、在校生の本来の席は前列の方である。
名残り惜しそうにイザークが去った後、待ち構えていたかのように、ダーヴィトが、その特等席を陣取った。ちなみに、ユリウスの右隣はリーナ、アニカ、ハリーの順で、一番端に追いやられたハリーは大いに不服だった。
「ダーヴィト、来てたんだ」
「やあ、我が麗しの金髪の天使は元気そうで。安心したよ」
「え……? うん、この通り元気だよ。ダーヴィトはこの式のために、わざわざウィーンから?」
今日のダーヴィトは、来賓席に座っていても遜色ないほど、ダークスーツが決まっている。口には出さなかったけれど、とても似合っている、とユリウスは思った。
「今日は、僕のゼバス生活で授かった素晴らしい悪友の記念すべき日だからね」
「ダーヴィトったら。大袈裟だね」
ユリウスは思わず吹き出す。
「こんにちはぁ。素敵なスーツ。こちらの卒業生の方かしら?」
ユリウスを通り越してダーヴィトの目の前に、いきなりアニカが顔を出す。
「ア、アニカ……?」
目的のためならば、障害物(リーナとユリウス)などものともしない恋多き女の行動力は衰えを知らず、そして場所を選ばない。
「こんにちは。ユリウスの同級生かな?」
片や、どんな状況に置かれても、スマートに対処する円熟した男。
「あぁら、嫌ですわ、そんなに幼く見えまして? ほら、よくご覧になってこの豊満な……」
その豊満な持ち物を、彼女は両手で押し上げようとすると、
「アニカっ! 他校の厳粛な卒業式で何やってんの! 失礼しました」
蛇のようにくねくねと伸びた躰を、リーナが無理矢理引き摺り戻した。
「何よう、挨拶くらい良いじゃないのぉ」
「ほら、もう始まるわよ。卒業生が入ってきたわ。ハリー、ちゃんとアニカに縄付けといてよねっ」
「そんな、僕には荷が重すぎるよ……」
その時、二列になって、卒業生が入場してきた。
ユリウスは、真っ先に長身の亜麻色の髪を見つける。
クラウスの姿だけを──。
イザークの鯱張った送辞が終わった。
目立つミスもなく、まるで何処かの手本をそのままなぞったような堅苦しい挨拶は、時間もきっかり二分半。生徒のみならず先生たちまでも、終了後、肩をほぐすように首をぐりんぐりん回していた。
「続きまして、卒業生答辞、ヴァイオリン科、クラウス・フリードリヒ・ゾンマーシュミット」
最前列の右端から、名前を呼ばれた当人が立ち上がる。後ろ姿なのに、ユリウスは、どきん、となった。
「ふふ、やっぱりカッコいいわね、あなたの彼」
リーナが小声でユリウスに囁く。
「う、うん……」
ユリウスは、それ以上言葉が出なかった。
クラウスは壇上への階段を上がり、演台まで歩を進める。それから、スタンドマイクの位置を合わせて正面を向いた。
ユリウスは口もとで手のひらを合わせ、じっと彼の姿を見ている。いや、見惚れている。終いには鳥肌まで立ってきた。
──ボク……変だ。いつもなら、もっと近くで顔を見ても、全然平気でいられるのに……。
「本日は、私たち9年生一同のために、大変盛大な式典を挙行していただき、心より御礼申し上げます。皆様のご祝辞、そして、この三年間苦楽を共にしてきた可愛い後輩からの暖かい送辞の言葉は、一人一人の胸に深く刻み込まれました」
送辞にも引けを取らない格式張った内容、なのに何処か新鮮で気品さえ感じるスピーチに、礼拝堂内は水を打ったように静まり返った。微動だにしない目線。揺るぎない声量。威風堂々たる佇まい。このまま滞りなく、彼はやり遂げてくれるだろう。誰もがそう思っていた。
「長かった学校生活も今日で──」
刹那の間。
「いや、この辺にしておこう。窮屈で退屈な挨拶は、いい加減聞き飽きただろうからな。在校生及び、列席の紳士淑女諸君! この場を借りて、どうしても言っておきたいことがある。まず初めに」
突然の方向転換に、場内がどよめき始める。ユリウスとリーナも、困惑の表情で互いに顔を見合わせた。
「クラウス・ゾンマーシュミット! 何をしている? 脱線するにもほどがあるぞ。そういうことは式典後にやりたまえ!」
厳しい顔のヘルマン・ヴィルクリヒが立ち上がって声を上げる。
「うるせー! ヘルマン・ヴィルクリヒ。俺なんかに答辞を任せたのが運の尽きだ。最後はきっちり締めてやるから黙って聞いてろ!」
一呼吸の後、
「ユリウス!」
クラウス・ゾンマーシュミットのバリトンが高い天井に跳ね返る。
え?
今、誰か、ボクの名前を、
呼んだ……?
「ユリウス・レオンハルト・アーレンスマイヤ」
──ふ、フルネームで呼ばないでぇ……。
ユリウスが、おそるおそる顔を上げると、クラウスが自分を見ている。この鳶色の瞳に、ボクは捕まったんだ。
いつから……?
たぶん初めて逢ったときから……?
「立ってくれるか?」
優しい目。優しい声。なのに、逆らえないのは何故だろう……。
「は……はい」
おずおずと、ユリウスは立ち上がる。魔法をかけられた人形みたいに。周囲の目が一斉に彼女へ向いた。
ダーヴィトとリーナが心配そうな面差しで、彼女を見ている。
よりにもよって答辞の途中で……。予測不可能な彼の行動は、イザークを唖然とさせた。
か細い声につられるように背中を捻ると、ステンドグラスから射し込む光が、選ばれし者のように彼女だけを捉えている。
「ユリウスだ」
「また綺麗になったんじゃないか?」
上級生たちの会話が耳に届く。
その通りだった。当然だ、と思った。これまでも、幾度となく聞いてきた賞賛の声。
色白の肌と紅い唇。儚げに立ち竦む姿は、まるで森から迷い出てきた金色の髪の妖精だった。
「上手いことやったよなぁ、クラウスも」
「まったくだ。羨まし過ぎるぜ」
露骨な発言に、イザークは眉を顰める。
思い起こしてみれば、一緒に編入したときからそうだった。細い肩や柔らかな髪に無遠慮に触れてくる手、舐めるように浴びせられる視線。傍にいて何度、目撃したことか。
それを彼女は、たった一人で撥ね退けて、撥ね退けて……。
──もしもダーヴィトやクラウスよりも、真っ先に知っていたら、僕が盾になって護ってあげられたのに……。
直ぐに、溜息と苦笑い。
──まるで立場が替われば、自分が勝ち取れたみたいな言い草だ。
どうしてこうも短絡的なのだろう。
戀愛は、早い者勝ちじゃあない。嫌というほど、思い知らされたではないか。
伝説の窓にさえ、選ばれなかった自分を。
「さて諸君、聞いてくれ! そこに立っているのは、俺の女だ」
はい……??
その場にいた全員の目が点になる。
額に手を当て天を仰いでいるのは、ヘルマン・ヴィルクリヒだ。
「ここを卒業したら、俺はパリへ行くことが決まっている。残念ながら、彼女とは暫く離れ離れだ。何が言いたいのかというと、その間、絶対に、彼女に手を出すな。ということだ」
静かなる脅声を、高性能マイクが礼拝堂の隅々まで行き渡らせる。
な・に・を・い・い・だ・す・の
こ・う・し・ゅ・う・の・め・ん・ぜ・ん・で
ユリウスの躰が震えだす。いや、さっきからずっと震えている。此処から逃げ出したい。一刻も早く。
それなのに、金縛りにあったみたいに、頭の天辺から爪先まで硬直していた。
「いいか? 破ったやつは容赦しねえから、よぅく肝に銘じておけよ」
クラウスが列席者全体を睨めつけた。イザークの近くで、軽口を叩いていた上級生たちの表情が凍りつく。
「特に、そこの羊の皮を被ったOB!」
クラウスが、ターゲットを指さした。
ダーヴィトである。
やれやれと言うように、ダーヴィトは両手を上げて、ホールドアップのポーズを取った。
「それから、さっき送辞を読んだやつ!」
止める間もなく二の矢が撃たれる。
「え!?」
イザーク、たった今、感謝されたと思ったら。
「ついでに、そっちのレーゲンの優男!」
三の矢。
「……あなたよ、ハリー」
冷静なリーナの声に、顔が引き攣る優男。
「言いたいことはそれだけだ。出来ることなら、パリまで掻っ攫っていきたいのが本音だが、俺も彼女もまだ学業が本分の身。ヒジョーに辛いところだ。その胸中だけは察してほしい」
羞恥のあまり身動ぎもできずにいるユリウスの横で、リーナが笑いを嚙み殺している。
「リーナぁ……」
「ごめん、ユリウス。だって……」
気がつけば、列席者のあちらこちらから、押し殺した笑い声が漏れ聞こえてくる。
ダーヴィトだけは、両手を上げたまま澄ました表情だ。
「ダーヴィト、お願い……、もう手を下ろして……」
蚊の鳴くような声である。
「大変だね、お前も。まあ、ある意味、羨ましくもあるけどな」
ダーヴィトは下ろした腕を膝に置くと、ユリウスの顔を見て微笑んだ。
「それって……、どういう意味?」
「ん、大した意味じゃないよ」
上手くはぐらかされてしまったようだが、今のユリウスには深追いする気力もない。
壇上では、クラウスが姿勢を正し、正面を向いて、咳払いをする。
「卒業が俺たちの終着点ではない。寧ろ、これからが人生の本番だ。それぞれ進む道は違えども、予測できない荒波が、俺たちに押し寄せてくるだろう。忍耐との戦いになると言っても過言ではない。しかし、必ず、それ以上に得るものもあるはずだ。そのことを教えてくれたのは、この聖ゼバスチアンだ」
ざわめきが、引き潮のように消えていく。
「校長先生始め諸先生方、人間としても、男としても、そして音楽家としても未熟だった私たちを、ここまで育て上げて下さり、本当にありがとうございました。聖ゼバスチアンの卒業生であることは私たちの誇りだと、何処へ行っても自信を持って断言できます」
席から立ち上がったり、両手で頭を抱え込んだり、来賓に平謝りしたり、右往左往していた校長及び教職員が神妙な面持ちに変わり始める。
最後に、クラウスは、ピアノ科教師へ向き直った。
「それから、へルマン・ヴィルクリヒ。敬称なしで済まないが……」
「何を今更。お前に『先生』呼ばわりされる方が、背中がむず痒くなって困る」
マイク無しでも十分に通る声で、ヘルマン・ヴィルクリヒは言葉を返した。
「あんたには、公私ともに、迷惑をかけたし世話にもなった。それは、たぶん今後も続いていくだろう」
「ほう。随分と確信に満ちた物言いだ。過度な自信は、破滅への階段を真っ逆さまだぞ。例えば、今日みたいな独り善がりの言動とかな」
ヴィルクリヒが、ユリウスを一瞥する。
「う、うるせえっ、最後まで聞けって言っただろうが! とにかく……、いいか? 二度は言わねえぞ! お世話になりました!!」
クラウスは、深々と頭を下げる。
ユリウスも、知らず知らずヴィルクリヒを見つめていた。
本当に、先生には助けてもらった。一言では言い尽くせないほど、たくさん、たくさん……。
もしも先生がいなかったら……、こんなふうに、もう一つの母校のように、この場所へ足を踏み入れることは二度とできなかっただろう。
「以上! 卒業生代表、ヴァイオリン科、クラウス・フリードリヒ・ゾンマーシュミット」
聖ゼバスチアンにおける歴代の答辞では聞いたこともないほどの拍手の渦に包まれて、クラウスは壇上を後にした。
階段を下りる直前、クラウスがユリウスの顔を見た。一拍半。強くて熱くて優しい眼差し。まるで世界に二人だけしかいないみたいに時間が止まる。彼の瞳は、普段と変わらぬ悪戯っぽい色をしていた。
こんなに恥ずかしい目に遭わされたのに、腹が立たないのは何故だろう。
いつの間にか羞恥も消えた。感情という泉を飲み干した小鳥のように。
廊下に立たされたまま忘れ去られた子供のように、ユリウスは、ぼんやりと立ち尽くしていた。
閉会後、数多の野次馬どもを振り切って、ホフマンは花嫁を連れ去った──。
少なくとも、イザークの目にはそう映った。
歓声と悲鳴と溜息が一体化したように空気が揺れる。銀幕のなかで観た一瞬の連写。
祭りのあとに漂う一抹の虚しさを感じながら、イザークは考える。
自分なら、同じことは出来るだろうか? 伝統と格式をぶち壊す勇気があるだろうか。
イザークは苦笑する。
いつも想像で終わるだけ。それが答えだ。
それでも、いつか……、
そこまで決意させる相手に、近い将来、出会えるだろうか……?
『馬鹿ねえ。あなたには、そんなことは似合わないわ』
脳裏を掠める知らない顔の知らない声。でも、金髪でソプラノだった。
先ず、もっと視野を広げるところから始めないと……。
誰だって好き好んで、あんな荒唐無稽な行動は選ばない。そうせずにはいられなかった彼は、幸せなのか、不幸なのか。
──それでも、やっぱり羨ましいよ。僕は……。
![]()
![]()
![]()
彼と彼女は、ドナウまでの石畳を歩いている。
何処よりも通い慣れた道程。
彼が此処を発つまでに、あと何回、二人で歩くことができるだろう……。
「今日のこと、怒ってるか?」
彼にしては怖々とした声だった。
「……ううん。びっくりしたけどね」
「お前は自覚がないから、あれくらい釘を刺しておかないと駄目なんだ。ダーヴィトはともかく、あのハリーって野郎までやって来るとは思わなかったぜ。なんで揃いも揃って諦めの悪いやつばっかなんだよ、まったく……」
理由なんて、言われなくとも解っている。それだけ彼女が魅力的だからである。
そして、それほどの相手を掌中にして、悠然と構えていられるほど自分はまだ大人ではないということだ。
「それで、不安は取り除けた?」
「いいや。前よりも、もっとお前を連れて行きたくなっちまった」
「ふぅん……」
「あーあ、参るよなぁ……」
「ふふ……、大丈夫だよ。あの後、アニカがね……」
「は? アニカ?」
![]()
![]()
![]()
『感動したわ、ユリウス! 良いわ、この私が引き受けるから任せといて!』
アニカが胸に手を当て、宣言する。
『な……何を?』
アニカが発言すると、ユリウスは、つい後退りをしてしまう。
『今後、あなたの半径1メートル以内には、金輪際、男を近寄らせないってことをよ。良いわね? みんな』
『アニカ、それは、いくら何でもちょっと無理があるんじゃないの?』
眉を顰めるリーナ。
『そうだよ! そんなことをしたら、僕だって近づけないじゃないか!』
必死のハリー。
『まあぁ、いい度胸ねぇ、ハリー。クラウスに何本矢を突き立てられたら目が醒めるのかしら?』
ハリーの胸に矢を突き立てる真似をするアニカ。
『うっ……!』
蘇る悪夢。背中を流れる冷や汗。
![]()
![]()
![]()
「そりゃあ……、頼もしいな」
「ね?」
淋しさを帯びた笑みで、彼女は彼を見つめる。
「電話するよ。毎日は無理だけど」
小指を絡めて指きりげんまん。
「いいよ、電話代、高くなっちゃうもん」
「何だよ、俺の声、聴きたくないのかよ?」
「本物の声じゃなきゃ聴きたくない」
「お前、無茶言うなよ。それが出来ないから……」
「嘘だよ。ごめん……」
握り締める指の力が強まった。彼女は、ずっと川を見ている。
突然、彼が制服の第二ボタンを引きちぎった。
「な、何してるの? ブレザーが破けちゃうよ」
「良いんだよ。この制服とも今日でおさらばなんだから」
ボタンを握らせた小さな手を、大きな手が包み込む。
「これ、俺の心臓。お前に預ける」
「心臓……?」
「第二ボタンは、一番心臓に近いんだ」
彼は自分の心臓の位置まで、彼女の手を導いた。
「……ほんとだ」
「俺の代わりな」
「クラウスの?」
「捨てるなよ」
「捨てないってば」
「電話もする」
「……うん」
ふわり……とキスが落ちてきた。
新緑と、彼の匂い。
「愛しているよ……」
彼女は、広い背中をぎゅっと摑んで目を閉じた。
痛みを伴った温かさが、ゆっくりと、じんわりと、躰中へ染み渡る。
分かってるよ、って言いたかった。ボクもだよ、って返したかった。
だけど……、声を盗られた人魚みたいに、言葉は泡になって海に沈んだ。
不思議と、涙は出なかった。また少し大人になったのかもしれない。
もう、哀しい涙は流さない。透明な小瓶に詰めて、ポケットに仕舞っておこう。
いつの日か訪れる最高に嬉しい瞬間のために──。
![]() イメージソング
イメージソング
![]() いつも『Debüt ‐α』シリーズ(別名「時空を超える」シリーズ)を読んで下さり、誠にありがとうございます
いつも『Debüt ‐α』シリーズ(別名「時空を超える」シリーズ)を読んで下さり、誠にありがとうございます![]()
振り返ってみれば、時系列通りに書いていたのは61話『美しき碧きドナウ』くらいまでだったかも(アメブロではシリーズ内の話に番号が付かないので不確かですが)。
終いには、番外編、閑話、挿話、余話(果ては回想、小品まで)等の前置きも書き尽くし、端折りだす今日この頃![]()
さて、次回は久々に、ベルばら『薔薇の奏で』シリーズをupする予定です。何故かと言うと、『Debüt ‐α』シリーズの次作が『薔薇の奏で』シリーズ(アメブロ未投稿分)とリンクする話だからです。
うーん、自分で自分の首を絞めるとはこういうことか…![]()
頑張ります![]()