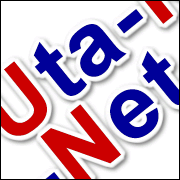昔、天使がおりました。
嵐の日、うっかり下界に飛ばされた天使は、美しい絃の音色に導かれ、古い都市の礼拝堂に降り立ちました。
窓から覗くと、一人の青年がヴァイオリンを弾いていました。
ひと目で、天使は恋に落ちました。
亜麻色の髪と鳶色の瞳の長身のヴァイオリニストに。
『断じて口を利いてはならない』
『背中の羽を一度たりとも羽搏かせてはならない』
誓いを破った瞬間、お前は消失する。
天界からも、当然──その男の前からも。
それが神々の王ゼウスと交わした条件でした。
クラウス・ゾンマーシュミットは、天使を飼っている。
名前はユリウス。
冬薔薇の季節に、ユリウスは、ピアノ科の五年生として編入してきた。
カトリック系音楽学校の聖ゼバスチアンは男子校だ。ユリウスは光に透けるほどの金髪と白い肌の持ち主で、男にしておくには勿体ない外見だったが、誰一人として疑うことはなかった。
そして、いつの間にか他の下級生たちと同じように、何処となく控えめにクラウスの周りにいた。気がつくと、彼の視界の端に映っている──そんな淡い存在だった。
或る日、それを覆す出来事が起こった。
放課後、クラウスは敷地内にある池でボートに寝転んでいた。初夏の木漏れ日が頬にちらつき、眩しげに瞬きすると、こちらを覗いているユリウスと目が合った。ユリウスは一瞬逃げようとしたが、
「乗るか?」
彼の軽い誘いに、一転、嬉しそうに微笑んだ。
「ボートは初めてか?」
ボートの上で物珍しげにキョロキョロする下級生を見て、クラウスは面白そうに笑う。ユリウスはこくりと頷いた。
ところが、水面に浮かんだ落ち葉に手を伸ばしたユリウスがバランスを崩し、その反動でボートが転覆し、二人して池に落ちてしまった。
クラウスは、ユリウスを抱えて何とか岸まで泳ぎ、ずぶ濡れになって這い上がるユリウスの背中を押し上げる。
その時、クラウスは、シャツ越しに薄っすら映る羽らしきものに気がついた。
「何だ? これ」
クラウスは思わず凝視したが、
悪事が見つかった子供のように怯え震える様子を見て、一旦黙る。それから、(運の良いことに)草地に放り投げてあった自分の上着を羽織らせて、彼は寄宿舎の部屋にユリウスを連れていった。
「先にシャワーを使え」
クラウスは着替え代わりに自分のシャツを渡して、ユリウスをバスルームに押し込んだ。それから目いっぱい暖炉に薪を焚べた。
クラウスがバスルームから出てくると、ユリウスは思いつめた顔でソファに座っていた。
「あのさ、俺の見間違いじゃあないよな?」
クラウスは、もう一度訊く。
ユリウスは姿勢を正し、ゆっくりと頷いた。金色の濡れ髪が一筋、額に垂れ落ちる。
やかんの音が鳴ったので、クラウスはソファから立ち上がり、ティーバッグの入ったカップにお湯を注ぐ。
彼はカップをユリウスに手渡して、隣に座った。
「見たい、って言ったら怒るか?」
ユリウスは、俯いたまま首を振った。そして、手に持ったカップをテーブルに置くと、背中を向けて、おずおずとシャツをずらす。
ある程度予測はついていたけれど、その肌は余りにも真っ白で、見てはいけないのではないかと、クラウスは目を逸らしかけた。
けれど、直ぐに、背中にあるそれに目が釘付けになる。
紛うことなき、羽だった。昔、絵本で見た天使か白い鳥に生えている──羽だった。
「お前、まさか……天使なのか?」
初めは冗談かと、例えば劇に使う装身具か何かを身に付けているのかと思った。
「それとも、鳥の化身……?」
それにしてはリアルである。今は小さく畳まれているけれど、いつ飛び立ってもおかしくないくらい羽自身が呼吸をしているようだった。
ユリウスは再び首を振った。
「じゃあ、やっぱり、天使?」
ユリウスは今度は頷く。先刻から、一言も口を利いていない。
そういえば池で会った時から、否、思い起こしてみれば、編入してきてから一度も声を聴いていない。何故、今まで気づかなかったのか。その不可思議な佇まいに、全生徒が目を眩まされていたのだろうか。
本当に喋れないのか。
もしや喋ってはいけない事情でもあるのだろうか? と彼は考えを巡らせる。
その唇から発する声はどんなだろう……。
「お前、家は?」
本当に天使なら──という素朴な疑問であった。
「毎日、何処から通ってるんだよ?」
ユリウスは儚げに微笑んで、顔の前で右手を振る。問題ない、と言うように。
「は? 問題ないことあるかよ」
クラウスは意味が解らなかった。まさか毎日、空から降りてくるわけではないだろう。誰かに見られたらどうするんだ。なんだか非現実的な話に、クラウスは頭が混乱してきた。
ユリウスは相変わらず淡く笑っているだけだ。埒が明かなかった。
「仕方ない、今日から此処に住むか」
突然の提案に、ユリウスは碧の瞳を丸くして驚いた。最初は困惑の表情で首を振ったり、考え込んだりしていたが、結局最後は押し切られる形になった。
そういえば、天使の性別は何だったか……。
そう思ってから、クラウスは即刻打ち消した。
「但し、これは二人だけの秘密だ。他の奴らにばれたら説明が面倒だからな」
人差し指を口に当てて、クラウスは囁く。
「いいか? 部屋に入る時は、細心の注意を払え」
森の中で廃墟を見つけた悪戯っ子みたいに、彼は楽しそうだった。なので、ユリウスもつられて笑ってしまった。
こうして、クラウスは天使を飼い始めた。
人間の容貌をした天使を。まるで捨て猫を拾うように。
ユリウス──光り輝く者。
地上に降りてきた天使。
背中の羽を見られても、彼の態度が変わらないことが、ユリウスには不思議だった。
気づかれた時、驚愕の余り羽を広げそうになったが、濡れていたのが幸いした。
自分が思うよりも、人間は柔軟な生き物なのだろうか。
いや……、彼だけが特別なのかもしれない。
それにしても、まさか彼の部屋に住めることになるなんて──。
ユリウスは、窓から空を見上げる。雲の上よりも、もっと上の懐かしい世界を。
取り敢えず、一歩前進? いや……半歩かも。
その根拠は……?
自信がない。喋れないのが致命的だった。
翼と声を捥がれた天使。まるで飛べない小鳥だ。
羽搏いたら躰が消失するなんて、天界にすら戻れないということだ。
簡単に諦めるな──ということだ。
溺愛なのか放任なのかスパルタなのか分からない。
──偏屈ジジイ。
空から睨まれた気がして、ユリウスは慌てて口を押さえた。
「天使って何を食うんだ?」
言っているそばから、買ってきたパンやサラダを、ユリウスは、ぱくぱく平らげた。そんなに腹が減っていたのか。クラウスはカップにお茶を注いだ。天使は、ごくごくと一気飲みした。体格と食欲が反比例している。
マジでペットを飼っているみたいだ、とクラウスは思った。
彼と寝起きを共にする、の意味を、ユリウスはよく理解していなかった。
寄宿舎の部屋のベッドは一台だけだ。それもシングルサイズ。
その晩、クラウスは、「俺はソファで寝る」と言った。
ユリウスは、とんでもない! と彼の腕を引っ張った。
喋れなくても、会話は成り立つ。身振り手振りの話し合い(口論)の末、
「ま、別に男同士だから同じベッドでもいいか。お前、ちっこいから収まるだろ」
という結論に達した。
しかし、ベッドに入って早々、クラウスは激しく後悔することになる。
決して男からは発生しないであろう甘い香りが、真横から漂ってきたからだ。蜜をたっぷり含んだ開きかけの蕾の匂い。
──どういう……ことだ?
当の本人は、すやすやと気持ち良さそうに、幸せそうに熟睡している。
その時、ユリウスが寝返りを打った。シャツの裾がはだけて、白い太腿が露わになる。それを朧な月が照らしている。
──お、男だ。こいつは男だ。天使だけど男だ。男の天使だ。男男男男男……。
彼は、自分で自分に呪文をかけた。一晩中。
そして、絶対に明日パジャマを買ってこよう、と決意した。
男だろうが女だろうが、美しいものに惹かれることの何が悪い。
それが彼の恋愛理念だ。
ちょっとした悪戯心で勝ち取った演奏会のパートナーに、彼は瞬く間に虜になった。
美しい金色の髪の天使。
けれども、その魅力的な碧の瞳が見つめているのは、常に別の男だった。
いつ、そうなったのか。
何故、そいつなのか。
尋ねたくても、天使は口を噤んでいる。
「ユリウス」
名前を呼ばれ、振り向いた次の瞬間、突き飛ばした。
相手の顔が想像以上に近づいてきたからだ。天使は意外と反射神経が良い。
しかし、体重の差は歴然で、その反動でピアノの椅子ごと床に倒れた。
「ユリウスっ! 大丈夫か……」
それでも、アンバランスな体勢で、近づいてくる上級生を突き離す。天使は平衡感覚にも優れていた。
射殺すような瞳が、男の動きを静止させる。
「分かったよ。悪かった、もう近づかないから」
上級生は躰を遠ざけて、長いリーチだけ伸ばしてくる。ユリウスは動かない。
「神に、誓うよ」
男は断言した。
その言葉を聞いて、ユリウスは漸く片手を相手に預ける。
ダーヴィト・ラッセンは、ゆっくりと天使を立ち上がらせた。
「そんなに激しく拒絶しなくても……。傷つくなぁ」
ピアノの椅子を起こしながら、ダーヴィトはぼやく。
ユリウスは楽譜を鷲摑みにして、レッスン室のドアを開けた。すると、目の前にクラウスが立っていたのでユリウスは驚く。驚いて声を発しそうになった。漏れたのは息を吸い込む音だけだった。
クラウス以外の人間に興味を持たれるなんて思ってもみなかった。
肝心のクラウスは、四六時中一緒にいるのに、同居人からちっとも進展しない。
──そりゃあそうか。
此処は男子校で、ユリウスのことを男だと、彼は信じて疑わないのだから。彼の傍にいるために、男子校だと承知の上で潜り込んだのは自分である。
それなのに、彼が悪いわけじゃないのに、なんだか腹が立ってきて、ユリウスは恨みがましい目でクラウスを見た。
──もう少しで、ファーストキスを奪われるとこだったんだから。
「何だよ? 何かあったのか?」
クラウスは、レッスン室の中で立ち尽くしている男を睨んだ。
「お前、何か余計なことしたんじゃないだろうな?」
「余計なことって? 例えば?」
珍しく、ダーヴィトは不機嫌だった。
よりによって、一番厄介なやつにユリウスとの同居がばれた。二人で寄宿舎に入るところを、うっかり見つかってしまったのだ。
ヴァイオリン科の上級生、ダーヴィト・ラッセン。
「どういうことだよ?」
まさか天使で家なき子だと正直に言えるわけもなく、クラウスが適当に誤魔化して事情を説明すると、
「どうして僕の可愛い小鳥と、お前が一緒に住んでいるんだ。え?」
歳の割には成熟している冷静沈着な男の仮面が剥がれた。
つまりダーヴィトは、編入してきた当初からユリウスに大層御執心だったようだ。
親友で悪友。誰よりも信頼の置ける男。だが、どうやらユリウス絡みのことに限っては、油断しない方がいいらしい。
「今度の学内演奏会で、僕の伴奏をしてくれないか?」
それが秘密を守る条件だった。
ユリウスが頷いたので、クラウスも渋々受け入れた。
ところで、この時点で、ダーヴィトは、ユリウスが女であると感づいていた。
唇擦れ擦れまで近づいた──ほんの数秒の間に。
──男の放つ香気じゃない。
畏るべし男、ダーヴィト・ラッセン。
イザーク・ヴァイスハイトは少しだけ拗ねていた。
彼と同時期に編入してきた金髪の天使に、誰もが色めき立っているからだ。一年が過ぎ、二度目の降誕祭を迎えても、状況は変わらなかった。
同じ学年のピアノ科なのにえらい違いだ。やっぱり人間、技量より顔なのか。
──誰がピアノ男子はモテるって?
そう思う自分が卑屈で嫌だった。
だいたい、男子校でモテたって、別に嬉しくも何ともない。
そういえば一度、学内演奏会で声を掛けられたことがあった。黒髪の美少女に。
『あの……、もし差し支えなかったら、私にピアノを教えて頂けませんか?』
はにかむように囁く仕草が可愛らしかった。
『すみません、校則でバイトは禁止されているんです』
『あ、そうなんですか……』
彼女は残念そうに立ち去って、それっきりになってしまった。
短いモテ期だった……。
確かに、ユリウスは綺麗だ。全身に光を纏っているかの如く。
初めて(なんだかよく分からないけれど曰くつきの)塔の窓から見た時は、女の子かと思って息を呑んだ。
だのに、ユリウスは滅多に笑わない。
皆の前で笑っているのを見たことがない。
否、一人を除いては。
聖ゼバスチアンのトップ・ヴァイオリニスト、クラウス・ゾンマーシュミット。
それが、イザークには面白くなかった。
それが、ダーヴィトには面白くなかった。
ヴァイオリンを弾いている時、ユリウスは、
同じ空間の片隅に佇んで、目を閉じてストラドの音色に聴き入っている。ある時は礼拝堂で、ある時はレッスン室で、僅かに開いたドアから金色の髪が覗いている。今日は礼拝堂だった。
──猫かよ。
クラウスは笑いを嚙み殺しながら最後まで弾き切って、
演奏を終えると、楽器を下ろし天使に近づき、そんなところにいると風邪引くぞ、と言った。
「そういえば、まだお前と合わせたことはなかったな」
年がら年中一緒にいるのに。
ユリウスは、待ってました、という顔になる。
「そうか、何か好きな曲はあるか?」
ユリウスは直ぐに、大事そうに抱えていた楽譜を差し出した。
「どれどれ、あぁ、《ロマンス》か。お前らしいな」
天使は、ぴょんと躰を弾ませる。
「これ、いつも持ち歩いていたのか?」
うんうん、とユリウスは頷く。
「ここは寒いから、レッスン室に行こう」
天使がクラウスの腕を引っ張った。早く早く、と急かすように。
言葉なんて無くとも、人は生きていけるのかもしれない。
「いつか……」
自分を見上げるユリウスの頬へ手のひらを滑らせて、青年は言いかける。
天使は首を傾げて続きを待った。
いつか──お前は天上へ帰ってしまうのか。今は畳まれた羽を広げて、俺の前から飛び立っていってしまうのか……。
それを口にするのが怖かった。
雪が溶けて川になって、もうすぐ春だった。
そして、それから先は、急展開だった。
クラウスは、ドナウで釣りをしていた。すると、橋の向こうから、ユリウスが走ってくるのが見えた。ばたばたばたと、明らかに足が遅い。
どうやら天使は、走るのは苦手らしい。
その時クラウスの網膜に、まるで予知夢のように、階段を転げ落ちるユリウスの映像が映った。
クラウスは、先手を打って急いで階段を駆け上がった。彼の躰ぎりぎりで、ユリウスが立ち止まる。
「飼い主を見つけた猫みたいだな」
飼い主を見つけた天使である。
ユリウスはにこにこ笑って、川岸に放り投げてある釣竿を指差した。
「何だ、釣竿、見たことないのか? あれで魚を釣るんだよ。お前もやってみるか?」
天使は大きく頷いた。
「気をつけて下りろよ」
その舌の根も乾かぬ内に、段差を踏み外したユリウスが、ふっと、クラウスの視界から消えた。予知夢的中。
「ユリウスっ!」
寸でのところで、クラウスは背後から天使を抱きかかえた。軽い。空気みたいに軽かった。
「馬鹿やろう! ちゃんと足元を見……」
──あれ?
右手の内側が妙に柔らかい。
見ると、手のひらにユリウスの胸がすっぽりと収まっている。仄かな隆起。
──何だ、胸か。
「は?」
刹那の静寂。
ばしん! とユリウスがその手を撥ね除ける。
「わあっ! ユリウス!」
支えを失った彼女の躰は、ずるずると地面まで落ちていく。けれど、残り三段だったので臀部を打っただけで済んだ。
クラウスは、地面に飛び下りる。
「だ、大丈夫か? 怪我は?」
ユリウスはこちらを見なかった。下を向いて、じっとして、胸を覆い隠していた。クラウスが横から覗き込むと、彼女の顔は真っ赤だった。
「えっと、お前さ……、あの……」
クラウスは核心を突く。
「女?」
いや、だから。
そもそも、天使の本来の性別は……。
ユリウスは、その場で石のように固まっていた。
クラウスは、じっと手を見て、脳内でさっきの感触を再生していた(すんな)。
ユリウスは、女だった。
天使だけど、女だった。
これで、全ての納得がいった。華奢な肩、細いけれど丸みを帯びた稜線、鼻孔を擽る甘い匂い、その他のあらゆる疑問の数々……。
良かった。取り敢えず。何が良かったのか、よく分からないけれど。
知らず知らず、クラウスは、頬が緩んでいくのを知覚した。
根本的な問題は、未だ解決していない気がするけれど。
堪えても堪えても、頬が緩んでいくのをクラウスは自覚した。
なんて単純な男だ。御伽噺の結末みたいに、何とかなると思っているのか。
クラウス・ゾンマーシュミットは、天使を飼っている。
金髪で、碧の瞳で、背中に羽が生えている──人間の女の貌をした天使を。
顔から火が出るほど恥ずかしかった。消えてしまいたかった。
いや、消えたら困る。
遂に、女だとばれてしまった。
いや、かえって、結果オーライ?
抱き竦められた時、どの神々よりも屈強な筋肉に眩暈がしそうになった。
霧が晴れたように、クラウスはすっきりした表情だった。とユリウスは感じた。
もしかしたら。
微かな期待。
だけど。
でも。
こんなにも、自分は悲観的だっただろうか。天使の癖に。
だけど。
でも……。
その夜。
クラウスは、ユリウスをソファに座らせた。いつになく、真剣な顔だった。
「例え天使だろうと、女だと知ってしまったら、もう一緒のベッドに寝るわけにはいかない」
ユリウスの表情が強張る。
「ちゃんと、けじめをつけないとな」
けじめ? 出ていけ……ということだろうか。
「回りくどいのは嫌いだから、単刀直入に言うぞ」
出ていけ、と?
「ユリウス……、俺が、好きか?」
ユリウスは、息を吸い込む。
「俺は、お前が好きだ」
と、クラウスが告った。
天使の目に、みるみる涙が溜まっていく。
「もう一度訊く。お前は、俺が好きか?」
彼を見つめたまま、ユリウスは動かない。膝にのせた手に、涙の雫が二粒落ちた。
それから、
もう消えてもいい──と天使はクラウスに抱きついた。
「好き……クラウス。あなたに逢いたくて、ボクは空から降りてきたの」
澄んだソプラノが言葉になる。
その声は──、毎夜幾度となく思い描いたその声は、男の堅牢な理性を溶かすマグマと化した。
鳶色の瞳と、涙に濡れた碧の瞳が混じり合い、
クラウスは、ユリウスにキスをした。彼は、彼女の柔らかな唇を何度も吸った。ユリウスは、クラウスのシャツにしがみつき、必死で応えた。
初めてのキスは、甘い涙の味がして、躰中の血管が熱くなって、頭の天辺から爪先まで生まれ変わっていくようだった。
彼の愛で、彼女は生まれ変わった。
青年は、天使を抱き上げ、ベッドの上にゆっくり下ろした。
そうして。
シーツの海を二人で泳ぎ、明けない夜を駆け抜けて──、
目を覚ますと、ユリウスは、生まれたままの姿で恋人の腕の中にいた。
「おはよう」
長い指が金色の髪を愛撫する。
「おはよう……」
躰があって良かった……、とユリウスは言った。
![]() イメージソング/『早春物語』原田知世
イメージソング/『早春物語』原田知世![]()