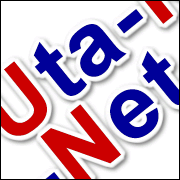ちょっと曲がり角。upするのに勇気がいった。後戻り出来ないし。
平穏な幸せのなかに訪れる二人にとって初めての分岐点。
今年の夏は駆け足で通り過ぎた。彼女の体感ではそう感じた。
ユリウス・レオンハルト・アーレンスマイヤは、7年生になった。
クラウスと初めて逢ってから二年。
彼女の人生に於いて、(まだ17年ほどしか生きていないが)最も衝撃的かつ刺激的で、濃密で楽しくて素敵で、そう……幸せな二年間だった。
『さっさと立てよ! 寮で火を焚いてもらってやる。俺の上等の毛布と……』
不意に、二年前の摑み合いの喧嘩の場面が彼女の脳裏に連写された。
『触るな!! ボクはいいんだ、触るな!』
最悪な初対面──。
どうして今頃そんなことを思い出したのだろう、とユリウスは苦笑する。
──別に良い思い出ってわけじゃないのにな……。
クラウスは、来年ゼバスを卒業する。
彼が卒業後どうするのか、ユリウスはまだ聞かされていなかった。
彼も決めかねているようだった。
決まったら真っ先に教えると、言ってくれてはいるけれど……。
でも本当は、聞くのが怖い、と思っている。訊きたいけど聞きたくない。知りたいのに知りたくない。
毎日、毎時、毎秒ごとに、振り子のように心が細かく揺れ動く。
クラウス・フリードリヒ・ゾンマーシュミットは、オルフェウスの窓から空を見ていた。
久し振りに見る眺めだった。
あの日も、今にも崩れ落ちそうな窓の縁に腰かけていたら、下を歩いているユリウスに出逢った。
今思えば──それが、運命の分かれ道、だったのだ。
当時は彼女の事情も知らず、鼻っ柱の強い、くそ生意気な下級生だと思っていた。今とは真逆もいいところだ。思い出しただけで笑いが込み上げてくる。
足音がしたので振り返ると、イザーク・ゴッドヒルフ・ヴァイスハイトが階段を上ってきた。
「クラウス、こんなところにいたんですか?」
「何だ、イザーク。また出会いを求めて来たのか?」
「違いますよ、茶化さないで下さい。あなたこそ、もしも誰かが通ったらどうするんですか?」
「ばーか、下なんか見てねえよ。空を見ていたんだ」
「そんなこと言って。知りませんよ、僕は」
イザークは、窓に近寄ろうとしなかった。
万が一にでも、クラウスと同じ女性を見る羽目にだけはなりたくないと思ったからだ。
あんな思いをするのは、二度と御免だった。
「ここで逢った時の、あいつのこと、思い出してた」
「ユリウスの?」
イザークの心の内を知ってか知らずか、クラウスは懐かしそうに目を細めた。
「ああ。つくづく小生意気なやつだった、と思ってさ。お前もよく振り回されていたよなぁ?」
「え? まあ、あの時は僕も……」
イザークはそこで言葉を切った。
「何です? 今頃。そうだ、ヴィルクリヒ先生が捜していましたよ」
「おっ、そうか。ダンケ」
「もう決めたんですか? ……例の話」
「うん……だいたいな。たぶんヴィルクリヒの話もそのことだろう」
「彼女には……、ユリウスには、もう話したんですか?」
クラウスが自分で決めたことに、横から口を出す筋合いは誰にもない。
けれど、ユリウスのことを考えると、つい要らぬ心配をしてしまうイザークだった。
「ん……今日、言うよ」
そう言い残し、階段を駆け下りていく後ろ姿をイザークは黙って見ていた。
決意を固めた男の背中を──。
その日、待ち合わせ場所に着いたのは、珍しくユリウスの方が先だった。
澄み切った爽やかな初秋の空。けれど、空気はひんやりと冷たかった。
今年の初雪は早いかもしれない……。
今年に限って何もかも早く感じるのは何故だろう?
理由は、たぶん知っている。知っていて、気づかない振りをしているだけだ。
ユリウスは川辺に膝を抱えて座り、ぼんやりと水の流れを眺めていた。
手が冷たかったので、セーターの袖を目いっぱい伸ばして指先まで覆う。
背中の半分まで伸びた髪が、時折り吹く川風に舞い上げられる。
「寒っ……」
背後から階段を下りる音。ユリウスは振り返った。
「よっ」
クラウスが、片手を上げて速足で近づいてくる。
座ったまま見上げたからか、いつもより大きく見えた。
「悪い、遅くなった」
「ううん。いつもボクの方が待たせてるし、たまにはね……」
「おっ、なんだか今日はえらく寛大だな」
「ボクがいつも短気みたいな言い方だね」
「あれ? 違ったか?」
どうしてこの表情を見ると、頭に血が上ってくるのだろう。
「もぉう! 逢った早々、怒らせたいの?」
「はは……、そんなつもりはないよ。おい、こんな所に座ってて寒くないか?」
クラウスは、ユリウスの隣に躰を密着させて座り込んだ。
「ちょっとぉ、くっつき過ぎだってば。狭いっ」
ユリウスの心拍数が跳ね上がる。
「狭いって、俺たちしかいないだろうが。暖かくてちょうどいいだろ?」
「そうだけど、でも……っ」
クラウスは寒々しい肩を抱き寄せると、体温を与えるように口づけた。
「ん……っは……」
「お前、耳まで冷たいぞ」
長い指が金の髪を掻き上げた。
「ちょ……やっ……」
「あっためてやる」
耳朶に落ちた唇が頬へ滑る。親猫が仔猫を舐めるように。
目が眩むような口づけが、少女の頬をみるみる赤く火照らせる。
「んん……、ク…ラ……」
「まだ……だ」
息をも吐かせぬ甘い攻撃に、少女の手が胸板を押し戻そうとするが、彼は抵抗を許さなかった。
強い抱擁。
いつもより激しい急くようなキス。ユリウスはついていくのがやっとだった。
そして、漸く、唇が離されると、
「も……息、できな…い」
さっきまで冷えていた彼女の躰は、湯たんぽみたいにぽかぽかしていた。
「悪い……。お前の後ろ姿にそそられて──」
クラウスは、ユリウスの鼻先擦れ擦れで息を吐く。
「なんだか無性に、むしゃぶりつきたくなったンだ」
「な……何言ってるの?」
「やっぱ17にもなると違うな。お前にも、少しは女の色気が出てきたのかな?」
冗談めかした声が言う。
「また……そうやって揶揄う。ついこの間まで、子供だって言ってた癖にぃ」
「はは、そうだったな」
「クラウス、今日はなんか変だよ」
「……そうか?」
「ね、何か言うことあるんじゃない?」
「──うん」
意を決したように、クラウスがユリウスの横に座り直した。
「あのな……」
下を向いたまま、ユリウスの心臓が、どくん、と波立つ。
「パリの、コンセルヴァトワールって知ってるよな?」
「コンセル……ヴァトワール? あぁ、うん。勿論。有名な音楽院じゃない」
「俺、そこに行くことに決めた」
「──え!?」
彼女は顔を上げてクラウスを見た。
「去年のオペラハウスの演奏会の後、ヴィルクリヒ宛てに推薦状が届いたらしい。それで、試験を受けてみようと思う」
「そう、なんだ。あの時の演奏、素晴らしかったもの。クラウスなら推薦が来るのは当然だよ。良かったね」
「喜ぶのは受かってからだけどな」
「大丈夫。絶対に受かるよ。クラウスなら」
寒さで口が回らないみたいに、言葉がぎこちなく刻まれる。
クラウスは、ユリウスを真っ直ぐ見つめた。
ユリウスは咄嗟に目を逸らす。本心を──動揺を見透かされそうで怖かった。
言葉が後に続かない。互いにそう思っていた。
少女の肩を抱く青年の手の力だけが、知らず知らず強くなる。
「クラウス、……痛い」
「あっ! 悪い。つい……」
ユリウスは、くすっと笑い、彼の肩に凭れかかった。
「パリ……、フランスか。遠いね」
「まぁ、そうだな」
「なかなか、逢えなくなっちゃう……ね」
じわり、と目頭が熱くなる。
「あぁ……。あぁッ! こんなお前を残していくの心配だっ!」
クラウスは唐突に叫ぶと、片手で髪を掻き毟った。
「え? なんで? ボクは大丈夫……」
「お前が大丈夫でも、周りが放っとかないんだよ!」
次に、彼は両手で頭を抱え込んだ。
「そんなこと言われたって……」
「あぁ、こんな時ダーヴィトがいてくれたら、まだ少しは──いや、駄目だ駄目だ! あいつだって、あわよくばお前を口説こうとするに決まってる!」
そして、半ば半狂乱。
「く、クラウス!?」
「かと言って、イザークじゃ頼りねえしなぁ……」
人畜無害は、頼りないと同義である。(イザークよ、今怒れ!)
「もおっ! 勝手に有りもしない想像しないでっ!」
高い声でユリウスが叫ぶ。
さっきまで泣きそうだったのに、何処かへ飛んでいってしまった。
初雪は時を置かずに舞い降りて──
古い街は、建物も樹々も石橋も、そこかしこで白い帽子を被っている。
放課後、ユリウスはゼバスに向かうため、急ぎ足で歩いていた。
約束の時間に遅れそうになり、彼女は少し焦っていた。
そのため、シュタイナーネ橋の真ん中で、凍った場所に気づかず、思い切り片足を突っ込んだ。
「あっ!」
躰がつんのめりそうになった時、
「危ないっ!」
間一髪で、ユリウスは誰かに抱き留められた。
「ご……ごめんなさい」
恐る恐る顔を上げたユリウスは、懐かしい顔を見て驚いた。
「ダーヴィト!?」
「相変わらず危なっかしいなあ、ユリウス」
変わらない穏やかな笑顔で、ダーヴィト・ラッセンがユリウスを見下ろしている。
「帰っていたの? いつ?」
「ついさっき駅に着いたところさ。まさか戻ってきて早々、天使を腕に抱くとは思わなかったけどね。役得だ」
「ご、ごめん……。ありがと」
ユリウスは顔を赤らめて下を向き、ぱたぱたとコートの裾を整えた。
「ゼバスに行くんだろ?」
「えっ? どうして知っているの?」
「クラウスに聞いた。学内演奏会で、またデュエットするんだって?」
「うん、今年で最後だからって誘われたの。クラウスも色々準備で忙しいのに……あ、準備っていうのはね」
「それも、聞いたよ」
「あ……そうなんだ」
不意に胸が苦しくなる。ユリウスは、唇をきつく嚙んだ。
──もうダーヴィトの前では泣かないって、決めたんだから……。
「ユリウス、大丈夫か?」
心配そうに見下ろしてくる温かい眼差しが、ユリウスの心を弱くする。
──そんな目で見ないで……。
「だ、大丈夫だよ。子供じゃないんだから」
自分の中で、しっかりと噛み締めて消化したつもりだった。
「あっ! ボク、早く行かなきゃ。今日も練習なの。クラウスを待たせちゃう」
「一緒に行こう。僕も顔を見せるつもりだったんだ」
走りだそうとしたユリウスの腕を、ダーヴィトが摑んだ。
「そうなの?」
「慌てないでゆっくり行こう。また転んで怪我でもしたら、僕が怒られるからね」
「もう、ダーヴィトまで」
ユリウスは唇を尖らせる。
「あのね、もし転んだとしても、自分で起き上がれるし、怪我だって、ちょっと膝を擦り剝くくらいで済むんだから。君もクラウスも心配し過ぎなんだってば」
「本当に言葉通りなら、僕だって心配はしないけどね」
ダーヴィトは眉尻を下げて彼女を見つめる。
「どういう意味?」
「いや……。ところで、曲は何にしたんだい?」
「『ロマンス』だよ」
「おお、いつかレッスン室で弾いていた曲だね」
ユリウスが顔を上げて、ダーヴィトを見る。
「よく憶えてるね」
「勿論。素敵なピアノだったからね」
「メインはヴァイオリンだよ。ボクはただの伴奏」
「伴奏だって大切だよ。デュエットなんだからね」
「それは解ってるけど……」
歩きながら話しているうちに、古い塔が近づいてきた。
その塔の窓が見えてくると、ユリウスの胸はまた締めつけられる。
別に、窓のせいで離れ離れになるわけじゃないのに……。
朽ちかけた御伽話のような伝説を、彼女は思い返していた。
本当は──離れたくない。行かないで、って叫びたい。
だけど口に出してしまったら、クラウスが困るのが解っているから、心の底に蓋をして鍵を掛けた。
それをまた頑丈な箱に入れて、極太の鎖をぐるぐる巻いて、南京錠を幾つも付けて海の底に放り込んだ。
それなのに……、何度沈めても海面に浮いてくる。
どんなに鍵を増やしても、どんなに重りを重くしても……。
学内演奏会当日も雪だった。
降誕祭に降る雪なんて珍しくない。
それでも、聖ゼバスチアンの礼拝堂には多くの観客が訪れていた。音楽学校の生徒でも優れた才能の持ち主にはファンがつく。ここ数年の筆頭はクラウス、次はイザークだろう。特に今回は、今年で見納めのクラウス目当ての観客が大半を占めているようだ。
控室で、クラウスがヴァイオリンをケースから取り出していると、ダーヴィトが入ってきた。
「何だ、お前、また来たのか」
「練習だけ見て帰るわけないだろう。何と言っても、お前たち二人のラストステージだからな」
「おい、今生の別れみたいな言い方すんな」
「成る程。ゼバスでのラストステージ、か?」
そこへ、楽譜を抱えたユリウスが走り寄ってくる。
「ダーヴィト、来てくれたんだ」
「勿論さ。ゼバスにいる君を見られるのも今回が最後かもしれないしね」
「どうかなぁ? さっきイザークに、来年は連弾をやらないかって誘われたんだけど、でも技術の差がね」
ユリウスは困ったように小首を傾げる。
「おいおい、あいつ、意外と抜け目がないな」
ダーヴィトが吹き出した。
「あンの野郎ぅ、後で絞めてやる!」
クラウスは弓を真っ二つに折りかける。
「はは……、しょうがないだろう。お前は来年はいないんだからさ」
瞬間、ユリウスの顔色が変わった。
「おい!」
クラウスが声を荒げ、ダーヴィトを睨みつけた。
「ちょ、ちょっと! 本番前に喧嘩なんてしないでよ」
ユリウスは慌ててクラウスの袖を引っ張る。
「悪かった。つい口が滑った」
ダーヴィトが小声で詫びる。
「いいの。気にしないで、ダーヴィト」
「行こうユリウス。出番だ」
クラウスはヴァイオリンを摑んでドアに向かった。
「あ、うん。ダーヴィト、また後でね」
「ああ、頑張れよ」
ユリウスは小走りでクラウスの後を追う。
「ユリウス、大丈夫か?」
舞台袖で、クラウスが恋人の手をぎゅっと握り締めた。
「うん」
ユリウスは、ぎこちなく微笑む。
「良い演奏にしようね、クラウス」
「おう! 任せとけ」
クラウスは、彼女の頭をくしゃくしゃっと掻き回した。
「ちょっとやめて! 次が出番なのに」
ユリウスが髪を押さえる。
「何だよぅ、好きなんだろ? こうされるのが。いつも洗いっぱなしなんだから変わんねーって」
「あのね、最近はちゃんと綺麗に整えてるんだから。見て分かんない?」
「そうか? 相変わらずあっちこっちぴんぴん跳ねてるようにしか見えないけどな」
「もぉうっ! 本番前に怒らせたいの?」
「はは、ごめんごめん」
彼女の顔が和らいだので、クラウスは密かに胸を撫で下ろした。
前奏者への拍手が聞こえ──二人の出番が来た。
ベートーヴェン『ロマンス』第2番──
ゼバスのレッスン室に二人でこっそり忍び込んで弾いた曲。
あの時は、ぶっつけだったけど、今回はたくさん練習した。時間の許す限り、レッスン室でも、ボクの家でも。
そして、曲を弾き終わるとキスをした。
一曲終わる毎に、時には小節の途中でも、どちらともなく引き寄せ合い、口づけを繰り返した。
「おい……、練習にならねって」
耳元で戯けたように彼が囁く。
「ボクのせいなの?」
唇を尖らせると、ちゅっと彼がキスをする。
そうして、二人で笑い合う。
どれだけ練習しただろう。
どれほどキスを交わしただろう……。
彼女の鍵盤を叩く指は、すべてを覚えていた。
彼の弦の強弱も、緩急も、呼吸の間さえも……。
彼の弓を奏でる手も、余すところ無く記憶した。
彼女の旋律が、何処で跳ねて何処で溜め、どの位置で震えるのか……。
演奏が終わり、幕が下りる。
拍手の音が遠くに聞こえる。
鍵盤に涙が落ちた。一粒、また一粒……。
慌てて袖で拭いた。けれど、後から後から絶え間なく零れてくる。
ピアノから立ち上がるどころではなかったし、顔すら上げられなかった。
その時、クラウスがユリウスの腕を摑んだ。
そのまま、レッスン室まで連れて行かれた。
ドアを閉めた途端しゃくりあげる恋人を、クラウスは抱き締める。
「泣くなって」
「泣いて……ないもん」
「はあ? じゃあ、その顔は何だ?」
涙でぐしゃぐしゃのユリウスの顔を、クラウスが覗き込む。
「あ……汗……」
「汗ぇ? 何だそりゃ? 子供だってもう少しましなこと言うぞ」
「……」
「あれ? 子供って言われて怒らないのか? 禁句じゃなかったっけ?」
「もぉう~ッ!」
ユリウスは目を真っ赤にして、摑みかかってきた。
クラウスは笑いながら、両手で彼女を抱き止める。
「お前、泣くか怒るか、どっちかにしろよ?」
「誰が怒らせてるのっ!」
「いてててっ! ばか、やめろって」
「ばかはそっちだよ!」
「何だとお? こいつめ」
俺の胸を叩きながら膨れる頬を両手で押さえ、強引に口づけた。
その瞬間、彼女の腕が俺の背中に滑り込み、力いっぱい俺の躰を抱き締める。
初めて喧嘩した日──弾け飛ぶように拒絶した小さな躰。俺を殴った細い腕。生意気な口を利く唇。
その全てが今、俺に縋って絡みつく。
彼の手のひらが、少しずつ熱を帯びて熱くなる。
長い睫毛から伝い落ち、両頬で煌めく……、この世で一番澄んだ水を彼は残らず吸い取った。
![]() 本日のエンディング&タイトルはこちらから
本日のエンディング&タイトルはこちらから![]()