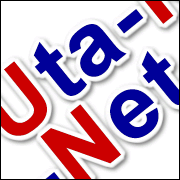龍の傷口から熱い血潮が流れ出し、
天晴れな勇士がそれを体に浴びた際、
両方の肩の間に一枚の広い菩提樹の葉が落ちてきました。
この場所こそあの人の急所なのです。
これが私の心配の種なのです。
(ニーベルンゲンの歌/第15歌章)
人は誰も、長い人生において、幸せと不幸せの配分は平等であるという。
今がどれだけ不幸でも、果てなく続く道の向こうには平穏な未来が待っている──と。
では、長く生きられなかった者はどうなのだ?
望む望まぬに拘わらず、第三者の手によって、その未来を絶たれた者たちは?
彼も彼女も、短い生涯のなかで、十分に幸せだったと嚙み締めながら、仄暗い水の底へ落ちていったと、
かけがえのない時代を過ごせたと、
瞬間瞬間、その透き間に塵一つ留めないほど蜜なひと時だったと……、
確信をもって、彼の、彼女の代わりに、誰が言い切ることができるだろうか。
結論から言う。
彼と彼女は、長い月日をかけて、明日への軌道を描き始める。移りゆく季節とともに。
ただ、そこに至るまでを語るには、幾許かの時間が必要である。
誤算
「来ちゃいけない!!」
たった一度の、悲鳴のような叫びが──凡庸な老人の仮面を剥いだ。
「逃げてアレクセイ!!」
その標的へ、現場にいた憲兵隊の全ての弾丸が放たれた。
剛健な背中と腰、屈強な四肢が、まるで糸の切れた操り人形のように、翻筋斗うって崩れ落ちる。
「アレクセイッ!!」
彼女は、弾かれたように地面を蹴った。
「奥様!? いけませんっ!!」
召使いの女が叫ぶ。
愛する夫のもとへ、ましてやその命の灯火が今にも絶たれようとしているところへ、決死の思いで、妻が駆け出していくことに何の不思議があるだろう。
「お戻り下さい! 奥様ぁっ!!」
「駄目だっ!! 戻れ!! ……ユリウ、ス……っ」
彼女の耳には届かない。呼び止める声も、銃弾の音も、人々のどよめきも聞こえない。
その碧眼が捉えたものは、最愛の夫であり、唯一無二の恋人であり、
彼女にとって、この世でただ一人の男──アレクセイ・ミハイロフ……、彼の姿だけであった。
『どんなことが起こっても、決して自分を失ってしまわないでくれ』
穏やかで厳しい彼の言葉が、永遠にも感じる距離を走る彼女の脳裡を過る。
『いいな……? ユリウス』
けれど、彼女は止まらなかった。
──Nein!……Nein!! Nein……!!
NEIN……!!
「来るな……、来る……な、ユリウス……!!」
「アレクセイ!! アレクセイ……、アレク…セイ……」
「ユ…リウス……、なんでだよ……、なんで……」
「一人でなんて、行かせないから」
「馬鹿だよ、お前は。……馬鹿やろうだ」
「ア…レクセ……」
──オルフェウスの窓、オルフェウスの窓、ぼくたちに力を貸して!!
──オルフェウスの、窓……!!
レオニード・ユスーポフは、生涯に於いて、少なくとも三つの間違いを犯した。
一つは、企ての駒として捕らえた、金髪の異国の少女を愛してしまったこと。
一つは、標的を仕留めるために、あろうことか彼女を囮に使ったこと。
最後の一つは、それこそがユスーポフ侯にとって最大の誤算であっただろう。
愛する者のためには命さえも厭わぬという彼女の覚悟を、
二人の絶ち難い結びつきを──甘く見ていたことである。
雪が降っている。
水の中に……?
躰が斜めになっている。
真っ直ぐに歩けない。
斜めだから?
それとも水の中だから?
躰中が冷たい。
けれど、手だけは温かい。
繋いだ手。
大きな手。
温かい手。
ぼくの手を繋いでいるのは誰……?
離さないで……!
置いていかないで、ぼくを。
置いていかないで!
クラウス……っ!
『──クラウス? クラウスだね? あぁ……、やっと逢えた……』
『ユリウス? まさか、思い出した……のか……?』
『またぼくを置いていこうとするなんて……、酷いよクラウス』
『お前、記憶が戻ったのか? 本当に? なのに皮肉だよなぁ……は、ははっ』
『何故笑うの? ちっとも可笑しくないんだけど』
アレクセイの手のひらに、ユリウスが爪を立てる。
『いてっ! 悪かった、悪かったよ。ごめんなユリウス』
アレクセイは華奢な手指を温めるように包み込んだ。
『しょうがないなぁ。じゃあ今回は許してあげる』
『おう、助かったぜ。お前に嫌われるのは死ぬことよりも辛いからな。Danke』
──ぼくだって、貴方が傍にいなければ、死んでいるのと同じだもの……。
仄暗い水底を、固く繋がれた手と手が、絡み合う二つの躰が、ゆっくりと流れていく。
浮いては沈みを繰り返し。
濁流は清流となり、円やかに二人を覆う。
永遠の恋人たちを……。
夢と現の中間を揺らぎながら進んでいく。
何処までも……。
誰にも、何ものにも、止めることは出来ない。
「まさか!? それは事実なのか? ロストフスキー」
「はい……。確かな筋からの情報です。重なり合った二つの躰がネヴァ河へ落ちていったと。召使いが止める間もなかったようで……」
淡々と、しかし少なからず動揺を隠せないセルゲイ・ロストフスキーの言葉をレオニードは遮った。
「本当か? 誰かと間違っているのではないか? 若しくは何処かに隠れているということは? 今一度、隅々まで部屋を捜索して……」
誰よりも信頼を置いているこの部下が誤った報告などする筈がない、ということは頭では重々理解していた。
そして言われるまでもなく、部屋のみならず、思い当たる場所は隈なく捜し尽くしているだろうということも。
それでも彼は確かめずにはいられなかった。別の答えが導き出せるのであれば何度でも。
「誠に残念ですが、大勢の目撃者もいるのです。やつの躰全体を護るように波うつ金色の髪は、銃を構える兵隊の目を眩ませるほどだったと。そのような髪の持ち主は、私は他には……」
レオニード・ユスーポフの威風堂々とした長身がぐらりと揺らぐ。
膝から崩れ落ちるのではないか、とロストフスキーは咄嗟に身を乗り出した。真っ青な顔で、瞬きすら忘れ、がくがくと躰を震わせる姿を見れば無理もないことである。
しかし、レオニードは持ち堪えた。書斎のライティングデスクに両手をつき、五指を曲げ、突き刺さるほど爪を立てた。もし彼の手の下に書類があったなら、粉々に裂かれていただろう。
「……私も知らぬ。その類稀な金の髪は……、他には……」
あの稀有な出会いの日から、意志に逆らうように自分の心を侵略し、抑え難い胸の疼きに狼狽した、ただ一人の少女だけだ。
この日、この時刻、この瞬間から、レオニード・ユスーポフは長きに渡り、悔恨の情に駆られることになる。
振り切ったはずの乙女が、彼にとって、それほどまでの存在であったのだと思い知らされるのと同時に。

誤報
いつの世にも、神の手を持つ医師と呼ばれる者は、少なからず存在する。
この混沌とした動乱の世に、一筋道を間違えれば悪魔の手先にもなり兼ねないその天賦の才は、歪むことなく廉潔な道を進み続けた。
そのことは当の本人だけではなく、過酷な運命に翻弄され続けてきた男と女にとっても、至極幸運なことであった。
「貴方の噂は、ペテルスブルクから毎日のように流れてきますよ」
ベッドの上で身動ぎも出来ずにいる男を見下ろして、実直な医師は言った。
「『血だるまになってネヴァ河へ沈んだアレクセイ・ミハイロフ』。
ただ、多少虚談が混じっているようです。第一に、貴方はこうして生きている。第二に、血だるまになったとは思えないほど銃痕がない。いや、それは言い過ぎかな。銃弾は貫通、又は掠めただけで済んでいる」
「先生……、そういうのは多少とは言わないんじゃ……つうっ!」
「ほらほら、まだ喋っては駄目です。それでも重傷には変わりないんですから。普通の人間なら瀕死と言ってもおかしくない状態なんですよ」
「あの……、妻の具合は……?」
「心配は無用です。驚異という言葉が相応しいのは、貴方より寧ろ彼女の方でしょう。貴方の奥様は、大神ゼウスより選ばれし者ですか? それとも地母神ガイアの生まれ変わりですか? いえ、答えなくて結構。少し眠ってください。また来ます」
結局、喋りたいことだけ勝手に喋って、医師は部屋を出ていった。
いずれにしろ、未だ寝返りすら打てないアレクセイに出来ることは何もない。
ぼんやりと天井を眺めることぐらいしか……。
命があることが──今でもまだ不思議だった。
死を覚悟した。
川に落ち、水底へ沈みながら、あぁ……これで終わりだ──と思った。
血の臭いも、燃えるような熱さも、
たちまち綺麗に消え去った。
凍るような冷たさと、薄れゆく意識のなかで。
沈んでいるのか。浮き上がっているのか。
流されているのか。漂っているのか。
暗闇の中で見えたのは、繋いだ手と怒っているようなお前の顔。
それでも……、
一緒なら良い。
お前を置いていくよりは……。
もう二度と離さない、と誓ったのだ。
ところが──、
目が覚めた時、一人だった。いや、男が一人、顔を覗き込んでいた。
──誰だ?
ここは地獄か? それとも……。
「ユリウス、は?」
自然と口をついて出た。真っ先に意識に上ったのがそれだった。
返事はない。
「ユリウスはっ!?」
次の瞬間、味わったことのない激痛が全身を貫いた。
「動かないで!!」
知らない男が、アレクセイの躰を押さえ込む。翳む視線がその男の顔を捉えた。
まだ若い。自分とさして変わらない年齢のようにも見える。
「金色の眩い髪の方ですか?」
「痛ぅ……! そう、だ。俺の、妻……だ」
「そうですか。奥様でしたか」
「まさか……、死んだ…のか? どうなんだ!? はっきり言ってくれ!!」
「落ち着いて! 傷が開いてしまいます。安心なさい。彼女も無事ですよ」
──嘘だろう……?
「本当か? 俺を騙しているんじゃないだろうな? 極寒のネヴァ河に落ちたんだぞ! そうだ怪我は? 銃弾を浴びたはずだ!」
一息に言い切った後、アレクセイは再び痛みで突っ伏した。息を吸い込むだけで、息が止まりそうになる。
「ははは……、それは貴方も同じでしょう。それにしても、さすが夫婦だ。殆ど同じことを奥様にも問い質されましたよ」
「……はぁ……?」
「『ぼくを騙しているんじゃないの? 真冬のネヴァ河に落ちたのに。怪我は? 蜂の巣になったはずだよ!』──だそうです」
「その喋り方……は……」
「不思議な人です。ご自分のことを『ぼく』と言う。女の方なのに」
男は穏やかに微笑んだ。
「あ……あ、あいつは昔から、それだけは……、変わらない……」
「奥様で、間違いありませんね?」
途中から、泣いていたと思う。
「間違いない……。ユリウス、だ」
アレクセイは、躰の痛みも忘れて泣いた。いや、痛みに耐えながら嗚咽した。堪えようとも思わなかった。
悲しい涙ばかりだった。幼い頃から、否応なしに突きつけられる永遠の別れ。
母親。兄。どちらも突然で、早過ぎた。
そして青春の終末に──ただ一人愛した乙女との腕を捥がれるほどの別離。
だが……、今は、
けれども今は……。
──神よ……、
「ありがとう……ございます……」
神よ、感謝します……。
記憶
「……クラウス」
「うん?」
遠い昔に慣れ親しんだ名前を、妻が呼ぶ。
「クラウス」
「……何だ?」
その綴りを嚙み締めながら、アレクセイは返事を返す。それを数回繰り返した。
懐かしい学び舎と、制服を纏った金髪の天使。
──屈託なく笑う俺のエウリディケ。
それから、これだけは言わなければと、
「二度も置き去りにして、本当に悪かった」
平身低頭で謝った。
「それは、ミュンヘンと、ペテルスブルクでのこと?」
──ああ……。
嬉しいけれど、気まずかった。
ユリウスの記憶が戻った。
レーゲンスブルクの想い出が、鮮やかに彩りを取り戻す。
紅色に染まるドナウ。雪白に埋もれる恋慕。グレイの雨の疾走と。
黄金色の抱擁──そして別れ。
「落ち葉が……」
そう呟いた彼女の頬に、一筋の涙が伝う。
「落ち葉が、ぼくたちに降りそそいでいたね……」
「ああ……。俺は、落ち葉と一緒にお前を抱いた」
それから、身一つで、最果ての地を目指してきた日のこと。
あの男に助けられ、囚われてしまったこと。
そしてあの日──混乱のペテルスブルクで、俺と出逢った。
反対に、今度は、ぺテルスブルクで俺に突き放された直後から、今回のネヴァ河に落ちるまでの記憶が飛んでしまった。当然ながら、俺と暮らし始めたことも、結婚したことも憶えていない。
どういった原理なのか、医師にも解らないようだった。あちらが戻ればこちらが……ということか。
初めはショックだった。だが、(花嫁になったことを忘れてしまった)ユリウスの方がもっとショックなのだ。
──俺のことを忘れられるよりは、よっぽどましだ。
焦らずに時を待とう。いつかきっと良い方に風は吹く。
「貴方が飛び下りた直後、雪崩れ込むように憲兵が押し寄せてきて、窓から落ちたところまでは覚えているんだけれど……」
一本の糸を手繰り寄せるように妻が言う。
「そうだったのか……」
恐らく、そのとき頭を打って、記憶を失くしてしまったのだろう。他に怪我をしたのか、重傷だったのか軽傷だったのか、問い質す術は今はない。
「……本当に済まなかった」
「クラウスには凄く昔のことかもしれないけれど、ぼくにとっては、つい昨日のことみたいに思えるんだ。きっと、思い出したばかりだからだね……」
まるで他人事のようなあっけらかんとした言い方が、逆に胸を抉ってくる。
邪気のない碧の瞳が見つめられ、居たたまれなくなってしまう。
「あのさ、非難するなら一息にやってくれないか。なんだか、その……真綿で首を絞められているみたいだ……」
「非難してるつもりはないのだけれど……。そんなふうに聞こえたならごめんなさい」
「だから、謝るのは俺。お前は謝るな」
「そんなこと言われても……」
「頼むから、謝らないでくれ」
困ったような顔で、ユリウスが微笑んだ。
「ねえクラウス。ぼくね、貴方との大切な思い出が取り戻せて本当に嬉しいの。レーゲンスブルクで……、聖ゼバスチアンで貴方に初めて出逢った日から、色々なことがあったよね。もちろん楽しいことばかりじゃなかったけれど。それも懐かしくて愛おしくて、今はね、その一片ずつを掬い取って浸っているところ。怒るのは、その後……、ね?」
「やっぱり怒られるのかよ……」
ユリウスが、くすくすと笑いだす。俺は苦笑した。
「貴方と結婚しているって聞いたときは、本当に驚いた。それを忘れてしまった自分が哀しくて、情けなくて……。でもね、今は不思議なくらい落ち着いているの。貴方が変わらずに、ぼくの傍にいてくれるからだね」
「当たり前だろ? 誰が離すかよ。どんなことがあっても、もう決して離さないって誓ったんだ」
「……嬉しいな。ぼくの……だんな様?」
ユリウスは淡く頬を染めて俯く。
あぁ可愛い。俺は思わず抱き寄せそうに──、
──まずい、まだ傷が……。
慌てて手を引っ込めた。
穏やかな表情の妻と一緒に、緩やかな時間が流れていく。二人で暮らした日々は記憶から消えていても、全く違和感は感じなかった。
「もしかしたら、彼女の頭の片隅に、潜在的に存在しているのかもしれません」
「いつかは……戻りますか? 先生」
「信じましょう。今、僕たちに出来るのは信じること。それだけです」
「いや……、命があるだけで十分ありがたいのに、贅沢な望みですよね」
「それは、贅沢とは言いませんよ」
無数の銃弾と、極寒のネヴァ河と。どちらか一方だけでも簡単に命は絶たれたはずだ。
どう考えても、それらを上回る力が働いたとしか思えない。
幸運な偶然か。
神懸り的な必然か。
それとも、伝説が尻尾を巻いて逃げたのか……。
慕情
家の近くを流れる川を、ユリウスは気に入っていた。何処となくドナウに似ていると彼女は言う。
その川辺にクラウスが座れば、釣りをしている姿が浮かんでくる。赤い薔薇が咲いていれば完璧なのに……、とも。
あの日──魚が跳ねたのだ、と年若い医師は言った。跳ねたように見えたのだ……と。
「こんな季節に? と初めは思ったんですけどね」
軽い気持ちで釣り竿を取って戻ってくると、魚ではなく人間が打ち上げられていた。
それが──俺とユリウスだったというわけだ。
繋がれた手だけでなく、固く抱き合うように躰と躰が重なっているのを見たときは、凍りついたまま死んでいると思ったらしい。
俺たちが生きていることに驚いたのは、俺たちだけではなかったのだ。医師の腕云々よりも、まず、息がある状態で、ペテルスブルクから流れ着いたこと自体、人智を超越しているという。
「正に、事実は小説より奇なり、です」
医師は言う。
「出来るなら、貴方の強靭な心臓を解剖して覗いてみたい」
口調は冗談めかしているが、表情は探究心剥き出しだった。
思わず一歩後退る。
「や、やめてくれ! せっかく生き延びたのに殺す気か?」
「はは……、冗談ですよ」
何処までが冗談で、何処からが本気なのか……、どうにも摑み切れない男である。
それでも、他のどんな職業でもなく、そこに医師がいなければ、俺たちは半時も持たなかっただろう。
命の恩人が彼であることに、何ら変わりはない。
ドイツの話に花が咲くと、お決まりのように、
「その頃は、クラウス・フリードリヒ・ゾンマーシュミットだね」
とユリウスは楽しそうに注釈をつける。
「それを言うなら、お前は、ユリウス・レオンハルト・フォン・アーレンスマイヤだぞ」
俺は仰々しく言い返す。
「今は、ただのユリウス・ミハイロヴァなの」
愛妻がにっこりと微笑んだ。
実際、名前なんてどちらでも構わないし、特別な拘りがあるわけでもない。
どちらも大切な自分の名前だ。ユリウスと出逢った時の「クラウス」も、今、彼女が愛情たっぷりに呼んでくれる「アレクセイ」も。
実際、その日によって、或いは時間帯によって、呼び方は「アレクセイ」にもなり、「クラウス」になったりもする。或る晩は、窓越しに空を眺める金色の髪が月に誘われるように揺らぎ、今にも泣きだしそうな声が「クラウス……」と呼んでいた。
焦燥感に駆られ思わず後ろから抱き竦めると、ゆるゆると振り向いた碧の瞳が、初めて存在に気づいたかのように安堵の息をつき、俺の胸に顔を埋める。
責められた方がまだましだ。そう思う。同時に、過去の自分を激しく悔いる。何度も。
記憶の箱に詰まっているのは、楽しいことばかりではない。すぐには嚙み砕けないものもあるだろう。
憤りも哀しみも、我慢せず、そのままぶつけてくれればいい。
一緒に解きほぐしていこう。それから、一緒に巻き直していこう。
「アレクセイ、随分髪が伸びたんじゃない?」
肩よりだいぶ長くなった髪を細い指が愛撫する。その日の妻は、「アレクセイ」の気分のようだった。
「そうか? まあ、ここにきてから一度も切ってないからな」
「貴方と初めて逢った頃は、肩にもついていなかったよね」
ユリウスは幸せそうに目を細める。
「お前、よく覚えてんなぁ」
「ねえ、ぼくが切ってあげる」
「え、出来るのか?」
「うーん。人の髪を切るのは初めてだけど、貴方の髪って癖もなくてさらさらだよね。だから、たぶん大丈夫」
「たぶん……?」
タイミングの悪いことに、無残に切られたショートヘアが脳裏に浮かんだ(あれはあれで可愛かったが)。
「いいから椅子を持ってきて。ほら、今日はお天気が良くて風も穏やかだし、散髪日和だよ」
そんなに楽しそうに言われては逆らえない。
仕方なく、俺はキッチンから椅子を取ってくる。
「ケープがないから、エプロンで代用するね」
ユリウスはエプロンを腰から外すと、背中から肩にかけ、首もとを紐で結んだ。
「お前、大雑把だなあ」
「ね、苦しくない?」
「ああ。それより肝心の鋏はあるんだろうな?」
「うん。待ってて、すぐに持ってくるから」
「動いちゃ駄目だよ」と言ってユリウスが家の中に入っていく。鋏を手にして、本当にすぐに戻ってきた。その足取りは軽やかで、銃創の後遺症は無さそうだった。何よりもそれだけが心配だった。本当に良かったと思う。
ドレスの裾捌きも、すっかり慣れたようだ。いつ頃からだったろうか……、と思いに耽る。一緒に暮らし始めた頃は、まだまだ覚束なかった気がする。
ミハイロフ家に預けてから、祖母にでも特訓を受けたのかもしれない。屋敷を訪ねた時、ドレスのままマルコーに乗っているところに出くわしたこともあった。
そう言えば、『おみ足がはだけるのも気にせずに跨れるので困ります』と、オークネフがよくぼやいていた。
初めは裾を踏んでばかりいて、その度に抱きつかれていたというのに、まったく大した進歩だ(たまには踏んづけてくれないだろうか、と期待している自分もいる)。
「どうしたの? にやにやして……」
「え? いや、してないって」
「……そう?」
していたかもしれない。隠すように唇を押さえた。
「どれくらい切りましょうか? ご主人様」
手櫛で髪を梳かしながら、戯けるようにユリウスが訊く。
「任せるよ」
「かしこまりました」
不規則な鋏の音が耳もとで鳴り始めた。緊張とは裏腹に、髪の毛がはらはら地面に落ちていく。
祖母とオークネフの消息は未だ不明だ。捜索の糸口すら摑めない。
あの日、屋敷に足を踏み入れた途端、最悪の事態を覚悟した。しかし、死体どころか一滴の血痕すら見当たらなかった。不思議なことに、マルコーまで消えていた。
攻撃の対象を失って、当てが外れた者たちの憤怒の行為を、不必要に破壊された屋敷の残骸が物語っていた。まるでノルマを果たすようにガラスというガラスは割られ、家具は一つ残らず叩き壊され、ドアや壁には無数の傷がついていた。忘れられたように無傷だった馬小屋が奇妙に映るほどだった。
ユリウスは無事だった(今思えば分かり易過ぎる手紙にまんまと誘き出され、二人して命を落とすところだったのだが)。
──では残りの二名は? 一頭は?
全貌は分からない。彼女の記憶の蓋が開かない限り。
けれど、信じよう。──信じたい。
祖母も老齢の執事も、そして愛馬も、必ず何処かで生きていると……。
夢中になるあまり、ユリウスが不自然に前屈みになった。金色の絹糸が両頬を何度も撫でる。
「なあ、擽ったいぞ」
「あ、ごめん」
ユリウスが長い髪を耳にかけた。
「お前の方こそ、少し切った方がいいんじゃないか?」
「じゃあ、後で貴方が切ってくれる?」
他愛もない会話。何のしがらみもない二人きりの場所で。
我慢する必要も理由もない。
背後から回り込んだ彼女の躰を抱き寄せる。
「きゃ……! 危ないじゃない。まだ途中なのに」
金の髪が波うつように顔中に降り注ぐ。
「こんな近くでお前の匂いを嗅がせられて、平静でいられる方がおかしいだろ」
「……え?」
鋏をそっと取り上げ、地面に落とす。
「アレクセ……」
唇が重ね合わさる。ふうわりと軽い躰が膝にのる。手のひらが柔らかな曲線を慈しむように包み込む。
風が変わるまで、そのままでいた。
ここは何処だろう? 違う世界の桃源郷だろうか……。
どんなところでも構わない。
俺の隣にお前がいれば。
ぼくの隣に貴方がいれば……。
希望も渇望も欲望も、
全ての望みを絶ち切られ、
最果ての極限で見たものは、早春に微笑む天使だった。
もう二度と、この手は離さない。否、離れないだろう。
あの激流でさえ、引き裂くことは出来なかったのだから。
風は、まだ変わらない。
せせらぐ水音に融けてゆく甘やかな吐息。
古びた街の聖なる鐘が祝福の音をそよがせる。
このままでいたい。ずっと……。
このままでいよう。二人で……。
これからも、
ずっと二人で。
ただ、その幸せを嚙み締めて──。
いきなりですが話が飛びます。原作の最も悲劇的なシーンから怒涛の展開。
こんなの半分ファンタジィだよなあと思いながら初めは書いていましたが、
途中で気が変わりました。
なるべく無理なく少しずつ空き過ぎた隙間を埋めていきます。
イメージソング『慕情』中島みゆき