文化ライターのブルーノです。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
皆さまのためになる話を少しでも多く提供させていただきたいと思います。
さて、今回は「技術士編」として、レジリエンスエンジニアリング(RE)の話をさせていただきます。
月刊技術士12月号/日本技術士会の中に、「原子力安全とレジリエンスエンジニアリングについて」が掲載されていましたので、私の感想などを交えてご紹介します。
1.レジリエンスエンジニアリング
(RE)とは
東日本大震災により、原子力に対する不安感は、国民みんなが痛感しているところです。
そして、技術に対する不安感は、最近の技術の高度化・システムの複雑化により新しいリスクが現れてきており、そのリスクを「システミック・リスク」と呼ぶようです。
その「システミック・リスク」に対応するために欧米の研究者が「レジリエンスエンジニアリング(RE)」という新しい安全方法論を急速に発展させています。
あまりに、用語が難しすぎて、頭にスッと入ってきませんよね。
レジリエンスの意味は「弾力性」、「復元力」であり、自然災害に直面した時の稼働継続性、回復力と解釈できます。
エンジニアリングの意味は「科学技術を応用して物品を生産する技術」、「人間工学」であり、そこでレジリエンスの意味と合わせて考えると、REの意味がおぼろげながら理解できそうです。
本書では、REが登場した背景は従来の失敗に着目し改善することによる「失敗着目型」の安全ではなく、人間・機械系としての「システム安全」を重視することや人間の認知特性や心理学、組織心理学などの面からも考察し、「失敗事例」だけでなく「成功事例」にも着目した考察が必要だと注目されてきたからとあります。
2.REの実現法について
本書では、REの能力と要件を次のように示しています。
〇4つの能力
・能力1:対処できる
何をすべきか知っている
・能力2:監視できる
何に注意を払い監視すべきか知っている
・能力3:予見できる
この先の脅威と好機の出現を知り得る
・能力4:学習できる
過去の成功・失敗の教訓を引き出せる
〇4つの要件
・要件1:変化への気づき
・要件2:リソースの確保
・要件3:能動的な対応
・要件4:良好事例も対象とした学習
これらの能力と要件は、一般社会や組織の中で既に用語や言葉を代えて使われているように思います。
REを特に目新しいものとして捉えるのではなく、これまでの仕事や業務経験の中で4つの能力や4つの要件を体系化して運用していけば、自然にREになるのではないかと思います。
3.REの雑感について
本書の報告者が次のように述べておられます。
「組織などのシステムの中でルールを定めて共有すると心理的には平穏をもたらすが、状況が大きく変化した場合には、その変化に対して実感をもって受け止めることがなかなかできないことがある。組織の中の個々がもっているバイアスなので、『組織などのシステム全体が、変化と対応を形式知化して共有すること』がREに繋がると理解した。」
なるほど、なるほど・・・
私は、REの肝は「変化の予見」、「変化への対応」、「暗黙知から形式知への変換」 だと理解しました。
なお、暗黙知とは「長年の経験やカンに基づく知識」であり、形式知とは「言語化して説明できる知識」のことです。
また、本書では、講演した先生の言葉も次のように紹介しています。
「失敗ばかり責めて陰鬱になるのでなく、良好事例に目を向けて褒めることで元気な安全を目指したい。」
この言葉には、私も深く同感しました。
実は昨年度、私の担当業務が安全管理に関わるものでした。
「事故をなくすにはどうすればいいのか?」と悩みましたが、事故を起こしてことを責めて、原因や再発防止策を練るだけでは、あまり改善が進んでいかないものでした。
事故原因は、大半が人間のミスです。
個人だけでなく組織として安全システムをマネジメントすることが重要であり、良好事例の紹介や褒める場をつくることの大切さを見に染みて感じました。
皆さまも、一度、社会全般、会社、家庭、個人の安全管理について考えてみてはいかがでしょうか?

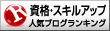
資格・スキルアップランキングへ
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
皆さまのためになる話を少しでも多く提供させていただきたいと思います。
さて、今回は「技術士編」として、レジリエンスエンジニアリング(RE)の話をさせていただきます。
月刊技術士12月号/日本技術士会の中に、「原子力安全とレジリエンスエンジニアリングについて」が掲載されていましたので、私の感想などを交えてご紹介します。
1.レジリエンスエンジニアリング
(RE)とは
東日本大震災により、原子力に対する不安感は、国民みんなが痛感しているところです。
そして、技術に対する不安感は、最近の技術の高度化・システムの複雑化により新しいリスクが現れてきており、そのリスクを「システミック・リスク」と呼ぶようです。
その「システミック・リスク」に対応するために欧米の研究者が「レジリエンスエンジニアリング(RE)」という新しい安全方法論を急速に発展させています。
あまりに、用語が難しすぎて、頭にスッと入ってきませんよね。
レジリエンスの意味は「弾力性」、「復元力」であり、自然災害に直面した時の稼働継続性、回復力と解釈できます。
エンジニアリングの意味は「科学技術を応用して物品を生産する技術」、「人間工学」であり、そこでレジリエンスの意味と合わせて考えると、REの意味がおぼろげながら理解できそうです。
本書では、REが登場した背景は従来の失敗に着目し改善することによる「失敗着目型」の安全ではなく、人間・機械系としての「システム安全」を重視することや人間の認知特性や心理学、組織心理学などの面からも考察し、「失敗事例」だけでなく「成功事例」にも着目した考察が必要だと注目されてきたからとあります。
2.REの実現法について
本書では、REの能力と要件を次のように示しています。
〇4つの能力
・能力1:対処できる
何をすべきか知っている
・能力2:監視できる
何に注意を払い監視すべきか知っている
・能力3:予見できる
この先の脅威と好機の出現を知り得る
・能力4:学習できる
過去の成功・失敗の教訓を引き出せる
〇4つの要件
・要件1:変化への気づき
・要件2:リソースの確保
・要件3:能動的な対応
・要件4:良好事例も対象とした学習
これらの能力と要件は、一般社会や組織の中で既に用語や言葉を代えて使われているように思います。
REを特に目新しいものとして捉えるのではなく、これまでの仕事や業務経験の中で4つの能力や4つの要件を体系化して運用していけば、自然にREになるのではないかと思います。
3.REの雑感について
本書の報告者が次のように述べておられます。
「組織などのシステムの中でルールを定めて共有すると心理的には平穏をもたらすが、状況が大きく変化した場合には、その変化に対して実感をもって受け止めることがなかなかできないことがある。組織の中の個々がもっているバイアスなので、『組織などのシステム全体が、変化と対応を形式知化して共有すること』がREに繋がると理解した。」
なるほど、なるほど・・・
私は、REの肝は「変化の予見」、「変化への対応」、「暗黙知から形式知への変換」 だと理解しました。
なお、暗黙知とは「長年の経験やカンに基づく知識」であり、形式知とは「言語化して説明できる知識」のことです。
また、本書では、講演した先生の言葉も次のように紹介しています。
「失敗ばかり責めて陰鬱になるのでなく、良好事例に目を向けて褒めることで元気な安全を目指したい。」
この言葉には、私も深く同感しました。
実は昨年度、私の担当業務が安全管理に関わるものでした。
「事故をなくすにはどうすればいいのか?」と悩みましたが、事故を起こしてことを責めて、原因や再発防止策を練るだけでは、あまり改善が進んでいかないものでした。
事故原因は、大半が人間のミスです。
個人だけでなく組織として安全システムをマネジメントすることが重要であり、良好事例の紹介や褒める場をつくることの大切さを見に染みて感じました。
皆さまも、一度、社会全般、会社、家庭、個人の安全管理について考えてみてはいかがでしょうか?

資格・スキルアップランキングへ