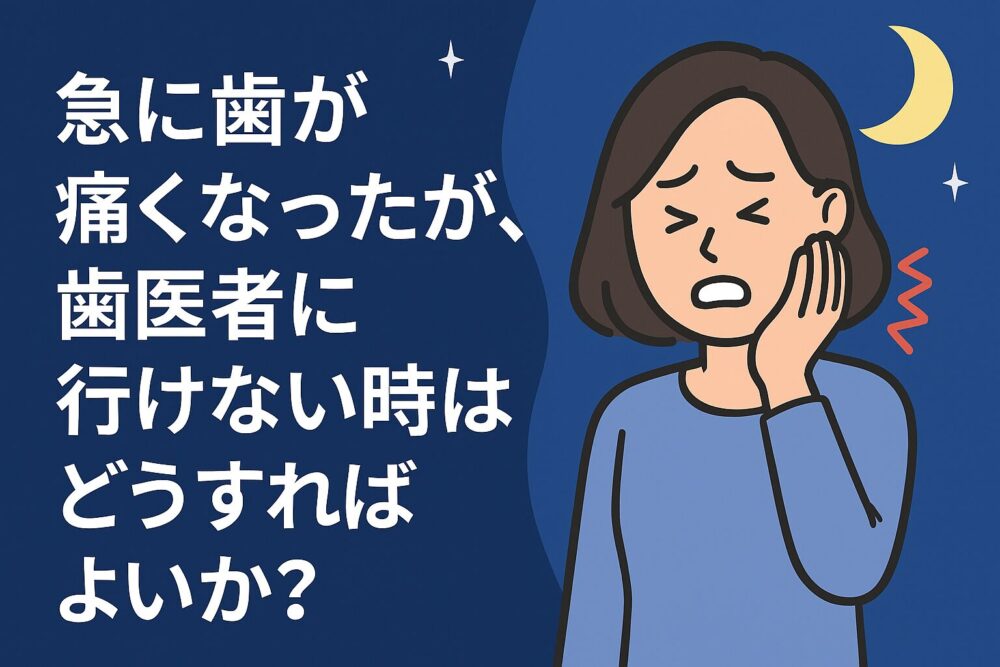(9月28日下書きした記事)
最近、知覚過敏に悩み始めている。
以前から歯がかなり傷んでいて
歯周ポケットも既に最も酷いレベルに達している。
9月上旬、歯医者に予約してあった
定期健診と歯石除去のお手入れに行ったが、
その後で知覚過敏が酷くなったようだ。
歯石除去で器具を使って磨くが
衛生士さんは毎回違う人だ。
今回、磨きすぎたんじゃないかと思う。
診察の最後にするフッ素塗布を
いつも断っているのだけど、
それが原因の可能性はあるかな?
・ ・ ・
ではフッ素って?
↓
虫歯には効くらしいが、体には有害。
(有害ということは知っていた)
・ ・ ・
知覚過敏予防剤を探すと
ほとんどが
フッ素入りの歯磨き粉ばかりである。
なので
その中でも、フッ素少な目を探していた。
なかなか見つからなかった。
・ ・ ・
知覚過敏予防で フッ素 無配合の 歯磨き粉を探す…
↓
↓
フッ素は入ってなくても他の添加物もある。
よくシャンプ-にも入っている
ラウリル硫酸Na や
研磨剤が入っているのも
避けたい。
また
「フッ化ナトリウム(フッ素として)」
と書いてあるものがある。
これはフッ素とは違うの?
(分からないけど念の為避ける)
これら↑全て入っていないものをさらに探した。
・ ・ ・
この商品ページにまとめてくれているので
参考に (このページの製品はイマイチだったが)
↓
知覚過敏を緩和する成分には、
乳酸アルミニウム、硝酸カリウム、ビタミンEなどがあります。
https://item.rakuten.co.jp/at-life/4901080772718/
★捕捉★ハミガキ粉を選ぶ際のポイントは、以下の3つです。
ハミガキ粉には、虫歯予防、歯周病予防、知覚過敏予防、ホワイトニングなど、
さまざまな目的に合わせて配合成分が異なるものがあります。
虫歯予防:フッ素が配合されているものを選びましょう。フッ素は、歯の表面をコーティングして、酸から歯を守る働きがあります。
歯周病予防:殺菌成分が配合されているものを選びましょう。殺菌成分は、歯周病菌の繁殖を抑える働きがあります。
知覚過敏予防:知覚過敏を緩和する成分が配合されているものを選びましょう。知覚過敏を緩和する成分には、乳酸アルミニウム、硝酸カリウム、ビタミンEなどがあります。
ホワイトニング:漂白成分が配合されているものを選びましょう。漂白成分は、歯の表面の着色を落とす働きがあります。
ご自身の口腔内の状態や、ハミガキ粉に期待する効果に合わせて、目的に合ったものを選びましょう。 配合成分ハミガキ粉には、研磨剤、発泡剤、香料、甘味料、色素などが配合されています。
研磨剤:歯垢や着色汚れを落とす働きがありますが、歯茎を傷つけてしまう可能性があるため、使用量を守りましょう。
発泡剤:泡立ちを良くする働きがありますが、泡立ちすぎると口の中が泡で満たされ、磨きにくくなるため、適度な泡立ちのものを選びましょう。
香料:口臭を予防したり、爽やかな香りを楽しんだりするために配合されています。
甘味料:口の中をすっきりさせるために配合されています。
色素:見た目を良くするために配合されています。ご自身の好みや、口臭や舌苔の気になる場合は、香料や発泡剤が配合されているものを選ぶとよいでしょう。
・ ・ ・ ・ ・
楽天市場で探して
値段の安い方から並べて1つずつ見て行った。
ここで4種類を記憶の為に残しておく…
以下、
楽天市場で見付けた順
https://item.rakuten.co.jp/d-fit/df2926/
ロックス プロ R.O.C.S. センシティブ ソフトミント 1本(94g)【知覚過敏】【ROCS PRO SENSITIVE ソフトミントフッ素不使用 天然 天然由来 無添加 美白ケア 虫歯予防 歯周病予防 口臭予防 着色除去 マグネシウム配合】
1,100円+送料378円
独自成分で虫歯予防 HAPコンプレックス
【商品の特徴】
●知覚過敏軽減
●ミネラル成分(リン・カルシウム・マグネシウム)配合
●ヒドロキシアパタイト配合
●高濃度キシリトール8%配合
●独自の技術で合成されたヒドロキシアパタイトが露出した象牙質を保護します。
●研磨性が非常に低いので敏感な歯にやさしく磨けます。
【不使用成分】
フッ素 研磨剤 ラウリル硫酸Na 合成着色料 動物性原料 鉱物油
【全成分】
水、グリセリン(保湿剤)、リン酸2Ca(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシアパタイト・シリカ(清掃剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、メチルパラベン・プロピルパラベン・シメン-5-オール(防腐剤)、リモネン(香味剤)
【ブランド】
R.O.C.S.(ロックス)
【発売元、製造元、輸入元又は販売元】
ロックス・ジャパン
原産国/製造国: ロシア
https://item.rakuten.co.jp/aromage/10004200/
COSLYS トゥースペースト センシティブ 歯磨きジェル ミネラル塩 低刺激 フッ素フリー ジェルタイプ ミント プロポリス配合 フッ素フリー 二酸化チタンフリー 研磨剤フリーロゴナ ミネラルはみがき 75ml
1,210円 +送料250円
成分
水、加水分解水添デンプン(保湿剤)、グリセリン(保湿剤)、アルギン酸Na(粘結剤)、キサンタンガム(粘結剤)、香料(着香剤)、ココイルグルタミン酸Na(洗浄剤)、安息香酸Na(防腐剤)、ステビアエキス(着香剤)、ラウロイルリシン(湿潤剤)、アロエベラ葉汁*(湿潤剤)、塩化Na(粘結剤)、エタノール、水酸化Na(pH調整剤)、プロポリスエキス(湿潤剤) (*オーガニック原料から得られた成分)
低刺激、ミント風味
製造国 フランス
総容量 75ml
代表カラー グリーン
ロゴナ ミネラルはみがき 75ml LOGONA オーガニック 海藻エキス ミネラル 虫歯予防 フレッシュミント 発泡剤不使用 フッ素不使用 合成防腐剤不使用 電動歯ブラシ対応
1,100円+送料400円
■成分:水、グリセリン、ソルビトール、炭酸Ca、含水シリカ、ココイルグルタミン酸Na、アルギン酸Na、ヘクトライト、キサンタンガム、海塩、スペアミント油、セイヨウハッカ油、モツヤクジュ樹脂エキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス*、チャ葉エキス、チョウジ花油、ヒバマタエキス、変性アルコール(小麦由来)、ラウリン酸スクロース、フィチン酸、香料 *=欧州の有機認定成分
■内容量:75ml
■生産国:ドイツ
https://item.rakuten.co.jp/jism/4987072027110-73-30001023-n/
生葉Sa 知覚過敏ケアタイプ 100g 小林製薬 シヨウヨウチカクカビンヨボウ100G
994円+送料550円
◆5種類の天然植物由来成分配合
◆歯槽膿漏を防ぐ薬用成分
・抗炎症作用:歯グキの炎症を抑えるグリチルリチン酸ジカリウム(甘草由来成分)
・殺菌作用:お口を清潔にするヒノキチオール(ヒバ含有合成成分)
◆知覚過敏の症状を防ぐ薬用成分
・保護膜作用:歯髄神経のまわりに保護膜を形成硝酸カリウム
・象牙細管封鎖作用:象牙細管を封鎖する乳酸アルミニウム
◆やさしいハーブミント味
※知覚過敏とは:歯槽膿漏などで歯ぐきが退縮し、象牙質が露出すると、表面の象牙細管の穴から歯髄神経に刺激が伝わり、しみたりする事です。
【効能・効果】
歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉(齦)炎の予防、歯がしみるのを防ぐ、口臭の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、むし歯を防ぐ
【使用上の注意】
発疹などの異常が出たら使用を中止し、医師に相談すること
口内に傷がある場合は使用をひかえること
目に入ったらこすらず、すぐに充分洗い流し、異常が残る場合は眼科医に相談すること
虫歯を伴う歯の痛みには効果がないので、虫歯で歯がしみる場合は歯科医師による治療を受けること
■成分:
湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン
溶剤:水、エタノール
基剤:含水ケイ酸
粘度調整剤:無水ケイ酸、ヒドロキシエチルセルロース
薬用成分:硝酸K、乳酸Al、グリチルリチン酸2K、ヒノキチオール
発泡剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン
安定剤:酸化Ti、エデト酸塩、アラントイン
pH調整剤:水酸化Na、クエン酸Na、クエン酸
香味剤:香料(和漢ハーブの香味)
可溶剤:POE硬化ヒマシ油
矯味剤:トウキエキス(1)、シャクヤクエキス
清涼剤:メントール
防腐剤:パラベン
着色剤:黄203、緑3、緑201
洗浄剤:ムクロジエキス
■販売名:生葉Sa
■商品区分:医薬部外品
■原産国:日本
発売元、製造元、輸入元又は販売元:小林製薬
↑
おおぉ、小林製薬だって!?
普段なら外国製よりも
日本製を優先するのだけど、
日本製は入っていてほしくない物の
どれかが入っている製品がなぜか多い。
だが、見つけた…
紅麹で激しく叩かれた小林製薬が作ってくれていた!!
この製品はかなり良いかも、と期待。