2017年1月2日
干支のとりは、なに鳥?はて?・・・酉てぇ!
なんぞやぁ?
はい!暇です。
酉てぇ!なんぞやぁ?・・・とり?鳥?鶏?なんのとり?
と言う事で、暇でしたので、調べました!
そして、干支の由来も、調べたので・・・報告!
まずは、干支の読み方から
子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)辰(たつ)・巳(み)
・午(うま)・未(ひつじ)
申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)
申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)
・・・はい!書けないし、読めんし!
教養ないし、常識ないし!・・・最低の爺です。(私)
では、本題に、


なに?この漢字は?
鳥は動物の鳥ですが、酉を「とり」と関連つけたのは、古代中国の戦国時代
(紀元前404~紀元前221)の頃だろうと言われています。
文献としては、後漢時代の書籍「論衡」が最古とされています。
「酉」に当てはめた「とり」は「鳥」ではなく「鶏」です。
酉は十二支と呼ばれている月を表す序数の8番目を表す文字でした。
「支」は区分するという意味です。
本来は「ゆう」と読まれます。
この暦の月の名前を庶民にも分かり易いように身近な動物の名前を
「酉」に当てはめた「とり」は「鳥」ではなく「鶏」です。
酉は十二支と呼ばれている月を表す序数の8番目を表す文字でした。
「支」は区分するという意味です。
本来は「ゆう」と読まれます。
この暦の月の名前を庶民にも分かり易いように身近な動物の名前を
当てはめたのだろうと考えられています。
「ゆう」の月に「とり」をあてはめたので「とりのつき」からの連想で
「ゆう」の月に「とり」をあてはめたので「とりのつき」からの連想で
「酉」を「とり」と読むようになりました。
ちなみに、とりのつきは、旧暦で月を表す表現。旧暦8月のこと。
古代中国では満月から満月の間を一つの単位として暦の「月」としました。
これを12月(個)集めると約1年の期間に相当します。(太陰暦)
この12の月に自然の季節の移り変わりをあらわす文字をあてはめました。
「酉」はもともとは酒をいれる壺からうまれた文字です。
しぼるという意味があります。
秋になって熟した果実を壺にいれてしぼる時節であるということから
この12の月に自然の季節の移り変わりをあらわす文字をあてはめました。
「酉」はもともとは酒をいれる壺からうまれた文字です。
しぼるという意味があります。
秋になって熟した果実を壺にいれてしぼる時節であるということから
この文字をあてはめました。
ではなぜ「酉」の月に「鶏」をあてはめたのかについては定説がありません。
この12の序列をあらわす文字は、時刻や方位をあらわすのにも
ではなぜ「酉」の月に「鶏」をあてはめたのかについては定説がありません。
この12の序列をあらわす文字は、時刻や方位をあらわすのにも
使われるようになりました。
中国の古代の陰陽五行説と結びついて、占いなどにも使われるようになりました。
中国の古代の陰陽五行説と結びついて、占いなどにも使われるようになりました。
・・・・?
結論
とりの酉は、こいつらしい!
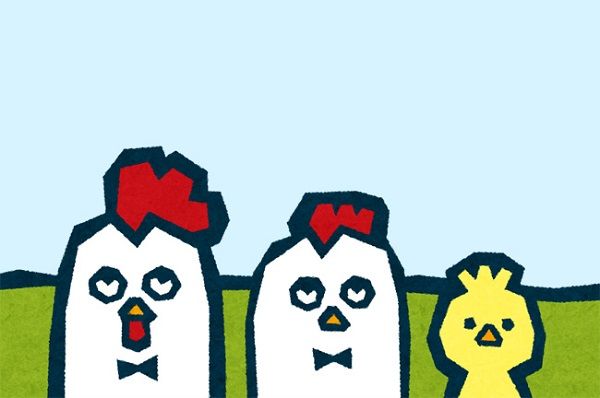
ニワトリ(鶏、学名:Gallus gallus domesticus
「ガッルス・ガッルス・ドメスティクス」)は、鳥類の種のひとつ。
代表的な家禽として世界中で飼育されている。
そして・・・干支のお話し~ぃ!
大昔の話。
神様が「一月一日の朝、一番から十二番目までに来たものを
1年交代で動物の大将にする」という手紙を書きました。
それを受け取った全国の動物たちは、自分が一番になろうと
翌朝まだ暗いうちから一斉にスタートしました。
でも猫だけは「一月二日の朝」とネズミから聞いていたので、出発しませんでした。犬と猿は最初は仲良く並んで走っていたのですが、そのうち必死になってしまい、
とうとう丸木橋の上で大げんかを始めました。
いよいよ新年の太陽が昇った時、前日の夕方から出発していた牛が
一番に現れました。
しかし牛の背に乗っていたネズミが、「神さま、新年おめでとうございまチュゥ」と、
牛の背中からぴょんと飛び下り、神さまの前に走っていきました。
一番はネズミになってしまったので、牛は「モゥモゥ!」と悔しがりました。
続いて虎が到着し、そして兎、龍がやってきました。
こうして次々に動物たちが到着し、蛇、馬、羊、猿、鳥、犬、猪、カエル、
の順番となりました。13番目になってしまったカエルは、がっかりして
「もうカエル」と言って帰っていきました。
さて、神さまと十二支たちの酒盛りが始まりましたが、
犬と猿はまだケンカをしていました。そこへすごい剣幕で猫が現れ、
ネズミを追いかけまわしました。だから、今でも猫はネズミを追いかけていて、
犬と猿は仲が悪いという事です。
13番目に到着したのはカエルであった説やイタチであった説もあり、
カエルはそのまま帰ったのですが、イタチは何度も神様にお願いした事から
みんなに内緒で毎月1日を「つ・いたち」と呼ぶ事で納得してもらったとも
言われています。