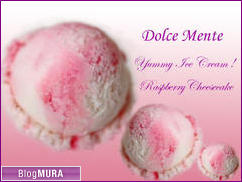フェイクスイーツとは、
本物の(食べる事ができる素材)を使うのではなく
樹脂・粘土・紙・砂・接着剤などの「異素材」を使って作る
「お菓子を模した」クラフトです。
食べる事ができる食材を、
クラフトの材料に使ったアクセサリーや雑貨は
「フェイクスイーツ」ではありません。
ですので、本物のお菓子・食べる事ができる食品を、
樹脂(レジン)に閉じ込めた雑貨は
「フェイクスイーツ」とは呼びません。
素材に本物のお菓子を使った場合の製作物は、
「リアルスイーツ」や
「本物のお菓子を閉じ込めた○○」と呼ばれています。
個人的な考えになりますが、
本物の食品をクラフト材料に使った物は
好きではありません。
食べ物を、工作や遊びの材料に使ってしまう事に
罪悪感を感じてしまうのです。
みなさんは、いかがですか?
あえて、材料に「食品」を使わなければならないのには、
きっと 何か特別な理由がある のだと思いますが、
私には納得できる理由を未だ見付ける事ができていません。
そういったクラフトは、
「樹脂で閉じ込めてるのは、本物のお菓子なんだよ。」
という驚き(インパクト)が込められた
「雑貨」や「工作体験」なのだと思うのですが、
なんだかモヤッとした気分になってしまいます。
粘土という素材があって、フェイクスイーツというクラフトもあるのに。
なぜ、あえて本物の食品・食材を使うのか?
「この雑貨は、本物の食べ物を使って作っているんです。」
「本物のお菓子を樹脂に閉じ込めて、アクセサリーを作りましょう。」
わぁ! 凄い! びっくりー! かわいいー!
作ったら、楽しいかもー!
作っているその場では、とても楽しい作業だと思います。
作業工程の楽しさは、充分に理解できます。
作る作業は、楽しいですよね。
食べる事ができる市販の食べ物・食材(パスタなど)を、
例えばお母さんは趣味のレジンアクセサリー作りに使います。
しかし、子供には日々の生活の中で
「勿体無いから、食べ物で遊んじゃ駄目!」
「食べ物を粗末にしちゃ駄目!」と言い聞かせます。
この場合、殆どの子供は
「お母さんだって、お菓子で遊んでる。」
「食べ物を、工作に使っている。」
と思うでしょう。
お母さんが楽しそうに作っているので、
子供は決して口には出しませんが
「大人が食べ物で遊ぶのは良くて、
子供が食べ物で遊ぶのは駄目なのはなぜ?」
と疑問に思っていることでしょう。
私も、同じです。
本物のパンの中身をくり抜いて、
UVレジンでコーティングしたインテリア雑貨や、
クッキー・飴・ビスケット・ドライフルーツに、
UVレジンやニスを塗ってアクセサリー雑貨を作っておられる方に質問です。
こういった場合、
子供にはどんな説明をしてあげるべきなのでしょうか?
「カワイイ物を作っているから、いい。」
「大人だから、いい。」という説明で正解でしょうか?
私は、子供にちゃんとした説明ができなければ
作っちゃ駄目だなぁと思っています。
焼きたてのパンやクッキーに、
何日もかけてUVレジンやニスを染み込ませて作ったブローチ。
樹脂の中に、飴を閉じ込めたアクセサリー。
ドライフルーツに、UVレジンをコーティングした雑貨。
食べられる食材を使った雑貨やアクセサリーは、
「食べ物で、遊ぶな!」と、厳しく躾けられた世代の私としてはNGです。
手芸店で、
「本物のお菓子にUVレジンを塗ってオリジナルのアクセサリーを作ろう!」
という子供向け講習の広告を見かけると、
かなりモヤッとします。
あと、こういった有機物から作られたものは
永久の物ではありませんし
UVレジンのコーティング層の厚みにもよりますが
触角が長くて黒光りして動きが早いアイツ
G が食べにきます。
大昔、まだフェイクスイーツを始めた頃、
「モデナ」で作ったケーキをアイツにかじられた事があります。
偽物の素材の粘土でさえ餌食になるのに、本物の食品だったら・・・ねぇ。
粉もんに湧くという、目に見えない虫も気になりますね。
常温で長期保存の小麦粉や胡麻も、使うにはちょっと躊躇してしまいます。
もしかしたら、目に見えない粉状の虫が湧いちゃってるかも!?
口にするものだったら、そんなの食べたくない。
でも部屋に飾ったり、アクセサリーで身に付けるのはOK?
なんだか、変ですね。
さて、そもそもこういった
有機物から作られた作品というのは「短命の作品」です。
それを踏まえてのお話です。
もったいないけれども、賞味期限が切れて
どうしても捨てるしかないという食べ物ならば…
ん~…、と考えた後に、ギリギリでOKの範囲に入ります。
(永久にそのままの形や色を留めておく物ではありませんが。)
リサイクルです。 /笑
完成品の見た目では
「賞味期限内」「賞味期限外」を素材に使っているかどうかなんて
分からないので、この妥協も限りなくNGに近いですが…。
食品サンプルに関してですが、
食品サンプルを作る工程の中で、
本物の食品を原型に使う事には、なんら問題はありません。
お仕事としての作業工程の一つですし、
当たり前のことですから。
(これをしないと、作れないという。)
でも、趣味で食品サンプルを作る…となると、
ちょっともったいない気持がでてきますね。
サイズも大きい事ですし。(^_^;
あ、でもリサイクルならOKかも。
本物のお菓子を樹脂(レジン)に閉じ込めた物の、呼び方。
…「これ、バッチリ当てはまってる!」
という言葉が浮かんだので紹介したいと思います。
本物のお菓子を樹脂で閉じ込めた物は、
「お菓子の標本」という呼び方がピッタリだと思います。
昆虫を樹脂に閉じ込めた標本と、同じ感じですね。
「食べ物の標本作り」となると、
単なる工作では無くなります。
雑貨として「カワイイ」の意味しかなく、
心のどこかで「なんだか、勿体無い」と感じていた物が、
「標本」という目線から見てみると、
そこには意味が発生しているのです。
(考え方次第で、大義名分ができる。ちょっと面白いなぁと思います。/笑)
食べ物を使うなんて勿体ないけど、
標本作りの学習の為~なんてね。
ただし、こういった物を
雑貨やアクセサリーとして販売してしまうとなると駄目。
まず、オリジナル性が問われます。
スーパーや輸入菓子店で買った
可愛いデザインのお菓子・綺麗な色のお菓子に、
UVレジンを塗って加工した物をアクセサリーとして販売。
それって、オリジナル? /笑
おかしくない?(お菓子だけに?/笑)
例えば、森永製菓のマリービスケットに
樹脂を塗って固めた物をブローチにして販売。
もちろん、作者のブランド名を記入。
・・・、いやぁ。
それって、あかんでしょ。/笑
自分のブランド名を付けて
オリジナルとして販売するんだったら、
お菓子もオリジナルで作らなきゃ駄目でしょ。
買ってきた市販の商品に、
少しばかり手を加えただけで
「私のブランド商品です!!!」って言っているようでは…
ホント恥かしい事ですね。
市販品を使う場合は、個人の範囲で楽しみましょう。
純粋に「標本」として考える「お菓子の標本」は、
「楽しい」や「カワイイ」だけを追求する「遊び」で
食品を無駄にするのとは違い、
やがて朽ちて行く食品を「標本」として残す事ができるのが
唯一のメリットかなぁと思います。
これは、もはや「クラフト」ではなく
理科の「標本作り」に値しますね。
子供にとっても
「標本作り」という体験にもなるわけですし、
無駄だとか勿体無いと思っていた事は
「学び」に変化するのです。
見る角度を変えると、
見える景色が違ってくるし、
考え方も変わり、意味も変わり、
それを伝える方法も変わってくると思います。
お菓子の標本作り…という意味があり、
個人的に(特に子供が)研究・学習とするのなら
「お菓子にUVレジンを塗る」
というのはOKへ修正してもいいかもと思います。
ポチっとしていただけると、嬉しいです![]()
ブログの応援、お願いします
あと、胡麻や小麦粉なんかの粉状の有機物に湧くという
目に見えないくらい小さな虫も気になりますよね。