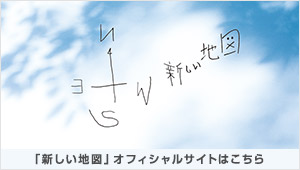【細胞について】(P205)
細胞の機能はタンパク質という「歯車」の働きによって決まることを見てきた。タンパク質が集団で働くことによって細胞は生理的に機能できるようになり、それが生命活動を可能にする。
タンパク質は物質的な構成要素であるが、タンパク質にぴったりはまるような環境からのシグナルがあって初めて働く。行動を生み出すもとになるたんぱく質は細胞質にあり、環境からのシグナルと細胞質を隔てているのは、細胞膜である。細胞膜が刺激を受け取り、それによって、細胞は生命を維持するための適切な反応を返すことができるので、細胞膜は細胞の「脳」だと言える。
細胞の脳の「知性」のメカニズムは、基本的に、内在性膜タンパク(IMP)のレセプタータンパク質およびエフェクタータンパク質によって構成される。機能的に定義するなら、これらタンパク質の集団は「知覚スイッチ」であり、環境からの刺激を受容して、反応を起こすたんぱく質経路へと情報を伝える。
一般に、個々の細胞が反応するのは、自分を取り巻く世界で起きていることに関する、ごく基本的な各種「知覚対象」である。これに含まれるのは、カリウムやカルシウム、酸素、グルコース、ヒスタミン、エストロゲン、毒物、光などなど、さまざまな刺激がすぐ近場の環境に存在するかどうかである。
細胞膜には何十万セットもの反射的スイッチが存在する。それぞれのスイッチが環境シグナルを個別に読み取り、その情報が統合されて複雑な行動が生み出される。
この地球上に生命が誕生して三十億年のあいだ、生命圏には、細菌や藻類、原生動物といった単細胞の生き物だけがいて、それぞれが自由生活をしていた。こういった生命形態では、各個体は孤立していると考えられてきたが、現在では、各細胞が地震の生理的な機能を制御するために用いるシグナル分子を環境に放出して、他の生物の行動にも影響が与えることがあるとわかっている。
環境に放出されたシグナルによって、散らばって存在する単細胞の生き物たちも、協調的な行動をとることが可能になる。環境にシグナル分子を分泌することにより、原始的な「共同体」として生活する機械を得て、単細胞生物の生存率は上昇した。
では、シグナル分子はどうやって共同体を作り出したのだろうか? 細胞性粘菌の粘菌アメーバーにその手がかりがある。
粘菌アメーバーは単独生活をしており、土壌中で食物をあさっている。環境内の食物を食べつくすと、細胞内では代謝の副産物であるサイクリックAMPが過剰につくられ、その大部分は細胞から外部へと放出される。
うえた粘菌アメーバーたちが放出したAMP(cAMP)は環境に蓄積していく。他の粘菌アメーバーが放出したcAMPがシグナル分子として細胞膜表面のcAMPレセプターに結合すると、アメーバーは遊走集落をつくり、集合して多細胞の”なめくじ”のようなもの(移動体)になり、移動体は生殖を行なう。
「飢餓」状態になって形成されたこの移動体内では、老化した細胞は互いのDNAを提供しあって次の世代をつくりだす。次世代の新しいアメーバーになる細胞は、不活性の胞子としてしばらく休眠している。食物が得られるようになると、食物分子がシグナルとなって休眠が打破され、新世代の単細胞は、粘菌アメーバーとしての生活を開始する。
ここで大事なのは、単細胞生物であっても、「認識」を共有し環境に「シグナル」分子を放出して、互いの行動を調和するときには共同体として生活しているということだ。
cAMPは、進化の過程においては最古参の部類に属し、細胞外に分泌され細胞の行動をコントロールする制御シグナルとして、古くから使われてきた分子である。人間の体内で働く基本的なシグナル分子(ホルモン、神経ペプチド、サイトカイン、増殖因子など)は、身体を構成する細胞の共同体を制御している。
かつてこれらの分子は、複雑な多細胞生物の誕生とともに出現したと考えられていた。だが、最近の研究によれば、生物の歴史のごく初期に、原始的な単細胞生物はすでに、「人間と同じ」シグナル分子を用いていたことがわかっている。
進化するうちに細胞は、細胞膜内にある「認識」タンパク質、内在性膜タンパク質の数を増やしていった。認識力を高め、生存確率をあげるために、細胞は集合しはじめた。最初は単純なコロニーだったのが、後には高度に組織化された細胞の共同体になっていった。
前に説明したように、多細胞生物では、細胞が特殊化して組織および気管をつくり、これら細胞集団が生理的な機能を分担するようになっていく。組織化の進んだ共同体では、もともと細胞膜の行なっていた情報処理は神経系や免疫系といった特殊化した細胞群が担うようになった。
(P208)
単細胞生物がしっかりとくっつきあって多細胞生物になり、有効な共同体を形成したのは、わずか7億年前だ。地球上に生命が誕生してからの歴史全体からすれば、比較的最近の話である。いわゆる動物や植物の誕生だ。
単独生活の細胞が用いるのと同じシグナル分子が、新しく進化した、この閉じた共同体でも用いられるようになった。生物体の機能をコントロールするシグナル分子の放出や分布を厳密に制御することによって、細胞の共同体は協力してそれぞれの機能を統合し、ひとつの生物固体として生きていくことが可能になる。
多細胞生物の中でも原始的な生物には特殊化した神経系は存在せず、シグナル分子は共同体の内部全体にひろがるので、各細胞は情報を共有することになる。分子(シグナル分子)の広がりが、ごく基本的な「心」をつくりだしているといえる。このような生物では、細胞一つ一つが、環境からの信号を直接読み取って自分の行動を調整している。
だが、多数の細胞が共同体を形成すると、それまでにはなかった力関係が生じる。独立して暮らしている細胞とは違って、共同体を構成する細胞は、めいめいが好き勝手にふるまうわけにはいかない。「共同体」というからには、その構成メンバーは共同して行動計画を遂行するのだ
(P209)
多細胞動物では、細胞一つひとつは、自分の肌(細胞膜)を取り囲むごく近場の環境条件を「見る」ことができるが、遠くの環境、とくに、生物固体の外側で何がおこっているかは認識できない。あなたの腹のなかにある肝臓の細胞は、局所的な環境シグナルには反応するが、あなたの目の前に強盗が飛び込んできたとしても、その情報をキャッチするだろうか? もちろん無理だ。多細胞生物が生きていくためには情報を精妙にコントロールする必要があり、それは中枢情報処理システムに任されている。
動物が進化して複雑になればなるほど細胞の特殊かも進み、特定の細胞集団が、行動を制御するシグナル分子の流れを統括的に管理するようになる。こうして、広範にわたる神経ネットワークを備えた中枢情報処理=脳が発達した。
脳の機能は、共同体体内でのシグナル分子のやりとりを調整することに在る。必然的に、細胞の共同体内では、認識の権威、つまり”脳”が情報を元にして決定をくだし、それ以外の細胞は脳の決定に不本意ながら従うようになる。
脳は身体を構成する細胞のふるまいを”コントロール”している。これは重要なポイントだ。わたしたちは、健康に問題が生じた場合、気管や組織を構成する身体の細胞に責めをおわせがちだが、それでよいのだろうか?
P210
大脳辺縁系=脳内部で特殊化が進み、制御シグナルを出して身体の細胞全体を従わせるような部位ができた。その一つが大脳辺縁系だ。
辺縁系が進化したことにより、化学物質によるやりとりのシグナルが感覚へと変換され、それは共同体内のすべての細胞が経験できる。わたしたちの意識はこれら”シグナル”を感情として経験する。
細胞間の連絡に用いられるシグナルの流れは身体の”心”といってもよい。意識は、このシグナルの流れを「読み取る」だけではなく、情動を生成することもできる。神経系はシグナルをコントロールしながら放出できる。このシグナル放出によって表出されるのが情動である。
P211
パートは実に明快な実験を行ない、「心」は頭の中だけに留まるのではなく、シグナル分子によって身体全体に分配されているという事実を立証した。
P214
潜在意識は「現在」という枠組み内だけで働く。
潜在意識にプログラムされた誤知覚は、「監視」されることなく習慣として存続し、わたしたちは、不適切でしかも制限された行動に縛られることになる。
P215
環境刺激に対するわたしたちの反応は、実際、知覚によってコントロールされている。だが、学習してきた知覚のすべてが正確だとは限らない。(中略)。
知覚は、生体機能を「コントロール」しているが、いま見てきたように
、こういった知覚は正しいこともあるが間違っていることもある。それゆえ、こういったコントロールする知覚のことは「信念」として規定して名付けて、より慎重に扱わなければならない。
信念は生体の機能をコントロールする!
(わたしたちは環境刺激に対して自分がどう反応するのか、意識的に評価し、いつでも好きなときに以前の反応を変更することもできる)。