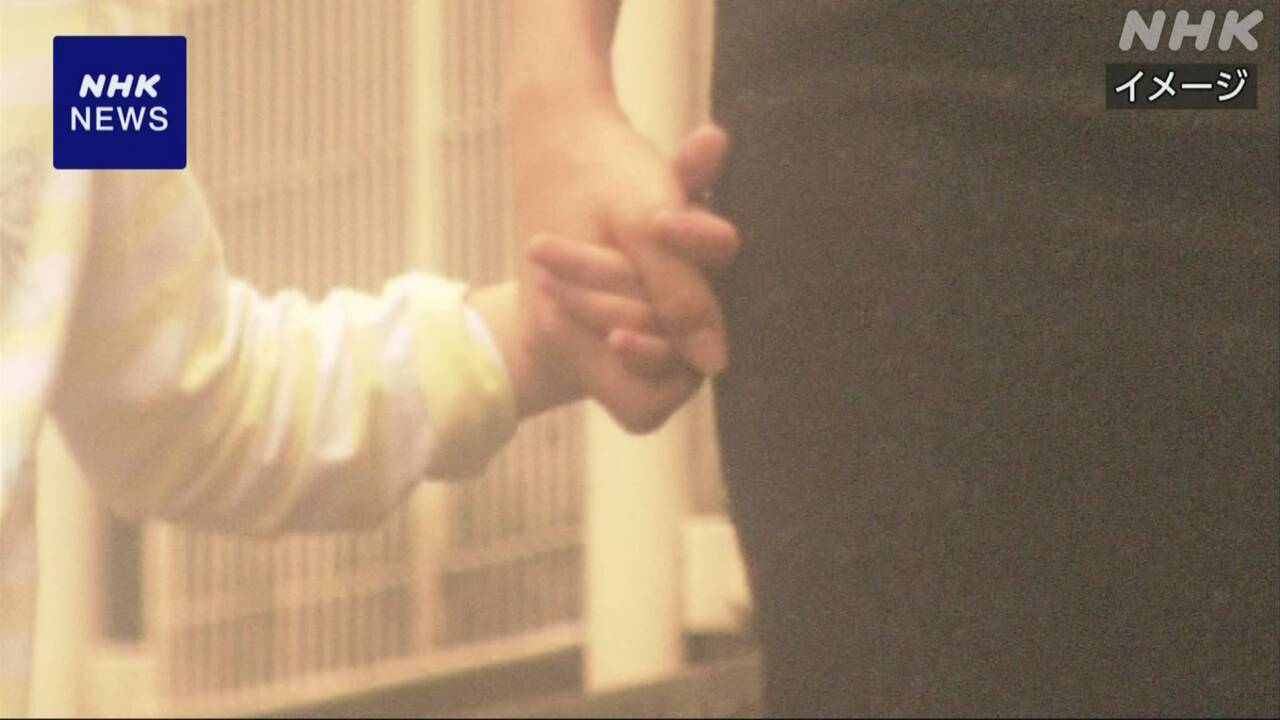ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
NHK
離婚後の「共同親権」導入へ DVや虐待の懸念など払拭できるか
離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした改正民法などが、17日に国会で成立しました。制度の運用開始に向けて、DV=ドメスティック・バイオレンスや虐待が続きかねないといった懸念や不安を払拭(ふっしょく)できるかが、課題となります。
改正民法などは、17日の参議院本会議で採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。
共産党やれいわ新選組などは反対しました。
改正法では、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
父母が協議して、共同親権か単独親権かを選び、合意できなければ、家庭裁判所が判断し、DVや子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となります。
制度の運用は、2年後の2026年までに開始される見通しです。
共同親権をめぐっては、DVや虐待が続きかねないといった懸念が根強く、国会の審議でも「精神的、経済的なDVや虐待もあり、証明が非常に困難だ」といった指摘が相次ぎました。
また、一方の親だけで判断できる「日常の行為」や「急迫の事情」についても、「具体的な行為がはっきりしておらず、子どもの利益を損ねるおそれがある」といった意見も出されました。
さらに家庭裁判所については、業務量が増えることが予想されるなどとして、国会が必要な体制の整備や職員の専門性の向上などを求めています。
小泉法務大臣は「審議の中でさまざまな課題を指摘されたので、法律の施行に向けて、これまで以上にエネルギーを注いで課題に取り組む」と述べました。
国は今後、関係する府省庁の連絡会議を設置し、制度の円滑な運用に向けたガイドラインの作成などを進める方針で、関係する人たちの懸念や不安を払拭できるかが課題となります。
家裁に重責、残る課題 対立激化で長期審理懸念 「定着に30年」の声も・共同親権
参院本会議で改正民法などが成立し、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」が2年以内に選択可能となる。
父母間で合意に至らない場合、家庭裁判所は共同親権とするかなどを判断する重責を担う。父母の対立が激化し、家裁の審理期間が長期化するなどの懸念は残り、ある判事は「制度定着まで20~30年かかるのではないか」と語る。
新制度では、共同親権選択後も子の進学や引っ越し、手術など重要な決定で父母の意見が一致しない場合、どちらが決めるかを家裁が判断することになり、役割は拡大する。
ただ、現状でも家裁の審理には時間がかかる傾向にある。司法統計によると、両親の離婚に伴って子の身の回りの世話や教育などについて決める監護者の指定を巡る審理は、2022年は平均9.0カ月(速報値)となっており、13年の6.3カ月から長期化している。
家裁関係者は、父母の対立が激しい案件の増加が背景の一つにあると指摘。要因として、妊娠・出産後も働く女性が増え、パートナーへの経済的な依存度が下がって自己主張しやすくなったことや、男性の育児参加が進んで養育の権利を求めるようになったことなどが考えられるという。
あるベテラン裁判官は「積極的に育児に関わり、子の将来を真剣に考えられるのであれば、感情的な主張は抑制されるはずだ」との見方を示す。現状については「中途半端に関わって自らの権利ばかりを求めてしまうケースもあるのではないか」と分析する。 非婚化、少子化が進み、離婚件数自体も長期的には減少している。ただ、共同親権の導入で父母間対立が激化し、家裁の負担も増す恐れは拭えない。
日弁連は「慢性的な裁判官、家裁調査官の人員不足により、審理や調査に十分な時間をかけられないなどの不都合が一層深刻になっている」と指摘。裁判官らの増員を含めた体制強化を求めている。