通常運営に戻ります。
新選組の尾形 俊太郎さんも、2013年に子孫のかたの存在が明らかにされるまでは伝説級の人でしたが、素性が明らかであってもなお半生を伝説で語られる人がいます。
その人が、今回紹介する尾形 百恵(おがた・ももえ、1881~1935ごろ)です。
奇しくも、新選組尾形さんと同じ姓のかた。でも、そもそも「おがた」(特に当て字は「緒方」)という姓は熊本には非常に多い地域姓で、発祥は豊後緒方荘(おがたのしょう、現大分県)と相場が決まっています。ついでにいうと、緒方荘のあった現緒方地区は宮崎県の高千穂や熊本の阿蘇といった神様ゆかりの地域と近い位置にあって、一族の先祖も蛇神だと伝わっている何気にすごい姓です。
おがたおがたといっても俊太郎さんは名字的には尾形ではないので、直接的に結びつくことはまぁないのでしょうけども、なんとか親戚筋くらいにはならないかと思っております。本当に安直な予想だけど。
百恵さんは鹿本郡吉松村の生まれで、俊太郎さんとは同じ郡の出身(鹿本郡は2010年に消滅)。ちなみに、百恵さんの生まれた1881年は元号でいうと明治14年。俊太郎さんこの時42歳、ご存命です。
実家は農家だったそうですが、父親が病弱だったため家督を譲っており、稼ぎ頭だった母親も早くに亡くなって生活が困窮していたといいます。
熊本市中心部にある二本木には、明治時代から戦前にかけて西日本有数といわれた巨大な遊廓がありました。中でも東雲楼(しののめろう)という名の楼閣は全国でも5本の指に入るといわれたほどで、そういった女性は最終的にはそこを目指し、色を売る。
とまぁ、ここまでは当時の世相を反映した女性の悲哀といいますか、ありがちですね。
二本木遊廓および東雲楼については小説や映像作品の題材にもたびたび使われていて、大奥やさくらん的なのがお好きなかたは『東雲楼 女の乱』(1994年)を見てみるといいかもしれません。かたせ梨乃さん・斉藤慶子さん・南野陽子さんのトリプル主演映画で、二本木の東雲楼を舞台にしています。私も若干興味があります。
↓こんなの
- 東雲楼 女の乱 [DVD]/TOEI COMPANY,LTD.(TOE)(D)
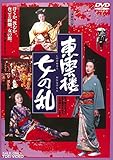
- ¥3,024
- Amazon.co.jp
ただ、私の関心はそこではなくて、またそれで話が終わっては伝承の一部にはなれど伝説にはならない。
尾形 百恵が伝説なのは、遊廓という閉じられた世界をいい意味でめちゃめちゃにし、更には日本を出て一孤島の女王となり、異国の島を統治したと綴られているからです。
これは、明治44年付の九州日日新聞(現・熊本日日新聞)に記載されている公式の記録で、百恵本人にインタビューしており、新聞記者たちも「確かに尾形 百恵なる女性は実在した」と言ったそうです。
百恵には8年の空白期間があり、その間は台湾を始め、朝鮮、シンガポール、そしてシンガポールから南へ150マイル(約240km)下った島「ヂマジア島」に渡っていたのだといいます。その「ヂマジア島」で、百恵は女王になった。
肝心の「ヂマジア島」が検索に全く引っかかってこず、実在した島の名なのかは全くもって不明ですが、「シンガポールから150マイル南」ということと、当時の日本政府の調べで「その島はオランダ領に属している」ことがわかっていることから、現スマトラ島のことをいっていることが予測できます。たびたび本を参考にさせていただいている郷土史家の勇 知之さんもそうお考えのようです。
百恵はもと二本木の遊女で、遊女になる前から強烈な個性を放っていたらしく、いわく「飽きっぽくて男のように気が強く、それでいて人を酔わせる不思議な愛敬があった」模様。むむ、なんか以前似たような人物を取り上げたことがあるような。
百恵「あたしは酒と男とスリルが大好きなのよ」(想像)
私は結局、そういう人種が好きなのよ(爆)
遊女になる前は奉公先を転々としていたそうですが、それはクビになったからではなく「飽きたから」。- 奉公先はむしろどこも大繁盛、老若男女問わず毎回ファンを作ってきて、辞めると言っても引き止められるほどなのだけれども、風のように去ってしまう。奉公先の人間が百恵を追って実家を訪ねてくることもあり、そのまま百恵の新しい職場の常連客になってしまうなんてこともあったそうです。
そして、お金が入るとそのファンたちと大豪遊してパーッと使い切ってしまう。そのある意味の“サービス”に、彼らはますます深くはまってゆく。
二本木の遊廓に入ってからもそれは同じで、楼主たちからは「こんな女が三人いると三年目には蔵が建つ」と一目置かれるほどに。しかし百恵はどこ吹く風で、飽きたからという理由であっさり遊廓を出ます。
あっさり出ますっつっても確か、遊廓ってば追手の厳しいところ。百恵のところにも当然追手が来て連れ戻されますが - 百恵「女だって人間なのだから一日や二日いなくなりたい時はある。国が亡びるわけじゃなし、それくらいでビクビクするな!」
と、逆に啖呵を切ります。するとなんと、立ち上がったのは遊廓の女性たち。
楼主に不満を募らせていた遊女が百恵の啖呵に勇気づけられ、ストライキを起こしたのです。
明治33年のことで、このストライキは東雲節として唄われ、全国的に有名になりました。
このストライキは、先ほど紹介した『東雲楼 女の乱』にも描かれているようです。
こうして女性をも一言でのぼせ上がらせた百恵ですが、百恵にとって飽きたことはもう過去のこと、ストライキのことも他人事に女衒と交渉し、一人台湾に渡ります。いわゆるからゆきさんです。
台湾へ行くことで借金を帳消しにした百恵は、遂に自由を得ます。徒歩旅行をして迷子になり、たまたま金鉱を見つけたり、朝鮮で専業主婦を経験してみたり、シンガポールで理髪店を経営してみたり。そして、理髪店の客として来た日系企業の現地日本人に接客の上手さを買われ、お得意先である島の酋長の接待を依頼されます。その島が「ヂマジア島」です。
この酋長がつまりはヂマジア島の「王」で、王に気に入られた百恵は好奇心のまま誘いに応じ、ヂマジア島に上陸。島民の生活を目にします。そして、王から「どのように立ち回れば島が潤うのか」相談されるのです。
百恵はこれまで培ってきた経営手腕を生かし、ヂマジア島に貢献します。ヂマジア島の特産物を発見してシンガポールで高く売り、薬代に充てたり。揉め事の仲裁も、回数を経るごとに裁判らしきものに洗練されていき、さながら国家の体を帯びてくるようになってきたそうな。
もちろん、そんな「モモエ体制」が面白くない者もおり、王をその座から引きずり下ろそうと目論む部族の長が島で暴動を仕掛けた際には日本刀を閃かして短銃をぶっ放し、鎮圧したという痛快な武勇伝も存在します。
これに痺れた王が百恵を正式に迎えることを決め、島民は彼女を「孤島の女王陛下」と崇めるようになった―――
このように百恵が新聞記者のインタビューに答えたのは8年ぶりに帰国した時で、またすぐにヂマジア島に戻らなければならないと言ったのだそうです。「世界のありとあらゆる物を食べてきたけれど、尾形家のだご汁に敵う物はない」と、在熊中は郷土料理でもあるだご汁を毎日食べ、以前の奉公先に行き人々に愛敬を振りまいた後、百恵は再び飄然と姿を消しました。
九州日日新聞の「南洋の美人王」記事の冒頭は「小説的の興味に富める」とあり、果たしてこれが嘘か真か、或いはどこまでが本当でどこからが嘘かわかりません。いや、このご時世きっと調べればわかるのでしょうけど、これはこれで壊したくない話じゃない。
全くあり得ない話かというと、私たちは実は似たような人生を歩んでいる人を今でもテレビで見ていたりする。私、百恵とスマトラ(ヂマジア)の王との話を読んだ時、真っ先にデヴィ夫人を想像しました。
だから、明治期ならばあり得たかも・・・って思いを馳せずにいられない。
少し野暮に突っ込んだ話をすると、百恵は昭和10年頃、帰国後移り住んだ東京大学の赤門前にあった自宅で亡くなったそうです。満州国も建国されており、もはや国民が海外に夢をみられる時代ではなくなっていました。
急激に弱っていき、晩年はもう用も一人で足せなかった、ということです。
