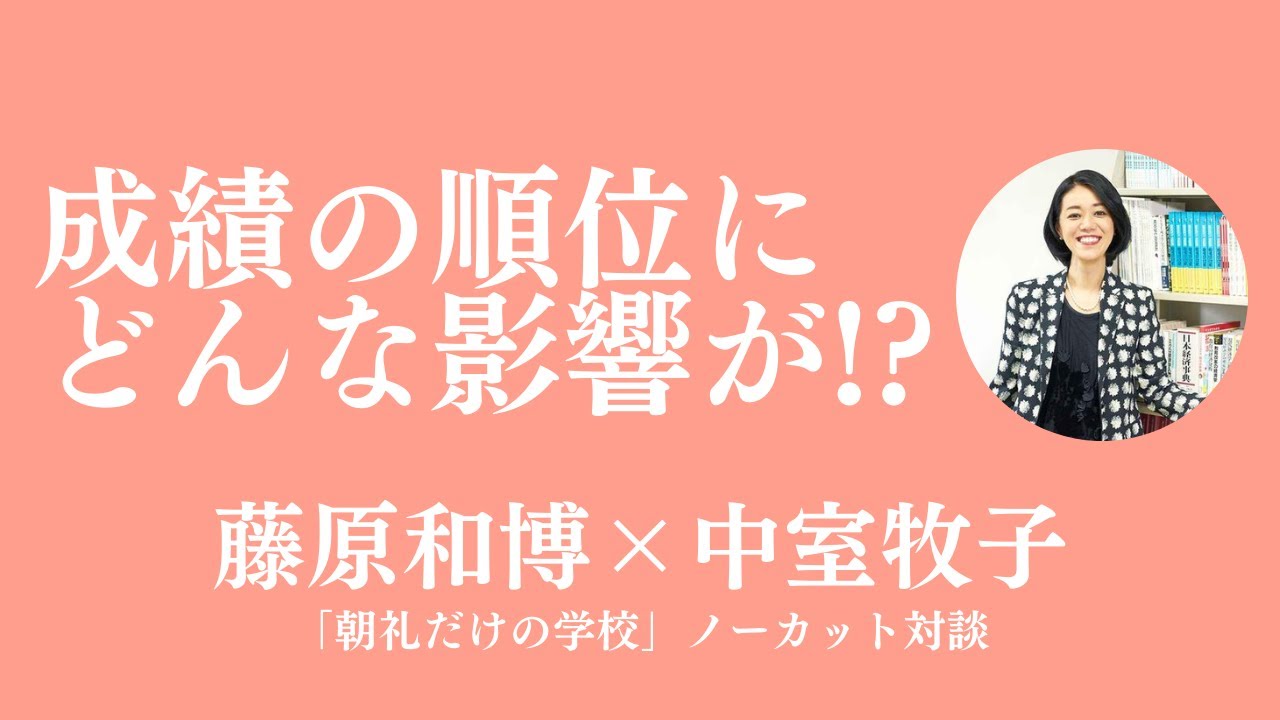先日書いたこちらのブログの補足です。
地上波の番組以外で、中学受験を話題にする番組がいくつか出てきていますが、最近で一番面白かった番組がありました。
「小さな池の大魚効果」の話を知ったきっかけの番組で、『円卓コンフィデンシャル』です。
先のブログには、論文ではなくこちらの話題を出した方がわかりやすかったかもしれません。
論文を元にこの効果を中学受験のプロたちが中学受験のその後を経験を元に語る番組でした。
出演者の方々とほぼ同じ意見を持ちました。
●“御三家”が蹴られる時代に!?最近人気が高まっている学校とは?●加速する大学の「推薦枠」拡大…変わる学校選び●「あえて第二志望」…目からウロコの理由とは? (引用)
御三家と言われる中学でも合格数が以前よりは多く出すようになったとか、補欠繰り上がりがまわるようになっているという話は耳にしていましたが、その理由分析に納得できました。
以下は番組の要約ページになります。
YouTubeの中では、私立・公立という選択や中高一貫校を選択する場合についても話を展開しています。
藤原さんも中学校長としての経験からも語っている部分もあります。
論文ではないフリートークなので、中室さんの研究を通しての得た考え方や感覚と捉えた方が良いかもしれませんが、時間があれば観てください。
経験則と照らし合わせても私は納得しています。
5分あたりから14分位までがこの埼玉県のデータから「小さな池の大魚効果」の研究を語っています。
↓
また、「日経テレ東大学」でも「小さな池の大魚効果」について話をされています(動画開始から4分40秒以降)。
こちらは少し踏み込んでいて、ビッグデータと個々人にそれを当てはめる場合の話や勉強だけでない低学年からの効果的な教育についても語られています。
進学校についての話は文字で書くと誤解もあるかもしれませんので、時間があれば観てください。
↓
人の集団を対象としたデータには、分析の難しさはいつも付き纏います。
属性的な違いや大きくどの集団を扱ったかにより、解釈に幅はでます。
個人個人の違いにも留意する必要もあること、同じデータでも、見方なかよって効果結論が変わることもあるとか。
大きなデータの中にいる個人でも必ずしもそのデータの通りではないということ。
データでいう結果はあくまでの確率論であるために、その背景にあるものやそのメカニズムを知ることが大事だと言ってもいます。
背景やプロセスをよく知っている親が、メカニズムを理解できて、方策をたてられたら、何らかの良い結果に導きやすいということだと思いました。
子育てに関しては、他人がこちらが絶対に正しいという問題ではないという見方も出来そうです。
この辺りのことも少しYouTubeの中で触れてました。
前の記事の補足を私なりにまとめると、ある程度以上というレベル感はあるものの、入学してから下位に沈むよりも、上位でいられる学校を選んだ方が長い目で見れば良いかも知れないということ。
第一志望には奇跡で合格すると、よほどの胆力や才能がないとキツく、その合格のせいで学力低迷や不登校になるケースをいくつも見てきました。
中学入試は小学生が受験生なので、その日の出来にムラがあることはあります。
一説によれば、合格者は同じ志願者で入試を行った婆、半分以上が入れ替わると言います。
もちろんこれはエビデンスはない話。
実感として、納得できる話だと思います。
何回入試をしても合格出来るような学校を実力相当校であるという見方も出来るのではないか。
合格判定模試などで1度も80%を切らないならば、上位を維持できる可能性をみることができるかなとも思います。
これから受験を迎える方には、お叱りを受けるかもしれませんが、いわゆるチャレンジ校を第一志望にしているならば、下手に合格せずに、あるいは合格しても進学せずに、第二志望を進学先として選択するのもやはりありだと思います。
ギリギリの実力で合格して、それでも下位にならない方法は一つあります。
それは中学受験の勉強と同じ分量をこなし続けることです。
難関進学校で面倒見が良くない学校の場合、勉強量はほとんどの生徒で減ります。
家庭学習ゼロという子も珍しくありません。
宿題もほとんどでないとなれば、そのようになりがちです。
そこで勉強を続けていけば順位は上がります。
みんなが遊んでいる間に実力をつけるつもりでやれたら大丈夫です。
しかし、注意点としては、親にやらされていては、周りがまた受験勉強を始めれば、簡単にさ順位は下がってしまいます。
お子さん自身が自分の意思でやることが必要ではあります。
子どもの教育というのは、個人個人の特性的な違いによって何が良かったかは異なっていくと思います。
ひとつでもより偏差値が高いいわゆる学力が高い進学校がカリキュラムが良く、切磋琢磨できる友人がいるということも、必ずしもその子にとっての正解ではないかもしれないです。
意外に知られていませんが、偏差値が高めでも、カリキュラムが大学受験向きかどうか怪しい中高一貫校だってあります。
先取りしないとか教科書つかわないとか……。
これは入学後の成績がどの位置かということ以前ですので、偏差値だけで信用せずに在校生などから情報を集めておいた方が良いです。
不登校生徒がどの程度の割合かなども併せて、リサーチしておくこともオススメします。
これは学校説明会では話題にならないことがほとんどです。
教育には圧倒的に正しいやり方は存在しないので、第二志望に進学なんかいやで圧倒的に第一志望という方がいても問題ないです。
色んな考え方があって良いと思いますし、みんなが同じやり方でも、効果結果には差が生まれます。
大学受験に向けて成績を伸ばしているお子さんについてのブログは第一志望に進学していないことが多いように感じています。
というか、有名中学受験ブログはだいたい第一志望には合格できずに終わることが多い印象だからかもしれませんが……。
今、どうしても第一志望でしんどいならば、違う考え方もあるよって、それをお伝えしたい方がいるのでつらつらとこのテーマについて書いてみました。
ブログとは「ウェブログ」の略称で、筆者(ブロガー)の日常や思想をまとめた記事を時系列で表示させるサイトのこと。
これはあくまでも私一個人の主観です。
エビデンスというよりは、経験則で書いてますので、そんな読み方をしてもらえたらと思います。
ブログではダイエット記事が人気だといいますが、ダイエットと中学受験は似ているなと思います。
ある人が10キロ痩せたいとして、その記録をつけようとそれを書く。
読んでくれた人と一緒に励まし合いながら、あるやり方で目標を達成した。
これからやろうとして読んでいた人も、それを実践してみたくなってやる人も出てくる。
でも、全員が10キロ痩せるわけではない。
ある人は全然痩せなかったと言い、ある人は20キロも痩せたと言う。
実際元々の体重も違うし、体質的なものや生活環境なども違いもある。
また、全く同じように実践した訳ではないかもしれない。
痩せなかったとしても、興味があれば、読み続けるということもあるし、痩せなかったと読むのをやめる人もいる。
痩せたとなれば、維持するために読んでくれるかもしれないし、もう必要がなくなり読むのをやめるかもしれない。
もっと自分と似た人のやり方を探して他のブログを読む人もいたり、自分の痩せた体験を同じようにブログに書いてくれる人も出てくる。
ブロガーとしては、自分の記録が終わって書くのをやめることもあれば、読んでくれる人がいて、反応してくれるとなんとなく書き続けてしまいますね。