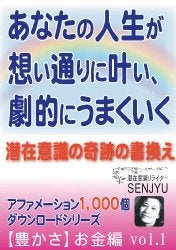欠乏感の裏にある思い込みとそのメリット:手放すべきか、活かすべきか?
スピ能力開花ティーチャー、
ZERO軸メソッドの
一源千光(いちげんちひろ)です。
私たちはしばしば、
「自分にはまだ足りないものがある」
「お金が不十分だ」といった
欠乏感や不足感に駆られて、成長や自己改善を目指します。
しかし、その成長の原動力がネガティブな感情に基づいていると、
達成しても満足感を感じにくく、
さらに「足りない」と感じ続ける悪循環に陥りやすいのです。
この記事では、欠乏感や不足感の裏にある思い込みと、
それをポジティブな原動力に変えて
持続可能な成長を目指す方法をシェアします。
欠乏感や不足感の裏にある思い込みとは?
欠乏感や不足感には、以下のような深い思い込みが隠れていることがあります
1. 自己価値の低さ
「自分には価値がない」
「他者よりも劣っている」という信念が、
無意識に欠乏感を生み出します。
この思い込みがあると、
どれだけ豊かでも「足りない」と感じがちです。
2. 制限された世界観
「資源や愛は限られている」と感じていると、
絶えず何かが不足しているように思えてしまいます。
3. 他者からの承認欲求
「他者に認められなければ自分には価値がない」という思い込みは、
周囲からの評価や承認が不足していると感じさせ、内なる充実感を妨げます。
4. 完璧主義
「すべて完璧でなければならない」
「少しでも欠点があるとダメだ」という完璧主義的な考えが、
現状に満足できず、
常に何かが足りないと感じさせてしまうことがあります。
5. 過去の経験からの刷り込み
過去の経験で「欲しいものが手に入らなかった」
「期待を裏切られた」といった経験が、
将来への不安や不足感につながっていることがあります。
6. 社会的な価値観の影響
「お金がたくさんあることが幸せ」
「地位や名誉がないと成功者ではない」
といった社会的な価値観に縛られ、
自分自身と比較して不足を感じていることがあります。
欠乏感や不足感のメリット
一見、ネガティブな感情に思える欠乏感や不足感ですが、
実はメリットもあります。
1. 成長の原動力
不足感があるからこそ、
「もっと良くしたい」
「もっと上に行きたい」という向上心となり、
自己改善を目指そうとする意欲が湧くこともあります。
2. 行動力を促す
不足しているものを補おうとする行動力、
新しいことを始めるきっかけになることがあります。
3. 共感やサポートを得やすい
共通の悩みを持つ人との共感や、
助けを求めることで人間関係が広がることもあります。
「足りていない」と感じることで、
他者からの共感やサポートを得るきっかけになることがあります。
4. 自己保護の役割
過去に失望や不安を経験した場合、
「多くを望むと傷つく」と学び、
不足している状態を好むことで期待を避け、
失望から自分を守ろうとする心理が働くことがあります。
欠乏感や不足感をポジティブな原動力に変えるメリット
欠乏感や不足感を基にした成長が、
「恐れ」や「不安」から来ているとしたら、
いずれそのエネルギー源が枯渇し、
心身に負担がかかるリスクがあります。
ネガティブな感覚をベースに成長を続けると、
達成しても「もっとやらなければ」「まだ足りない」
という感覚が繰り返され、満足感が得られにくいです。
過剰になると自分を追い詰めたり、
常に「不足している」と感じる習慣につながる可能性があります。
ポジティブな動機づけにシフトすることが心身にとっても大切です。
ポジティブなエネルギーで成長を目指すと、
以下のようなメリットが得られます
1.持続可能なエネルギー
自己愛や自己肯定から来る成長エネルギーは持続性が高く、
余計なプレッシャーをかけずに自然な成長を促します。
2.満足感と達成感が高まる
「不足しているからやった」ではなく、
「自分の可能性を広げたかったからやった」
と感じることで、深い満足感が得られます。
3.創造的な思考が促進される
ポジティブな動機づけは、
恐れや不安から来るエネルギーよりも柔軟で
創造的なアイデアを引き出し、
新たな挑戦を意欲的に支えます。
4.自己肯定感の向上
「自分は十分に価値がある」という自己肯定感が高まり、
自信を持って行動できるようになります。
5.人間関係の改善
他者との比較をやめ、
ありのままの自分を認めることができるようになり、
人間関係が円滑になります。
6.新しい可能性への開拓
「もっと」ではなく「今あるもの」に感謝し、
目の前のことに集中できるようになり、新しい可能性が開けます。
具体的なシフトの方法
欠乏感を完全に無くすことは難しいかもしれませんが、
その感情と上手に付き合っていくことは可能です。
1.自分の感情を観察する
「今、自分はなぜ不足を感じているのか?」
を客観的に観察し、その根源を探る。
2.目標を「不足感」ではなく
「喜び」や「可能性」に基づいて設定する
「これができたら楽しそうだ」
「もっと自分を活かしていきたい」
という気持ちから成長目標を設定する。
3.自己肯定の習慣を持つ
「自分はすでに価値があり、
今以上の成長はさらに自分を広げるためのもの」
という認識を持つことで、
欠乏感から解放され、自己価値を強化できます。
自分の良いところを見つけ、認め、褒めましょう。
4.今あるものに感謝する
感謝の気持ちが増えることで、欠乏感が少しずつ和らぎます。
日々の「充実感」を意識的に感じる習慣を取り入れると、
成長の基盤がより健全なものに変わります。
例えば、望む多額な金額ではなくても
財布の中に100円でも有ると思うので
「100円もある!」と感謝しましょう。
今、自分が持っているもの、できることに感謝するのです。
5.目標を設定し、小さな達成を積み重ねる
具体的な目標を設定し、
達成に向けて努力することで、
達成感や充実感を得られます。
小さな目標を設定し、達成を少しずつ積み重ねることで
「できた」「進んでいる」という充実感が増します。
例:「今日はやるべきことを1つ終わらせよう」
といった小さな目標を設定し、
達成できたら「よくやった」と自分を褒めます。
小さな達成が自信を築く積み重ねになります。
6.他人と比較しない
欠乏感は、他者と自分を比較することからも生まれやすくなります。
自分の成長や達成感は、自分自身の基準で評価するよう意識しましょう。
自分だけの価値や成果を見つけることで、
他人に振り回されない心の安定を得られます。
例:SNSなどで他人の成功を見て焦りを感じたとき、
「私が成長している部分はここだ」
「自分にはこんな良い点がある」と、
自分に焦点を戻し、感謝を感じる時間を持ちます。
7.ポジティブなセルフトークを習慣にする
欠乏感を感じたとき、
自分に対してネガティブな言葉をかける代わりに、
励ますようなポジティブな言葉を使う習慣をつけましょう。
セルフトークを変えるだけでも、
心の中で自分に肯定的な意識が生まれます。
例:「これができないからダメだ」と思ったら、
「私は成長中だ」「できるようになる途中だ」
と言い換えます。
ポジティブなセルフトークが欠乏感を和らげ、
前向きなエネルギーを引き出してくれます。
8.他者への貢献を意識する
人の役に立つことは、自己価値を強く感じさせ、欠乏感を和らげます。
感謝されたり、役に立つことを実感すると、
自分に価値があると感じやすくなります。
例:小さなことでも構いません。
家族や友人に助けを提供する、困っている人に手を差し伸べるなど、
自分の価値が感じられる行動を意識してみましょう。
9.瞑想や呼吸法で心を落ち着ける
欠乏感が強くなるときは、不安や焦りが影響していることが多いです。
瞑想や深い呼吸を取り入れて、心を落ち着けましょう。
瞑想を通じて「今この瞬間」に集中することで、
欠乏感から解放されやすくなります。
例:毎日5分だけでも、呼吸に意識を向ける静かな時間を作ります。
雑念が浮かんだら「今、ここにいるだけで十分」と自分に伝え、
心の安定を図りましょう。
まとめ
欠乏感は、決して悪い感情ではありません。
しかし、それが過度に強くなると、
心の健康を損なう可能性があります。
自分の心に正直に向き合い、自分にとって何が大切なのかを考え、
自分にあった方法で、徐々に欠乏感を卒業することがおススメです。
その過程で「ポジティブな原動力」が自分に
どれだけ良い影響を与えるかを体感できるはずです。
欠乏感が完全に無くなるわけではないかもしれませんが、
上手に付き合いながら、
より豊かで充実した日々を送りやすくなるはずです。
★プロのサポートが必要な方は、ご相談下さい。
【フォーム】からお待ちしています。
最後までお付き合い、ありがとうございます。
この記事が少しでもお役にたてましたら、
応援ヨロシク![]() お願いします。
お願いします。
一源千光・いちげんちひろ
(^人^)愛と感謝と祝福を込めて
Blessings Light Creations
∞祝福回運 研究所∞
音声ファイルの件で、ご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。
本書中の一部のURL中に、不要な「ドット」があり 修正のため訂正を、アマゾンに申請しておりますが、
微細な1部分のみのため、中々、修正の受理がされません。
お手間をおかけしますが、URLの中のドット「.」を、削除して[youtube]として下さい。
それでも、無理でしたら、誠に申し訳ございませんが amazonでの注文メール(注文番号と注文日)をコピペの上、 お問合せ下さいますようお願い申し上げます。
★音声ファイルでは、ちゃんとエネルギーを体感して頂いてます。
Copyright (C) Prakash.co.,ltd. All Rights Reserved.