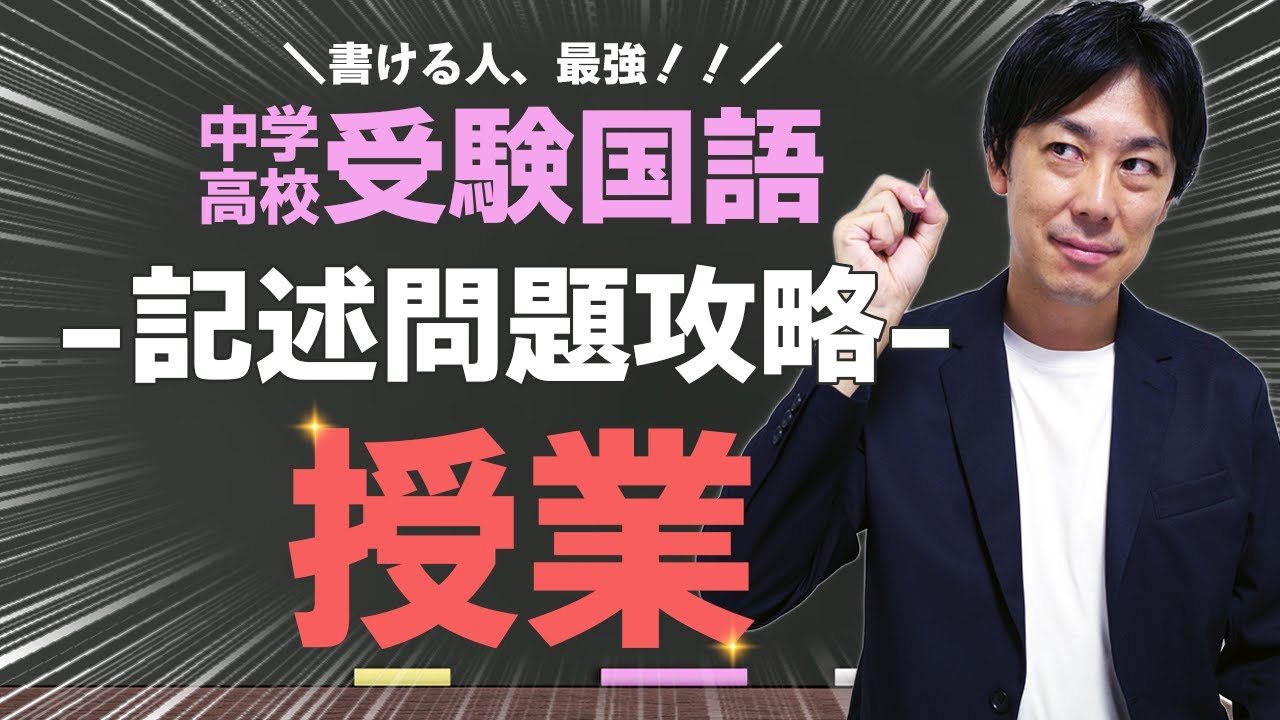昨日の続きです。
公開模試で時間切れで後半白紙だらけとなった国語に対して、てこ入れで長文読解の演習をすることにしました。
ただ、長文読解演習頑張りますー、だけでは芸がありません。
まあ、芸があるとかないとかいうことよりも、どうやって効率的に勉強して点を取れるようにするかですが![]()
そこで、今抱えている課題解決を考えながらYoutube等で研究。
受験指導専門家 にしむら先生の↓このあたりの動画が参考になりました。
1.受験国語はパターン
限られた時間で大量の文章を読んで問題を解くにはある程度雑に読む必要があり。
ただ、雑に読んで雑に解答しても得点は出来ません。
物語文でも説明文でも論説文でもある程度お決まりのパターンがあるので、なんとなくオチが想像できれば類推しならが早く文章を読むことができるようになるとのこと。
確かに似たような展開の文章が多いです。特に物語文はそうですね。
読書で国語力をつけるのは時間もかかる上に説明文などはなかなか読めないので、実際の入試の国語問題を読んでパターンを学ぶのがよいとのこと。
日能研もたしか6年生になれば入試問題が検索、ダウンロードができるようになったかと思いますが、四谷大塚は会員登録すれば無料で見ることができるので、絶対受けない学校(男子校とか地域が違う学校とか)の入試問題の文章を片っ端から読むのがよいらしい。
パターンを学ぶってのは正直そんなに簡単じゃないけど、やってみる価値は大ありです。
2.記述問題の裏技
記述は積み木方式で解く。
①まずは問われていることをに対して、最後の結びを決める
例)~どんな場合ですか?→○○な場合
~なぜですか?→○○だから
~どんな気持ちですか?→○○な気持ち
よくココは表記で減点されていたので当たり前のことですがこういうのは大事です。
②問題の文章から引用してきて結びに追加していく
③指示語(あれとかこれとか)は直して、記述回答だけでわかる文章にする。
記述もテクニックなのでこういった基本的なことを意識して解く。
1、2を踏まえて、解ききれていない栄冠問題や絶対受けない学校の入試問題の文章を読むということに取り組んでいこうと思います。
テスト時間が限られているから問題演習は15分とか20分で解く。
計算と同じく長文読解も筋トレとして毎日やる。
こつこつやっていければ成果がきっとでる勉強だと思います。
と方針はだいたい決まりましたが、5年生になってぐっと時間がなくなったので、問題は時間が確保できるかですね![]()