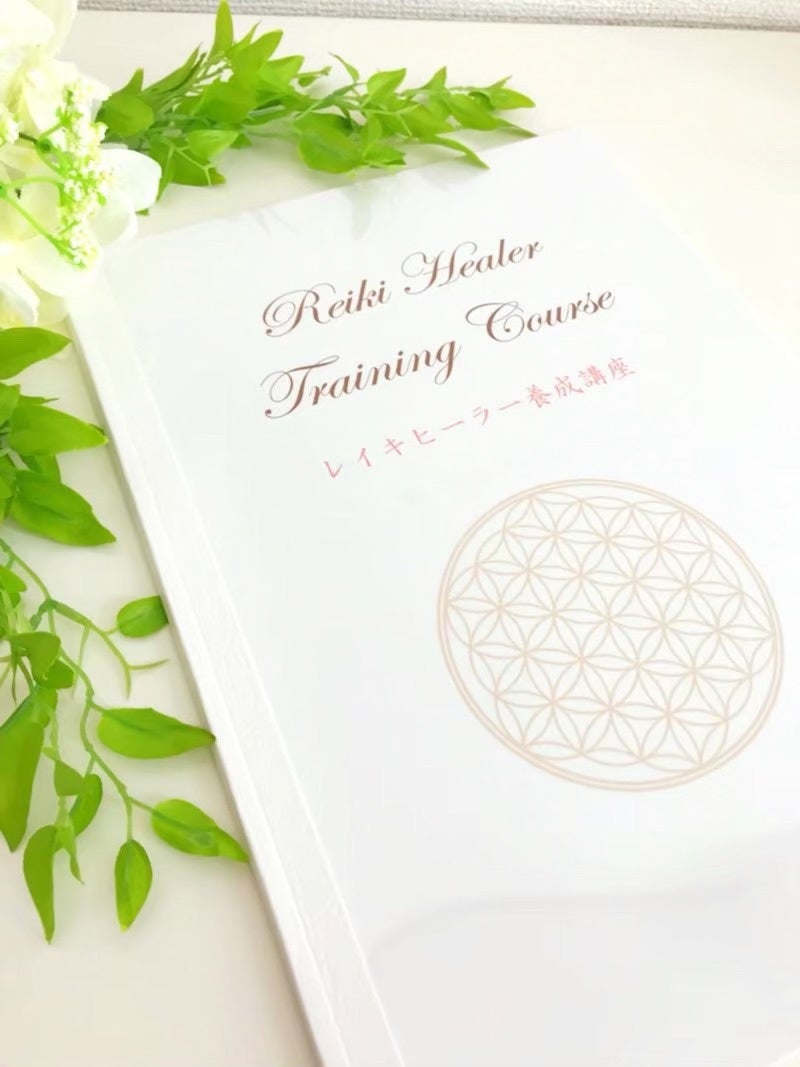天使のシンフォニー 瑛怜菜(Elena)です
いつもご覧頂きましてありがとうございます
青森県八戸市小中野にあります
「御前(みさき)神社」へ行って来ました。


【御前(みさき)神社】
青森県八戸市小中野八丁目1-19
【御祭神】
◆住吉大神(すみよしおおかみ)
・底筒男命(そこづつのおのみこと)
・中筒男命(なかづつのおのみこと)
・上筒男命(うわづつのおのみこと)
イザナギノミコトが禊をした際に誕生した三柱の神。
心身の穢れを祓い清める厄祓い神の他、
航海安全・和歌・農業・漁業の神として篤い信仰を受けています。
神功皇后が辛卯年(221年)の卯月上の卯日に、
大阪・摂津の地に住吉大社を創建されたことにちなみ、
神使(神様のお使い)は兎(うさぎ・卯)といわれています。
◆息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)
(神功皇后)
第14代仲哀天皇の皇后で、
住吉大神の御神託により、
懐妊したまま新羅遠征を行い、
凱旋後、第15代応神天皇(八幡様)を出産した「安産の神」でもあります。
◆武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)
神功皇后の功臣としてしられ、
特に新羅遠征の功により「戦いの神」として祀られています。
12代景行、13代成務、14代仲哀、15代応神、16代仁徳と5代天皇に仕えた長寿健康の忠臣で、
過去5回も肖像画に選ばれています。
(御前神社のパンフレットより)
【御由緒】
当社の主神三坐は別に住吉の大神とも称され、
古来、 航海安全・和歌・農業・漁業に関わる神として信仰崇敬されてきた。
さらに古事記・日本書紀の記するところの伊邪那岐命が、
黄泉の国の汚れを受け、
禊祓をされた時に海中より生まれなさった故事から、 身の汚れ心の汚れを祓清める神としても信仰されてきた。
社伝によると
住吉三神の教えを受けた息長帯姫命 (神功皇后) が新羅遠征の後に従者の武内宿禰を陸奥に下向させ、
新井田川の川口小浜に安着した折り、
住吉三神の神霊を受け小祠を造営したことが、 当社の誕生であったと伝えられている。
宿禰は住吉三神を三崎御前と仰ぎ、
神功皇后をもお祠りすることになる。
その後、 坂上田村磨が当社に参籠したという言い伝えもある。
古くは雷林の地名で呼ばれていた湊館鼻の地から、
平成七年秋に小中野・江陽の産土神であることとお浜入りにもゆかりある現在地に遷座造営された。
この御前神社は、



お詣りし終えると、宮司さんが出てきて、
社殿を開けて下さり、
こちらのひな人形を見せて下さいました。


そして神社の裏の方に「トトロ」があると教えて下さり、案内をして下さいました。

剪定士の方が切って下さったそうです。
新緑の季節や夏になったら、
緑のトトロになって映えそうですね。

このトトロの前で引き語りをしている女の子のYOUTUBEを見つけました。
そして宮司さんが次に教えてくれたのは、
敷地内に、
昔「下町の玉三郎」こと「梅沢富美男」さんが(売れる前に)熱心に宮司さんのお話を聞いて下さったりして、祈願されたそう。
そして、梅を植えられたそうで、
その梅も見せて下さいました。

こちらです。

春になって花が咲いたら、
また来ようと思います。

宮司さんが社殿の中に入れて下さり、
色々と説明をして下さいました。
そして社殿の中に四神が飾られてありました。
角に飾られてありましたが、
角に神が宿るという信仰があったそうです。
昔は八戸の港というのは「小中野」のことを指していたそうです。
現在は「小中野(町内名)」は「小中野」を差し、
「湊」というのは
新井田川の橋を渡って向こうの側の方「湊地区」を差します。
その証拠に、小中野地区の銀行は全部、
小中野にありながら「湊支店」となっているそうです。
それは昔の名残なのだそう。
なので、港(湊)の氏神様として舘鼻にあった場所に以前あった(引っ越す前の)御前神社は、地域の氏神様だったそうです。
御前神社の宮司さんが川口神社も兼ねているそう。
【川口神社のご祭神】
速瀬織津比賣神(はやせおりつひめのかみ)
速秋津比古神(はやあきつひこのかみ)
速秋津比賣神(はやあきつひめのかみ)
というお話をしていましたら、
宮司さんが「ケガレ」の話をして下さいました。
「ケガレ」というのは、
「汚れ」「穢れ」と書いたりしますが、
あれは違うんです。
元々日本人は「言葉」は持っていましたが、
「漢字」は持っていませんでした。
中国から入ってくることによって、
自分達と似たような発音のものなどを当てていった、とか。
そして「ケガレ」というのは、
日本人の「元氣」の「氣」が枯れてくること、
弱まってくることを「氣が枯れてくる」「氣枯れ」「気枯れ」と言ったそうです。
そして「氣が枯れずに充実していること」を
『晴れ』と言ったそうです。
川口神社はまさに禊をするための、
身体を清めるための神社であり、
川の入り口の神社だったので、
海を、漁を持ち運んでくれる神様と考えられていたそうです。
御前(みさき)神社では、
うさぎのおみくじなどが売られていましたが、

宮司さんが
「これは昨年うさぎ年で、
余ったから売っているのではないんです。
兎をお祀りしているんです」
可愛いおみくじですね。
↓こちらは宮司さんの大学の先生、
金田一京助 直筆の色紙だそうです。

金田一京助さんが文化勲章を受章した時に
昭和天皇に贈った詩で
「大君のまけのまにゝゝ国たみの
ふたたびくにをおこささらめや」
(多分こんな感じだと思います
 達筆すぎて…分かりにくいですが…)
達筆すぎて…分かりにくいですが…)
意味は、
「天皇陛下さまのお考えやお気持ちを心得た部下の人達がそれぞれ日本国中に色んな地方に広がっていって、その教えを国民一人一人に説いてまわれば、日本は再び素晴らしい国を起こさないだろうか。
必ず起こします。私はその一人として頑張ります。」
というような意味だそうです。
これを昭和天皇に詠んで、昭和天皇はとてもお喜びになられたのだそう。

金田一京助さんと石川啄木は、
盛岡で親友だったそうですが、
その話も沢山お話して下さいました。
長くなりましたので、
また今度の機会に(笑)。
では最後までお読み下さりありがとうございました。

 LINEからのお問合せも可能です。
LINEからのお問合せも可能です。
◆公式LINE

@elena358




【作品参考一覧】
パワーストーンブレスレット
サンキャッチャー
オルゴナイト
フラーレン
アクセサリー・ヒーリング雑貨
そしじ・書道作品アイテム











![]()
 LINEからのお問合せも可能です。
LINEからのお問合せも可能です。