※ 記事の更新がないときは、過去記事、もしくは、右下のツイッターに科学ニュースなどを載せていますので、そちらをお楽しみください。
アトピー性皮膚炎は
子どもの1割がかかっているとされ、
成長とともによくなる傾向があります
アトピーは、英語で atopic
その語源はギリシャ語で
「捉えどころのない」「不思議な」
を意味する「アトポス(atopos)」
に由来します
topos が「場所」で、
その前の a は否定を意味するため
atopos で「捉えどころがない」
となります
日本皮膚学会での診断基準は
1.痒みがあること
2.特徴的な発疹と分布
3.慢性・反復性経過
原因はまだ解明されていません
この度、
慶應義塾大学の研究グループが
新たな発見をしました
Kobayashi et al. (2015)
"Dysbiosis and Staphyloccus aureus Colonization Drives Inflammation in Atopic Dermatitis"
Immunity 42(4): 756-766.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2015.03.014
ちなみに、
Immunity という専門誌は、
免疫学関連の学術雑誌で
Impact factor が20くらいの
かなり権威のある雑誌です
皮膚の表面や、腸などには
目に見えない細菌がたくさんいて
それらをまとめて常在菌と呼びます
常在菌がいてくれるお陰で
病気を引き起こす菌が増えにくく
なっています
アトピー性皮膚炎が進行すると
皮膚表面にいる細菌の種類が減り、
過半数が黄色ブドウ球菌になることが
分かっていましたが、
詳しいことは分かっていませんでした
慶大グループは、
アトピー性皮膚炎を発症するマウスに
皮膚細菌を付けたところ、
黄色ブドウ球菌 と C. bovis という
異常細菌に占められました
アトピー性皮膚炎を発症するマウスで
離乳直後から異常細菌に効く抗生物質を
持続的に投与したところ、
常在菌が保たれていて、
皮膚炎も発症しなかったとのこと
つまり、
常在菌がその多様性を保つような
仕組みさえ整えてあげたら
アトピー性皮膚炎の発症が
抑えられるのではないかという
可能性が出てきたのです
著者らも言っている注意点があります
今回の実験で、
抗生物質で異常細菌を抑えましたが、
実際には、2種類の抗生物質を
数週間単位で長期投与するという
腸内細菌への悪影響も充分に考えられる
方法ですので、
今回の実験をすぐにヒトで試すのは
現実的ではありません
現在の治療方針としては、
ステロイド剤で炎症を抑えるのが
主流ですが、
アトピーで異常細菌が増えてバランスが
崩れた皮膚細菌の分布を
正常化するという新しい治療戦略が
登場するかもしれませんね
慶應義塾大学のプレスリリース
(おしまい)
文:生塩研一
お読みいただきまして、ありがとうございました。
リクエストやコメントもお待ちしています。お気軽にどうぞ~!
対応できない場合はごめんなさい。。
このブログはランキングに参加しています。
私の順位を見てみたい方、応援してくださる方は、
下のバナーをクリック
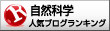
自然科学 ブログランキングへ

にほんブログ村
Facebook の「いいね!」も嬉しいです!
Twitterもやってます

アトピー性皮膚炎は
子どもの1割がかかっているとされ、
成長とともによくなる傾向があります
アトピーは、英語で atopic
その語源はギリシャ語で
「捉えどころのない」「不思議な」
を意味する「アトポス(atopos)」
に由来します
topos が「場所」で、
その前の a は否定を意味するため
atopos で「捉えどころがない」
となります
日本皮膚学会での診断基準は
1.痒みがあること
2.特徴的な発疹と分布
3.慢性・反復性経過
原因はまだ解明されていません
この度、
慶應義塾大学の研究グループが
新たな発見をしました
Kobayashi et al. (2015)
"Dysbiosis and Staphyloccus aureus Colonization Drives Inflammation in Atopic Dermatitis"
Immunity 42(4): 756-766.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2015.03.014
ちなみに、
Immunity という専門誌は、
免疫学関連の学術雑誌で
Impact factor が20くらいの
かなり権威のある雑誌です
皮膚の表面や、腸などには
目に見えない細菌がたくさんいて
それらをまとめて常在菌と呼びます
常在菌がいてくれるお陰で
病気を引き起こす菌が増えにくく
なっています
アトピー性皮膚炎が進行すると
皮膚表面にいる細菌の種類が減り、
過半数が黄色ブドウ球菌になることが
分かっていましたが、
詳しいことは分かっていませんでした
慶大グループは、
アトピー性皮膚炎を発症するマウスに
皮膚細菌を付けたところ、
黄色ブドウ球菌 と C. bovis という
異常細菌に占められました
アトピー性皮膚炎を発症するマウスで
離乳直後から異常細菌に効く抗生物質を
持続的に投与したところ、
常在菌が保たれていて、
皮膚炎も発症しなかったとのこと
つまり、
常在菌がその多様性を保つような
仕組みさえ整えてあげたら
アトピー性皮膚炎の発症が
抑えられるのではないかという
可能性が出てきたのです
著者らも言っている注意点があります
今回の実験で、
抗生物質で異常細菌を抑えましたが、
実際には、2種類の抗生物質を
数週間単位で長期投与するという
腸内細菌への悪影響も充分に考えられる
方法ですので、
今回の実験をすぐにヒトで試すのは
現実的ではありません
現在の治療方針としては、
ステロイド剤で炎症を抑えるのが
主流ですが、
アトピーで異常細菌が増えてバランスが
崩れた皮膚細菌の分布を
正常化するという新しい治療戦略が
登場するかもしれませんね
慶應義塾大学のプレスリリース
(おしまい)
文:生塩研一
お読みいただきまして、ありがとうございました。
リクエストやコメントもお待ちしています。お気軽にどうぞ~!
対応できない場合はごめんなさい。。
このブログはランキングに参加しています。
私の順位を見てみたい方、応援してくださる方は、
下のバナーをクリック

自然科学 ブログランキングへ
にほんブログ村
Facebook の「いいね!」も嬉しいです!
Twitterもやってます
