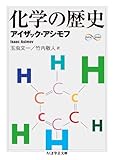 | 化学の歴史 (ちくま学芸文庫) 1,512円 Amazon |
今年、秋、ありました???
気づいたら冬になっていて困惑している管理人です。なんだか年々「秋」の存在感が薄れて行っている気がします。いつ焼き芋を食べればいいのか、いつ栗ごはんを炊けば良いのか。いつ「あーきのゆうひーにー」と歌えば良いのか。
さて、本日の本はアシモフ『化学の歴史』です。
先日読んだ『タングステンおじさん』があまりに面白くて、もっと化学の発見の歴史を詳しく知りたいと思って手に取りました。アシモフと言えばロボット三原則に代表されるSF作家としての顔や、黒後家蜘蛛の会などのミステリー作家としての顔が有名ですが、彼は生化学の研究者でもあるんですよね!(むしろこっちが本業なのか?)彼の筆力にかかると、ややもすると退屈に思いがちな化学の歴史が、なんともドラマチックなものに変わります。
副題に『プロメテから原子力まで』とあるように、本作は古代から20世紀中盤あたりまでの化学の発見の歴史をわかりやすくまとめたものです。『タングステンおじさん』の記述とも被るところがあったので、楽しく読むことができました。
特に、今ではその考え方が否定されている「フロジストン」という燃焼に関わる概念のお話はとても面白かったです。確かに空気中の何かが物質と反応するなんて、分かりませんものね。
他には、原子の構造が分かったのって、ここ最近のことなんだ!ということに驚きました。いまの化学の授業では、最初の方で原子の構造を習うと思います。でも、実際にはα線や中性子線などの放射線が発見されて、やっとわかったことだったんですね。化学を教科書で勉強することもとても大切だけれど、こういった副読本で研究の過程を勉強することも楽しいことだなと思いました。
『タングステンおじさん』が、思い出や主観を交えた自伝的な化学史だったのに対し、アシモフの記述は客観的ですこし淡泊に感じました。しかし、発見の歴史の素晴らしさは色あせずに伝わってきます。良書だと思います。