ミステリーの毒を科学する―毒とは何かを知るために (ブルーバックス)/講談社
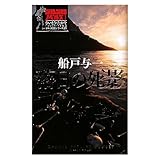
¥797
Amazon.co.jp
本日の本は、推理小説・理科ネタ!
山崎昶さん『ミステリーの毒を科学する』です。最近はまっているブルーバックスの本です。(アフィリエイトの画像、表紙が何故か違います……なぜだろう……)
推理小説に毒物はつきもの。『ローマ帽子の秘密』のあの人も、『火刑法廷』のあの人も、『Xの悲劇』のあの人も、名作あるところに毒物あり。でも、私たち素人はその毒物がどんなものだかよくしりません。
「ペロ……これは、青酸カリ!」なんてことは本当に出来るのか。推理小説常連の青酸カリ、アコニチン、ニコチン、モルヒネに始まり、そんなもので人を殺せるの!?というものまで、古今東西の毒物の流行廃り、その正しい使い方(?)を東京大学理学部化学科卒業の作者が面白く読ませてくれます。
第一章では、「これが毒になるの?」というものを紹介。アンモニア水・水・炭酸ガスなど「毒」から少し離れた化合物が紹介されています。炭酸ガスというのは一酸化炭素のことですね。昔は都市ガスに一酸化炭素が含まれていたからそれを充満させて人を殺せたそうですが、今はそんな事ないのでちょっと気分が悪くなって終わりなんだとか。
第二章では身近な毒物が紹介されています。推理小説に使われる毒物って時代を反映させてるものが結構ありますよね。例えば四鉛化炭素という物質は、水には溶けないそうで、お酒に混ぜないと人を殺せないんですね。しかも大量に入れないと殺せない。そんなお酒を現代出されたらさすがに怪しいなって思っちゃいます。
でも『ウーザック沼の死体』という作品が書かれた禁酒法時代。みんなあの手この手で似非お酒を作って飲んでいたんですね。だからこんな毒物でも殺す事が出来たという訳。
青酸カリの項では「ペロ……これは青酸カリ!?」のあのシーンを考察するに足る情報が書いてました。青酸カリは皮膚にちょっと付着したぐらいでは死なないんですね。150mg~200mgも食べさせなきゃならない。どれくらいの量かっていうと写真を感じでは小さじ一杯くらいありました。ペロっと嘗めたくらいでは死なないようです。あの体は子供、頭脳は大人の眼鏡坊主は大丈夫です。
第三章ではメジャーな化合物が紹介されています。ヴィクトリア時代好きとしては阿片の頁が面白かったですね。阿片ってOpium(オピアム)という英語に中国語を当てたものなんですが、世界史なんかではアヘン戦争って書きますよね。でもわざわざカタカナ表記にするならオピアム戦争にしろよっていう人もいたのだとか。
今でこそ麻薬のイメージが強い阿片ですが、昔は阿片チンキという家庭薬だったそうです。ホームズかフランケンシュタインで瓶の薬を口にする描写があった気がします。
さて、最後の章では存在しない毒・不明な毒が紹介されています。かの『ハムレット』で父親を殺した毒物は一体なんであるのか?等歴史的に謎な毒物が検証されています。
大変面白く読めました。推理小説って毒の種類が犯人の特定につながる事はほとんどないですが、だからこそ作家さんの個性が出るのだと思います。ミステリ・毒好きにはおすすめです。
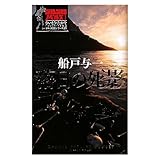
¥797
Amazon.co.jp
本日の本は、推理小説・理科ネタ!
山崎昶さん『ミステリーの毒を科学する』です。最近はまっているブルーバックスの本です。(アフィリエイトの画像、表紙が何故か違います……なぜだろう……)
推理小説に毒物はつきもの。『ローマ帽子の秘密』のあの人も、『火刑法廷』のあの人も、『Xの悲劇』のあの人も、名作あるところに毒物あり。でも、私たち素人はその毒物がどんなものだかよくしりません。
「ペロ……これは、青酸カリ!」なんてことは本当に出来るのか。推理小説常連の青酸カリ、アコニチン、ニコチン、モルヒネに始まり、そんなもので人を殺せるの!?というものまで、古今東西の毒物の流行廃り、その正しい使い方(?)を東京大学理学部化学科卒業の作者が面白く読ませてくれます。
第一章では、「これが毒になるの?」というものを紹介。アンモニア水・水・炭酸ガスなど「毒」から少し離れた化合物が紹介されています。炭酸ガスというのは一酸化炭素のことですね。昔は都市ガスに一酸化炭素が含まれていたからそれを充満させて人を殺せたそうですが、今はそんな事ないのでちょっと気分が悪くなって終わりなんだとか。
第二章では身近な毒物が紹介されています。推理小説に使われる毒物って時代を反映させてるものが結構ありますよね。例えば四鉛化炭素という物質は、水には溶けないそうで、お酒に混ぜないと人を殺せないんですね。しかも大量に入れないと殺せない。そんなお酒を現代出されたらさすがに怪しいなって思っちゃいます。
でも『ウーザック沼の死体』という作品が書かれた禁酒法時代。みんなあの手この手で似非お酒を作って飲んでいたんですね。だからこんな毒物でも殺す事が出来たという訳。
青酸カリの項では「ペロ……これは青酸カリ!?」のあのシーンを考察するに足る情報が書いてました。青酸カリは皮膚にちょっと付着したぐらいでは死なないんですね。150mg~200mgも食べさせなきゃならない。どれくらいの量かっていうと写真を感じでは小さじ一杯くらいありました。ペロっと嘗めたくらいでは死なないようです。あの体は子供、頭脳は大人の眼鏡坊主は大丈夫です。
第三章ではメジャーな化合物が紹介されています。ヴィクトリア時代好きとしては阿片の頁が面白かったですね。阿片ってOpium(オピアム)という英語に中国語を当てたものなんですが、世界史なんかではアヘン戦争って書きますよね。でもわざわざカタカナ表記にするならオピアム戦争にしろよっていう人もいたのだとか。
今でこそ麻薬のイメージが強い阿片ですが、昔は阿片チンキという家庭薬だったそうです。ホームズかフランケンシュタインで瓶の薬を口にする描写があった気がします。
さて、最後の章では存在しない毒・不明な毒が紹介されています。かの『ハムレット』で父親を殺した毒物は一体なんであるのか?等歴史的に謎な毒物が検証されています。
大変面白く読めました。推理小説って毒の種類が犯人の特定につながる事はほとんどないですが、だからこそ作家さんの個性が出るのだと思います。ミステリ・毒好きにはおすすめです。