こんにちは。やっと、3年生の前期を終えました。これから2か月間の夏休みはバイトや旅行を楽しもうと思います。
前にも記事にしましたが、ハンガリー国立大学に友達が通っているので、夏休みはその友達を訪問しようと思っています。
今日は医学部の入り方の王道といえる『一般入試』についてかこうと思います。この入試制度が一番一般的ですが、一般的であるので実は一番書きにくく、後回しにしていました。
書きたいことはたくさんありすぎてまとまらくなってしまうので、簡潔に書くことにします。
そして、また次回に細かいことをかこうと思います。
<一般入試とは>
一般入試とは、多くの人が大学受験と言われたときに一番最初に思いつく入試方法です。
国公立大学であれば、年明けにセンター試験を受けて、その後、大学の個別試験を受けるというもので、私立大学であれば、2月3月に大学に筆記試験を受けるというものです。
医学部に入る人の9割以上がこの一般入試によって入ってくると思います。
<出願条件>
受験資格は、高校を卒業している、または見込みがある(現役生で卒業が確約されている)、もしくは高校を卒業程度の学力が認められている必要があります。
なので日本の高校を卒業していれば受験が可能です。高校を中退したもしくは高校に行っていないという人は、大学入学資格検定に合格すれば受験が可能です。
<合否判定>
国公立大学と私立大学では大きく異なります。また、大学によってもその判定基準が大きく異なります。
次回以降にそれぞれ詳しく説明します。なので今回はざっくり書きます。
①国公立大学
センター試験の結果+大学の個別試験の結果(筆記試験、小論文、面接)
で合否が判定されます。ただ、大学の個別試験はその大学で行い、また、また問題も記述で採点に労力がかかることもあり、あまりに多くの人が受験すると、その受験させる場所がなかったり、採点がしきれないので、センター試験の結果で1次選抜を行う大学が多いです。
②私立大学
筆記試験+面接や小論文
で合否を判定します。筆記試験は出願をすれば受けることができます。100人の定員に3000人程度が出願します。そのために多くの大学は、筆記試験は大学ではなく、貸会議室で行います。(この会場として有名なところとしては、五反田のTOCビルです。幕張メッセでやる大学もあります。)
この人数の採点をするため、マーク式の大学が多いです。この筆記試験の結果で2次試験に進むことができるかが、決まります。
2次試験は大学で行われます。ここでは面接と小論文というパターンが多いです。しかし、この小論文や面接は厳密な点数化というよりは段階評価である印象を受けます。2次試験で逆転とかといったことはなく、1次試験ができた人が結局合格しているという印象を受けました。
<倍率>
これも国公立大学と私立大学で異なります。
①国公立大学
国公立大学では前期日程と後期日程があります。
一般入試の定員のほとんどを前期日程でとるので、枠が多いので、前期日程のほうが倍率は低くなります。
倍率は大学、年度でも大きく異なりますが、2倍~10倍程度になります。ですが、上でも説明した通り、会場の面からセンター試験の結果で個別試験の受験資格を定員の3倍~10倍までの人数にしか与えないという大学も多いです。これは足切りと呼ばれるのですが、この足きりを厳密に行う大学もあれば、定員の3倍までとすると書いてあっても、その40人くらい多い人数まで受けさせてしまう大学もあります。
一方で、後期試験は募集している人数が少なく、そもそも後期日程を設けている大学は少ないです。そのために枠が少ないので、とても倍率が高くなります。
10倍~30倍にもなります。ですが、これは見かけ上の数字になります。なぜかといいますと、後期日程は受験しに来ない人が多いからです。
これは、出願を前期日程と後期日程の出願が同時に行われるからです。たいていの人が前期日程と後期日程の両方に出願します。そのために、前期日程で合格してしまった場合は受けに来ないからです。そのために願書だけは出した、受験会場に来ない受験者が多いんです。
②私立大学
大学によりますが、20倍~50倍になります。
2次試験では、5倍~10倍までに選抜されます。
今回はここまでにします。お読みいただきありがとうございました。
次回から国公立大学と私立大学と別に書いていこうと思います。
ではまた✋
 |
全国医学部最新受験情報 2020年度用
2,750円
Amazon |
 |
医学部に入る 2020 (週刊朝日ムック)
1,404円
Amazon |
 |
「医学部に行く!」と決めたらまず読む本 2020年版 (日経ムック)
1,430円
Amazon |
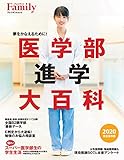 |
プレジデントFamily 医学部進学大百科 2020完全保存版 (プレジデントムック)
1,760円
Amazon |
 |
現役ドクターが教える! 医学部合格への受験戦略・勉強法
1,540円
Amazon |