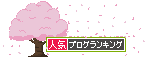「国難」とも評された東日本大震災が起こってから二年が経過した。
いまだ三十一万人ほどが住み慣れた土地から離れることを余儀なくされ、仮設住宅や民間の借り上げ住宅などで暮らしているという。津波によって震災前の街並みが跡形もなく押し流され、復興の見通しがなかなか立たぬまま更地と化した東北沿岸部の様子も伝えられている。
この間、テレビ番組や新聞報道ではたしかに、節目節目に「あの日を忘れない」などと銘打って、被災地の様子、避難生活を余儀なくされている人びとの様子などが、被災地ではない地域の人びとに伝えられてきた。
だがその一方で、マス・メディアの次元において日を追うごとに目立つようになったのは、この国の人びとが「大騒ぎ」するためのニュースが時々に移り変わっていく模様ではなかったか。
オリンピックが始まれば、震災前と変わらず、日本選手がいくつメダルを獲得したかといった報道が国民の関心事となった。解散総選挙が実施されるとなれば、どの政党がどれほどの議席数を獲得するかといった選挙予想に終始し、政権交代がなされるか否かに国民の注目が集まった。
安倍政権による景気回復への国民の期待の高まりが伝えられたかと思うと、次には、2020年の東京へのオリンピック招致に、そして野球の国際大会で日本チームが三連覇を達成するかどうかに、この国の人びとは一喜一憂している。
こうした何の脈絡もないかのような国民による数々の「大騒ぎ」を見ていると、二年前に誰も彼もが日本人の「絆」や「つながり」の大切さを事あるごとに強調し、被災した人びとと「ともにある」ことを確認していたのはいったい何であったのだろうかと疑いたくもなる。
もっとも、それぞれの「大騒ぎ」には、必ずといってよいほど、「被災した人たちを勇気づける」だの、「震災復興のため」だのといった、被災地を忘れているわけではないことを強調する決まり文句が付けられはする。
だが結局のところ、この国の人びとの多くは、他の人たちと群がって大騒ぎすることができる素材が、皆と同じであるという一体感を確認できる事柄が、どこからか与えられるのを日々待っているだけなのであろう。
被災地の人びととの間だけでなく、震災の前からすでに国民間の「絆」も「つながり」も断たれ、「国民であること」の自覚を持ち得ない不安が、人びとを日々の「大騒ぎ」に駆り立てているのだと思われる。
本来問うべき事柄は、まず、「国民であること」の自覚を持ち得ない不安が何に由来するのか、ということのはずだ。
『表現者 平成25年5月号』 黒宮一太