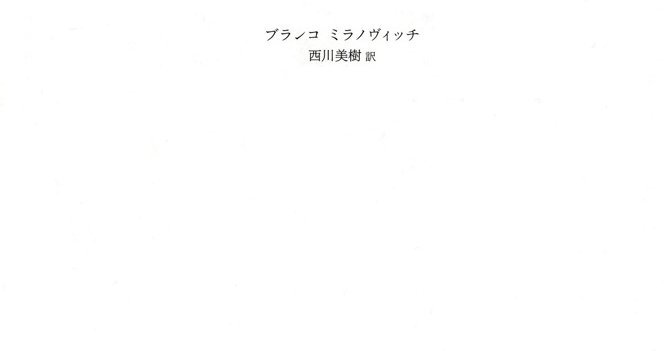1.ミラノビッチが描く資本主義の形
前回のブログでミラノビッチが描く資本主義の5つの形を載せるのを省略した。
ミラノビッチの場合、経済学者が使う通常の分類とは異なる。「古典的自由主義」「ケインズ主義」「新自由主義」「新ケインズ主義」というような経済政策の原則のような分類は用いていない。
ここで最後に、欧米の資本主義社会のこれまでの発展について要約し、未来に何か起きるかを推測してみよう。最初に、現存する三つのタイプのリベラル資本主義(第2章で定義した)、さらに現実には存在したことのない仮説上の二つのタイプ、すなわち民衆資本主義と平等主義的資本主義について概説する。それから、私たちがこの二つのタイプのどれかひとつを達成するために役に立つと思われる政策について説明しよう。
・古典的な資本主義
労働者は労働のみから収入を得て、資本家は資本のみから収入を得て、すべての資本家はすべての労働者よ りも裕福である。すなわち、労働者と資本家の所得分配が重複しない。課税と移転を介した再分配はきわめて最小限のものにすぎない。個人間の不平等は大きい。富の優位性は世代間で継承される。この資本主義のかたちはリカードーマルクス型資本主義とも呼ばれる。
・社会民主主義的な資本主義
労働者は労働のみから収入を得て、資本家は資本のみから収入を得るが、すべての資本家がすべての労働者よりも裕福とはかぎらない。無償もしくは利用可能な医療と教育を含めた課税と移転を介し、かなりの再分配が存在する。個人間の不平等は中程度である。教育に比較的平等にアクセスできることから、世代間の所得移動性が確保される。
・リベラル能力資本主義
ほとんどの人は労働と資本の双方からいくらか収入を得ている。資本所得の割合は所得水準とともに上昇し、大金持ちの場合、ほとんどが資本所得である。だが超富裕層(たとえば上位5%)もかなりの労働所得を得ている。社会が豊かになるにつれて資本の割合が上昇すること、また同じ個人のなかで高い資本所得と高い労働所得が結びつくことが、個人間の不平等の拡大につながる。課税と移転の制度によって総所得のかなりの部分が再分配されるが、私立教育や医療への投資を金持ちが好んで選択することで、社会的分離主義がますます重みを持ってくる。世代間の移動性は社会民主主義的な資本主義よりも低い。
・民衆資本主義
誰もが資本所得と労働所得をほぼ等しい割合で得ている。それでも人びとの所得には差がある。ある者は、資本所得と労働所得のどちらもより多く得ている。資本の割合が増えることは、個人間の不平等の拡大にはつながらず、不平等の上昇傾向は見られない。直接の再分配は限られるが、無償の医療と教育が世代間の所得移動性を促す。
・平等主義的資本主義
誰もが資本所得と労働所得の双方をほぼ等しい量で受けとるため、資本の割合が大きく伸びても不平等の拡大にはつながらない。個人間の不平等は低い。再分配における国の役割は社会保険のみに限られる。所得が比較的平等であることは、機会の平等を保証する。リバタリアニズム、資本主義、社会主義がたがいに近づく。
きわめて抽象的ではあるが、資本主義がいかに進化していくかという問いは。リベラル能力資本主義がもっと進化した段階、つまり民衆資本主義の段階に移行できるか否かにかかっている。民衆資本主義では、(1)資本所得の集中(ならびに富の所有の集中)がより少なく、(2)所得の不平等がより縮小し、(3)世代間の所得の移動性がより高くなるだろう。また最後の点は永続的なエリート層の形成を防ぐことにもつながる。この資本主義に移行するには-こうした移行が好ましいとわかれば-たとえそれがどんなに優れた意図を持つ、どんなに優れた設計のものであっても、漸進的な政策を採用するだけでは十分でない。測定可能な明確な目標を念頭に置くことが重要である。民衆資本主義か平等主義的資本主義のどちらかを目標にするならば、その目標に向かった進歩の度合いを測定することはわりと簡単で、今日私たちが持つ知識と技術を使えば可能である。進歩をチェックする最も重要な二つの目安とは、富と資本所得の集中が減少しつつあるか、そして世代間の(相対的)所得の移動性が改善しつつあるかどうか。どちらも長期的な指標であり、毎年の変化にはあまり意味はないかもしれない。それでも、このように目標を定め、数年ごとに前進しているかどうかを測ることはできるだろう。
この目標に向かって進むための政策は、そのすべてをこれまでの章で説明してきたが、それらは比較的簡単なものであり、次の四つにまとめることができる。
1 中間層を対象に、とくに金融資産と住宅資産のアクセスに税制上の優遇措置を設け、それに応じて富裕層に増税し、さらに相続税率を再び引き上げる。目的は、富裕層の手にわたる富の集中を減らすことにある。
2 公教育の予算を顕著に増やし、その質を改善する。公教育の費用は中間層だけでなく所得分布の下位30%に入る人びとも利用できる程度まで下げなければならない。目的は、世代間の優位性の継承を減らし、機会の平等化をより現実のものにすることにある。
3 市民と非市民との二者間の強固な分断をおそらく終わらせる「軽い市民権」を導入する。目的は、ナショナリストの反発を招くことなく移民を許可することにある。
4 政治運動への資金提供を厳しく制限し、出所は公的資金のみに限定する。目的は、富裕層が政治プロ七スを牛耳り、永続する上位層を形成する力を弱めることにある。
『資本主義だけ残った』p.255~258
現在、人類の到達点は「リベラル能力資本主義」であるというミラノビッチの理解だ。
今後、資本所得と労働所得の割合と社会的な再分配の視点で、所得の格差がある「民衆資本主義」、個人間の不平等が低い「平等主義的資本主義」をミラノビッチは描いている。
どちらも不平等の拡大にはつながらない世界だ。
今後、リベラル能力資本主義はそういう社会を目指すと予測している。
社会主義というイデオロギーも生産手段の私的所有の廃止とも無縁の世界だ。
2.アセモグルとロビンソンが捉える中国の未来
ブランコ・ミラノビッチは、中華人民共和国のことを政治的資本主義と「資本主義」のカテゴリーで考える。
そして、この体制はソ連のように早々には滅びないのだという。
ダロン・アセモグルとジェイムズ・A・ロビンソンが『国家はなぜ消滅するのか』(早川書房)で、中国は、民主化しないかぎり、収奪的制度の国が技術革新できないとされる技術水準に達したとたんに衰退するはずで、ソ連のように滅びると書いている。
ミラノビッチはそれを批判しているのだ。
アセモグルとロビンソンの中心的な考えのひとつは、「収奪的」制度というものだ。それは経済的資源を収奪し、政治権力を集中させることを目的としてエリート層が支配する政治経済的制度のことで、そこでは政治的な力と経済的な力がともに発生し、たがいを強化し合う。だがこの考え方は共産主義についてはうまく処理できていない。共産主義では政治的な力と経済的な力はせいぜいきわめて弱くつながっているにすぎない。
アセモグルとロビンソンの説に従えば、共産主義国で見られる政治的な力の集中は、経済的な力にも集中をもたらすはずだ。ところが、これは共産主義体制下では明らかに事実ではなかった。さらに経済的な優位性は、いったん獲得されても世代間でいかなる有意なかたもでも継承されなかった。
したがって共産主義という、そのもとで20世紀の半分以上を世界人口の3分の1が過ごしたシステムが、彼らの説からはほぼそっくり抜け落ち、それについて説明できていない。さらに中国とヴェトナムの経済的成功も説明されていない。これらの社会は、アセモグルとロビンソンが「包摂的」制度と呼ぶもの-すなわち人びとが広く経済活動に参加でき、法の支配のもとに運営され、著者らによれば経済成長に不可欠とされるもの-を持ってはいないが、それでもこの二国は世界屈指の成長を記録し、中国の最近の記録は人類史上最高のものだ。そのためアセモグルとロビンソンは『国家はなぜ衰退するのか』で、こうした国々の成長は永久に続くことはありえないし、もっと具体的に言えば、中国は民主化しないかぎり、収奪的制度の国が技術革新できないとされる技術水準に達したとたんに衰退するはずだと主張し、こうした国々の成功を否定するはかなかった。
「中国は最終的には衰退するに違いない」とのこの歴史観は、何ものも永遠には続かないといった退屈な道理を語る以外すこぶる説得力を持たない。
『資本主義だけ残った』p.86~87
しかし、アセモグルとロビンソンは中国の「収奪的」制度について、こう分析している。
一九四九年、共産党は毛沢東の指揮の下、ついに蒋介石の国民党を打倒した。一〇月一日に中華人民共和国の成立が宣言された。一九四九年以降につくられた政治・経済制度はきわめて収奪的たった。政治的には中国共産党の一党独裁体制だった。以来、中国ではほかのいかなる政治団体も認可されていない。毛は一九七六年に死去するまで、共産党と政府を全面的に支配した。そうした専制的かつ収奪的政治制度に伴っていたのが、高度に収奪的な経済制度だ。毛はただちに土地を国有化し、ありとあらゆる所有権を一挙に廃止した。地主をはじめ反体制と見なした階級を処刑した。市場経済は原則的に廃止された。地方の住民は徐々に集団農場に組織されていった。金銭と賃金は「労働点数」に置き換えられ、この点数を物資と交換できた。一九五六年には国内旅券か導入され、政治的・経済的管理強化のため、適正な許可のない旅行は禁じられた。あらゆる産業が一様に国有化され、毛はソ連を手本とした「五ヵ年計画」を通じて、産業の急速な発展を促進する野心的な試みを開始した。
あらゆる収奪的制度がそうであるように、毛政権も、いまや支配下に置く広大な国土の資源を搾取しようとした。中国共産党は米や穀物などの農産品の販売を独占し、農民に重税を課すのに利用した。工業化を目指す試みは一九五八年以降、第二次五ヵ年計画の開始とともに悪名高い「大躍進」政策となっていく。毛は、小規模な「裏庭」溶鉱炉によって鉄鋼の生産量を一年で倍増させると発表し、中国か一五年後にはイギリスの鉄鋼生産に追いつくだろうと公言した。唯一の問題は、そうした目標を達成できる現実的な方法かないことだった。目標達成のためには金属くずを見つけなければならず、人々は家にあった鍋やフライパン、鍬や鋤といった農具さえ溶かすことを余儀なくされる。畑を耕すはずの労働者か鉄鋼をつくるために鋤を破壊し、それとともに自分だちと国全体の食糧をつくる能力をも破壊した。その結果、中国農村部は苛酷な飢饉に見舞われた。学者たちは毛の政策の役割と、同時期に起きた干ばつの影響の大きさを比較して論じるか、二〇〇〇万人から四〇〇〇万人を死に追いやった原因として大躍進か中心的役割を果たしたことを疑う人はいない。毛沢東の支配下にあった中国では暴虐の証しとなる数字は集計されなかったため。正確な死者数はわからない。一人あたりの収入は四分の一ほど減少した。
大躍進の産物の一つは、共産党幹部の鄧小平の変節だった。革命闘争で多大な戦果を収めた司令官であり、「反右派」闘争を率いて多数の「革命の敵」を処刑に至らしめた鄧小平が考えを変えたのだ。一九六一年、中国南部の広州での会議の席上、鄧小平は「黒いネコであれ白いネコであれ、ネズミを獲るなら良いネコだ」と述べた。政策が共産主義に見えようか見えまいか構わないということだ。中国に必要なのは、国民が食べていげるようにするために生産を促進する政策だった。
ところが、鄧小平はまもなく、自分か新たに見いだした実利主義のせいで苦境に立たされる。一九六六年五月一六日、毛沢東は、中国の共産社会をむしばみ資本主義を蘇らせようとする「ブルジョア」の利権によって革命か脅かされていると述べた。対抗策として、毛はプロレタリア文化大革命、通称「文化大革命」を宣言した。文化大革命は一六ヵ条の要点に基づいていた。
『国家はなぜ消滅するのか(下)』p.270~271
鄧小平が変節するまで中国は、ソ連と同じだったのだ。
しかし、鄧小平は資本主義の導入を考えた。
だが、毛沢東はブルジョアの復活を許さなかった。
それで、鄧小平はまた失脚した。
けれど1966年に毛沢東が死去してから潮目が変わった。
鄧小平は再び政治の表舞台に現れたのだ。
鄧小平も華国鋒と同様に、共産主義体制の廃止と包括的市場への転換を望んではいなかった。鄧小平もまた、共産主義革命によって権力の座に就いた同じグループの一員だ。だが、彼も支持者たちも、みずからの政治支配を危険にさらさずとも十分な経済成長を達成できると考えていた。みずからの権力を脅かさないような収奪的政治制度下での成長モデルを掲げていたのだ。それは、中国の人民がもっと高い生活水準をぜひとも必要としたからでもあるし、また、毛沢東の治世と文化大革命期を通じ、共産党に対する有意義な抗議行動かすべて弾圧されていたからでもある。そうした成長を達成するために、彼らは文化大革命のみならず毛時代の制度の遺産の多くを否定したかった。包括的経済制度への大がかりな移行なしには経済成長は達成できないと、彼らは気づいていた。だからこそ、経済を改革し、市場の力とインセンティヴの役割を強化したいと考えた。また、個人所有の範囲を広げ、社会と行政における共産党の役割を減らすと同時に、階級闘争のような概念を排除したいと望んだ。鄧小平の一派は外国からの投資と対外貿易にも寛大で、国際経済との統合を目指す政策をさらに積極的に進めたかっていた。だが、それにも限度があり、真に包括的な経済制度の構築や共産党による経済支配の大幅な緩和は考えてもいなかった。
中国にターユングーポイントをもたらしたのは、華国鋒の権力と、その権力に従って四人組に対抗しようという彼の意思だった。毛の死去からひと月と経たないうち、華は四人組を打倒する政変を起こして全員を逮捕させた。そして、一九七七年三月に鄧小平を復職させた。
そうした成り行きにも、華自身が鄧小平の政略に敗れたために起きた次の重要な段階にも、必然性はまったくない。鄧小平は国民が文化大革命を批判することを奨励し、彼と同様に文革時代に迫害された党員を共産党のあらゆるレベルの要職に配置しはじめた。華は文化大革命への関与を否認できなかったため、不利だった。また、権力の中枢に身を置いてから比較的日が浅かったため、鄧小平が長年培ってきたほどの人脈や私的な人間関係を持だなかった。一連の演説で、鄧小平は華の政策を批判しはじめる。一九七八年九月、鄧小平はあからさまに「二つのすべて」を攻撃し、正しい手法は毛の発言すべてに従って政策を決めるのではなく、「事実から真理を探る」ことだと指摘した。
鄧小平はまた、民衆からの圧力を巧みに華に転嫁しはじめた。そうした圧力か最も強く反映された一九七八年の「民主の壁」運動では、国家への不満を綴った壁新聞か北京で掲示された。一九七八年七月、鄧小平の支持者だった胡喬木が経済改革の基本方針を示した。そのなかには、企業にもっと大きな主導権と権限を与え、生産にかかおる決定をみずから下させるべきだとか、政府か価格を設定するのではなく需要と供給か釣り合う価格設定が許されるべきだとか、国家による経済全般の規制を緩和すべきだ、といった意見か含まれていた。そうした提案は急進的だったが、鄧小平は影響力を強めつつあった。一九七八年一一月から一二月にかけての中国共産党第一一期中央委員会第三回全体会議が突破口を開いた。華の反対をものともせず、以後、党の綱要は階級闘争でなく経済の近代化とすることか決められた。この全体会議では、一部の省で試験的に「農家請負制」を実施することか発表された。これは集団農業を改め、農業に経済的インセソティヴを導入する試みだった。翌年には党中央委員会が「事実から得た真理」の概念を核とすることを是認し、文化大革命は中国人民にとって大きな災厄だったと明言することになる。この時期を通じて、鄧小平はみずからの支持者を党、軍、政府の要職に任命して地歩を固めた。中央委員会内の華の支持者に対抗するには時間を要したものの、同等の権力基盤を築くに至った。一九八〇年に華は首相を辞任せざるを得なくなり、趙紫陽が後任となった。一九八二年に華国鋒は党中央委員を解任された。だか、鄧小平はそこで止まらなかった。一九八二年の第二一回中国共産党大会および一九八五年九月の中国共産党全国代表会議で党の指導陣と幹部をほぼ全面的に入れ替えた。新たな陣営にはかなり若手の改革派が入ってきた。一九八〇年と一九八五年を比べると、八五年までに二六人の共産党政治局員のうち二一人、一一人の共産党書記局員のうち八人、一八人の副総理のうち一〇人が代わっている。
政治における革命を成し遂げ、国家の実権を握った鄧小平と改革派は、経済制度のさらなる変革に次々と着手した。手はじめは農業だった。一九八三年には、胡喬木の構想に従い、農民に経済的インセンティヴを与える農家請負制(生産責任制)が一律に採用された。一九八五年には国家による穀物の強制的買い上げ制度が廃止され、自由意思による契約システムに取って代わられた。農産品価格の管理統制は一九八五年に大幅に緩和された。都市経済では、国営企業にさらに大きな自律性か与えられ、一四の「開放都市」が指定されて外国からの投資の誘致が可能になった。
『国家はなぜ消滅するのか(下)』p.275~277
社会主義国家で、資本主義の生産手段の私的所有を認めることはソ連のごく短期間あったことがある。
新経済政策(ネップ)と呼ばれたものだ。
1917年のロシア革命後、ソ連は内戦のなかにあり、物資が十分ではなかった。そこでレーニンが行ったのは戦時共産主義による食料の配給制だった。
その後、足りない食料を補うため、生産力の向上が必要になった。それで、レーニンは農村に私的生産手段を持たせる政策を採用した。それがネップだった。
しかし、鄧小平は大規模に資本主義を導入した。
生産手段の私的所有を認め、市場経済を復活させた。
そのなかで戴国芳という起業家が現れた。
戴国芳は、鉄鋼会社を興した。
しかし、そこで中国共産党は態度を変えた。
戴国芳は、中国に都市化の波が押し寄せることに早くから気づいていた。一九九〇年代には、新しい幹線道路、ビジネス街、住宅、高層ビルが中国のいたるところで増えはじめ、戴は、そうした成長が向こう一〇年間、勢いを増すばかりだろうと考えた。そして、経営する江蘇鉄本鋼鉄有限公司が、非効率的な国営製鉄工場に比べればなおさら、低コスト生産者として大きな市場を獲得できると判断した。戴はまさに巨大な鋼鉄工場の建設を計画し、常州の党地方幹部の支援を得て、二〇〇三年に着工した。だが、二〇〇四年三月、プロジェクトは北京の中国共産党の命令で中止され、戴は逮捕されたが、理由はいまだに明示されていない。当局は、彼の口座に有罪につながる証拠を見つけられると踏んだのかもしれない。結局、戴はそれから五年間を拘置所および自宅軟禁状態で過ごし、二〇〇九年に微罪で有罪判決を下された。本当の罪状は、国が後援する企業と競合する大規模プロジェクトを開始したことと、それを共産党上層部の認可なしにしたことだ。それか、ほかの人々がこの事件から学んだにちがいない教訓である。
戴のような起業家に対する共産党の反応は、驚くにはあたらない。鄧小平の側近で初期の市場改革計画の中心的立案者とされる陳雲は、経済を「籠の鳥」にたとえて、党幹部の大半の考え方を要約した。すなわち、中国経済を鳥とすれば、党の支配は籠にあたり、鳥がもっと健康で活発になるためには籠を大きくしなくてはならない。だが、鍵を開けたり籠を取り除いたりしてはいけない。鳥が飛び去ってしまうからだ。一九八九年、江沢民は中国の最高権力者である共産党総書記になってまもなく、この考えをさらに進め、起業家に対して当局が抱く疑念を要約して、彼らを「詐欺、横領、贈収賄、脱税に手を染める自営の商人や行商人」と形容した。一九九〇年代を通じて、外国からの投資か中国に流れ込み、国営企業の拡大が促進されてもなお、民間企業は疑いの目で見られ、多数の起業家が資産を没収され、投獄さえされた。民間企業に対する江沢民の見方は、弱まりつつあったものの、まだ中国全土にはびこっていた。中国のある経済学者の表現を借りれば、「国営大企業は巨大プロジェクトにかかおることができる。だが、民間企業が同じことをして、ことに国営企業と競合すると、あらゆる角度から問題か降りかかる」
すでに多数の民間企業か中国で操業し利益を上げる一方で、経済の多くの要素はいまだに党の指揮と保護の下に置かれている。ジャーナリストのリチャードーマグレガーの記事によれば、中国の国営大企業のトップの机には、必ず赤い電話か置かれている。その電話か鳴るのは党が企業に指令を出すときで、あれをしろ、ここに投資しろ、これをターゲッ卜にしろという命令が伝えられる。そうした巨大企業はいまだに党の指揮下にある。その事実を私だちか思い出すのは、党が企業の役員の交代、解雇、昇進をほとんど説明もなく決定するときだ。
『国家はなぜ消滅するのか(下)』p.295~296
要するに、国家と競合するような分野で起業するのは許さないということだ。
どんな手段を使ってでも国家が、中国共産党が潰しにかかるのだ。
中国共産党の露骨な影響力と収奪的制度から想起されるのは、ソ連の一九五〇年代から六〇年代にかけての経済成長とこんにちの中国の成長の類似点だが、明らかな違いもある。ソ連が収奪的な政治・経済制度の下で成長を遂げたのは、中央集権化された司令系統に従い、産業のなかでも軍備と重工業に資源を強制的に配分したためだ。このような成長か可能だったのは、取り戻すべき遅れか多かったからでもある。収奪的構造下での成長は、創造的破壊か不要な場合のほうか達成しやすいのだ。中国の経済制度はたしかにソ連のそれよりは包括的だが、中国の政治制度はいまだに収奪的だ。共産党は中国では絶対的な力を持ち、国家の官僚機構、軍隊、メディア、経済のかなりの部分を全面的に支配している。中国国民には政治的自由かほとんどないし、政治的プロセスへの参加も皆無に近い。
中国の成長が民主主義をもたらして多元化を進めるだろうと、多くの人が長いあいだ信じてきた。一九八九年には天安門のデモが、開放の進展のみならず共産主義体制の崩壊につながることさえ予感させた。ところか、デモ参加者に向かって戦車が出動し、平和的革命どころか、いまでは歴史書に天安門広場虐殺と書かれる事件となった。多くの点で、中国の政治制度は天安門事件の余波により、さらに収奪的になった。共産党総書記として天安門広場の学生たちを支援した趙紫陽をはじめ改革派は粛清され、党は市民の自由と報道の自由の弾圧にさらに力を注いだ。趙紫陽は一五年以上にわたり自宅に軟禁され、彼の公的記録は徐々に抹消されていった。政治改革支持者のシンボルになることさえ許されなかったのだ。
こんにち、党によるメディアの支配は、インターネッ卜を含め、かつてないほど厳しい。そうした支配のかなりの部分は自己検閲を通じて達成されている。報道機関は、趙紫陽や劉暁波に言及してはいけないことを心得ている。劉は民主化を求めて政府を批判し、ノーベル平和賞を受賞してもなお、獄につながれている。自己検閲を支える機構は、ジョージー・オーウェルの『一九八四年』さなから、会話の盗聴や通信の傍受、ウ弋フサイトの閉鎖、新聞を休刊にすることばかりか、イソターネッ卜上の個別のニュース記事を選んでアクセスを妨害することさえ可能だ。それらがすべてさらけ出されたのか、二〇〇二年から党総書記を務める胡錦濤の息子の汚職の嫌疑が二〇〇九年に持ち上がったときだった。党の機関はただちに対応に乗り出し、この件に関する中国メディアの取材を阻止できただけでなく、『ニューヨークータイムズ』や『フィナソシャルータイムズ』のウェブサイト上から関連する記事を選んでアクセスできないようにもした。
経済制度を党か支配しているせいで、創造的破壊の進行は強力に抑えられており、政治制度に抜本的改革かないかぎりぱその状態か続きそうだ。ソ連の場合と同じように、収奪的政治制度下での中国の成長は、取り戻すべき遅れが多かったからこそ実現できた。中国の国民一人あたりの収入は合衆国、西欧にはいまだに遠く及ばない。もちろん、中国の成長はソ連の成長よりはかなり多様で、軍備と重工業のみに依存してはいないし、中国の起業家は創意工夫の才を大いに発揮している。それでも、収奪的政治制度から包括的制度への移行かなければ、この成長はいずれ活力を失うだろう。政治制度が収奪的であるかぎり、過去の同様の事例と同じく、成長は本質的に限られたものとなる。
『国家はなぜ消滅するのか(下)』p.298~299
天安門事件は、ソ連の崩壊が進む頃に起きた。
ちょうどゴルバチョフの北京訪問と時期が同じだった。
というより中国の学生たちも中国にソ連のようなペレストロイカ(改革)、グラスノスチ(情報公開)が起きることを期待してゴルバチョフを迎えようとしていたのだ。
私たちの理論か明らかにしているように、ことに国家の中央集権化がある程度達成された社会では、このような収奪的制度下の成長は可能だし、多くの国では最も描きやすいシナリオでさえあるかもしれない。そうした国はカンボジアやヴェトナムから、ブルンジ、エチオピア、ルワンダにまで及ぶ。だか、収奪的政治制度下での成長のあらゆる例と同様に、その種の成長は持続しないことも、この理論によって示されている。
中国の場合、遅れの取り戻し、外国の技術の輸入、低価格の工業製品の輸出に基づいた成長のプロセスはしばらく続きそうだ。とはいえ、中国の成長は終わりに近づいているようでもあり、とくに中所得国の生活水準にいったん達したときには終わると見られる。最も可能性の高いシナリオは、中国共産党と、力を増しつっある中国の経済エリートが向こう数十年間、権力をきわめて強固に把握しつづけられるというものかもしれない。その場合、歴史と私たちの理論か示すところによれば、創造的破壊を伴う成長と真のイノヴェーションは訪れず、中国のめざましい成長率はゆっくりとしぼんでいく。だか、そうした結末は、あらかじめ運命づけられているのではない。収奪的制度下での成長が限界に達するまえに中国か包括的政治制度へ移行すれば、避けられるのだ。にもかかわらず、次節で見るように、中国かより包括的な政治制度へ移行するとか、その移行か苦もなく自然に行なわれるとか期待できる理由は、ほとんどない。
『国家はなぜ消滅するのか(下)』p.300~301
中国などを見ていると、いくつかの法則がある。
国家の中央集権化がある程度達成された社会では、収奪的制度下の成長は可能である。
多くの国では最も描きやすいシナリオでさえあるかもしれない。カンボジア、ヴェトナム、ブルンジ、エチオピア、ルワンダなど。
しかし、また収奪的政治制度下での成長のあらゆる例と同様に、その種の成長は持続しないこと理論化できる。
それは収奪的政治制度のおかげではない。収奪的政治制度にもかかわらず成長したのであり、過去三〇年間の中国の成功体験は、収奪的経済制度からの脱却とはるかに包括的な経済制度への移行のたまものだ。そうした包括的な経済制度への移行は、きわめて独裁的で収奪的な政治制度の存在によって、容易になるどころか難しくなったのである。
独裁体制下での成長を是認する別の考え方は、そうした成長の短所を認めつつも、独裁体制はたんなる通過段階にすぎないと主張する。その発想の出所は、政治社会学の古典的理論の一つで、シーモア・マーティン・リブセットが唱えた近代化論だ。近代化論によれば、すべての社会は成長とともに近代化され、発展し、文明化したものになっていき、とりわけ民主化へと向かう。近代化論の賛同者の多くは、成長のプロセスの副産物として、民主主義と同様に包括的制度も生まれると主張する。さらに、民主主義は包括的政治制度と同じではないにせよ、通常選挙と妨害の少ない政界の競争によって、包括的政治制度か発達していく傾向かあるとする。近代化論にはさまざまな型かあり、教育を受けた労働者階級が民主主義とよりよい制度へ自然に導いていくとする説もある。ややポストモダン的な近代化論では。
『ニューヨークータイムズ』紙のコラムニスト、トマスーフリードマンが、マクドナルドのハンバーガー店がある程度の数まで増えた国では、民主主義と制度か後に続くはずだとさえ述べている。どれもバラ色の未来像を描いている。過去六〇年以上にわたり、収奪的制度のある多くの国さえ含む大半の国々かいくらかの成長を経験してきたし、労働者階級の教育の顕著な向上を達成した。したがって、労働者の収入と教育水準がさまざまな形で上がりつづけるにつれ、民主主義、人権、市民の自由、所有権の保障といった良い変化が後に続くはずだというのだ。
近代化論は学界内外に幅広い支持者を持つ。たとえば、中国に対する最近の合衆国の姿勢はこの理論によって形成されてきた。ジョージ・H・W・ブッシュ(父)は中国の民主化に向けた合衆国の政策をこう要約した。「中国と自由に貿易せよ。そうすれば、時間がわれわれに味方する」。西側と自由に貿易すれば中国は成長し、近代化論か予測するように、その成長が中国に民主主義とよりよい制度をもたらすという考え方だ。ところが、一九八〇年代半ば以降の合衆国‐中国間の貿易の急速な増加は中国の民主主義にほとんど影響しなかったし、今後一〇年間に続くと見られるより緊密な結びつきも、同様にあまり影響しないだろう。
合衆国の主導による侵攻後のイラクの社会と民主主義の動向に関しては、近代化論のせいで楽観視する人か多かった。サダムーフセイン政権下での深刻な経済不振にもかかわらず、二〇〇二年のイラクはサハラ以南のアフリカ諸国の大半ほど貧しくはなかったし、国民の教育水準も比較的高かったため、民主主義と市民の自由、それに多元主義と呼べるものさえ発展する基盤か整ったと思われた。イラク社会か混乱と内戦に見舞われると、そうした期待はたちまち打ち砕かれた。
近代化論は正しくないと同時に、破綻しつつある国家の収奪的制度という大問題にどう立ち向かうかを考える助けにもならない。近代化論の正しさを示す最も強力な証拠は、富裕な国家は民主主義体制を持つ国家であり、市民の権利と人権を尊重し、機能する市場と全般的に包括的な経済制度に恵まれているということだ。それでも。その関連性か近代化論の正しさを裏付けると解釈するのは、包括的な政治・経済制度か経済成長に与える主要な影響を無視することになる。本書を通じて論じてきたように、過去三〇〇年間に成長を遂げ、こんにち比較的裕福になった社会は、包括的制度を持つ社会だ。それによって私たちの周囲に見られる物事が説明できることは、事実の見方を少し変えてみると、よくわかる。すなわち、過去数世紀間に包括的な政治・経済制度を構築した国家か持続的経済成長を達成した一方、過去六〇年から一〇〇年のあいだにもっと急速に発達した独裁体制では、リプセッ卜の近代化論の主張に反し、民主化が進んではいないのである。実は、それは驚くにはあたらない。収奪的制度下で成長が可能なのは、まさに、そうした成長が収奪的制度そのものの排除を必ずしも自動的に意味するわけではないからだ。実際、そうした成長が生まれるのは、収奪的制度の支配者が経済成長を脅威と見るのではなく、みずからの体制を支えるものと見るからであることが少なくない。中国共産党も一九八〇年代以降、そのような見方をしてきた。また、ガボン、ロシア、サウジアラビア、ベネズエラのように国の天然資源の価値か上がることから生じる成長は、そうした独裁体制から包括的制度への根本的転換にはつながりにくいことも、驚くにはあたらない。
『国家はなぜ消滅するのか(下)』p.303~304
過去三〇〇年間で成長を遂げてきたのは包括的制度を持つ社会だ。
過去数世紀間に包括的な政治・経済制度を構築した国家か持続的経済成長を達成した一方、過去六〇年から一〇〇年のあいだにもっと急速に発達した独裁体制では、近代化論の主張に反し、民主化が進んではいない。
それは驚くにはあたらないのだ。
なぜなら、収奪的制度下で成長が可能なのは、まさに、そうした成長が収奪的制度そのものの排除を必ずしも自動的に意味するわけではないからだ。実際、そうした成長が生まれるのは、収奪的制度の支配者が経済成長を脅威と見るのではなく、みずからの体制を支えるものと見るからであることが少なくない。
中国の施政者にとって、経済を鳥とすれば、党の支配は籠にあたる。
鳥がもっと健康で活発になるためには籠を大きくしなくてはならない。だが、鍵を開けたり籠を取り除いたりしてはいけない。鳥が飛び去ってしまうからだ。
社会主義イデオロギーを掲げる中国と言う国家は、経済を国家の支配下に置き、私的生産手段をもつ企業も国家の統治下に置いてしまうのだ。国家の領域を侵す企業は取りしまる。
社会主義イデオロギーで支配するためにテクノロジーの発達したネットワークでは、そのテクノロジーで検閲を行う。イスラム過激派が潜むウイグルでは、テロ防止の名目でテレビカメラが監視する。
ここでは国家、それを支える共産党が支配するのだ。
共産党員は人口の8分の1に迫る人数がいて、企業の共産党支部でも習近平の思想を教える。
党員は知能が高い低いに関係なく、国家に奉仕する性格の良い者が選ばれる。
ソ連の失敗をすべて補っているように見える。
ただ、政治的な複数主義(プルラリズム)以外は。