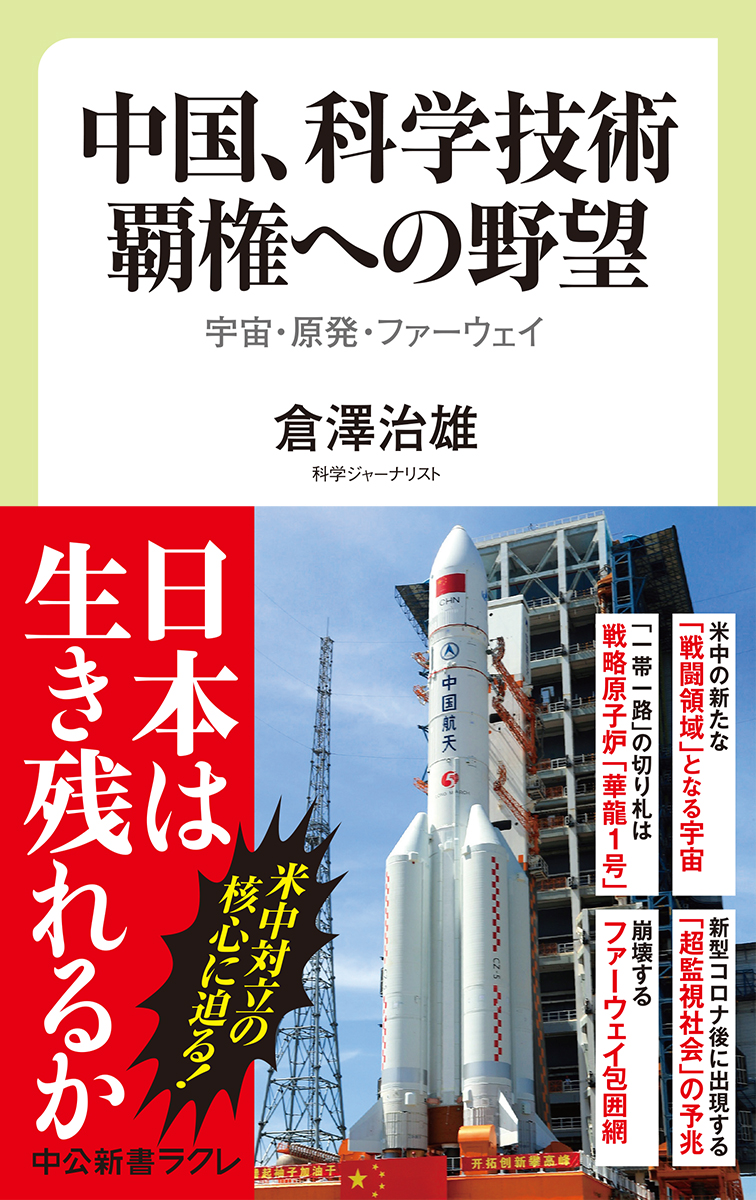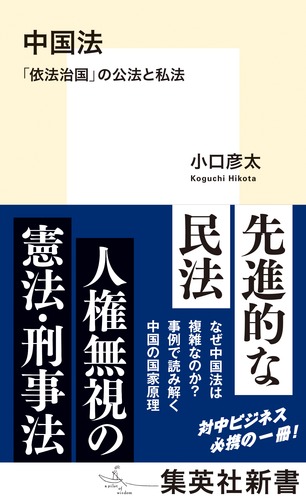(その8)未来社会としての中華人民共和国
生産手段の私的所有が搾取を生み、ブルジョア階級が生産手段をもつことが生産力の向上と人間の発達を阻害しているという考えのもとに、プロレタリア階級による生産手段の所有を目指すのが社会主義革命でした。
社会主義革命のあとプロレタリアート独裁によって、国家を建設し、共産主義社会を目指すというのがレーニンの革命の道筋。レーニンによるとエンゲルスの言っていた民主制による革命でも、その「民主制」さえ、将来、国家としては消滅すると考えていました。
中国は清朝の末期に孫文が辛亥革命で中華民国を樹立しました。そして蒋介石の中国国民党と毛沢東の中国共産党による抗日戦線を経て、毛沢東の社会主義革命により中華人民共和国になりました。中国もヨーロッパ型の民主制というものを経験していません。

ソ連では1980年代に、ゴルバチョフが登場し、ペレストロイカ(改革)、グラスノスチ(情報公開)を進めました。しかし、その改革は共産党の一党支配への批判にまで及び、エリツィンの登場により共産党の解体に至りました。

その頃、中国ではすでに社会主義国として巨大な市場を抱え込む政策を取っていました。
鄧小平は四つの基本原則を提唱し、中国はその方向に進んでいました。
① 社会主義への道
② プロレタリア独裁(後に人民民主独裁と表現を改める)
③ 共産党の指導
④ マルクス・レーニン主義、毛沢東思想
一方、民主化を要求する人々を社会主義、共産党の指導の転覆を図る「反革命分子、悪質分子」と露骨に非難し、断固とした対処を求めました。

1989年6月4日は天安門事件が弾圧された日です。
鄧小平は外資や資本主義を導入しながら、国家を共産党の指導の下、プロレタリア独裁のもとに置く。資本主義思想がそれとともに入ってくるのを排除するという矛盾した管理国家として発展させる道を選んだのでした。

その後の中国はどのように統治されているのでしょうか?
NHKのBSでマイケル・サンデルがアメリカ、中国、日本の学生たちと討論をする番組があります。2022年に「中国は民主主義国か?」というテーマの回がありました。

中国の学生は、アメリカとは違うが「中国は民主主義国」だ。アメリカとは違う、もう一つの「民主主義」を世界に示していると主張しました。
サンデル教授は、「複数政党制」「直接選挙」「言論の自由」は民主主義の必要条件か?と質問しましたが、中国の学生は、民主主義には3点全て不必要だと回答していました。
それは次のような理由です。
・「複数政党制」について、政党から出た人は国民の一部の代表であり、全国民の代表ではない。複数政党制のもとでの選挙にはお金の問題が付きまとう。
選挙ではどちらが勝つかが焦点となり、国民の問題などの争点に焦点があたらない
・「直接選挙」について、中国には「推薦」もある。
単に手続きの違いで、合理的な方法がとられれば良い。
50%の支持で大統領となった人が、全ての国民を代表することができるのか?
・「言論の自由」について、言論は何かの問題解決に使うから大切なのであり、怒りや不満を表明するためのものではない。

中国人学生たちは、中国は民主主義国家だと考えているのです。
国民が信用する人が国民のことを考えて政治をしている、という主張です。中国共産党は国民のなかで選ばれた人たちの集団です。その人たちがつくる政府やエリートが研究する科学を国民は信用しているので、コロナ対応、シャットダウン、ワクチン接種がうまく行ったとの意見もありました。
逆にポピュリズム(トランプなど)は民主主義ではないと言っていました。特にトランプについては、かつてトップだった人がツイッター、フェイスブックを締め出されたのは、人権侵害、検閲ではないのかとも批判していました。
それに対して、アメリカと日本の学生は、民主主義に必要なものは、直接選挙、言論の自由、複数政党の存在であると主張しました。
でも、中国の学生たちは、そのような政治システムよりも、いかに国民の役に立っているかの実効性のほうが大切で、トランプのように一部の国民の利益だけを考えているトップが出てくるほうが問題だと指摘していました。
確かに一理あると思ってしまう議論でした。
社会主義を目指す中国が行き着いたのが、サンデルと話していた学生たちの意見なのでしょう。

では、生産手段の社会化という共産党によるプロレタリア独裁の国家統治のもとで、表現や言論の自由は制限されてもいいのでしょうか?
でも、この議論はどこかで聞いたことがあるような気がします。
日本共産党には、党首公選制を必要ない、党外で異論を唱えれば除名が当然だという理屈がありますが、それと似ています。
これを不破哲三元共産党委員長は、国家の死滅の説明として共産主義のルールの例でこう述べていました。
その一つの実例として、日本共産党という“社会”をあげてみたいと思います。これは、四十万人からなる小さい規模ですが、ともかくひとつの“社会”を構成しています。そして、規約という形で、この“社会”のルールを決めています。そこには、指導機関とか規律委員会などの組織はありますが、国家にあたるもの、物理的な強制力をもった権力はいっさいありません。この“社会”でルールが守られているのは、この“社会”の構成員が、自主的な規律を自覚的な形で身につけているからです。ルール違反があれば、処分を受けますが、その処分も強制力で押しつけるものではありません。
党首公選制は派閥を作るからダメなんだとか、上部機関に候補者を信任する選挙方法でも議論をしているから最も民主主義的なんだという論理です。
国家や政党という組織で、直接選挙、複数からの選択、言論の自由は重要ではない。
日本共産党の党員や中国の若い人たちが、どうしてそう思うようになるのか?
中国の場合、この国の統治の方法と深く関係していると思います。
中国は、国家として、いや共産党の軍隊を整備し、その兵力は世界有数になっています。
科学技術開発も今や特許などではアメリカに次ぐ力を備えています。
統治として整備している法体系は、市場を抱え込む社会主義国家として、民法では契約法を細かく取り決め、憲法では精神的自由を制約し、国家や公共性を重視する体系になっています。
裁判は二審性ですが、冤罪事件で検察側が負ける事例もあり、昔のような人民裁判の印象はありません。
思想や表現の自由と深く関係する情報の管理はどうでしょうか?
共産主義を目指す未来社会としての中華人民共和国。
そこでは何が重要視され、何を抑制しているのでしょうか?
これが肝とも言えますが、中華人民共和国は、グラスノスチから国家崩壊に至ったソ連の失敗に学んでいるように思えます。