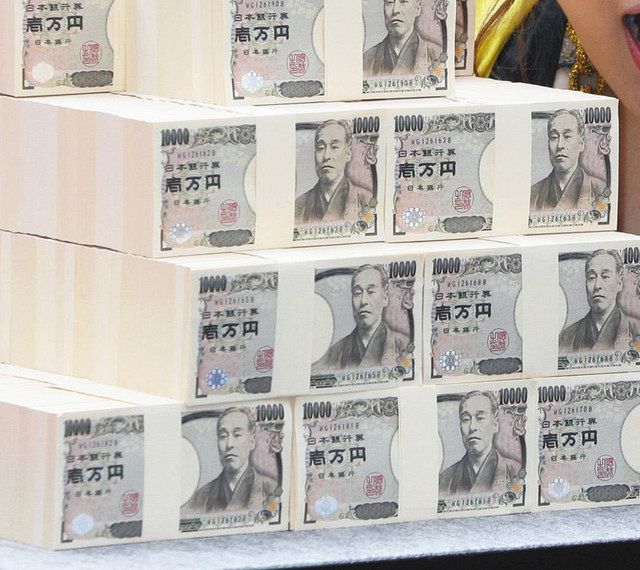今の日経平均株価の動きはアルゴリズム取引によるものだとする見方もあるが、おそらくそうではない。
アルゴリズム取引というのは、
「自らの取引によって株価が乱高下しないように売買注文を分散したり、また株価が割安と判断したタイミングで自動的に買い注文を出したりする」アルゴリズム取引|証券用語解説集|野村證券 (nomura.co.jp)
という手法であるため、今の値動きは全くそのようにはなっていない。
(もしアルゴリズム取引によるものなのだとしたら、相当おかしいアルゴリズムを採用している)
では今の値動きはどういうものなのかというと、これはまともなプロがやっているようには思えず、自らの力を誇示する目的で巨額資金を一気に投じるというものであり、目立たないように注文を入れてカネ儲けをしている「上手い」やり方なのではなく、大艦巨砲主義のような「ロマン系」のやり方をしている。
そのため、注目を浴びることにも繋がり、理由もなく噴き上げ続けるこの株価指数を不審な目で見る者も多くなってきているはず。
不審な目で見られるだけならいいが、あまりにも稚拙で下手なやり方であるため、恐らく嘲笑の対象にされてきているのだろう。
それを日銀がやっているのではないかという疑いがあるが、いくらなんでも日本の中央銀行がそのようなバカな連中であるとは思えないため、恐らく余程の巨額資金を持つ何者かが集団でこの相場を作っている。
つまり、どこかの巨大ヘッジファンドが富裕層から巨額資金を集め、短期的にどれだけ株価を上げられるかというチャレンジをしているのだろう。
しかし、それがどのようにカネ儲けに繋がるのかは分からない。
【参考】
ロマン(〈フランス〉roman)
感情的、理想的に物事をとらえること。夢や冒険などへの強いあこがれをもつこと。「ロマンを追う」「ロマンを駆り立てられる」
浪漫(ロマン)とは? 意味や使い方 - コトバンク (kotobank.jp)
【参考】
大艦巨砲主義
(比喩的に)大きな組織や大掛かりな設備が、強い競争力をもつとする考え方。大きすぎて柔軟性を欠き、小回りの利かないところを冷やかして言うこともある。
大艦巨砲主義(タイカンキョホウシュギ)とは? 意味や使い方 - コトバンク (kotobank.jp)
恐らく年内に誰も株なんか買いたくない状況になっているのだろうが、その時に売りを浴びせることをためらう者は誰もいないのだろう。
これだけ相場操縦をしてきたのだから誰も株を大量に売り続けてもそれが悪いことだとは思うはずがない。
日銀は株を無限に買い続けるために無限に資金を創造するということはないはずであり、もし今も日銀が株を噴き上げているのであれば、リスク許容度が並ではない。
常識的に考えれば、相場環境が悪化していくことが予想されるのであればポジションを減らし、現金の比率を高めるものだが、なぜかそれと逆のことをしている者がどこかにいる。
それは少しでも株価が下落すれば大変な含み損を抱えることになるような巨大なロングポジションを保有しているようだ。
つまり、今、踏み上げられているショート勢と、踏み上げているロング勢の立場がいずれ逆転することが容易に想像でき、恐らくもう間もなくそうなるのだろう。
厳密に言えば、今もなお果敢に攻め続けているロング勢の方が圧倒的にポジションサイズは大きいのだから、立場の逆転ぐらいではなく、全てを失うだけでは済まされない程の損失を出すのだろう。
今の状況を整理すると、相場環境が悪化していく中で巨大なロングポジションを構築し続けている者がどこかにいて、ショート勢とロング勢を比較すると、ロング勢の方がとてつもなく大きいポジションを持っている。
政府やその息の掛かった主要メディアなどは当然のように聞こえのいい話しかせず、統計データにも嘘が多い。
本当は既に様々な問題が顕在化しているのに多くの市場参加者はそれを無視し、いつまでもお祭り騒ぎをやっている。
「彼ら」が気づく頃にはもうどうしようもない事態に陥っている。
「彼ら」はポジションサイズこそが最も大きいリスクであることを知らなかったのだろう。
恐らく、今も日本株を大量購入し続けている者は自らの失敗を認めることができず、ひたすら上げ続けない限り評価損益が大きいマイナスになってしまうため、もう後戻りできずに資金が尽きるまで上げ続けようとしているのだろう。(少しでも下がってしまったらとんでもない含み損を抱える者がどこかにいる)
これは必ず負けるゲームをやっていることになり、早晩、それは現実になる。
民主党政権時代に財務省は為替介入を行ったが、それは超円高の時だったからドル買い円売りが成功している。(しかし、実際にはそんなことをやる必要はなかったようにも思える)
今、財務省が為替介入をするのであれば、当然、今は円安の時なのだからドル売り円買いをすることになる。
白川・黒田日銀時代に日銀は37兆円(簿価)規模のETF購入を行ったが、これも株価が低迷していたり、暴落していた時だったから成功している。(現在、日銀が保有するETFは時価で70兆円ほどだが、ETFの株数を増やしたのではなく、株価が上昇しているために金額が大きくなっている。)
もし植田日銀が、歴史的株高なのに今後、相場環境の悪化が予想される中で大規模な先物買いや特定の現物買いをし続けているのであれば、まず間違いなく失敗することになる。(さすがに日銀がそんなことをしているとは思えないため、件の「巨大ヘッジファンド」とお祭り騒ぎをしている個人によるバブル相場なのだろう。)
「彼ら」は自らを拷問器具で痛めつけるような奇行をしている。
それはちょうど安部公房の小説「R62号の発明」のように思える。
※日経平均株価の5年騰落率はインドの株価指数に迫る勢いとなっている。しかし、長期で見ると日経平均株価は上昇しておらず、今後の日本経済がインドのように成長していくとは思われていないことが分かる。(つまり、短期資金によって噴き上げているだけ)
NI225 39,910.82(▲1.90%)日経平均株価 | Google Finance
【参考】2024年2月16日の記事
日本株がバブル期後の最高値を更新する中、日本銀行が保有する上場投資信託(ETF)は時価で約70兆円と、日本の年間の税収に匹敵する規模に膨らんでいるもようだ。
ニッセイ基礎研究所の井出真吾チーフ株式ストラテジストの試算によると、日経平均株価が34年ぶりの高値を付けた15日の取引終了時点で、日銀が保有するETFの簿価37.2兆円に対し、含み益は約32兆円に達した。
日本株の最大保有者である日銀は、少なくとも時価評価上はマーケット最大の勝者だ。日経平均株価が今年さらに上昇すると予想するアナリストもおり、今後も増加し続ける可能性がある。日本の年間税収に匹敵する資産価値は、大規模金融緩和策からの出口を熟慮する植田和男総裁にとって課題の一つとなる。
井出氏は「あまりにも規模が大き過ぎて市場で売るにも売れないし、日銀のみで決めることはできない」と指摘。「これは国民に還元されるべきものだ。どうするかの決定には官邸、財務省、金融庁など他の多くの省庁の参加が必要になるだろう」と語った。
日銀のETF買い入れは、異例の非伝統的政策から離れる姿勢を示唆するかのように、昨年は3回にとどまり、今年はまだ行われていない。
大半のエコノミストが4月までにマイナス金利の解除を予想する中、日銀の内田真一副総裁は先週、ETFの買い入れについて、「2%目標の持続的・安定的な実現が見通せるようになり、大規模緩和を修正する時には「やめるのが自然」と語った。
日銀は2010年、金融市場のリスクプレミアム低下を目的に白川方明総裁(当時)の下でETFの購入を開始。新型コロナのパンデミック(世界的大流行)で市場が混乱した際は積極的に買い入れを実施した。
井出氏は、日銀が保有するETFの3分の1は日経平均株価、残りはTOPIXに連動していると推定している。
日銀は現在、年間約12兆円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じてETFを購入する方針を示している。植田総裁は今月、買い入れの継続が適当かどうかを検討した後、保有ETFの処分については「もう少し先で考えるという時間的余裕がある」と語った。
井出氏は、日銀保有のETFについて、「総裁は会見で『買っちゃったもの』と発言した。そういった言い方からすると、日銀はこんなに大量に購入したことを後悔している面もあると感じる」と指摘。その上で、「後始末はしっかりとしなければならない」と述べた。
※2011年に財務省が行った為替介入によって財務省はかなりの含み益があるのだろう。
その金額がいくらなのかは分からないが、もしかするとその時の含み益を根拠として何らかの形で株式市場への介入資金を調達し、株高であるうちに日銀がETFを処分しようと思っているのかもしれない。
東日本大震災発生当初、G7は協調介入を行っているがその時の日本側の介入額がいくらなのかは分からない。
しかしその後、財務省は単独で介入を行っており、その介入額は4兆5129億円だったと言われている。
財務省には外国為替資金特別会計という一般会計とは別に設けてある会計があり、それは「主にドル建ての米国債で運用」されているらしい。
そしてその資産残高は2022年時点で約1兆3000億ドルだと言われている。(1ドル=150円で換算すると195兆円)
為替介入の含み益だけではなく、円安によって米国債も含み益がかなりあるのかもしれないが、金利の上昇によってそれほどでもないという記事もある。(2022年時点での話)
野党はその「埋蔵金」を使って、物価高で苦しむ個人や事業者を支援するべきだと政府に求めているが、政府はそのような救済に使ったのではなく、株式市場の相場操縦のために使ったのかもしれない。
【参考】2011年9月1日
野田佳彦新首相は8月に財務相として、約7年半ぶりの大規模な為替介入を実施した。しかし、円・ドル相場は戦後最高値を記録。新内閣の発足直後から一段の対応を迫られる可能性もある。
政府・日本銀行による8月(7月28日から8月29日まで)の為替市場介入額は4兆5129億円。財務省が31日夜に発表した。介入は日米欧の主要7カ国(G7)が東日本大震災直後の3月18日に円売り・ドル買いの協調介入を実施して以来、約5カ月ぶり。日本単独での介入は昨年9月15日以来。単月の規模では昨年9月の倍以上で、2004年3月以来の大きさとなった。
野田佳彦財務相は8月4日、日本単独で同日に為替介入を単独で実施したと発表。過度の円高は東日本大震災からの復活を目指す日本経済に悪影響を及ぼすと説明した。日銀による追加金融緩和もあり、円・ドル相場は同日、1ドル=80円台に下落。しかし、19日には75円95銭と約5カ月前につけた戦後最高値を突破した。
東短リサーチの高橋雄一研究員ら市場関係者は8日、日銀当座預金の要因別増減などに基づき、4日の介入額を約4兆5000億円と推計。円・ドル相場はその後も急落する場面があったが、介入ではないとの見方だった。仮に介入が同日だけだった場合、1日の介入規模としては過去最大となる。それでも、介入当日の円安・ドル高は3円余りで、3営業日後には4日の高値を上抜けてしまった。
【参考】2022年10月9日の記事
――2011年の東日本大震災の後の3月18日、財務相として為替介入を決断しました。当時はどういった思いでしたか。
「東北に津波で大きな被害が出ているときに、経済金融の大津波が重なるのではないかという強い危機感を持ちました。日本の危機だというのに、1ドル76円台まで5円近く円高が進みました。保険会社が保険金の支払いのために、ドル資産を売って円を調達するという投機筋のシナリオに基づく動きでした。米国のガイトナー財務長官に賛同をいただき、主要7カ国(G7)が足並みをそろえる16年ぶりの協調介入でした。マーケットが開いて日本が動き、各国も続くように動く。国際的な連帯のありがたさに、鳥肌が立つような感動がありました」
【参考】2022年10月26日の記事
外為特会は為替相場の安定のため、急激な変動時の為替介入などに備えて設置。主にドル建ての米国債で運用され、今年3月末時点の資産残高は約1兆3000億ドル。円換算の決算残高は約158兆円だった。
玉木氏は、円安によって外為特会が円ベースで膨張していると指摘する。今月6日の衆院代表質問では、年初の1ドル=116円から145円になった際に約37兆円増したとの試算を披露し、「国の特会は円安でウハウハだ」と強調。「円安で苦しむ個人や事業者のため、緊急経済対策の財源に充てて」と求めた。
ただ、評価益を現金化するための米国債売却は為替介入とみなされ、米政府などから批判を浴びかねない。そこで、玉木氏は売却せずに評価益相当額の政府短期証券を発行し、財源を生み出すことを提唱する。
これに対し、岸田文雄首相は「外為特会の資産は将来の介入に備え保有している」などと経済対策に使うことを否定。財務省は、為替相場次第で評価益が評価損になることもあるとした上で「たまたま今、為替変動でプラスになっているからといって、評価益をあてに財源に使うのはふさわしくない」と冷ややかだ。
もっとも、外為特会に着目しているのは野党だけではない。自民党の伊藤達也元金融担当相は17日の衆院予算委員会で「小泉政権で特会改革に取り組んで『埋蔵金』を掘り起こした」と振り返り、外為特会を是正する必要性を強調。日本の外貨資産の規模は先進国で突出して大きく、一部を売却しても米政府の理解は得られるとも語った。
最近の物価高を受け、ネットでは外為特会の評価益なども含めて「『埋蔵金』を使ってほしい」との意見が飛び交っている。
【参考】2022年7月27日の記事
「為替だけを見ると円安はもちろん弊社にとってプラスで、外貨建て資産の含み益が増えていく。だが、今回は金利で結構やられている。為替と金利の影響を両方足すと、外貨建て資産全体で(収支は)トントンから若干マイナスというイメージだ」