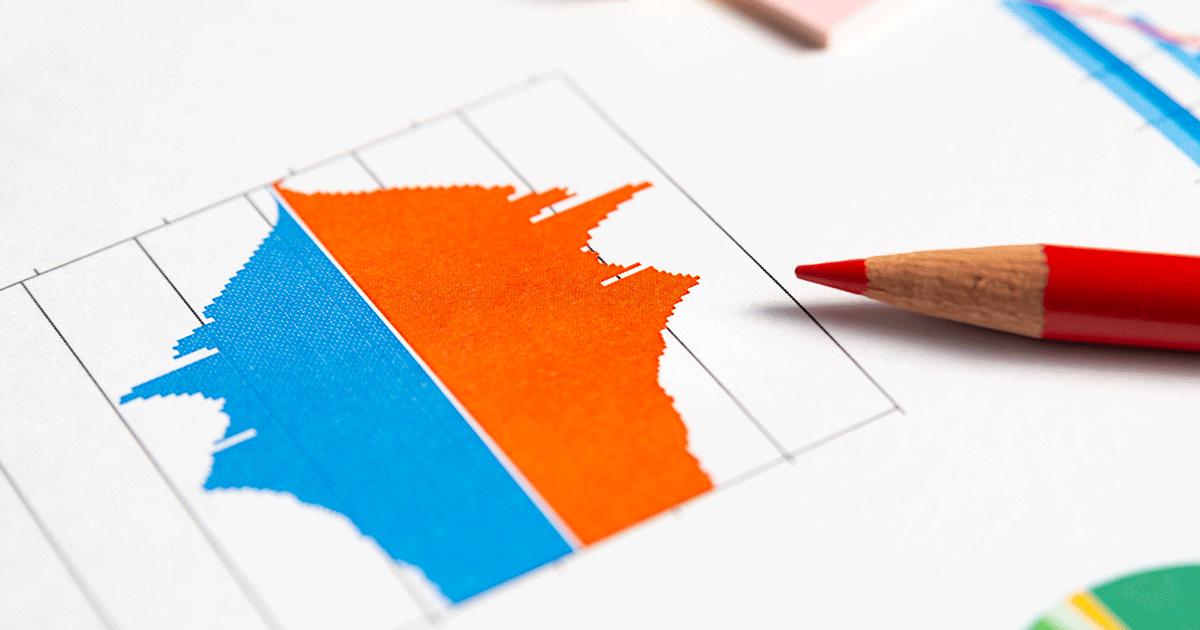日経平均株価が33,000円を超えているが、どうやら可能であれば40,000円ぐらいまで吊り上げようとしているらしい。(実際にそこまで行く可能性は低い)
相変わらず海外投資家が買っていると言われているが、海外勢が日本株を上値追いして吊り上げているとは思えない。(円安傾向が続く中では尚更そう言える)
スクリーニングをしてみると、13日の日経平均株価を押し上げたのはまた商社株だった。
(丸紅、住友商事、三井物産、双日、伊藤忠商事、三菱商事、豊田通商など)
これまでずっと非常に強い上昇を続けてきた商社株だが、まだ上値追いをしている。
なぜかトヨタ、ホンダ、いすゞ自動車、マツダ、デンソー、横浜ゴムなどの自動車関連も強く上昇している。
アドバンテスト、ルネサスエレクトロニクス、HOYA、味の素、SCREENホールディングスなどの半導体関連も同様に強い。
最近の日経平均株価は2023年3月16日からほとんど一本調子で上昇を続けてきたが、これは商社株、自動車株、半導体株だけでなく、
・エーザイ、第一三共、富士フィルムホールディングス、アステラス製薬、大塚ホールディングス、中外製薬
・神戸製鉄所、日本製鉄
・京成電鉄、東武鉄道
・鹿島、大林組、清水建設、日揮ホールディングス、長谷工コーポレーション
・三井不動産、東急不動産、大和ハウス、積水ハウス
・信越化学、三井化学、UBE、日東電工
・安川電機、ヤマハ発動機、三菱電機、富士電機、パナソニック、ソニーグループ、セイコーエプソン、京セラ、ヤマハ
・テルモ、オムロン
・関西電力、中部電力、東京ガス
・フジクラ、住友電気工業、コムシスホールディングス
・三菱重工業、川崎重工業、IHI、コマツ、日立建機、太平洋セメント
・大日本印刷、凸版印刷
・日本たばこ産業、ニチレイ、キッコーマン、ニッスイ
・NTTデータ、NTT
・リクルートホールディングス、資生堂、日立造船、セコム、ファーストリテイリング、KDDI、ダイキン、日本板硝子、シチズン時計(これらは個別株物色)
・イオン、セブン&アイホールディングス、丸井グループ、三越伊勢丹ホールディングス
・荏原、村田製作所、東京エレクトロン、ファナック、オークマ、キーエンス、TDK、アマダ、SMC、ミネベアミツミ
・三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、東京海上ホールディングス、オリックス、日本取引所グループ
・オリエンタルランド、東宝、任天堂、ネクソン、バンダイナムコホールディングス
・サッポロホールディングス、アサヒホールディングス
さらにはNECや富士通など、幅広く強く上昇してきた。
もう少し長い間隔で見ると川崎汽船、商船三井、日本郵船などの海運も非常に強い。
大体はセクター別に物色している点を見ると、何となく年金(GPIF)が無理に買っているような印象を受けるが、さすがに運用成績を無視してそんなことをするとは常識的には思えない。
誰が買っているのかはよく分からないが、いずれにしても巨額資金を一気に投入してひたすら買い続けるというやり方をしている。
もし年金がこの異常な上値追いをしているのだとしたら、暴落があった時にとんでもない巨額損失を出すことになる。
・追記
これまで日経平均株価を特にけん引してきた商社株は資源価格の高騰と円安によって恩恵を受け、過去最高益になっているが、これはロシアのウクライナ侵攻を受けてのことであり、日本株はロシアのおかげで爆上げしていると言っていいのかもしれない。
しかし、商社株以外にも非常に強く上昇している銘柄が幅広くあることから、日本はそんなに景気が良く(収入と消費が好調)、設備投資も活発で、先行きに不安がないのかというと全くそんなことはなく、日銀短観(3月)の大企業製造業の業況判断DIは前回調査から6ポイント悪化の「+1」程度であり、5四半期連続での悪化となっている。
「リベンジ消費」も起きず、個人消費の回復傾向が他国に遅れて強まっていくとの期待も崩れている。
リスクは物価高から景気悪化へ:景気後退前夜の日本経済を映す3月短観 | 2023年 | 木内登英のGlobal Economy & Policy Insight | 野村総合研究所(NRI)
アメリカの金融危機、世界的なインフレなどもあり、まだまだ予断を許さない状況になっている。
企業債務がトリガーとなる米国経済・金融危機 | 2023年 | 木内登英のGlobal Economy & Policy Insight | 野村総合研究所(NRI)
消費者動向調査を見ても、持ち直してきてはいるが「好景気」とはとても言えないことが分かる。
日本株は実体経済からかけ離れた動きをしているが、誰が何の目的でやっているのかは不明であり、どういう資金を使っているのかも定かではない。
国内外の経済を見ても、国際情勢を見ても、新型コロナウイルス・インフルエンザ・麻疹などの感染拡大を見ても、先行きが明るいようには思えず、少子高齢化や労働力不足や低賃金といった状況も全体としては何ら改善していないのだから、もし岸田政権が株の上昇にばかり固執しているのだとしたら後々大変なことになるのだろう。
極東の紛争や災害のリスクもあるはずだが、真剣に取り組んでいるようには思えない。(どの問題に対応するにしても場当たり的な発言をしたり、感覚の狂ったバラマキばかりやっていて、何も理解していないように見える。)
・追記
日経225構成銘柄の中で半導体関連銘柄として最も好業績のアドバンテストは株価も異常な伸びになっているが、半導体製造工場の設備投資がアメリカを中心に堅調になっていることが主な要因らしい。
「主要半導体メーカーの在庫調整プロセスが2023年中にはほぼ完了」し、2024年から大きく回復する予想が出ている。
受入れ国・地域別の2024年の支出見込み額は、「日本については、大幅な落ち込みとなった前年(50%減)から一転し、同82.2%増の70億ドルとされている」とのことから、2024年以降は非常に強い需要回復予想になっている。
「2022年半ばごろを境に、需要にブレーキがかかった世界の半導体市場。2023年前半も、悪化する市況に回復の兆しが見えない状況が続く。世界の主要半導体メーカー各社はグローバル市場の急激な変化に対応すべく、在庫調整・削減の取り組みを優先しており、製造装置や素材などの周辺企業も深刻な受注減に直面する。」
「半導体需要が減少する中でも、先端半導体の製造工場の新設や増設のための設備投資は、米国を中心に2023年も堅調に伸び、過去最高額を更新する見通しが示されている。」
とジェトロのレポートにはある。
スマートフォンやパソコンなどの末端市場の需要は弱く、最大の需要国である中国の経済失速は改善する見込みがないにもかかわらず、アメリカ、韓国、日本、台湾は積極的に半導体分野への投資を加速させており、カナダの技術情報サービス会社TechInsightによれば前述の通り、2024年から非常に強い半導体の需要が予想されている。
しかし、極東の地政学リスクは日々高まる一方であり、特に台湾情勢で問題が生じれば半導体分野への打撃は避けられないはず。
実体経済を見ても消費が低迷している中で本当に2024年から末端需要が大きく回復するのか疑問がある。
要するに、今後、極東での紛争リスクが高まり、全体として見れば景気は悪く、消費も低迷しているのに日本やアメリカなどの政府は妙に半導体分野への投資に前のめりになっている。
政府としては半導体への期待が非常に強いようだが、その根拠が個人的にはよく分からない。
もしTechInsightの予想が外れ、深刻な景気後退、極東での紛争、大災害などが起きれば半導体分野への投資は先走り過ぎたことになり、また失速することになるのだろう。
(現時点では政府内にそのような悲観的なシナリオは全くないらしい)
(結局、アメリカは中国へ半導体規制を行っていたり、台湾有事が起きやすくなるように台湾を国連に加盟させようとしていたりするが、アメリカの思惑通り台湾有事になった場合に備えて自国にTSMCなどの工場を建設しているのだろう。しかし、そのような投資は末端の需要回復とは関係ないはず。それどころか、むしろさらに需要が低迷するように思える。)
・追記
バークシャー・ハサウェイが6/19に日本の5大商社株を買い増したとの報道が出ている。
(厳密に言えばその完全子会社のナショナル・インデムニティー・カンパニーが三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅、住友商事の株式保有率を上げている。)
確かに19日の三菱商事や三井物産の株価を見てみるとまた上昇しているが、バリュー株を長期保有する目的でバークシャー自身が株価を吊り上げているとは考えにくい。
普通はバリュー株の長期投資が目的なのであればこのような株価のつり上げなどしないように思える。
よく調べてみると、バークシャーは2020年頃から三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、丸紅、住友商事の株式取得を進めていて、その時から9.9%まで保有率を引き上げる可能性を示していた。
しかし、円安傾向がさらに継続している中でここまで爆上げさせながらわざわざ高く株を買って長期保有するものなのだろうか。
そろそろ仕上げの段階に入り、提灯を付けることで約2年間保有してきた日本の5大商社株を売りさばこうとしているのか、それとも何らかの理由があってどうしても日本の5大商社株が欲しかったのか、そのどちらかなのだろうが、単に分散投資の観点から買い増しただけなのではないかという記事が2022/11/21の時点で掲載されている。
個人的にはバークシャーが既に安値で仕込んで大量保有していた商社株を別の誰かが最近になって異常に吊り上げ、バークシャーの方はもう売り払って利益を出そうとしているのではないかと思える。
もしそうなのであれば、バークシャーは現在、莫大な含み益があり、これから大量に処分することによって吊り上げている者は高値掴みをして大損することになる。
19日になってさらに「買い増した」と報じているが、実際にはほとんど買っていない可能性がある。
(ほんの少ししか買っていなくても「買い増し」であることに変わりはない。また、「9.9%まで保有することを望んでいる」とのことだが、必ずその保有率になるまでひたすら買い続けるとは言っていない。)
【参考】
バフェット氏は約2年前、バークシャーが約1年間かけて日本の5大商社株を5%超取得したことを明らかにした上で、長期保有を意図しているとして保有率を最大9.9%に引き上げる可能性を示唆していた。今回は、為替の円安進行や資源価格の高騰などにより、商社各社の業績が足元で好調に推移している中での保有比率の引き上げとなった。
いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は、円安が止まらなければ投資しても損になるため、米国での金利上昇が終わり、円安も止まるとの観測が市場で広がる中、保有を増やす「タイミングはばっちり」だと指摘した。さらに、分散投資の観点から米国以外での投資を増やす意向があり、日本特有のバリュー株として買い増したのではないかと推察した。
バフェット率いるバークシャーが5大総合商社を買い増し|会社四季報オンライン (toyokeizai.net)
・追記
日本企業の設備投資は主にソフトウェアに対してのものであり、それ以外についてはあまり回復していないのだと「みずほリサーチ&テクノロジーズ」の調査チームは解説している。(2023年3月29日の記事)
ソフトウェアが伸びている主な理由は深刻な人手不足であり、人手不足を補うために投資しているらしい。
(化学と生産用機械はソフトウェア以外も伸びているが、これが恐らく半導体関連なのだろう。)
みずほリサーチ&テクノロジーズ : コロナ禍でも堅調なソフトウェア投資 ─ 設備投資の本格回復に向けた嚆矢になるか? ─ (mizuho-rt.co.jp)
・おまけ
暴落リスクを分かっていて年金が狂った買い方をしているのであれば、岸田政権は意図的に年金の積立金を無くそうとしていることになるが、もしそうならこれから凶悪犯罪がさらに増えていくのだろう。
狂人のような官僚の思惑通り、これまで虐げられてきた層が生活に困って奴隷労働をしてくれることはないように思える。
最近、関東学院大学の教授が年金の積立金(200兆円)を取り崩して「第1子に1000万円の給付を」などという提言をしているが、こういう発言が大々的に報じられていることからも、岸田政権内にそのような考え方をしている者が一定数いるようにも思える。
(そもそも、一般常識として、年金の保険料を払っている者が勝手にそのようなバラマキをされて何とも思わないわけはないし、ただでさえ現役世代の保険料負担が重すぎることを理由に受給開始年齢の引き上げをしているのに、この大学教授は何を言っているんだと思ってしまう。)
一時期、BNFやcisといった「ジェイコム株大量誤発注事件」で大儲けし、その後も巨額の利益を叩き出して数百億円儲けたとされる胡散臭い者が世間を騒がせたことがあったが、これもナチズム的思想を持つ官僚や一部の業界関係者の都合で作られたペテン師(打ち子)のような存在なのだろう。
(最近ではすっかり表に出てこなくなったが、さすがにバカげた資産推移と取引手法だったため、余程のバカ以外騙されなくなったためなのだろう)
これらの人物は「乖離率が大きい銘柄が買い」(つまり、負け組の銘柄や何か問題を起こした銘柄)とか、パチンコで儲かりまくった経験を活かして株でも勝ったなどという嘘を吐き、人を欺いてきたが、当然、こういう人物は人を儲けさせようとしていたのではなく、人を嵌めるために官僚や業界関係者が演じさせていたにすぎない。
日本の官僚には団塊世代と団塊ジュニア世代を邪魔だと思っている者がどうやらいるらしく、その世代の数をどうしても減らしたいという目的から、つまらない悪さをしているように思える。
そういう連中からすればそれらの世代が奴隷労働に回って死ぬまでこき使われたり、自殺などしてくれれば最高ということなのだろうから、いろいろと悪知恵を働かせたり嫌がらせなどをして「間引き」するということなのだろう。
・追記
BNFなどのペテン師(役者)を信じて急落している負け組の株を買ってリバウンド狙いなどしていれば、当然負けるわけだが、そのように誰かを陥れたり、誰かを犠牲にすることで誰かが助かるといった手口が横行していた時期があった。
ろくでもない銘柄を売りさばいたり、下げ相場の時にポジション整理をするには、誰かが急落していく中で買ってくれないといけないことになる。
つまり、どこかの大株主の都合のためにメディアや証券業界などが役者を立てて人を欺き、財産を奪っていたのだろう。
そのような詐欺的行為によって財産を失ったり、最後の希望を失ったりした者が結局、奴隷労働コース確定になる。(あるいは自殺か犯罪者コースになる。)
それは国にとって必要な存在なのだから、単に大株主や証券業界などの都合だけで詐欺的行為を働いていたのではなく、奴隷を必要とする企業や、自殺者を必要とする官僚や、犯罪者を必要とする警察なども関わっていたように思える。
そしてBNFやcisのようなペテン師(役者)の年齢はちょうど団塊ジュニア世代や氷河期世代と重なっており、まさにその世代をターゲットにしていたのではないかと思えてならない。