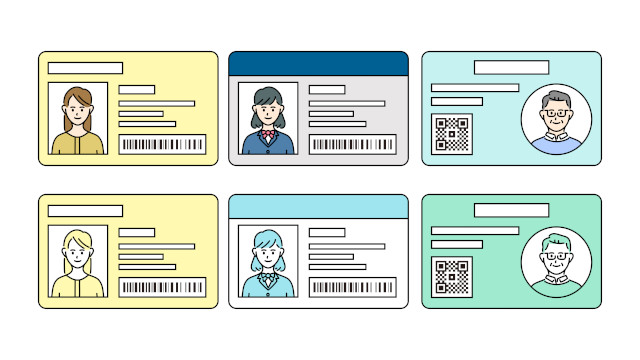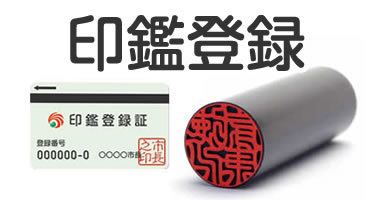デジタル庁では以下のようにマイナンバーカードの安全性を強調している。
マイナンバーカードの安全性
・紛失時の一時停止
・24時間365日のコールセンターを設置
仮に紛失した場合、個人番号カードコールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
マイナンバーカード券面
・顔写真付のため悪用は困難
仮に紛失しても、第三者が、容易になりすますことはできません。
・各種対策により偽造は困難
文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施す等により、券面の偽造を困難にしています。
ICチップ
・ICチップには必要最小限の情報のみ記録
「税関係情報」や「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
・ICチップに記録されている情報を確認可能
券面事項表示ソフトウェアを利用し、ICカードリーダ/ライタにかざすことで、ICチップに記録されている情報を確認することができます。
・記録情報の盗取は困難
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
・利用には暗証番号が必要
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
・セキュリティの国際標準の認証を取得
ICカードのセキュリティの国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。
しかし、マイナンバーカードが盗難されたり紛失したりした場合、最悪の場合、別の顔写真を貼ったり代理人を使ったりすることで本人になりすまして、住民票の入手や書き換え、印鑑登録の変更、婚姻届や死亡届などの行政手続きが可能になるという指摘もある。
もし本当にそんなことが可能になれば、本人が個人番号カードコールセンターに電話するまでの間に勝手に死亡届が出されて記録上は死んだことにされたり、見ず知らずの誰かと婚姻関係にあるということにされたり、印鑑登録を変更されて住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続など、重大な契約をされてしまったり、住民票を変更されて銀行口座の取得などに悪用される、といった悪質な犯罪に利用される危険性がある。
政府与党がなぜここまで急いで制度を変更したいのかは不明だが、自民党は安倍政権以降、あまりにも強引なやり方で法整備をしてきた経緯があり、いずれの法整備も国民にとって害になることばかりだったために今回の件も非常に不信感がある。
【参考】
河野太郎デジタル相は2022年10月13日、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、紙やプラスチックカードの健康保険証を2024年秋に廃止する方針を発表した。既存保険証の新規発行を停止することで、マイナンバーカードへの置き換えを推し進める狙いだ。
政府が今回示した方針案では、紙やプラスチックカードの保険証は2024年秋から新規発行をやめる。発行済みの保険証はこれ以降も使えるが、住所変更や転職などによって保険証の記載事項や発行機関が変わった際には、マイナンバーカード上での再発行だけになる。マイナンバーカードの取得を強く迫ることになるため、実質的な「マイナンバーカード義務化」との見方が強い。
・追記
マイナンバーカードで本人確認として使われる顔写真は発行日から10回目の誕生日を迎える頃でなければ更新されない。(18歳未満は5回目)
10年近くも同じ写真を使うというのも本人確認機能として不十分な感覚がある。
本人が年を取ったり何らかの障害を負ったりすることで顔が変わってしまっているために、行政の方では本人なのに偽物判定されてしまうといったこともあり得る。
また、暗証番号を知っていれば盗んだマイナンバーカードに使われている写真とそっくりの人物を使って行政手続きや契約をすることが可能になる恐れもある。
つまり、別人の写真を貼ったりしなくても、暗証番号が漏れていると顔さえ誤魔化すことができれば通ってしまう。
これまで特に問題があった制度でなかったのであれば、なぜここまで強引に新制度の導入を急ぐのか疑問。
河野太郎デジタル相は「もっと前倒しができるかを考えよ」などとデジタル庁内で発言し、妙に時間的にプレッシャーをかけている。
人間というのは時間的余裕を失うと必ずと言っていいほど判断ミスを犯すため、マイナンバーカードを普及させるにはもっと説明やセキュリティについて対策が必要なはず。
河野太郎という人物はハンコ文化を衰退させたり、ワクチン接種に前のめりになっていたり、マイナンバーカードの普及を急いだりしていることから、妙に現状変更を試みる人物であり、保守的な人物ではないらしい。