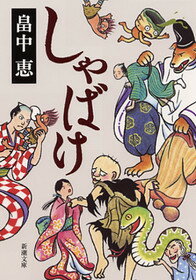2023年11月のテーマ
「いっぱいあるぞ!時代小説」
第二回は、
「しゃばけ」
畠中恵 著、
新潮文庫、2004年 発行
です。
畠中恵さんは漫画家のアシスタントやイラストレーターを経て小説家になられたという方です。私はこの「しゃばけ」シリーズ以外の作品は読んだことがないので、申し訳ないですが、作者について語れることはほとんどありません。
「しゃばけ」はシリーズ第一作目にあたり、2001年の日本ファンタジーノベル大賞・優秀賞受賞作品です。
ドラマ化、アニメ化、漫画化もされている人気作なので、ご存じの方も多くいらっしゃると思いますが、一応あらすじを。
江戸有数の大店、廻船問屋の若旦那・一太郎は生まれつき体が弱く、十七歳になるまでに何度も死にかけたことがあります。両親は一人っ子の一太郎を大層かわいがり、常に彼の体調に気を配っています。若旦那の周囲にはいつも妖怪たちがいて、中でも強い妖怪の犬神と白沢は人間に化けて廻船問屋で働きながら若旦那のお目付け役をしています。
両親とお目付け役の妖怪たちにいつも気を配られ、ありがたいとは思いながらも息苦しく感じてしまうのは年ごろの若者としては仕方のないところ。彼らの目を盗んでやっと外出した帰りに、一太郎は人殺しを目撃してしまいます。
その日を境に周囲でおかしな事件が起こり始め、どうやら一太郎にも無関係ではないらしい…。
虚弱体質ではあるけれど聡い若旦那と、若旦那第一の妖怪たちが活躍する"時代劇・ファンタジー・ミステリー小説"です。
この小説はすごく長いシリーズの始まりの一作なわけですが、なぜ一太郎には妖怪が見えるのか、妖怪の犬神と白沢が一太郎を守ってくれているのはなぜなのか…という根本的な謎がまずあり、その理由が明らかになるのと、作中で一太郎にも降りかかってくる事件の謎の解決との両方がきれいにまとまっていて、"はじまりの物語"としてとても優れていると思います。
また、文章がやわらかく、時代小説なのに現代風に感じられて尚且つ興ざめしないところが作者の手腕が光っていると思います。
時代小説を読んでいると、言葉遣いや風俗、情景描写などでその時代の息吹が感じられないと味気ないですし、作家さんの方でもなるべく雰囲気を出すように力を注いであるなあと感じます。
要するに、読みやすさを重視してあまりにも現代風の文章で書くと時代小説としての雰囲気が壊れてしまい、このジャンルの小説特有の情趣を感じられなくなって、かえって作りものっぽく感じたり安っぽく感じたりしてしまうのではないかと思います。
ですが、「しゃばけ」はそのあたりのバランスが絶妙で、読みやすいんだけどちゃんと江戸時代だと感じられる言葉遣いで書いてあるのです。
具体例を挙げると、擬声語・擬態語をカタカナで書いてない…「どすん」「げほっ」「するり」みたいに、ひらがなで書いてある。さらに言うと、「がつっとぶち当たって」ではなく「がつんとぶち当たって」のように書いてある。要するに、短く切った印象を与える言葉を使わないようにしてある気がします。
侍がではなくて、商人が主人公だからか、一人称が「あたし」だったり、語尾に「~だい?」とか「~だねえ」がついたり、言葉遣いがとにかくやわらかいと感じます。
そのため、堅苦しい感じがなくて、のんびりと読めるような気持がするのです。
あとは、やはり登場人物(?)が魅力的。若旦那のキャラクターも体は弱いが決して心は弱くないですし、お付きの妖怪である仁吉こと犬神は役者かと見まごう美形だし、佐助こと白沢は腕っぷしの強い大男ときています。ほかに出てくるたくさんの妖怪たちも可愛かったり怖かったり。若旦那にお菓子をねだるやつがいるかと思うと、一緒に碁を打ったり、道案内をしてくれたりと楽しい存在です。
ストーリーはもちろん面白いんだけれども、私にとって「しゃばけ」の面白さは妖怪たちに囲まれた一太郎の生活そのものに興味が尽きないというところにあるのだと思います。
彼はずっと病弱で、これから劇的に体が強くなるとはとても思えません。
弱い体に対するいら立ちや不満という屈託をずっと抱えているにもかかわらず、生きていること、みんなに生かされていることに感謝と申し訳なさを感じている。閉じこもっていることが多い彼の友達は幼馴染の栄吉の他には妖怪ばかり。人と違う生き物だけれど、一太郎はそいつらとワイワイ生活していて、はた目には楽しそうにさえ見えます。
第一、日本人なら妖怪…好きですよね?
「しゃばけ」はファンタジー小説ではありますが、れっきとした時代小説です。
漫画やドラマで楽しむのもいいですが、私としては、作者のやわらかい文章で時代小説というものを味わってみてほしいと思います。
おすすめいたします。(*^▽^*)