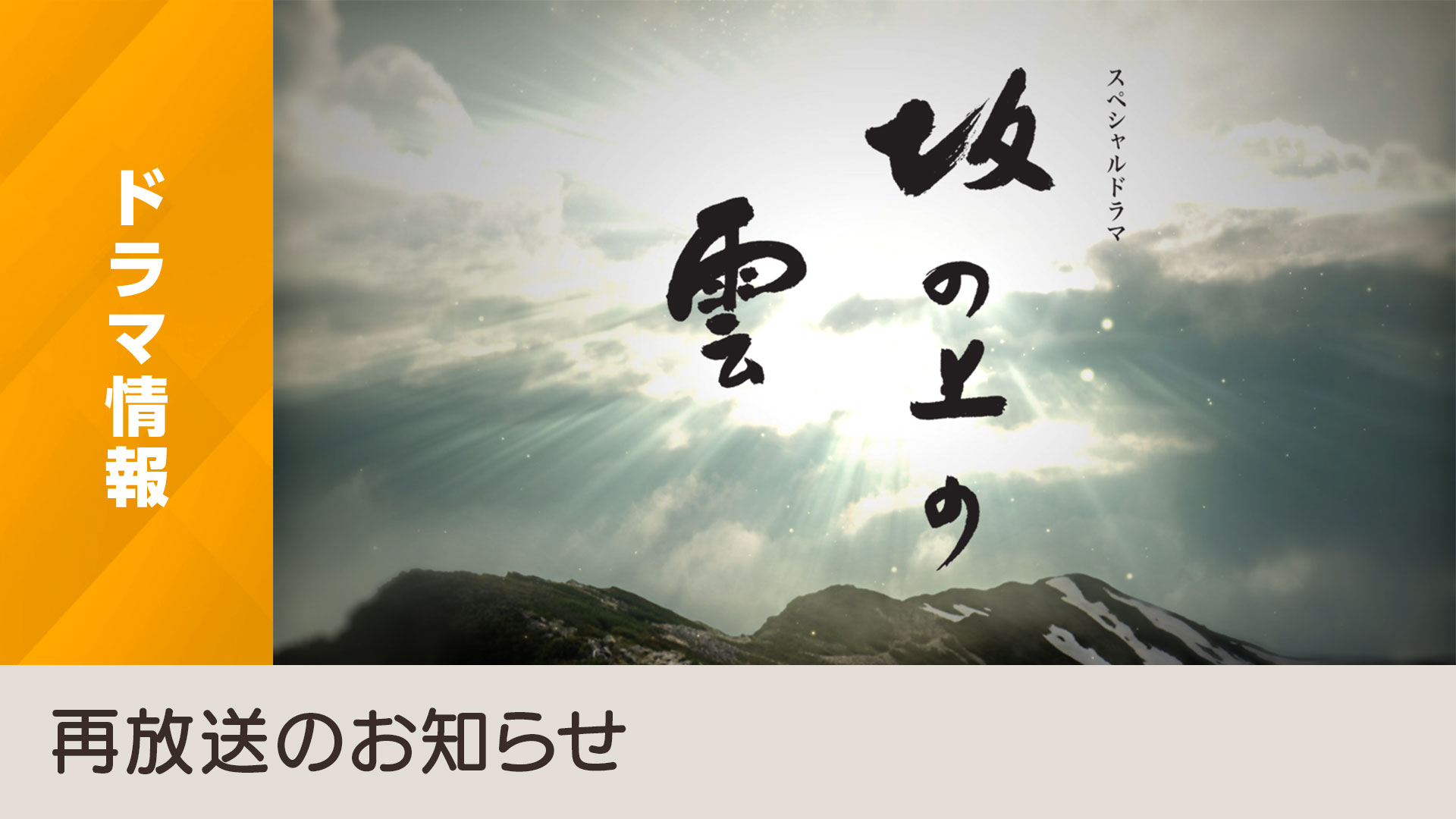ふとネットでみかけた記事ですが、15年前に3年に分けてNHKで放送された「坂の上の雲」が9月に再放送されるそうです。司馬遼太郎氏原作のこの小説、私は大学生の頃に読んで、司馬作品の中でも一番好きになって、以後、10年に一回くらいの頻度で読み返しています。主な主人公は愛媛・松山の城下町に生まれた秋山兄弟と正岡子規。この3人を中心に日清・日露戦争の時代を背景にしたスケール感のある長編小説です。
![]()
![]()
![]()
![]()
私自身は日本国内を旅するときはこの小説ゆかりの土地があると必ず訪れるようにしてきました。![]()
*愛媛県松山市の坂の上の雲ミュージアム、秋山兄弟の生家跡
*大分県竹田市の広瀬神社(広瀬武夫を祀ってある神社です)
*鹿児島市の加治屋町。(たった70戸しかない集落から西郷隆盛、大久保利通、大山巌、東郷平八郎などが出てます)
*神奈川県横須賀市の戦艦三笠。
*京都府舞鶴市の司令長官官舎。(東郷平八郎が初代司令長官が過ごした家)
*新潟県長岡市の山本五十六記念館(五十六さんは若い頃に日露海戦に従軍。
*愛知県犬山市の明治村・西郷従道邸
すぐ思いつくものだけでこんなところに行きました。
生前の司馬さんは小説の映像化は許可してなかったそうです。この小説のスケール感はとても映像では表現できないからではないかと思ってました。実際、放映が3年に分けられたのも製作費がかかりすぎたからかなあ?とも思ってます。近年は日露戦争は本当に祖国防衛戦争だったのか?とかいう見方があったり、司馬史観も見直す動きがあるようですが、停滞と閉塞ばかりを感じる今の日本にいて、そこから司馬作品に描かれた明治期をみると、同じ日本でこんな時代があったのかと思うくらい新鮮な気持ちになります。爽やかな五月の風に吹かれているような。人間の成長過程でいえば当時の日本は「青年期」。庶民のひとりひとりにまで生気と躍動感があった時代です。
長い目でみると、日露戦争で勝ってしまったことで国民が勘違いして、のちの太平洋戦争につながるともいえるのだけれど、この時代の精神って学ぶこと多いと感じます。秋山弟を演じた本木雅弘さんは小説のイメージそのままの感じ。兄役は阿部寛さん。この役で阿部さんに豪快なイメージを持つようになりました。子規役の香川照之さんは怪演〜。最後のほう子規にしか見えなくて。
いまから楽しみです。