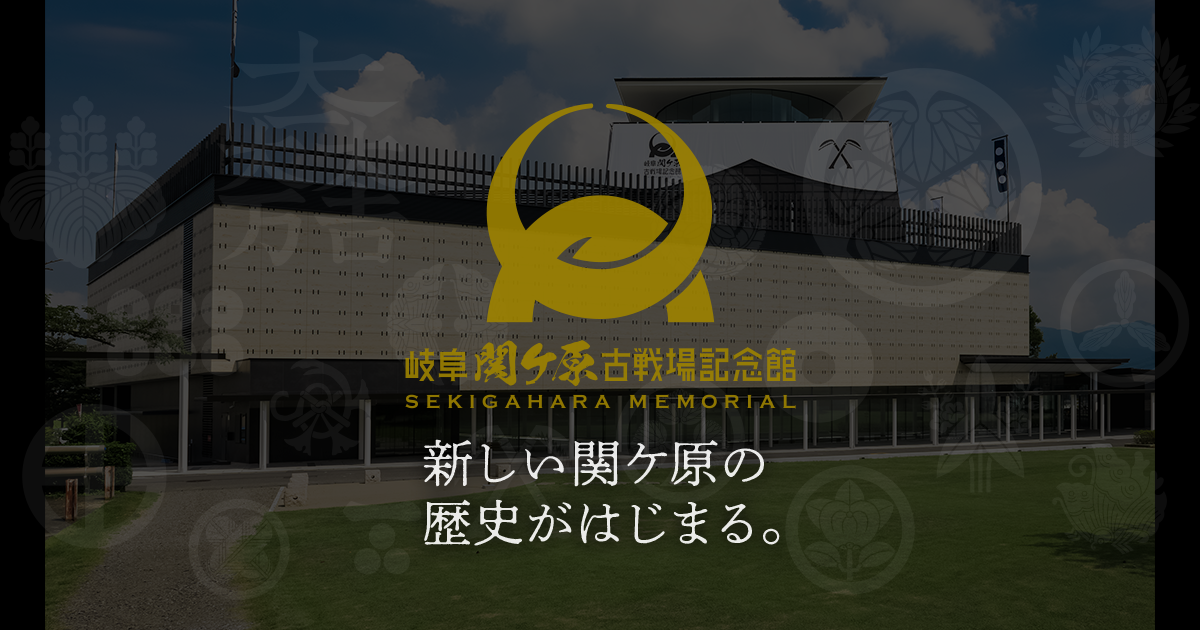4月30日。岐阜県の関ヶ原古戦場に行ってきました。過去に3回訪れていて今回で4回目です。前回までは三重県から出かけていたため関ヶ原は随分遠いところにある印象でしたが、現在の住居から地図をみると意外と近いことを今更ながら知りました。北琵琶湖沿いの一般道を通って90km、2時間弱の距離です。
この日はお昼ごろに現地に到着し、東西武将らの陣跡を巡りました。全て周ることはできませんでしたが合戦場でのそれぞれの陣跡の距離感を感じることができたように思います。
この日、最初に向かったのが古戦場記念館です。
関ヶ原古戦場を最後に訪れたのはもう15年くらい前。当時はかなり古い資料館などがあったのみでこんな立派な建物はありませんでした。この記念館、内部には最新の映像技術を使ったシアターや戦国時代の武具甲冑や古文書などの展示エリア、最上階は古戦場を360度の角度から見渡すことができる展望室などがあり、関ケ原を訪れる人はぜひ行くべきところかと思いました。各武将らの甲冑展示などレプリカではありましたが緻密に再現されていて迫力がありました。
前回、昔の資料館(いまもあるのかな?)を訪れた時には、大将級の人のものではなく、実際に戦場で戦っていた兵士が着用していた、1600年当時の鎧甲冑の本物が展示してありました。黒ずんでボロボロになった鎖帷などです。戦場にハイエナのように現れた盗賊が戦いで亡くなった人の身体から刀剣や鎧をはぎ取っていったそうで、もしかしたら私が観たものもそのひとつだったのかもしれません。何かとりついてそうな怖さがありましたが、今回目にした展示品はとても美しい工芸品のようでそんなおどろおどろしさは全くありませんでした。
シアターは時間の都合で観ませんでした。風が吹いたり椅子がガタガタ揺れたり実際の戦乱を体感できるリアルさがあるそうで、時間待ちの行列ができていました。
最上階からの眺めです。位置的に古戦場のほぼ中央にあり、ここから関ヶ原の地形を眺めながら、布陣の様子などを想像することができます。
記憶っていい加減なものです。初めて関ヶ原の街を訪れた時、何もないところだなと思っていたはずなのに、今回再訪してみたら結構建物も多くあって驚き。
地理的な概要を頭に入れて、これから各陣跡巡りです。最初に向かったのは石田三成陣跡がある笹尾山です。
三成の重臣、島左近の陣地は真横に。この人も戦国武将では人気ありますね。
矢来が再現されています。
笹尾山を登りました。数分程度の軽い登山です。
展望台があります。ここから古戦場が一望できます。
合戦当時の布陣図がネットにあったのでお借りしました。石田三成は戦場を一望でき、交通の要衝を抑えられる笹尾山に布陣しました。地図の左上の隅っこです。
赤色が東軍、青色が西軍です。こうやってみると高台や山など高地に西軍、平地に東軍となっているのがわかります。その形状は「鶴翼の陣」といって青色の鶴が翼を広げて赤色の相手を包み込むようなかたちです。人数も西軍のほうが多くて、戦術的には西が圧倒的勝利になっていたはずなんです。・・が、西軍の武将たちの殆どは三成が期待したように動きませんでした。右翼にある南宮山の毛利軍は一兵も動かさず、松尾山に布陣していた小早川秀秋は徳川軍に寝返り、その周囲にいた脇坂、朽木氏らも寝返り味方に攻撃をしかけます。
とっても頭の良かった三成は完璧な戦の準備をしていたのですが、現実は理論通りには動かなかったんです。三成はいわゆるエリート官僚タイプだっただけに加藤清正とか福島正則らのような武断派の武将たちからは嫌なやつみたいな感じで嫌われてました。この好き嫌いの感覚、いまの時代でも一緒ですね。そういう両者の感情面での齟齬を見抜いて武将たちの心をつかんでいたのは東の家康でした。私は関ヶ原の戦いの経緯については司馬遼太郎の小説で詳細を知りましたが、データや計算値だけでは物事は動かないということを当時強く感じたことが今も印象に残っています。といいながらも司馬小説の影響を受けてるためか三成のことは結構好きなんですが。
この次は西軍の島津義弘、小西行長らの陣跡にいってみました。長くなりそうなので3回くらいにわけようと思います。続きます~