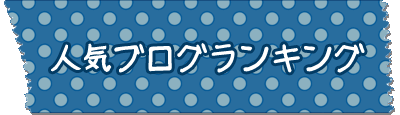「ティール組織」を斜め読みしました。
集団にはいろいろな形があり、
どんな形も一長一短あり、これだという答えはありません。
世界は常に変化しています。
ならば、
組織の形態も臨機応変さが重要だということ。
一つの形に縛られず、状況状態、向き不向きによって変更可能な
のりしろを持つことが大切だと思うのです。
※昨日は急遽サントリーホールサマーフェスティバル2018に参戦。素晴らしい時間でした。
今朝の朝日新聞「文化・文芸」欄に
「指揮者薬袋オケ『耳』で協奏」という記事がありました。
オケの奏者は周りの音を十分に聴かず、ハーモニーを作り出せていないことが多いと感じる。
ヒエラルキー構造に原因をみる。指揮者、コンサートマスター、首席奏者と「指示する人が多すぎる。志を持って入った人も、がんじがらめで意欲を失う」。
なるほど、それは一般の組織にも起こっていることでしょう。
自発性を引き出すため、アイコンタクトを禁止。ボーイング(弓の上げ下げ)はそろえず、コンマスや首席は固定せず、交代制にした。
そういう体制にすることでオーケストラに
何が起こったのかというと、
「弦がまとまり、音がイメージしやすくなった。耳が開いて全体が聞こえ、肩の力が抜けて楽に弾けた」
ここには自主性と協調とがバランスよく成立していますよね。
納得です。ただし、向き不向きもあるようです。
構造が複雑で大編成の曲は「聴き合う」だけでは合わせるのが難しい。「お薦めはモーツァルト」だという。
近現代に入り、
音楽が徐々に巨大化、複雑化することによって
演奏する側にも一定のヒエラルキーが
求められるようになったという点が、
産業界の発展に伴う、会社組織の巨大化、複雑化と
まったく相似形であることが
実に興味深いです。
「ティール組織」とは、
自主経営(セルフマネジメント)、全体性(ホールネス)、
存在目的を重視する独自の慣行を持つ組織と定義されますが、
組織を機能させるには、
メンバー個々が自律的であることと
組織に相互信頼が浸透していることが条件になります。
ちなみに、僕が思うのは、
構造が複雑かつ大きなものでも、
ZERO的つながりが醸成されれば
オケの場合のように「聴き合う」だけで合わせることが
容易にできる組織も作れるだろうということです。
今僕はそのことに挑戦しようとしています。
ということで、8月最後の日曜日。
善い一日でありますよう。
ありがとうございます。
ランキング・バナーのクリック何卒ご協力よろしくお願いします。m(_ _)m
自分を知ることからすべては始まる
ワークショップZERO
⇒http://seminar.opus-3.net/
ベーシックコース
★第87期東京コース:2018年9月2日(日)&9日(日)
★第88期東京コース:2018年10月13日(土)&14日(日)
★第89期東京コース:2018年11月17日(土)&18日(日)(予定)
★第5期西日本コース:日程調整中【広島県福山市内】
アドバンスコース
☆第6期東京コース:日程調整中