おはようございます。
昨晩は渋谷のとある企業様での
クラシック音楽講座でした。

モーツァルトを軸に
「全体観と挑戦」というテーマで
お話をし、映像で音楽を楽しんでいただいたのですが、
「全体観というのがよくわかりませんでした」
という感想をいただいたので、
捕捉の意味を兼ねてここに書いておこうと思います。

そもそも天才といわれる作曲家というのは
基本的に「全体観」に優れているのだと僕は思います。
というのも、例えば交響曲のスコアなどを見ると
明確ですが、楽器の選択含め縦の線が空間を表し、
横が音楽の流れ、つまり時間を表しています。
で、通常は、というか一般的には1曲に
何ヶ月、あるいは何年もかけて推敲し、作品を完成させる。
それですら大変な能力なのですが、
モーツァルトは異様に速筆だったと。
例えば、1788年のわずか2ヶ月ほどの間に
性格の異なる3つの交響曲を書き上げており、
しかもそれぞれが類稀な傑作であることが
驚異なわけで。
要は、最初から頭の中ですべてがそのまま
鳴り切っていたということです。
最初から最後に至るプロセス、時間感覚と
楽器のバランスという空間感覚のすべてが
完全であるという奇蹟とでもいいましょうか。
これこそは「全体観」以外の何ものでもない。
残された彼の手紙などでもわかりますが、
人生というものを悟り切ったようなものも
残されている。
つまりは、自分の死期すらわかっていて、
すべてが見えていたのではとすら思える。
そんなことを感じながらカール・ベームの指揮する
「ジュピター」交響曲を聴いておりました。
モーツァルトに限らずですが、作曲家というのは
本当にすごいですね。
あらためて思ったのです。
さて、本日は第56期ZERO第1日目です。
今日も楽しく、かつ有意義に過ごしたいと思います。
下のランキングボタンをワンクリックしていただけると幸いです。応援、ご協力よろしくお願いしますm(__)m
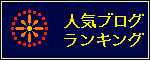
人気ブログランキングへ
昨晩は渋谷のとある企業様での
クラシック音楽講座でした。

モーツァルトを軸に
「全体観と挑戦」というテーマで
お話をし、映像で音楽を楽しんでいただいたのですが、
「全体観というのがよくわかりませんでした」
という感想をいただいたので、
捕捉の意味を兼ねてここに書いておこうと思います。

そもそも天才といわれる作曲家というのは
基本的に「全体観」に優れているのだと僕は思います。
というのも、例えば交響曲のスコアなどを見ると
明確ですが、楽器の選択含め縦の線が空間を表し、
横が音楽の流れ、つまり時間を表しています。
で、通常は、というか一般的には1曲に
何ヶ月、あるいは何年もかけて推敲し、作品を完成させる。
それですら大変な能力なのですが、
モーツァルトは異様に速筆だったと。
例えば、1788年のわずか2ヶ月ほどの間に
性格の異なる3つの交響曲を書き上げており、
しかもそれぞれが類稀な傑作であることが
驚異なわけで。
要は、最初から頭の中ですべてがそのまま
鳴り切っていたということです。
最初から最後に至るプロセス、時間感覚と
楽器のバランスという空間感覚のすべてが
完全であるという奇蹟とでもいいましょうか。
これこそは「全体観」以外の何ものでもない。
残された彼の手紙などでもわかりますが、
人生というものを悟り切ったようなものも
残されている。
つまりは、自分の死期すらわかっていて、
すべてが見えていたのではとすら思える。
そんなことを感じながらカール・ベームの指揮する
「ジュピター」交響曲を聴いておりました。
モーツァルトに限らずですが、作曲家というのは
本当にすごいですね。
あらためて思ったのです。
さて、本日は第56期ZERO第1日目です。
今日も楽しく、かつ有意義に過ごしたいと思います。
下のランキングボタンをワンクリックしていただけると幸いです。応援、ご協力よろしくお願いしますm(__)m
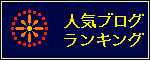
人気ブログランキングへ