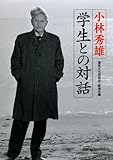こんにちは。
先ほどまで我孫子にいたのですが、
東京はひと雨降ったようですね。
午前中は雲一つない真っ青な空だったのに
路面が濡れていてびっくりしました。
それにまた雲行き怪しいので
また雨になるのでしょう。
さて、往復の車中で「小林秀雄 学生との対話」
を読みました。
僕の世代だと小林秀雄は国語の教科書でも有名で
受験の現代文では必須でしたので、当時相当読んだものです。
ちなみに、今では「全集」まで手元に置いています。
それにしてもこの人のイメージは厳格で気難しい
というものですが、ともかく言葉のひとつひとつに
説得力があり、いちいち膝を打ちます。
確かに学生の質問自体が稚拙だと剣もほろろなんですがね・・・。
昭和49年8月5日、鹿児島県霧島での講義
「信ずることと考えること」後の学生との対話から。
母親は子どもに対して、観点など持っていません。彼女は科学的観点に立って、心理学的観点に立って、子どもの心理を解釈などしていません。母親は子どもをチラッと見たら、何を考えているか、わかるのです。そういう直観は、交わりから来ている。交わりが人間の直観力を養うのです。精神官能だとか、やかましいことを言わなくとも、僕らは感応しているのです。まるで千里眼みたいに、人間が一目でわかるということもあるのですよ。
P119
「交わりが人間の直観力を養う」のだと。
しかもすでに僕たちにはそれが備わり、
日々養っているのだと。(ここポイント!)
うまいことおっしゃる、さすがです。
ただし、これは40年前の講演ですからね。
その後の僕たちの直観がどうなっているのかはわかりません。
さらに、「人間はどうして言葉を必要とするのでしょう?」
という質問に対しては、様々例をあげながら次のように。
言葉ぐらい人間を助けているものはないけれども、こういう便利なものはいつでも人間を迷わしますよね。いつでも、物には裏表があるのです。理性はこんなに人間を助けているけれど、人間は助けてくれるものの虜になるんです。不思議です。だが、こういう不思議を解く人はいません。解けないよね。
人間は自分の得意なところで誤ります。自分の拙いところでは決して失敗しません。得意なところで思わぬ失敗をして不幸になる。言葉もそれと同じだな。言葉もそれと同じだな。あまり使いやすい道具というのは、手を傷けるのです。
P120
世界の表裏をはっきり見抜き、明言してますね。
しかも、はっきり「わからない、答えられない」と
言い切った上での回答ですからね。
この潔さ、断言が素晴らしいのです。
ところで、質疑に入る前の講演の内容自体が実に面白い。
当時流行したユリ・ゲラーの念力について前置きしつつ
「科学万能」「科学優先」主義の世情を憂えた考察になっています。
長くなるのであえて抜粋しませんが・・・。
電車の長旅は格好の読書時間。
ということで、本日はおしまい。
長くなりました。ありがとうございます。
人気ブログランキングに参加しています。
下のランキングボタンをワンクリックしていただけると幸いです。応援、ご協力よろしくお願いしますm(__)m

先ほどまで我孫子にいたのですが、
東京はひと雨降ったようですね。
午前中は雲一つない真っ青な空だったのに
路面が濡れていてびっくりしました。
それにまた雲行き怪しいので
また雨になるのでしょう。
さて、往復の車中で「小林秀雄 学生との対話」
を読みました。
僕の世代だと小林秀雄は国語の教科書でも有名で
受験の現代文では必須でしたので、当時相当読んだものです。
ちなみに、今では「全集」まで手元に置いています。
それにしてもこの人のイメージは厳格で気難しい
というものですが、ともかく言葉のひとつひとつに
説得力があり、いちいち膝を打ちます。
確かに学生の質問自体が稚拙だと剣もほろろなんですがね・・・。
昭和49年8月5日、鹿児島県霧島での講義
「信ずることと考えること」後の学生との対話から。
母親は子どもに対して、観点など持っていません。彼女は科学的観点に立って、心理学的観点に立って、子どもの心理を解釈などしていません。母親は子どもをチラッと見たら、何を考えているか、わかるのです。そういう直観は、交わりから来ている。交わりが人間の直観力を養うのです。精神官能だとか、やかましいことを言わなくとも、僕らは感応しているのです。まるで千里眼みたいに、人間が一目でわかるということもあるのですよ。
P119
「交わりが人間の直観力を養う」のだと。
しかもすでに僕たちにはそれが備わり、
日々養っているのだと。(ここポイント!)
うまいことおっしゃる、さすがです。
ただし、これは40年前の講演ですからね。
その後の僕たちの直観がどうなっているのかはわかりません。
さらに、「人間はどうして言葉を必要とするのでしょう?」
という質問に対しては、様々例をあげながら次のように。
言葉ぐらい人間を助けているものはないけれども、こういう便利なものはいつでも人間を迷わしますよね。いつでも、物には裏表があるのです。理性はこんなに人間を助けているけれど、人間は助けてくれるものの虜になるんです。不思議です。だが、こういう不思議を解く人はいません。解けないよね。
人間は自分の得意なところで誤ります。自分の拙いところでは決して失敗しません。得意なところで思わぬ失敗をして不幸になる。言葉もそれと同じだな。言葉もそれと同じだな。あまり使いやすい道具というのは、手を傷けるのです。
P120
世界の表裏をはっきり見抜き、明言してますね。
しかも、はっきり「わからない、答えられない」と
言い切った上での回答ですからね。
この潔さ、断言が素晴らしいのです。
ところで、質疑に入る前の講演の内容自体が実に面白い。
当時流行したユリ・ゲラーの念力について前置きしつつ
「科学万能」「科学優先」主義の世情を憂えた考察になっています。
長くなるのであえて抜粋しませんが・・・。
電車の長旅は格好の読書時間。
ということで、本日はおしまい。
長くなりました。ありがとうございます。
人気ブログランキングに参加しています。
下のランキングボタンをワンクリックしていただけると幸いです。応援、ご協力よろしくお願いしますm(__)m