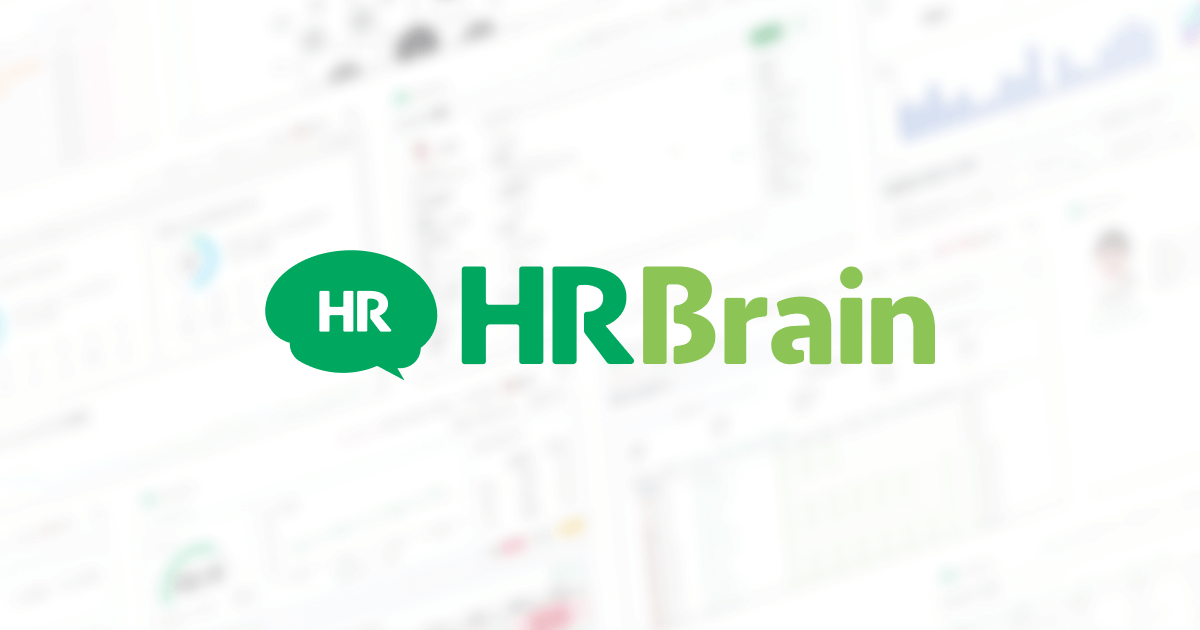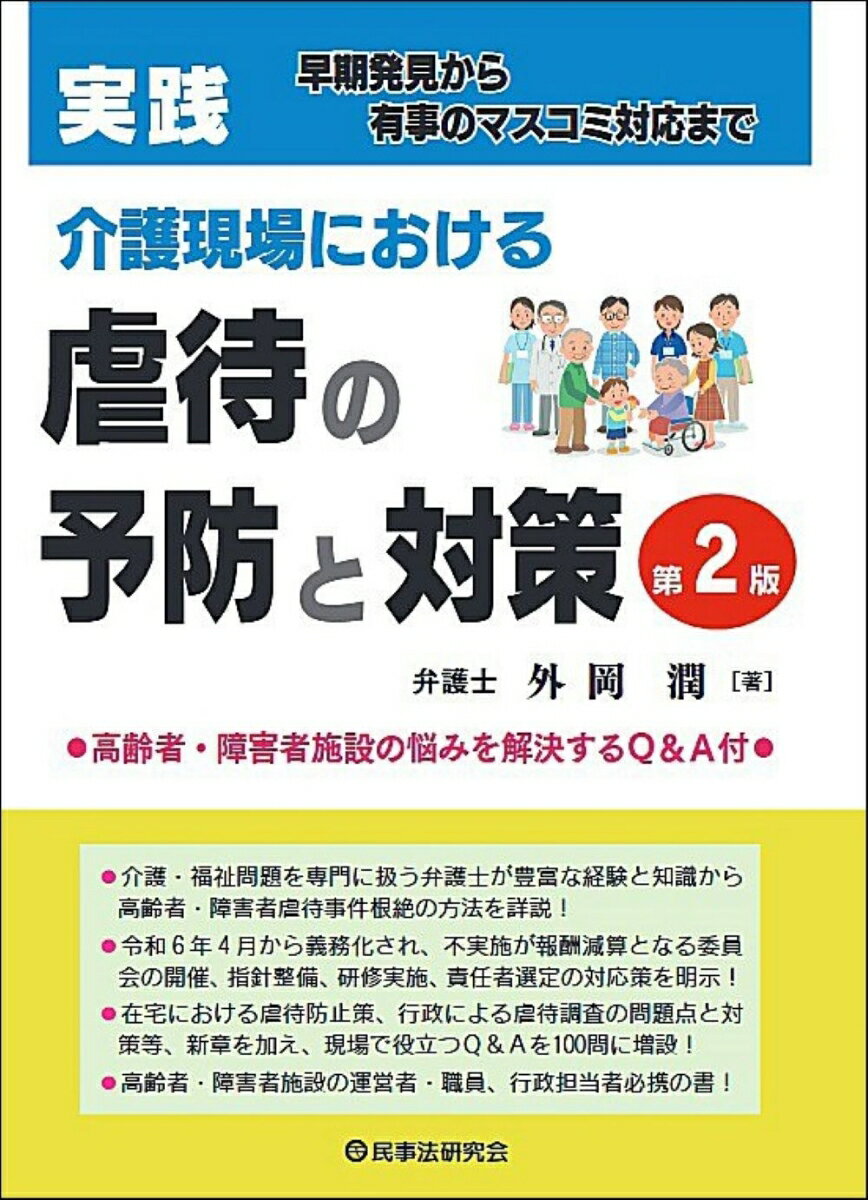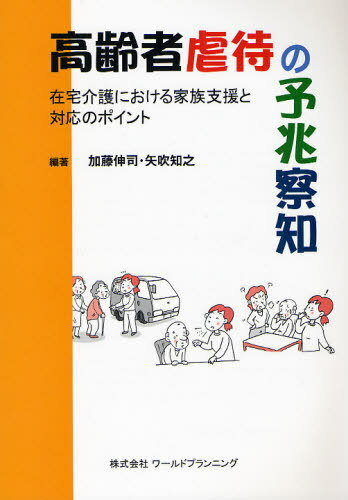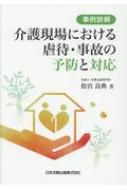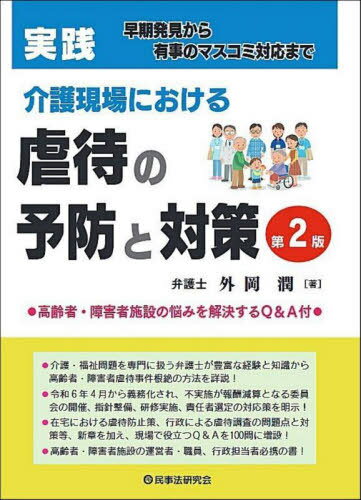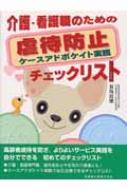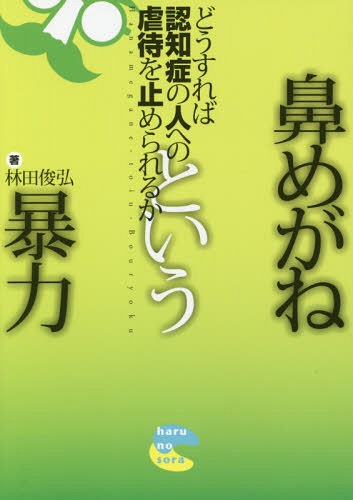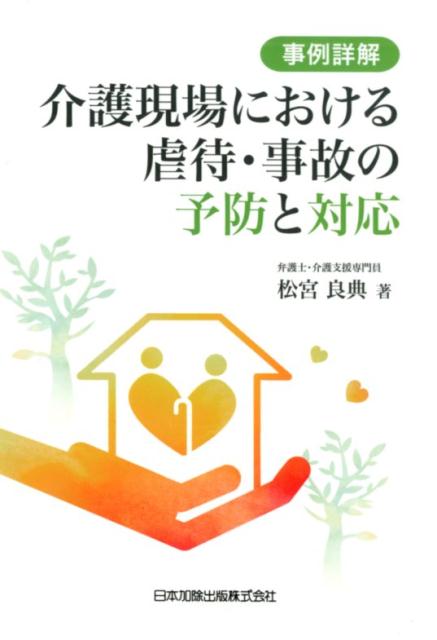こんにちは。
実は20年前は介護の業界で働いていました。なのでこういう事件は受け止めるのが辛いですね。
僕は最初にこのニュースを聞いた時に、また無資格者の起こした事件なのだろうと思っていました。現実に介護の世界では、専門の知識や経験がなくても就労することが出来ます。
✅ 無資格でも働ける可能性が高い施設区分
🧩 なぜ「無資格・未経験OK」が常態化しているのか
・構造的な人材不足
厚労省の推計では、2040年には約272万人の介護職員が必要とされており、現状から+57万人の増員が求められています。この逼迫した状況が「誰でもいいから来てほしい」という採用姿勢を生み出しています。
・制度的な“入口の広さ”
介護職は、2024年4月から「認知症介護基礎研修」の受講が義務化されましたが、入職後1年間の猶予期間があるため、無資格者でもすぐに働けます。つまり、「とりあえず現場に立てる」構造が制度的に許容されている。
・業務の切り分けによる“形式的安全”
無資格者は「生活援助」などの非接触業務に限定されることが多いですが、実際には有資格者の指示のもとで身体介護にも関わるケースがあり、現場では境界が曖昧になりがちです。
ただ、今回の事件に限って言えば、事件を起こしたのは「介護福祉士」でした。介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格であり、取得には一定の実務経験や教育課程の修了が必要になります。当然のことですが、介護や医療の現場において「倫理観」の低い人の就労は、ただでさえ人手不足で疲弊している現場において、望まない暴力事件などが起こる一因だと思っています。
⚠️ この構造がもたらすリスク
・倫理観・共感力の未検証
知識以前に「人としての適性」が問われる職種であるにもかかわらず、採用時にそれを見極める仕組みが弱い。
・事故・虐待の温床
介護知識がないまま現場に立つことで、誤った対応や感情的な衝突が起こりやすく、結果として暴力事件や事故につながる。
・職場の教育負担が増加
現場の有資格者が新人の教育に追われ、ケアの質が低下する。しかも教育の質は属人的で、標準化されていない。
最後の「教育の質は属人的で、標準化されていない」という言葉が痛いですね。結局は新人のこれから先の介護の質は「先輩次第」という事になります。暴力的な介護を是とする先輩に教われば、その後輩はその先もそれが是になり、その後輩も...という「負のスパイラル」が起こるわけです。こういった現場において、虐待があるかどうかは事業所の自己管理能力しか頼るものは無いのでしょうか?介護現場における暴力や虐待は、氷山の一角しか表に出ていない可能性が高く、業界全体がその「見えない部分」をどこまで把握しているかは、制度の透明性と倫理意識に関わる重大な問題です。
🧊 表に出ない暴力の“氷山モデル”
厚生労働省の令和5年度調査によると、介護施設従事者による虐待の通報件数は3,441件、そのうち虐待と認定されたのは1,123件でした。つまり、通報された中でも約3分の2は「虐待ではない」と判断されているわけです。 しかし、ここで重要なのは..
・通報されていないケースが圧倒的に多い可能性
認知症の方や寝たきりの方は、暴力を受けても言語化できず、周囲も気づきにくい。
・施設内で“揉み消される”ケースも存在
実際、虐待が認定された施設のうち約19.1%は過去にも虐待事例があったにもかかわらず、改善されていない。
・通報者の約28.7%が施設職員自身
これは内部告発が一定数あることを示す一方で、残りの7割以上は沈黙しているという現実も浮かび上がります。
🏢 業界はどこまで把握しているのか?
・厚労省は毎年詳細な調査を実施
虐待の発生要因として「知識・意識の不足」「ストレス」「倫理観の欠如」が上位を占めており、制度的には問題を認識している。
・虐待防止研修の実施率は75.1%
つまり、約4分の1の施設では研修すら行われていない。
・虐待防止委員会の設置率は64.6%
委員会がない施設では、虐待の兆候を組織的に検知・対応する仕組みが欠如している。
「性善説」にたてば、表に出ている問題が全てとも考えられるでしょう。しかし現実にはどうなのでしょうか?それを分かっているのもまた現場なのです。現場の声を管理者はきちんと吸い上げているのでしょうか?対応は十分ですか?そういった対応が必要な事は法令で決められており、定期的な「監査」で確認をされているはずですが...
🕵️ 外部から虐待を発見する仕組みはあるのか?
はい、制度上は存在します。ただし、実効性には課題があります。
1. 自治体による立入検査・監査
・介護保険法や老人福祉法に基づき、都道府県や市町村は施設に対して立入検査や運営指導を行う権限を持っています。
・虐待の通報があった場合、自治体は事実確認のための調査を実施し、必要に応じて改善命令や指定取消しなどの行政処分を行うことができます。
2. 通報制度(高齢者虐待防止法)
・虐待を発見した者には市町村への通報義務があります(第21条)。
・通報者は不利益な扱いを受けないよう保護される規定もあります。
3. 監査の実態
・実際の事実確認の方法は、「任意の調査協力依頼」が約81.6%、「監査(立入検査)」が約20.9%と、強制力のある監査は少数派です。 ・任意調査では施設側の協力が前提となるため、施設ぐるみの隠蔽があると実効性が低下します。
⚠️ 実効性の限界と構造的課題
・自治体のリソース不足:監査を行う職員が足りず、継続的なモニタリングが困難。
・再発事例の多さ:虐待が認定された施設のうち、過去にも虐待があった施設が約19.1%。つまり、改善命令が形骸化している可能性があります。
・施設の協力次第で調査の精度が左右される:任意調査では、施設が情報を隠せば真相にたどり着けない。
・監査員の専門性が十分とは限らない:介護現場の複雑さに対して、監査員が制度や現場の実態を十分に理解しているとは限らず、表面的なチェックに留まることも。
・施設との“なれ合い”の懸念:地域密着型の施設では、行政と施設が長年の関係を持っていることもあり、厳正な監査が行われにくいケースも。
「制度の構造を疑う」視点が非常に重要です。監査という仕組みがあっても、それを担う人間の倫理観・専門性・独立性が問われるということです。では、今回事件のあった埼玉県宮代町ではこの施設を監査していたのか?という疑問がわいてきます。
🏢 宮代町の監査制度の概要
・宮代町は地方自治法に基づき、定例監査を毎年度実施しています。
・令和6年度の定例監査報告書は公開されていますが、個別の介護施設名や虐待事案に関する記載は確認できません。
・埼玉県全体では、令和5年度に12,005施設のうち約3,600件に対して監査・指導が実施されており、介護事業所に対する特別監査はゼロ件でした。※虐待の疑い、不正請求、最低基準違反などがあれば、周期に関係なく即座に特別監査が入ります。
📆 介護施設の監査・実地指導の周期
埼玉県周辺の県の状況も調べてみましたが、出てきた情報は似たようなものでした。やはり制度の方にもすでに破綻が起きているように感じます。もはや「一部の施設の問題」ではなく、業界全体が“麻痺した倫理感”の中で制度疲労を起こしていると見るべき状況です。監査制度があっても機能していない。通報制度があっても使われない。研修制度があっても形骸化している。これは偶然ではなく、構造的な“見逃しの連鎖”です。
🧠 業界全体の“麻痺”を生む構造
・制度疲労と慣れ合い
長年の人手不足と慢性的な業務過多により、「多少の不適切行為は仕方ない」という空気が蔓延。これは現場だけでなく、行政側にも波及している。
・倫理より効率が優先される風土
「虐待ゼロ」より「稼働率100%」が評価される構造。施設運営者も行政も、数字で動く仕組みに囚われている。
・“沈黙の文化”の制度化
通報者が孤立する、監査が形式的に終わる、改善命令が履行されない―これらが繰り返されることで、「声を上げても意味がない」という諦めが定着してしまう。
ここまでは、制度の破綻と施設の稼働状況についての問題に触れてきました。基本的には現場に必要なのは永続的な「教育」だと思っています。ただ「介護福祉士」などの国家資格は知識と技術の証明にはなりますが、人間性や倫理観の保証にはなりません。そして、介護や医療の現場では、まさにその「人間性」が命を左右する場面が日常的にあるのです。だからこそ、資格よりも“適性”を見抜く仕組みが必要不可欠なんではないでしょうか。介護職員による暴力事件が報道されるたびに、「そもそもこの人は介護に向いていたのか?」という疑問が湧きますよね。実際、採用時に適性を見極める仕組みは存在しますが、導入状況にはかなりばらつきがあります。
🧠 採用時に使われる主な適性検査の種類
性格検査:協調性・共感力・ストレス耐性などを数値化
状況判断テスト:介護現場での対応力をシミュレーション
ストレス耐性・感情コントロール:暴力や衝動的行動のリスクを予測
価値観・倫理観の診断:介護職としての使命感や倫理意識を測定
🏢 実施されていない理由と課題
にもかかわらず、すべての施設がこれらを導入しているわけではありません。その背景には以下のような事情があります
・人手不足による「とりあえず採用」:適性よりも即戦力が優先されがち
・コストと手間の問題:適性検査の導入には費用と運用の手間がかかる
・面接官の主観に頼る傾向:短時間の面接で「人柄」を見抜くのは困難
この中でも特に注目して欲しいのは『ストレス耐性』です。心身にかかる負荷(ストレス)に対して、どれだけ冷静に、柔軟に、そして持続的に対応できるかという“心理的な強さ”を指します。単に「我慢できるか」ではなく、ストレスをどう受け止め、どう処理し、どう乗り越えるかという複合的な力です。
🧠 ストレス耐性を構成する6つの要素
🔍 高い人 vs 低い人の特徴
介護や医療の現場では、ストレス耐性は倫理観と直結すると言っても過言ではありません。耐性が低い状態で放置されると、善意の人でも暴力的な行動に陥る可能性がある。だからこそ、採用時にこの6要素を診断する仕組みが必要なんです。実は調べてみると最近では、ストレス耐性や心理的適性を簡単にチェックできるアプリやWebシステムが多数登場していて、介護・医療現場でも導入が進みつつあります。しかも、スマホやPCで数分で完了できるものも多く、個人でも無料で試せるツールもあります。
📱 ストレス耐性を測定できる主なアプリ・システム
※以下は各リンクとなります
驚くほど多くのストレス耐性診断ツールが存在しているにもかかわらず、介護業界ではまだ十分に周知・活用されているとは言えないのが現状のようです。実際、調査によると導入している事業所は増えてはいるものの、制度的な義務や支援が乏しいため、普及は限定的です。行政はこういったフォローも含めて立ち入って改善してほしいと願うばかりです。
介護や医療の現場はとっくに疲弊しているのに、行政が管理を丸投げしては業界の未来はありませんよ。どんなに高い理想を持って職に就いたとしても、いずれ心は疲弊し、燃え尽きてしまう。虐待が見つけにくい「仕組み」のままなら、誰にもバレないし...今は仕事を回す事が優先でしょ...そうやって現場が間違いを重ねた結果が今回の事件に繋がったのだと思う。責任の一端は行政にもあると思うのです。
最後に、介護現場の改善を掲げて選挙に当選した政治家たちよ、何か実績は残せたのかい?現場は良くなったの?
そう、今も懸命に現場で働いてる人達を「使い捨てないで欲しい」と心から願います。どうか助けてください!
《本日の一曲》
岡崎体育 / 式
弾き語りでめちゃ練習してるお気に入り曲です😆