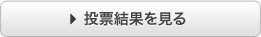街はすっかり日が暮れていた。
駅前は帰宅するサラリーマンや学生の姿が目立った。
「カンパ~イ」
「なんで乾杯なん?」
「凄いことだよ」
「これからだよ。これから」
宮本トウマは、ビールをグッと喉に流し込んだ。
「プハ~!」
その美味しさに思わず声が出る。
「いい飲みっぷりね」
「学生の頃もこんな風に呑んだけど、社会人になってからビールの本当の美味さを知ったな」
テーブルの向かい座っているのは、学生時代から付き合っている恋人佐伯アスカで、彼女の方は大学院に身を置いていた。
「そんなに違う?」
「違うな。学生時代って、まだ社会のことがよく分かってない気がするわ」
「ヘェ~。なんかトウマ、上から言うんじゃない?」
「ちょっとな。バレバレか?」
「良いんじゃない。さっきの話の続き聞かせてよ」
アスカに言われて、トウマは手を叩いた。
「そうやった。さっき、店員が来たからな」
そう言うと、トウマは今日の出来事をアスカに聞かせた。
今年の春、トウマは大学を卒業し、とある食品会社に就職した。
三年生の頃はまだ証券会社を狙うつもりにしていたが、有名でもない私立大学の学生だったトウマは、直ぐに現実を思い知る事となった。
「営業っていうのは、もちろん人との出会いなんだけど……。それは入り口の話なんだ」
トウマよりも知名度のある国立大学の学生であるアスカが相槌を打つように小さく首を縦に振った。
「今日行ったスーパーは……、地域でトップの繁盛店とは違う。だけどその店にだって、顧客というか、いつも足を運んでくれる主婦達がいるんや」
「うんうん」
「俺は、レトルトの御かゆを卸したいんや。分かる?」
「分かるよ」
そこで、トウマがビールに手を伸ばした。
「御かゆと言えば……。知名度のある食品メーカーがあるやろ?」
「あるね。トウワ食品にコトブキ。テレビでもCMが流れている」
「そうや。アスカならどっち買う? ウチの会社と地名のある会社と」
すると今度は、アスカが枝豆に手を伸ばした。
「トウマの会社のこと、知っているから……」
「だけどそういうのなし。営業ってもっとシビアなもんや」
「だったら、コトブキの買うかな。あの女優さん、好きだし」
「だよな~」
自分から振っておきながら、トウマは背もたれに体を預けた。
「やっぱり、CMの効果って大きいよな。親近感や清潔感のあるタレントが、笑顔で何度も語りかけてくるから」
「うん。そうね」
「ウチの会社は、それを全部、営業がするんや」
「うん。聞きたい」
「楽やないで。最初は、害虫でも見るような扱いや」
アスカの表情があからさまに曇った。
「こんにちは~。それからウチの会社を名乗る。でも売り場の担当者は大抵、そっぽ向いている」
「挨拶しても?」
「そりゃそうさ。考えても見てみ。すでに有名どころがちゃんと商品を置いて行っているんや。担当にしたら、それで何も困れへん!」
「確かに、そうね」
「そうだろう。余計な仕事が増えるだけ、面倒っていう感じや」
「そっか……」
アスカも相手の態度に何となく理解を示した。
「だけどどうするの? 話なんて聞いてもらえないじゃない」
「何も説明せんよ。だけど挨拶だけして帰る」
「それで置いてもらえるようになるの?」
「まぁ~、ならんやろな」
トウマが焼き鳥を食べた。
「でもな。相手も人間やろ? 毎日、毎日、顔出して、挨拶してみ。顔くらい嫌でもおぼえるで」
「そっか。そうしたら、脈があるってことね」
「アスカはホンマに学生やな~。発想が変わってない。顔覚えたら、賢い相手なら避けるようになるわ」
「ええ? 避けられるの?」
「そうや。だってな。もともと、ウチの商品、必要ないんやもん」
言われてみればそうだと思うアスカだった。
「さて、どうするでしょう?」
「全然、わかりません。降参。トウマ、教えて!」
「実はな。ここからが本当の営業なんや」
「うん」
アスカが心持顔を寄せたのを知って、トウマはワザとビールに手を伸ばした。
「教えてよ~!」
「それやねん」
「何?」
「今、アスカ、俺の話を聞きたがったやろ?」
「うん」
「相手もな。本人には言えない小さな悩みとか疑問ってあるもんなんや」
「例えば?」
「それはもうケースバイケースやけど、他のスーパーの事だったり、品揃えのことだったり……」
「へぇ~」
「「どうなの?」って具合に訊かれたりするんや。もちろん、ウチの商品とは全く無縁のな」
「どう答えるの?」
「それはもう、精神誠意で答えるよ。不思議やけど、売り場の担当者から信頼されたら、話ってトントンと決まっていくことが多いんや」
「へぇ~」
「営業をな。大変って言う人も知っている。でもな。人の出会いは楽しいし、やっぱり人間同士やから、誠意って伝わるんや。ただ気をつけないかんのは、相手にも仕事があるってこと。今まで慣れ親しんできたやり方があるから、それを教えてもらうところからはじめるんや」
「トウマ、凄いね。学生時代は、「どうなの?」って思ったけど……」
「俺、成長したやろ?」
「直ぐ調子に乗るところは変わってないね。ビール呑む?」
「そうやな。アスカも呑むやろ?」
トウマが手を挙げて店員を呼んでいた。
その姿は、偉そうでもなく萎縮したものでもなかった。昔と変わったように感じるのは、自信がみなぎっていた。そして、お人よしな部分は少しも変わっていなかった。
「人って強くもなるし弱くもなる。持ちつ持たれつやからな」
トウマが急に言い出した言葉の背景をアスカは察することが出来なかった。しかしそんなトウマは、活き活きとして輝いて見えた。
「トウマ、他の話も聞かせてよ」
「他の? そうやな。別の店でな……」
枝豆を口に入れると、ちょっと考えていたトウマは話し始めた。そんなトウマをアスカは頬杖をつきながら嬉しそうに見つめていた。
 ブログネタ:プラス思考?マイナス思考?
参加中
ブログネタ:プラス思考?マイナス思考?
参加中