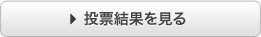「いつもの所で待っているから」
帰りのホームルームが始まる直前、席に座っていた僕の横を通り過ぎようとしたカノンが早口で言った。
「う、うん」
だけど僕の声は小さい。カノンはクラス委員をしている優等生で、父親は町でも名の知れた整形外科を開院していた。
そんなカノンが、どちらかと言えば目立たない部類に入る僕を誘うのか謎に思えてならなかった。
先生が教室に入ってくる。教壇に立ち一礼して、二つ折になったプリントの束を見せてカノンの名前を呼んだ。カノンもそれが当たり前のように、さっと立ち上がって最前列までやって来て、端から人数分のプリントを分けていった。
僕は、そんなカノンの姿を見つめる。きっと隣りの小野くんだって、前に座る滝井さんだって、見つめているに違いない。そして、誰もがカノンを優等生だと思っていた。
「プリントは渡ったかな?」
ころあいを見て、先生が説明を始める。カノンは、一仕事を終えて自分の席へと戻っていく。ほとんどの生徒がプリントの内容に気を取られていても、僕はカノンを斜めうしろから見つめていた。
「……。ということだ。では今日はこれまで」
先生がそういうと、見事なタイミングでカノンが起立と言い、礼と続けた。
我先にと駆け出していく生徒。雑談をしながら帰って行く生徒。いろんな生徒がいた。ものの五分もすると教室には誰も姿もなかった。もちろん、カノンの姿も……。
僕はおもむろに席を立って、カバンを提げた。そして教室を出て、いつものように四階の図書室へと向かった。
「どうしたの? 遅かったわね」
図書室には、ほとんど誰もいなかった。いるのは、カウンターの中に図書委員の下級生二人が貸し出し作業に追われていた。
「うん。トイレに寄ってから来たんだ」
僕はそう答えて、カノンの隣りに腰を掛けた。
「どう?」
「うん」
僕は、カバンの中から一冊の青いノートを出してそれをカノンに渡した。カノンは何も言わずにノートを広げて、そこに書かれた無数の言葉を目で追った。
「嘘!」「ええ?」
カノンは文字を目で追いながら、無意識につぶやいた。そんな彼女をわずか三十センチの距離で僕は見つめていた。
どのくらいだろう。僕の中では三分くらいに感じたけれど、もしかしたらもう少し長い時間だったかもしれない。
「森くんはきっと作家になるんじゃない?」
「どうかな。わからないよ」
僕は、ノートを返してくれたカノンに答えた。
「お話はどこで書くの? スラスラと思い浮かぶの?」
すこしの質問をカノンはした。僕は、答えられるときは直ぐに答えたが、どう答えていいか分からないときはしばらく考え込んで「分からないよ」と言う事もあった。
「森くんは好きな人いるの?」
「分からないよ」
「どうして? 好きな人がいるかいないか分からない?」
「……。分からない」
「そうなんだ。私はいる。ジュンくん」
「ああ~」
僕は、曖昧な返事をした。
カノンが答えたジュンとは、僕が書いている作り話の主人公だった。僕やカノンと同じ中学三年生で、あまり目立たない少年だった。
「森くんは、ジュンくんがアズキちゃんと結ばれると思う?」
「分からないよ」
「そうだよね。今はまだ言えないよね。だけど、アズキはあんな風に見えて寂しがり屋なんだと思うの。みんなからは優等生だといわれたりするけど、もっとドジな女の子じゃないかと……。違うかな?」
そんなカノンが急にテーブルに頬杖をついて外を見た。その横顔を僕は、じっと見つめていた。どうしてカノンが放課後に僕を呼び出し、図書室が閉められる時間ギリギリまで帰ろうとしないのか。僕には不思議でしょうがなかった。
「キスしたことある?」
「ない」
「ないの? 私も」
僕は、カノンの瞳にじっと見つめられて動けなかった。
「恥ずかしいね」
カノンが両手で自分の顔を扇いだ。僕は、何が起こったのかも分からなかった。想像していたよりもずっと一瞬のことで、その感触さえはっきりと覚えていなかった。
「ジュンくんはキスしたことあるの?」
「ないよ。多分だけど」
「アズキちゃんは?」
「どうだろう。あるかもしれないけど……。ないのかな?」
「ねぇ~、森くん。森くんは家に帰ってから、私のことを思い出すことある?」
「分からないよ」
「私はあるよ。今頃、森くんは続きを書いているのかなって……」
なぜカノンが僕のノートに作り話が書いてあるのを知ったのかと言えば、これでも僕は、バスケ部に入っていた。練習中に不注意で骨を折って、しばらく練習に参加できない日々が続いた。それでも体育館に行っては、みんなの練習を見学してたりしていた。
けれどどうにも見ていると焦ってしまって、放課後に教室で思いついたことを書くようになった。
いつしかそれが作り話へと発展して、たまたまカノンに何を書いているのかと尋ねられたのだった。
幸いにして登場人物は全て架空だったし、カノンがどうしても読みたいというからノートを渡したというわけだ。
「これ、森くんが書いたの?」
最初に見た時、カノンはものすごく驚いていた。僕のクラスでの印象は薄かったし、実際、カノンと長く話したのもその時が初めてだった。
「ねぇ、森くん」
「なに?」
カノンはテーブルに伏せるよな姿勢で、顔だけを横に向けて僕を見つめた。
「いつか本当に作家になったら、私のことを書いてくれない?」
「……分からないよ」
「いいの。ジュンくんとアズキちゃんみたいに、名前を変えていても。だからお願い。私のことを書いて!」
あまりにカノンが強く頼んできたので、僕も断れなくなった。
「そのうちね」
「うん。ありがとう」
カノンが伏せた姿勢のまま微笑んでいた。
僕たちは中学を卒業した。
別々の高校へと進学し、それから顔を会わせることはなかった。僕は、時々、カノンの家でもある整形外科病院の前を通る。しかしそこで、偶然にもカノンに会うことはなかった。
なぜなら彼女は海外の高校へと留学していて、大学もまた日本には帰って来なかった。僕は高校を出て就職し、あれ以来作り話を書くこともなかった。
そんなカノンから届いたのは、一枚の絵葉書だった。
見るからに大柄の男性の隣りに立って、カノン似の女の子を抱きかかえていた。
「元気ですか?」
そんな書き出しに、僕はふと中学時代を思い出していた。
あの物語に出てくるジュンとは僕のことで、アズキはカノンのことだというのは、きっと彼女も知っていたに違いなかった。
だからカノンも、言いにくいときはアズキやジュンの名前を借りて、僕に質問することがあった。あの頃、僕はまだカノンに好きだと伝えることは出来なかった。唯一、ジュンがアズキに告白したとき、カノンは今までで一番喜んでくれたことを覚えている。
絵葉書に書かれたメッセージを読み終えて、僕はまた中学生だった頃を昨日のことのように思い出していた。