「WEB × クリエイティブで実現する地域活性」レポート
モバイルでご覧の方はこちらをご覧ください。
画像も表示されます(Ti-daブログで運営している沖縄LOVElog)。

PLANNING OFFICE Codaでは、沖縄の音楽を基軸にしたビジネスモデルを企画する
「沖縄音楽活用型ビジネスモデル創出事業」を県より受託しています。
この事業のもと、2010年12月22日に、株式会社ロフトワークの林千晶氏を迎え
「WEB × クリエイティブで実現する地域活性」というテーマで講演いただきました。
講演会場となった沖縄県立博物館・美術館には、沖縄音楽関係、広告代理店、県内企業、
行政関係、そしてクリエイターと、80名強の方々にお集り頂きました。
株式会社ロフトワークは、クリエイティブの流通を目指し2000年に設立。
インターネットが普及しはじめた頃でありながらも、
多くの日本企業ではネットを充分に活用したビジネス展開に
未だ消極的な面も持っていた頃でもあったとか。

それから10年。世界はインターネットの普及と共に大きな変化を生み出したと林氏は言及します。
ブログやSNSに加え、個人がリアルタイムに情報を発信するtwitter(ツイッター)や、
共同バイイングというシステムを導入する事で企業は定数の顧客をつかむことができ、
消費者は通常よりも安価で商品を購入できるGROUPON(グルーポン)の登場など。
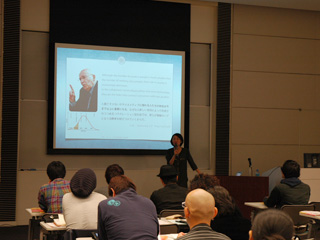
このようなインフォメーションテクノロジーの進化によって、
企業から個人へ向けた情報発信から、個人 対 個人の情報共有が可能となりました。
林氏は、インターネットで広がるこれからの世界を、
マーケティング専門家のフィリップ・コトラーの言葉を引用し「Marketing 3.0」と説明。
複数のユーザー間のコラボレーションが、同時多発的に繰り広げられるプラットフォームを
有効活用できる企業が、今後のネットビジネスにおいて重要であると解説しました。
[補足]コレまでのマーケティング世界の目的
Marketing 1. 0の世界…産業革命から始まった、商品を大量生産し販売すること
Marketing 2. 0の世界…顧客満足度をあげ、保持すること
Marketing 3. 0の世界…企業の利益を追い求めるだけでなく、
関わる全ての人にとってより良い世界となる活動やプロジェクトである

ロフトワークでは、ネットの世界でダイナミックに個人と個人を結びつけることで
Marketing 3. 0の世界の実現化に向けてプロジェクトを推進してきたとか。
それが分かりやすい形で表現されているのが、越後妻有アートトリエンナーレや
瀬戸内国際芸術祭と連動した、地域名産品リデザインプロジェクト「Roooots」。

このプロジェクトでは、2年間で31品目55アイテムのリデザイン商品が市場に出回りました。
林氏は、このプロジェクトの進行手順の詳細を解説してくれました。
[プロジェクト手順]
1. 発掘
地元の原料や素材を用いた商品で、メーカーがデザインでビジネス成果を高めたいと願っている商品であること。
2. 公募
インターネット上でデザインを公募。
メーカーの思いや対象商品の魅力を、インターネット上で紹介し、
ロフトワークが運営する日本最大級のクリエイターネットワーク「loftwork.com」を通してクリエイターに伝達。
応募デザインはリアルタイムに公募サイトに反映され、メーカーもクリエイターも
どのような提案がなされているのかを、リアルタイムで見る事ができる。
クリエイター間で刺激が生まれ、よりクオリティの高いデザインを提案しようという動きが高まる。
3. 選抜
プロダクトデザイン、マーケティングなどプロフェッショナルが応募作品を審査。
リデザインするこで、商品の魅力がユーザーにより伝わり
現実化までのプロセスに、クリエイターのオリジナリティを活かすことができ、
実現可能であるというビジョンがみえるもののみを採用
4. 協働
採用クリエイターがメーカーに赴き、作り手の思いを汲み取る。
クリエイターとメーカーの意見が分かれた時は、実行委員会が、仲介役として課題解決をサポート。
こうして出来上がった商品は売上平均を3~5倍、なかには10~20倍にまで増幅させたほか
国内外で数々の賞を受賞し、高い評価を得ています。
林氏は、「インターネットが普及した今、世界は手の届くところにある」と言明。
そこで、もっと自分たちのビジネスを世界とリンクさせるために、
ウェブサイトをバイリンガル、トリリンガルにすることを提案。
翻訳の依頼と回答をネット上でダイレクトに仲介するサイト「my gengo」を紹介してくれました。
また、クリエイターにはflicker(フリッカー:写真を共有するコミュニティサイト)などを用い作品をインターネット上に公開することも提案。
インターネット上で、もっとダイナミックに情報を公開することで、
世界を手の届く所に近づける事ができると力説しました。
そこで気になる著作権法についても触れます。
ネット上で公開されている写真やイラストなどは、通常著作権法により、
第三者が勝手にその画像を用いることはできません。
「プロの世界はそれでも構わないが、もっとパーソナルなやり取りの中では
著作物がもっと誘起的に、柔軟に流通することでクリエイティブがダイナミズムになる」と話します。
そうした考えのもとに設立された団体が「Creative Commons」a 。
林氏は「Creative Commons」のアジア・プロジェクト・コーディネーターも務めています。
Creative Commonsでは、わかりやすい世界共通のサインを用いて
作者が著作物に対する利用規程を、世界中の人に分かりやすい形でアピールことを提案。
前述したflickerやウィキペディア
また六本木ヒルズ内の森美術館も「Creative Commons」のライセンスを取得しています。
最後に、林氏は今講演のポイントとして
「Many to many collaboration=多数と多数によるダイナミックなコラボレーション
「To the World=世界への発信」
そして「Openness=オープンな世界の可能性 ※進化は優れた先人の功績によって生じることから」に触れ、締めの言葉としました。
次回は、音楽関係者やメディア関係者を交えた
パネルディスカッションについてレポートいたします。お楽しみに。
沖縄LOVElogがひと目でわかるダイジェスト、こちらをご覧ください。

画像も表示されます(Ti-daブログで運営している沖縄LOVElog)。

PLANNING OFFICE Codaでは、沖縄の音楽を基軸にしたビジネスモデルを企画する
「沖縄音楽活用型ビジネスモデル創出事業」を県より受託しています。
この事業のもと、2010年12月22日に、株式会社ロフトワークの林千晶氏を迎え
「WEB × クリエイティブで実現する地域活性」というテーマで講演いただきました。
講演会場となった沖縄県立博物館・美術館には、沖縄音楽関係、広告代理店、県内企業、
行政関係、そしてクリエイターと、80名強の方々にお集り頂きました。
株式会社ロフトワークは、クリエイティブの流通を目指し2000年に設立。
インターネットが普及しはじめた頃でありながらも、
多くの日本企業ではネットを充分に活用したビジネス展開に
未だ消極的な面も持っていた頃でもあったとか。

それから10年。世界はインターネットの普及と共に大きな変化を生み出したと林氏は言及します。
ブログやSNSに加え、個人がリアルタイムに情報を発信するtwitter(ツイッター)や、
共同バイイングというシステムを導入する事で企業は定数の顧客をつかむことができ、
消費者は通常よりも安価で商品を購入できるGROUPON(グルーポン)の登場など。
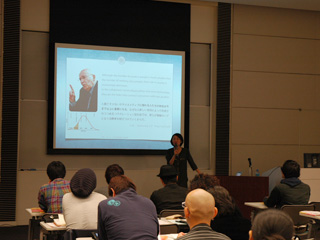
このようなインフォメーションテクノロジーの進化によって、
企業から個人へ向けた情報発信から、個人 対 個人の情報共有が可能となりました。
林氏は、インターネットで広がるこれからの世界を、
マーケティング専門家のフィリップ・コトラーの言葉を引用し「Marketing 3.0」と説明。
複数のユーザー間のコラボレーションが、同時多発的に繰り広げられるプラットフォームを
有効活用できる企業が、今後のネットビジネスにおいて重要であると解説しました。
[補足]コレまでのマーケティング世界の目的
Marketing 1. 0の世界…産業革命から始まった、商品を大量生産し販売すること
Marketing 2. 0の世界…顧客満足度をあげ、保持すること
Marketing 3. 0の世界…企業の利益を追い求めるだけでなく、
関わる全ての人にとってより良い世界となる活動やプロジェクトである

ロフトワークでは、ネットの世界でダイナミックに個人と個人を結びつけることで
Marketing 3. 0の世界の実現化に向けてプロジェクトを推進してきたとか。
それが分かりやすい形で表現されているのが、越後妻有アートトリエンナーレや
瀬戸内国際芸術祭と連動した、地域名産品リデザインプロジェクト「Roooots」。

このプロジェクトでは、2年間で31品目55アイテムのリデザイン商品が市場に出回りました。
林氏は、このプロジェクトの進行手順の詳細を解説してくれました。
[プロジェクト手順]
1. 発掘
地元の原料や素材を用いた商品で、メーカーがデザインでビジネス成果を高めたいと願っている商品であること。
2. 公募
インターネット上でデザインを公募。
メーカーの思いや対象商品の魅力を、インターネット上で紹介し、
ロフトワークが運営する日本最大級のクリエイターネットワーク「loftwork.com」を通してクリエイターに伝達。
応募デザインはリアルタイムに公募サイトに反映され、メーカーもクリエイターも
どのような提案がなされているのかを、リアルタイムで見る事ができる。
クリエイター間で刺激が生まれ、よりクオリティの高いデザインを提案しようという動きが高まる。
3. 選抜
プロダクトデザイン、マーケティングなどプロフェッショナルが応募作品を審査。
リデザインするこで、商品の魅力がユーザーにより伝わり
現実化までのプロセスに、クリエイターのオリジナリティを活かすことができ、
実現可能であるというビジョンがみえるもののみを採用
4. 協働
採用クリエイターがメーカーに赴き、作り手の思いを汲み取る。
クリエイターとメーカーの意見が分かれた時は、実行委員会が、仲介役として課題解決をサポート。
こうして出来上がった商品は売上平均を3~5倍、なかには10~20倍にまで増幅させたほか
国内外で数々の賞を受賞し、高い評価を得ています。
林氏は、「インターネットが普及した今、世界は手の届くところにある」と言明。
そこで、もっと自分たちのビジネスを世界とリンクさせるために、
ウェブサイトをバイリンガル、トリリンガルにすることを提案。
翻訳の依頼と回答をネット上でダイレクトに仲介するサイト「my gengo」を紹介してくれました。
また、クリエイターにはflicker(フリッカー:写真を共有するコミュニティサイト)などを用い作品をインターネット上に公開することも提案。
インターネット上で、もっとダイナミックに情報を公開することで、
世界を手の届く所に近づける事ができると力説しました。
そこで気になる著作権法についても触れます。
ネット上で公開されている写真やイラストなどは、通常著作権法により、
第三者が勝手にその画像を用いることはできません。
「プロの世界はそれでも構わないが、もっとパーソナルなやり取りの中では
著作物がもっと誘起的に、柔軟に流通することでクリエイティブがダイナミズムになる」と話します。
そうした考えのもとに設立された団体が「Creative Commons」a 。
林氏は「Creative Commons」のアジア・プロジェクト・コーディネーターも務めています。
Creative Commonsでは、わかりやすい世界共通のサインを用いて
作者が著作物に対する利用規程を、世界中の人に分かりやすい形でアピールことを提案。
前述したflickerやウィキペディア
また六本木ヒルズ内の森美術館も「Creative Commons」のライセンスを取得しています。
最後に、林氏は今講演のポイントとして
「Many to many collaboration=多数と多数によるダイナミックなコラボレーション
「To the World=世界への発信」
そして「Openness=オープンな世界の可能性 ※進化は優れた先人の功績によって生じることから」に触れ、締めの言葉としました。
次回は、音楽関係者やメディア関係者を交えた
パネルディスカッションについてレポートいたします。お楽しみに。
沖縄LOVElogがひと目でわかるダイジェスト、こちらをご覧ください。
