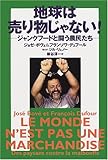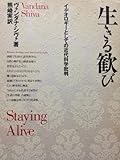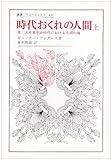経済成長なき社会発展は可能か? <脱成長>と<ポスト開発>の経済学
セルジュ・ラトゥーシュ
中野佳裕訳
作品社
2010年7月
一言コメント
成長や開発を見直し、社会や人生のあり方を根本から見直す――すでにこのテーマについて読んできた人間としては、今までの話のまとめという感じで、少々面白みに欠けた。もちろん、はじめてこのテーマに接近する人にとてっては、ほどよい入門書になると思う。でもできれば、昨日ピックアップしたようなブックガイドの本を読んだ方がよい。
本書は、もとは2冊の本を1冊にしたものである。
MOSTプログラムの主任秘書 であったアリ・カザンシシジル主宰の政策論文のためにユネスコが立案した企画を通じて生まれ、「経済発展と断絶した時代の構築へ向けた足掛かりを造る」 (23ページ)ために書かれ、もともとは「水平連盟」というもので議論された内容であるという。
「MOSTプログラム」は、「社会変容のマネジメント」(Management of Social Transformations)の略が「MOST」で、文科省のHPによれば、「グローバリゼーション、都市化、人の移動等による社会の変容に関する研究、政策形成との連携を目指して平成6年(1994年)に設立されたプログラム」だそうである。
「水平連盟」は、訳注によると「フランスにおける<ポスト開発>思想の先駆者である経済学者フランソワ・バルタンの同志によるアソシエーション。ラトゥーシュは水平連盟の主宰者の一人である」(23ページ)とのことだが、門外漢には何のことやらさっぱりわからない。
具体的にはシンポジウムを開催し、「開発を解体し、世界を再生する」というテーマを議論したようだ。これが2002年。
1960年代の「開発の最初の10年」と言われている時代、つまり、イリイチがまさしく「開発」に異議を唱えていた時代から今に至るまで、「ポスト開発」学派は形成されてきたと言う。いつのまに?
そういえば、ヴォルフガング・ザックスが編纂したThe Development Dictionary(邦題:「脱「開発」の時代」)という本が1992年に刊行されていたが、ここに名を連ねている人たちが、このメンバーのようだ。
この学派の中心思想は、「発展概念を根本から問いただすことをその分析の主眼に置いている」(26ページ)というから、イリイチの頃からその基本はさして大きく変容していないようである。
また、経済的発展にとどまらず、「社会開発」「人間開発」「地域開発」などもその亜種として登場。
「発展概念は、普遍主義を装うがゆえに概念的な欺瞞であり、甚大な矛盾を孕むがゆえに実践的な欺瞞でもある」(84ページ)とし、自文化中心主義的なこの概念を批判する。
なかには「共愉にあふれる〈脱成長〉」という章題があるのみならず、引用から本文にまで、「バナキュラーな社会」など、イリイチの言葉があふれている。これはこれでイリイチに親しんできた者には、少々不気味である。
自分なりにちょっとふりかえってみよう。
世界のさらなる「発展」のためには、経済成長を大前提とし、「途上国」と呼ばれる国々の「開発」が求められる、という考え方に最初に疑義が呈されたのが、1970年代であった。
無限成長を「神話」とみなしたり、「成長」の限界を訴えたり、「脱」産業社会を目指したり、エコロジーという活動になったり、地球環境問題を考えたり、いろいろな言い方、考え方が現れた。
代表的な論者、もしくは理論的な支柱としてよくとりあげられたのは、ポランニー、
サーリンズ、フロム、ベイトソン、ローマクラブ、イリイチ、ゴルツ、エリュール、シューマッハーといった面々であった。
ところで、2011年3月11日以降、しばしば登場する主張の一つに、原発を稼働しないで産業や経済の成長を止めると日本は滅亡してしまう、というものがあった。
原発のみならず、以前から問われていたのは、「開発」や「成長」そのものであるが、このことを知らずして、相変わらず同じようなことを言っているのに、驚いたものだ。
少しは歴史的な蓄積をふまえて、議論が深まっているのでは、と多少は期待していたが、実際は、まったくそうではなかった。
「原発」を「開発」「発展」のシンボルととらえ、それをやめ ることは、「日本をダメにする」「産業が立ち行かなくなる」「原始的な暮らしに戻りたいのか」といった幼稚な批判が、今なおマスコミや個人の書き込みなどにたびたび現れる。
それらを聞くにつれ、この半世紀、何も変わっていなかったのだ、と切なくなる。
ただ同時に、逆もしかりである。
そうした「成長」「開発」の推進派の思考回路の停滞だけが起こっているのではない。
反対の、懐疑派や批判派においても、同様の事態が起こっているのではないかと危惧する。
本書を読んで思ったのは、この危惧が、決してはずれていないのではないか、ということだった。
もちろん、地域通貨やフェアトレード、災害時のボランティア、脱原発デモなど、まったくこうした流れが絶えてきたわけでも、衰退したわけでも、変化がなかったわけでもない。
私はそのなかに、希望を見出している。
しかし、それにしても、今一つ方向性を見失ってきたことも事実である。
むしろ今回、原発事故によって、ようやく「覚醒」した気配があり、惰眠におぼれてしまっていた私たちはもう一度、自分たちの暮らしや世界、社会について、「原発」を通じて見直しをはかりはじめている、という言い方ができると思う。
それにしても、なぜ停滞したのか、考えてみた。
思い当たるのは、やはり、原発をはじめとした「エネルギー論」に対する徹底した追求がなされなかったことである。
私は、イバン・イリイチの思想(ならびにそれを日本で紹介した山本哲士)に大学より親しみ、学校教育、病院医療、自動車交通、エネルギー、家事労働、など、次から次へと自明な日常に疑問符を投げかけるその著作を読むたびに、新鮮な驚きを抱いてきた。
今でも学校における学級崩壊やいじめの問題、医療過誤、過剰投薬や医療費の高騰など、明らかに社会問題としてとらえられ、ある程度議論されている分野もあるが、エネルギー論は、いくつかの大きなハードルがあって、避けられてきたように思われる。
まず、学校、医療、交通と比べて、エネルギーは、「公共性」があまりにも高く、それを「サービス諸制度」でくくることができない、ということ。
水道や電気は、生活においても産業においても、絶対的なインフラであり、それを止めるとか、やめるとか、少なくする、という発想が今までしにくかった。
以前に当ブログで書いたが、もちろんイリイチは「エネルギーと公正」というタイトルがそのものずばりの本で、この問題を扱っている。
扱っているにもかかわらず、この本は、「サービス諸制度」としての「交通機関」の問題、つまり、歩いたり自転車を用いるのではなく、自動車を用いることはどういうことなのかを考えることに比重が置かれてしまい、「インフラ」としての電力に対して、どうとらえるのかに着目しがたくなっていた。
結果として「エネルギーと公正」は、自動車と自転車という二つのテクノロジーを対比させるあまりに、生活全般の「電力」を問いつめることは、やや副次的なテーマとなっていた。しかし今思えば、インフラとしてのエネルギーを思考すること、これこそが、この資源の少ない列島に生きる私たちにとっての産業社会論のもっとも重要な部分であったはずだ。
そういう意味でも本書は、一体この四半世紀の空白をどのように埋め、確かな足取りをもったオルタナティブ論がどう展開されてきたのだろうか、と期待しつつページを繰ってみたが、正直言ってあまり興味がわかなかった。
エネルギー論が中心にない、経済論なのである。必要なのは、室田武のようなエネルギーの経済学でもない。エネルギー安全保障論や国防論といった政治的視点も内包させ、かつ、それをもう一歩、「暮らし」や「生活」と結びつけられるような検証が求められている。ある意味では「地球環境論」としてエネルギーを検討するということかもしれないし、「哲学」としてエネルギーを考えるということなのかもしれない。
肩すかしをくらった感じである。
- 経済成長なき社会発展は可能か?――〈脱成長〉と〈ポスト開発〉の経済学/セルジュ・ラトゥーシュ

- ¥2,940
- Amazon.co.jp