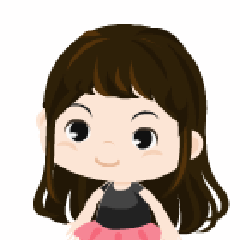おはようございます。
前回のブログでは、マネーフォワードとfreeeのクラウド会計の両方を実際に操作して感じた違いについて書きました。
今日は、複雑な減価償却費の計算をシミュレーション出来るサイトを発見したので、それをご紹介するとともに、私の苦労話を書こうと思います。
【減価償却費のシミュレーションが出来るサイト】
こちらです。↓
減価償却(~H18年度) - 高精度計算サイト (casio.jp)
減価償却(H19~23年度) - 高精度計算サイト (casio.jp)
減価償却(H24年度~) - 高精度計算サイト (casio.jp)
【減価償却費の計算が複雑化している件】
私は減価償却費計算の税制改正のあった、平成19年に新卒で経理に配属となり、入社初年度に250%定率法への対応に取り組みました。
私も経理時代にとても苦労しましたが、減価償却費の計算ってとても複雑なんですよね。
定額法は、取得時期によって、以下の2パターンで計算しなければなりません。
・平成18年度までに取得した固定資産→旧定額法
・平成19年度以降 〃 →新定額法
定率法の場合は、3パターンもあります。
・平成18年度までに取得した固定資産 →旧定率法
・平成19年度~平成23年度に取得した固定資産 →250%定率法
・平成24年度以降に取得した固定資産 →200%定率法
また、資産の種類によっても、償却方法が定められています。
・平成10年度以降に取得した建物 →旧定額法または定額法
・平成28年度以降に取得した建物付属設備、構築物 →定額法
なお、土地は価値が減少しないため、償却しません。
したがって、減価償却方法として定率法を採用している会社は、最大で以下のパターンで償却費の計算をしている可能性があります。
・土地…償却なし
・建物…平成9年度以前に取得 →旧定率法
平成10年度以降~平成18年度に取得 →旧定額法
平成19年度以降に取得 →定額法
・建物付属設備、構築物…平成18年度以前に取得 →旧定率法
平成19年度~平成23年度に取得 →250%定率法
平成24年度~平成27年度に取得 →200%定率法
平成28年度以降に取得 →定額法
・車両・運搬具、機械・装置、工具、器具・備品 …
平成18年度までに取得した固定資産 →旧定率法
平成19年度~平成23年度に取得した固定資産 →250%定率法
平成24年度以降に取得した固定資産 →200%定率法
※機械装置は、平成20年度に税制改正により耐用年数が見直された。
ちょっとこれは複雑すぎますよね。
【私の実体験】
私が平成19年度に250%定率法を導入したとき、会社の固定資産の状況は以下の通りでした。
・減価償却方法は、定率法を採用
・固定資産の総数は数百点あり。
・固定資産台帳はExcelで管理
・全種類の固定資産を保有(土地・建物、無形固定資産(ソフトウェア等)もあり)
具体的な実務の運用としては、計算方法ごとにExcelのシートを分けて計算していました。
・旧定額法
・新定額法
・旧定率法
・新定率法
上記を以下の手順で集計し、会計システムへ仕訳を入力していました。
①ピボットテーブルで、勘定科目、部門で集計
↓
②Excelのフォーマットに串刺し集計
↓
③②のデータをもとに、会計システム用の仕訳ファイルを作成
↓
④③を会計システムへインポートして仕訳入力
勘定科目数×部門数の仕訳が生じたので、仕訳の行数は100行ほどあり、かなり多かったです。
数百点の固定資産を、複雑な計算方法でExcelで計算しているので、かなりの集中力が必要で、計算が間違っていないかとても心配でした。
その後、200%定率法の導入前に、減価償却費計算のアウトソーシングを行いました。
現物管理は自社で行う必要がありますが、アウトソーシング先に取得や除却、移動の連絡を行うだけで、会計システムの仕訳ファイルまで作成してもらえました。それを会計システムにインポートするだけで仕訳が生成され、忙しい決算の時期に劇的に楽になり、感動したことを覚えています。
【カシオの高精度計算サイト】
冒頭の、カシオのサイトですが、条件を選択すれば、1年目から備忘価額1円に至るまでの減価償却費のシミュレーションが出来るため、便利だなと思いました。
平成19年度以降の定率法の償却費計算は、調整前償却額が償却保証額に満たなくなると、計算式が切り替わり、改定取得価額×改定償却率で備忘価額1円まで償却しますが、その計算が複雑で難解なんですよね。
中小企業は、早期償却のメリットのある定率法よりも、計算方法が簡便な定額法を採用しているケースも多そうですね。
現物管理も含めて、固定資産の数が多い会社は苦労していると思います。
今度、現物管理の注意点についても、ブログに書いていこうと思います。