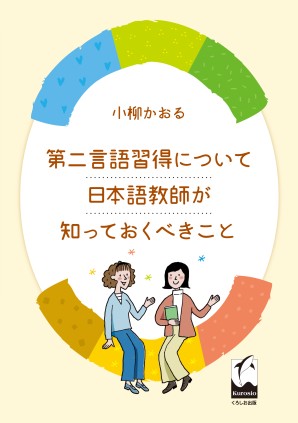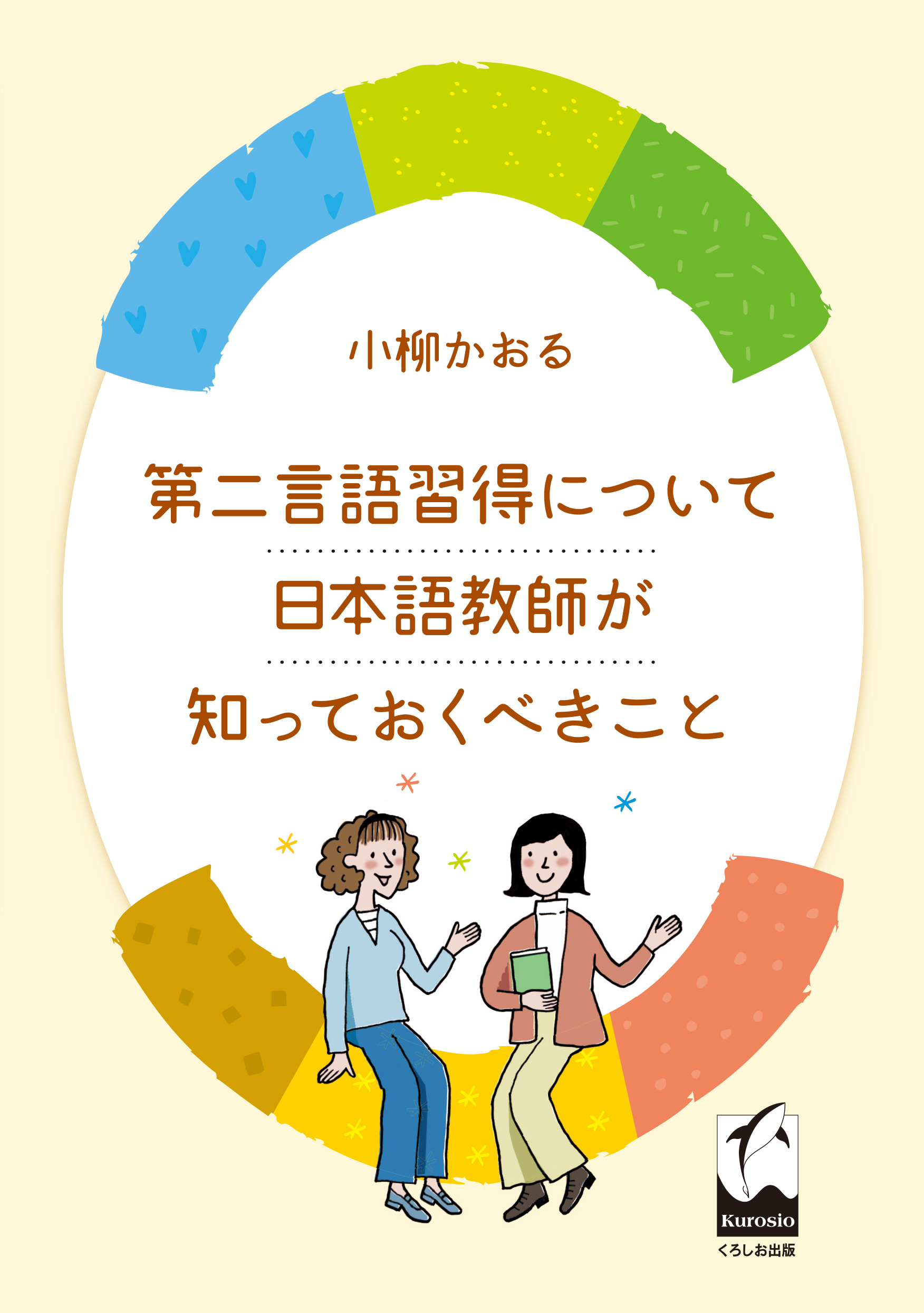私が養成講座に通ったのは、10年以上前のことです。とても有名な学校に通い、いろいろと教えていただきました。しかし、現在は、日本語教師の働く場所や環境も変化しています。それで「勉強しなおさなくちゃいけない!」と思い、いろんな研修会に参加しました。そのなかでも、何度でも復習したいと思ったものをご紹介します。
第二言語習得の ”正しい理論” を知る
昔々、親切な先輩方から、「て形や普通形など形の練習はこうやるのよ」と教えていただきましたが、実は、て形や普通形を作れることが日本語の運用能力のアップに直接関係しているわけではないんですよね。
でも、教師も学習者も、細かな文型の説明やパターンプラクティスをすると、「私、勉強したな」という満足感があるので、ついやってしまうのかもしれません。
(もちろん意味交渉のない練習はつまらなくて、すぐ飽きる人も多いです。)
これから日本語教育に携わろうと思う人はもちろんですが、ベテランと呼ばれる方々こそ、もう一度、第二言語習得の理論を学び直すことが大切なのではないでしょうか。正しい理論を知って、日々の実践に反映していくと、教師も学習者も楽しく有意義な時間を過ごせると思います。
第二言語習得に関する大切なことがギュッとまとめて書かれています。理論系は、難しくて挫折しがちなのですが、160ページほどなので、最後まで読み切ることができます。
各項目毎に “ここがポイント” というコーナーがあるのですが、ここを読むだけでも、目から鱗です。
- 学習者が身につけるべきは、本物の伝達能力、言語運用能力である。(p5)
- 言語処理における文法処理では、教室の文法説明で与えられるようなメタ言語的知識が直接使われることはない。(p9)
- 学習者は、最初は無動機の状態で、外から強制されて外国語を始めることもあるが、そこから外国語学習への意味や価値を見出して動機づけられるプロセスが重要である。(p58)
- 学習者は外国語の熟達度を身につけた将来の自分を強く念じ、それに向かって授業の中で小さな喜びや達成感が得られるように努めるような自己調整ストラテジーを使って、動機づけを維持すると良い。また、それが、新たな学習ストラテジーだと言われている。(p64)
- 意味あるコンテクストの中で言語を使っていることが前提で、その中でタイミングが訪れたときに教師が介入し、言語形式と意味/機能を同時処理させるFocus on Form(F on F)が習得を最も促進する。(p81)
- 習得のプロセスは、文法規則を知ることにより始まるのではなく、インプットを受けることから始まることに留意する。(p103)
- 言語習得は暗示的な学習メカニズムに依存している。母語話者は規則から言語を作り出しているわけではない。第二言語の学習メカニズムも同様にとらえるので、単なる動詞や文の変形練習は再考する余地がある。(p117)
- 学習者がメッセージを作り出すことなく、ただ形のみに焦点を当てた口頭練習を行っても、本当の意味での流暢さは生まれない。(p117)
(引用:小柳かおる『第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと』
(くろしお出版、2020))
どうでしょうか?この部分を読むだけでも、とても勉強になりますよね。
ぜひ、この本を読んで、正しい理論をきちんと学び直しましょう♪
くろしお出版で行われたオンラインセミナーの情報は、こちらから確認できます。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。