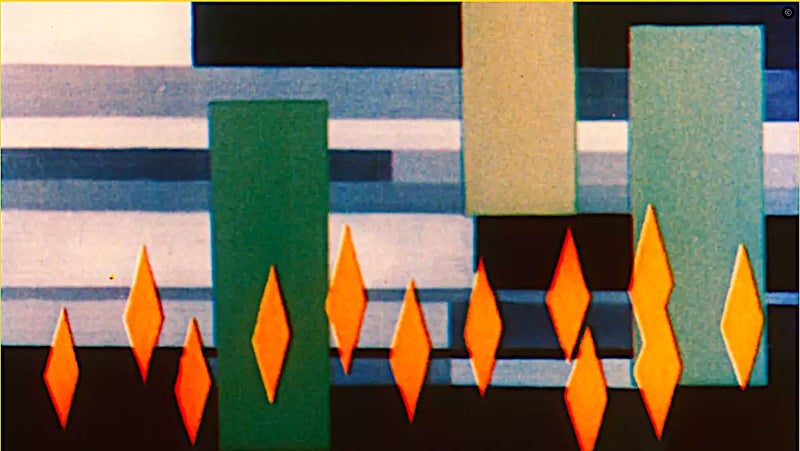イメージの世界(2)
(承前)
4. 映像の意味:その構築と解体
他者にいかに意味をわからせるか?
ひとつひとつのショットには意味がある。それは多くの場合、たったひとつの意味だけしかもたない「一義的」意味ではなく、たくさんの細部が複数の意味の可能性を暗示するような「多義的」意味をなしている。そうした意味を探し出し手繰りよせながら、作者はショットをつなぎ、ひとつの作品を作りあげ構成していくのだが、その意味や構成がつねに観客にそのまま理解されるとはかぎらない。私の決めた意味と観客の見出す意味が違っていることの方が多いからだ。ときには観客にはなんの意味も発見できず、単にばらばらに切り刻まれた素材としかみえないこともありうる。
ショットに意味があるだけでは十分ではなく、その意味を「わからせる」ように伝える努力をしなければ、作者にはわかっても他者である観客にはわからない。ある映像を見ながら作者が感じる感情・気分・実感などが、そのままで観客に確実に伝わる保証などどこにもない。メディアとは自分のもの(自分が生まれながらに持っていたもの)ではなく、他者とコミュニケートするために使われる社会的な表現手段であり、意味も自分ひとりのものではなく他者に伝え共有するためのものである。だから、表現とはなにより他者のためになされるものといえる。
前章「切り取りと配列」でみたように、たしかに断片的な映像が適切につなぎ合わされれば、時間と空間を(現実とは別の連続体に)組み立て直すことができるのだが、そこでイメージがたがいに結びつき、ひとつの連続的な流れが生まれてこなければ、作品のイメージ体験と意味とはうまく一致しない。観客が作品を見終ってからばくぜんと理解できるのではなく、見ている最中にショットにふくまれた意味や感情を観客に明確に、その時点でわからせるように、映像の作り手はつねに意識しておくべきだろう。テンポの早い作品、複雑な物語やコンセプトをふくむ作品、時間が複雑に入れ替わったり並行したりする作品ほど、その点を注意しておく必要がある。
そのためにはまず、カメラが自分の目の延長であるとか、自分の見たままにカメラが撮影してくれるという安易な考えを捨てることである。カメラは「他者の目」であると意識し、カメラによってそのショットの意味をクロースアップし他者に伝えるつもりで撮影することである。また、単に物理的にショットをつなげば、それでただちにイメージが結びつき、時間がすんなり流れると考えないことである。受け手である観客のなかで意味が形成され、イメージがつながりあっているかどうか、たえず他者の目で見、他者の立場で考えることである。
物語を語ることから別のリアリティへ
なぜあるショットとあるショットをつなぐと意味が生まれたり、生まれなかったりするのか。また、その意味が作者には完全にわかっているのに、観客にはわかったり、わからなかったりするのか。これは、編集や構成によって意味を構築していく映像表現にとって本質的な問題といえる。
それを知るためには、自分の作品ではなく他人の作品を客観的に見てみる習慣をつけるのがいいだろう。また、映像表現の歴史とは、映像を組み立て意味を組織化する歴史でもあったのだから、映像がどのようにして物語を語り、複雑な意味や感情を伝達してきたかという歴史的過程を、あらためて分析的に見直すのも役に立つだろう。
1895年に発明されたとき、映画(1ショットのみだった)の伝える意味は、カメラの前で起こっている出来事それだけだった。駅に列車が入ってきて、停車し、乗客たちが降りた、というように。そして、前章「ショットの配列と時間構成」の節でみたように、物語を語る必要からショットが増えていき、当初スムーズに連続していなかったショットが次第に細分化されてスムーズにつながっていくにつれ、最初単一だった視点はどこにでも存在できる複雑な多視点へと変化していき、本来単一の視点では描けなかったはずの状況や事態まで「意味の文脈」として表現していくようになる(過去と現在のまざりあい、2つの場所での同時進行、など)。こうして映画はばらばらのショットを組み合わせていながら、物語としてもイメージの集合としてもひとつの統一された全体を構成するようになったのだ。
1920年代になると、さまざまな撮影技法や編集技法を「レトリック」(修辞学)として物語に結びつけるサイレント映画の「話法」がいったん完成し、どんな物語でもほぼ思いどおりに語ることができるかに思われた。そうしたスムーズな物語の手法に対して、ロシアの映画人は「モンタージュ」という手法で映像の意味を強調・転換し(物語の伝達以上に)感情の高まりやイデオロギーの批判を表現しようとした(前章「モンタージュとコラージュ」参照)。また、フランスを中心としたアヴァンギャルド映画(前衛映画)は、物語より視覚的なリズムや形式を重視したり、挑発的に無意味なつなぎで物語を解体したり、夢のような主観的ヴィジョンで映画を構成しようとしたりした。
ところが、1930年前後に本格的に映画に「音」がつけ加わることで(「トーキー映画」の登場)、サイレント期に洗練された物語話法やそれに対抗するさまざまな実験は一度根本から組み立て直さざるをえなくなった。映像だけの表現に音がつくことによって映画の意味は複雑に変わってしまったからである。せりふの声色の意味、画面外からの声や音の意味、音楽の生む意味、なにげない物音のもつ意味など、音はひじょうに多様で微妙な意味を映画に持ちこんだ。しかし1940年代になると、今日の映画やテレビがそれに基づいて映像を組み立て伝達しているようなスタンダードな映画の話法(いわゆる「映画文法」)があらためて確立し、現在も古典とされるようなすぐれた作品を次々と生みだしていった(それによって映画は古典性をもつ芸術表現という地位も得た)。そこでは映画というメディアは透明化し、音も照明も演技もすべては物語のスムーズな展開に結びつけられ、さながらストーリーがひとりでに語られるかのような錯覚を生んだ。
おおまかに言って1950-60年を境いに、そのように古典的に完成され完結したスムーズで美しい約束事の世界に対して、それを「解体」し別の形でリアリティや真実味を求めようとする動きが目立ってくる。悲惨で危機的な現実とか、きわめて内面的な心理を、ハリウッドのハッピーエンド・ドラマと同じスムーズな話法で描けるはずがないと若い作家たちは自覚しはじめたのだ。映画はそんなに簡単にどんな物語でも語れてしまうのか、誰が語っているかは重要ではないのか、というイメージや意味に対する根本的な疑問もそのベースにあった。
物語の解体と意味の零度
イタリアのネオレアリズモを筆頭に、1960年代のフランスのヌーヴェルヴァーグの作家たちやアメリカの「アンダーグラウンド映画」と呼ばれた実験映画作家たち、さらにはポーランド・チェコ・ハンガリー・ユーゴなどの東欧諸国やブラジル・メキシコ・キューバ・アルゼンチンなどラテンアメリカ諸国の若い映画作家たちが、それぞれ違った形で、ハリウッド的なスムーズな物語話法を意図的に壊したり否定して、新しい表現と新しいリアリティを打ち立てようとした(一例をあげれば、ロマン・ポランスキー、イエジー・スコリモフスキ、ヴェラ・ヒティロヴァ、ヤンチョー・ミクローシュ、ドゥシャン・マカヴェイエフ、グラウベル・ローシャ、フェルナンド・ソラナスなど)。日本では1960年代の大島渚や松本俊夫がその代表格といえる。
《勝手にしやがれ》(ジャン=リュック・ゴダール、59年)や《大人は判ってくれない》(フランソワ・トリュフォー、59年)といったヌーヴェルヴァーグ初期の映画の大きな特徴は、撮影所の外でドキュメンタリーのように即興撮影したことだったが、それはスタジオのなかですべてをコントロールし完全主義的に撮影をくりかえすハリウッド・スタイルの否定であり、現実の複雑さや偶然性を受け入れることだった。しかも、そこにしばしば映画館や映画の話題が登場し、映画というメディア自体の文化や歴史に対する引用・批判・自己言及が行なわれるようになったのも特徴的だった。
ヌーヴェルヴァーグ(Nouvelle Vague, 仏語で"新しい波", 英語ではNew Wave)のなかでも、もっとも徹底した解体を行なったのは、まちがいなくゴダールだった。ゴダールは映画話法の古典的完成とそれが作り出す堅牢な意味の構築に対して、一貫して抵抗し批判しようとしたといえる。1960年代前半の映画でのカメラの直視や字幕の入れ方、60年代末から70年代の「ジガ・ヴェルトフ集団」での政治映画、それにつづく「ソニマージュ」(グルノーブルにゴダールが設立したビデオや16ミリのための映像工房)でのビデオ・エッセイ(75-80年)をへて、80年代に劇映画へ復帰して以降も一貫して、音と映像の関係とは、光とは、映画の意味とは、を問いつづけ、未知なる形の作品を生み出してきた(《右側に気をつけろ》87年、《ゴダールの映画史》88-98年、《新ドイツ零年》91年、《ゴダールの決別》93年など)。
断片性を強調するようなショットつなぎ、画面(映像)と画面外(音楽、雑音、声)との対話やディスコミュニケーション、そして直線的ストーリーを拒絶し何が主題かわからぬほどに矛盾を共存させる編集。ゴダール映画を構成する非凡な1ショット1ショットは改めてスクリーンで確認してほしい。
「ゴダール・ソシアリスム」2010予告編(本編102分の全ショットを1分に圧縮したもの)
こうした姿勢は、ときに映像を意味づけないという地点(意味の零度)にまで達する。ロシアのアレクサンドル・ソクーロフの異常な長回しや歪んだ画面は物語的な秩序を逸脱していき、冥界のような引きのばされた時空間のなかから夢想的・瞑想的な体験があふれ出てくる。ソクーロフよりはるかに過激な夫婦作家ストローブ=ユイレ(ジャン=マリー・ストローブ&ダニエール・ユイレ)の映画になると、ふつうの映画の手法による出来事の「映画的な再現」そのものがいったん拒絶され、ただ風景や現実や事物が無造作に「提示」されるばかりにみえる。
たとえば《セザンヌ》(89年)では、セザンヌの人生を映画によって再現したり、絵にふくまれた意味をカメラが探し出したり、誰とも知れぬナレーターがすべてを解説したりはしない。セザンヌが描いたサント・ヴィクトワール山やセザンヌの絵そのものが長々と固定ショットでうつしだされ、そこにセザンヌの言葉(J・ガスケの評伝から)を読む声がかさなる。あるいは突然、ジャン・ルノワールの《ボヴァリー夫人》(33年)やストローブ=ユイレの《エンペドクレスの死》(86年)の1シーンが何の説明もなくそのまま引用されたりする。今日のふつうの映画とは極端に隔たり、異様なまでに異なった映画だが、ストローブ=ユイレはこういう形で映画というメディアに対する批判的な考え方やテーマに対する「解釈」を浮き上らせるのである。
ストローブ=ユイレ「モーゼとアロン」71予告編(アーノルト・シェーンベルクの歌劇[未完]に基く)
属する文化によって意味も変わる
カナダの先駆的なメディア学者マーシャル・マクルーハンの『グーテンベルクの銀河系』(62年)には、こんな映像の意味と無意味のエピソードが出てくる。
アフリカ先住民の部落で西欧の衛生監視員が溜り水の処理など衛生教育映画(約5分)を見せ、上映後に確認のため何を見たか聞いてみると、みな「ニワトリを見た」と答えたというのである。衛生監視員はニワトリなど見た覚えがない。注意深く見直していくと、ほんの1秒ほど画面右下をニワトリが横切ったのを発見できたという。
未開社会の人々は、ばらばらの映像を組み立て衛生教育のメッセージを伝える約束事(つまり映画が何を言おうとしているか)自体を理解できなかったが、生活とつながりのあるニワトリについては現実感をもって「見る」ことができたのである。二つの異文化の間で、意味と無意味はたがいに逆転している。同じ映像でも異質な文化は異なる解釈を生む。属する文化によって、何を見るかという知覚まで変わってくるのである。
別の例をあげると、私たちが「7色」と信じて疑わない虹の色にしても、ベルギーやオランダの言語では5色、ショナ語では3色、バッサ語では2色に分けるのだという。虹自体は連続した色の変化をなしているのだが、それを何色に識別するかは万国共通ではなく、文化や言語によって違ってくるのである。しかし虹を7色に見てしまう私たちが、それを5色や2色に見ること(一度身につけた文化から異文化の知覚へと変えること)はきわめて困難でもある。
このように社会や文化によって規定される知覚もふくめ、映像の意味は実際にはたくさんの意味の層が重なりあって構成されていると考えることができる。だからこそというべきか、意味を解体し、意味の零度から組み立て直そうとする試みの究極には、文化的・社会的意味を極力切り捨ててしまおうとする映像が存在するのである。
青一色の画面だけが延々とつづくデレク・ジャーマンの《BLUE》(93年)のように、何も見せない映画はその一例である。この作品は作者が以前から構想していたものだったが、94年2月に彼がエイズで死去する前に完成された最後の作品となり、すでに盲目状態に近かった作者自身の視聴覚体験を表わすものともなった。したがって、ここでの何も映らない画面は、単なる意味の否定ではなく、作者の盲目状態を一時的に観客に体験させるという特別な積極的「意味」も担っていた。
しかし、そこからさらに意味を切り捨てて先へ進むこと、たとえば《BLUE》のナレーションも音楽もなくしてしまうと、理解は不可能となろう。あらかじめ意味づけられた世界やその見方を拒絶し、言語や文化も拒絶して、それらを越えた「純粋無垢な映像」を求め、何の意味づけもなしに「世界そのもの」を見せようとするとき、その意味を他者にわからせ他者の理解にまで辿りつくのは限りなく困難である。
映像もひとつの文化的コミュニケーションであるかぎり、作り手と受け手が文化を共有していることがつねに意味理解の前提となるからである。
5. 映像のレトリック:色の意味作用
色がもつ象徴的意味
私たちは色のある世界に生きているが、映像のなかの色はただ現実の色彩を再現するだけでなく、ある色をシンボリックに強調したり、モノクロとカラーを対比したりと、レトリカル(修辞的)にその意味が演出されることも多い。
「赤」が火や血や太陽を象徴し生命の活力を表わすと同時に、危険信号の色であるのは多くの文化圏に共通するといわれ、そのシンボリズム(象徴性)は赤旗から赤飯まではばひろく生活のなかに入りこんでいる。かつてキリスト教絵画では、青は精神性、赤は聖母の慈愛などと色の象徴的意味が厳密に決められていた。また現代では、実験映画作家スタン・ブラッケージが幼年期の記憶と結びつけて赤い色を強調するように、特定の色に個人的な象徴的意味を与える作家も少なくない。そして、同じ赤い色でも暗い赤と明るい赤では印象がまるで変わるのである。
映画のなかで、ある色だけが強く印象に残ることがあるのは、多くの場合こうした隠された意図や計算と関係がある。ときには、白黒映画の一場面が記憶のなかでカラーになっていることさえある。思い出が「色褪る」などという表現があるが、色の記憶、記憶の色は、イメージがもつ不思議な一面とつながっているようである。
カラー映画の成立
映画には、はじめ白黒(B&W、ブラック・アンド・ホワイト)のモノクロームの世界しかなかった。色をつけるには白黒フィルムに場面全体を青や黄色に染めたり手作業で1コマずつ人工着色するかだった。幾多のカラーフィルムの実験をへて、最初の実用的カラー映画システムとされる「3色法テクニカラー・プロセス」が完成するのは1932年、最初のテクニカラー長編映画は《虚栄の市》(35年)だった。3本のネガ(マゼンタ・シアン・イエロー)に色成分を分解し、そこからカラー印刷工程に似た方式で上映用ポジプリントをつくる3色法テクニカラーは、のちのイーストマンカラー(化学的プロセスによるプリント)と違い染色転写プロセスを用いたので、とくに赤や青の原色が強烈で、非現実感が強くなった。そのため、初期のカラー映画はファンタジー、歴史劇、エキゾティックな物語、贅沢なミュージカルなどの大作に主として使われ、今日とは逆に白黒映像が「現実的」とみなされていた。
テクニカラー初期の代表作《オズの魔法使》(39年)では、冒頭とラストの現実シーンが白黒、途中の幻想シーンはすべてカラーで撮影された。白黒から黄色や青の極彩色が突然目に飛びこんでくる場面転換は、人工的で鮮やかなテクニカラーの発色に対する当時の驚きをそのまま表現していた。この種の強烈な色彩性は、現代映画ではもはや例外的となったが、たとえばグラウベル・ローシャの《アントニオ・ダス・モルテス》(69年)やセルゲイ・パラジャーノフの《アシク・ケリブ》(88年)など神話的祝祭性と結びついて画面に登場することがあるのは興味深い。
カラーのなかのモノクロの意味
フランソワーズ・サガンの小説を映画化した《悲しみよこんにちは》(57年)で、監督オットー・プレミンガーは、主人公の現在の無気力なパリ生活を白黒、去年の愉しい思い出をテクニカラーで、と皮肉に対比した(撮影はフランス人だが30年代から英語圏映画でも活躍したジョルジュ・ペリナール[1897-1965])。パーティーで歌手グレコのけだるい歌に合わせて踊るジーン・セバーグの顔(白黒)にリヴィエラの真っ青な海と空が重なる場面は印象的だった。
カラー映像が当り前の今日では、白黒のモノクロミー(無彩色・単色性)がカラー映画初期とは違ったさまざまな意味作用で修辞的に使われている。劇映画でもコマーシャルでも、カラーと白黒が混在している場合は、注意して見ればかならず表現上の意味づけや区別があるはずである(たとえばテレビ・コマーシャルでは、ウイスキー、ビール、宝石など微妙な色の商品を強調するため、それ以外をモノクロにすることが多かった)。
また、カラー映画のなかで「夢」のシーンがモノクロで表現されることも多く、たとえばアンドレイ・タルコフスキーは《ノスタルジア》(83年)など多くのカラー作品で白黒シーンをそのように使った。いっぽうヴィム・ヴェンダースは、《ベルリン 天使の詩》(87年)の前半では「天使」の世界と視点をモノクロームで描きながら、ときどき地上の「現実」をカラーで挿入、後半で主人公の天使が地上に堕ちると映画もカラーとなるという使い分けをした。これらは「恣意的」(作者が勝手に決めた)色分けなのだが、現実がカラー、非現実がモノクロで描かれた点は共通し、観客が意味を理解するうえで混乱することもなかった。
美術史家・辻佐保子の『中世絵画を読む』(岩波書店)によれば、中世の宗教画では天使や天国など不可視世界・霊的世界はしばしばモノクロで描かれたという。今日の映画で白黒/カラーが、現実/非現実とか現在/過去といった「空間的・時間的な異次元性」の表現として使われる根拠ともいえるし、セピア色の映像がノスタルジーを呼び起こすようなモノクロームの感情性もそうした伝統と無関係ではないだろう。
ファウンド・フッテージ(前章コラム参照)の手法による、かわなかのぶひろの実験映画《スイッチバック》(76年)では、古い白黒ニュースフィルムの映像や古い絵葉書のうえに突然カラーの指が入ってくる瞬間に、過去と現在のタイムスリップ感覚が表現されていた。
ビル・ヴィオラのモノクロ表現
ビデオ・アーティスト、ビル・ヴィオラは、《ショット・エル・ジェリッド/ 光と熱の肖像》(79年)で、チュニジアの砂漠にあるジェリッド塩湖の熱と蜃気楼をカラーで描き出したが、その前にイリノイなどの吹雪の風景をモノクロで描き、砂漠と雪、暑さと寒さを、カラーとモノクロで対比した。ここでもやはり、モノクロには空間的・時間的な異次元性が表れていた。
ビル・ヴィオラの場合、しばしばカラーとモノクロを混在させた作品を作ってきたが、最近ではモノクロームだけのビデオ作品(シングル・チャンネル/ インスタレーションではないテープ作品)のほうが多く、これはカラー映像がふつうのビデオアートの世界ではきわめて珍しいことである。ヴィオラは、現象界だけでなく人間の内的・精神的なイメージの世界(夢や天国のイメージなど)に深い関心をいだく作家だけに、「生と死」という主題にからんで彼のモノクロ重視の表現はさまざまな解釈を呼び起こし興味深い。
作者の母の死と9か月後の子供の誕生をモチーフに生まれたヴィオラのモノクロ・ビデオ作品《パッシング》(91年、これをもとにしたビデオ・インスタレーション《天国と地上》92年もある)では、「白と黒だけの夜のイメージや水中シーンをつかうことで、心の多層的な生(記憶、現実、空想など)がまざりあった、知覚や意識の境にあるトワイライト(薄明)の世界を描いてみたかった」と自作解説に書いている。
映像表現では色そのものも色がないことも重要な表現要素となってくるのである。
6. 映像と抽象表現
具象的な再現から非対象のイメージへ
イメージと意味の関係を考えるうえで避けて通れないのが「抽象」という問題である。私たちは、眼球や網膜を通して、世界をたえず具象的・再現的に捉えているのだが、もう一方では同時に、目を閉じたとき脳裏に浮かぶ漠然とした模様のような形で、抽象イメージというものを脳(あるいは心)の中に生み出してもいるからである。
それは「言語」で表現できる意味や論理では単純に捉えきれない、まさに「イメージ」と呼ぶしかない世界なのだが、20世紀の芸術家たち(なかでもヴィジュアル・アーティスト)のなかには、映像を含むさまざまなメディアを使って、そうした内的な抽象イメージを表現することができると考え続けた人々がいた。
現代美術においては、抽象絵画は20世紀の主潮流といってよいほど支配的なものであったが、それが美術史に登場したのは1910年前後のことである。ヴァシリー・カンディンスキー(1866-1944,ロシア出身ドイツ)、フランティシェク・クプカ(1871-1957,チェコ出身フランス)、ピート・モンドリアン(1872-1944,オランダ)、カジミール・マレーヴィチ(1879-1935,ロシア)、ロベール・ドローネー(1885-1941,フランス)らが、それぞれ異なる理由や動機からほぼ同時期に抽象絵画を創始し、理論化したのだった。
František Kupka「Mme Kupka among Verticals[垂直線のクプカ夫人]」1910–11, MOMA
それは要するに、外界の対象を再現して描くのでなく、「非対象」(ノン・オブジェクティブ:「無対象」とも訳され、ノン・フィギュラティブ[非具象]ともほぼ同義)の色と形の世界を描く絵画であり、それを通して精神・感情・神秘などを描こうとする絵画であった。
こうした抽象絵画登場の背景には、現実を機械的に再現する写真という複製メディア(1839年~)の出現により、平面に手で描く絵画という表現の役割を画家たちが改めて考え直し、再定義しなければならなかった事情もあった。そうしたアクチュアルな問題意識のなかから画家たちは、色や形態を純粋に探究しようとしたり、ルネサンス以来の「遠近法」というイリュージョンによる3次元空間の再現を否定して絵画(タブロー)の平面性を強調したりし始めるのである。なかでも、音楽を絵画表現に置き換えようとしたり、「共感覚」(シネスシージア:ひとつの刺激から複数の感覚が同時発生すること)を表現しようとする「聴覚体験の視覚化」という関心は注目すべきものだったといえる(逆に、音楽で色など視覚的なものを表現しようとする試みも同時期にあった)。
1910~20年代にひろまった抽象絵画は、さらに第2次大戦後になるとアメリカでジャクソン・ポロックやヴィレム・デ・クーニングらの「抽象表現主義」として大旋風を巻き起こし、いよいよ抽象絵画が美術界を席捲するようになる。
動く抽象絵画から「ヴィジュアル・ミュージック」へ
こうした美術界の動向が「動く抽象絵画」という形で映像メディアのなかに入ってきたものが抽象映画だった。しかし、1920年代はじめにドイツのハンス・リヒターやヴィキング・エゲリング(スウェーデン出身)といった抽象画家が「絶対映画」と呼ばれる抽象映画(抽象アニメーション)を作って以来、論議の的となってきたのは、本来カメラのレンズを通して外界の対象を客観的に捉える映画というメディアで、「非対象」の抽象世界を描くのが妥当なのかどうかであった。
今日のように、コンピューター・グラフィックスやミュージックビデオのなかで頻繁に抽象映像がみられる時代には、こうした論議のポイントはかえってわかりにくいかもしれないが、もともと、写真的映像の最大の特質は、現実を忠実に再現する具象性・再現性にあり、それが抽象絵画発生の一因にもなったのであるから、写真や映画を非具象・非再現的な抽象表現に使うのはメディア本来の方向とは逆なのではないかという否定的な考え方にも十分な理由があったのである。
リヒターやエゲリングと同じ時期に、やはりドイツのオスカー・フィッシンガー(1900-67)は、早くから抽象映像と音楽の一体化を夢みて、《スタディ》シリーズ(29-34年)などで実験をくりかえしていた。フィッシンガーの抽象アニメ作品は、もちろんクラシック名曲と画の動きのシンクロ(同期性)のおもしろさが魅力のひとつにはちがいないが、それは単なるシンクロをこえて視覚と聴覚を合体させる「ヴィジュアル・ミュージック」(視覚化された音楽、目で見る音楽)と呼ぶべき試みであった。
オスカー・フィッシンガー 上「スタディNo.6」(30) 下「ラジオ・ダイナミクス」(42)
ユダヤ人であったオスカー・フィッシンガーは、ナチスの台頭と弾圧により36年アメリカへ亡命することを余儀なくされるが、それによって彼が住みついたアメリカ西海岸からは、ホイットニー兄弟、ハリー・スミス、ハイ・ハーシュ、ジョーダン・ベルソン、ラリー・キューバら、戦後アメリカ実験映画を代表する抽象アニメーション作家たちが数多く育つことになった(ディズニー・プロの《ファンタジア》[40年]ももとはといえばフィッシンガーのアイデアであったが、抽象イメージのみという案が却下され、彼は途中で手を引いてしまった)。
フィッシンガーがその後一貫して追求し、西海岸に多くの後継者を生んだ「ヴィジュアル・ミュージック」の系譜や歴史的展望については、キース・グリフィス(ブラザーズ・クエイのアニメ作品のプロデューサーでもある)が監督したアート・ドキュメンタリー《アブストラクト・シネマ》(93年、ダゲレオ出版VHS発売)がくわしく、必見である。
抽象映像と時間
抽象映像のもうひとつの重要な側面は、それが「非物語的」な映像であること、つまり直線的にストーリーが展開していく物語映画の時間構成とは本質的に異なる点である。ちょうど音楽には意味や物語がないのと似ている。音楽とおなじく(そして抽象絵画とはちがって)映画・ビデオ・CG等の抽象映像には「時間」が伴っている。
劇映画の場合なら、時間にそって物語が展開し、前の出来事が原因となって後の出来事(結果)が起こるという関係(因果関係)によって意味が組み立てられている。こうした物語的構成とは異なる時間構成の形式として、抽象映像にみられる「音楽的」な構成がある(それ以外にも、よくみかける非物語的な構成としてカタログ的羅列がある)。
抽象イメージが物語と離れて、変化する色や形を純粋な形式的原理で組み立てようとしたとき、リズム・反復・ハーモニー・対位法といった音楽の構成原理が、映像表現のなかに取り入れられていったのである。
映像が音楽と結びつくもうひとつの動機として「聴覚体験の視覚化」という関心をあげることができるが、これについては近年のミュージックビデオにもっとも顕著な展開をみることができる。こうしてコンピューター・グラフィックスやビデオクリップにまで受けつがれた抽象映像の流れは、いまでは美術・映画・ビデオ・コンピューターなどヴィジュアルアートの諸ジャンルを横断して歴史的に見直すべき時期にあるといえる。 [了、再録終わり]
ⓒ西嶋憲生 2000/2024