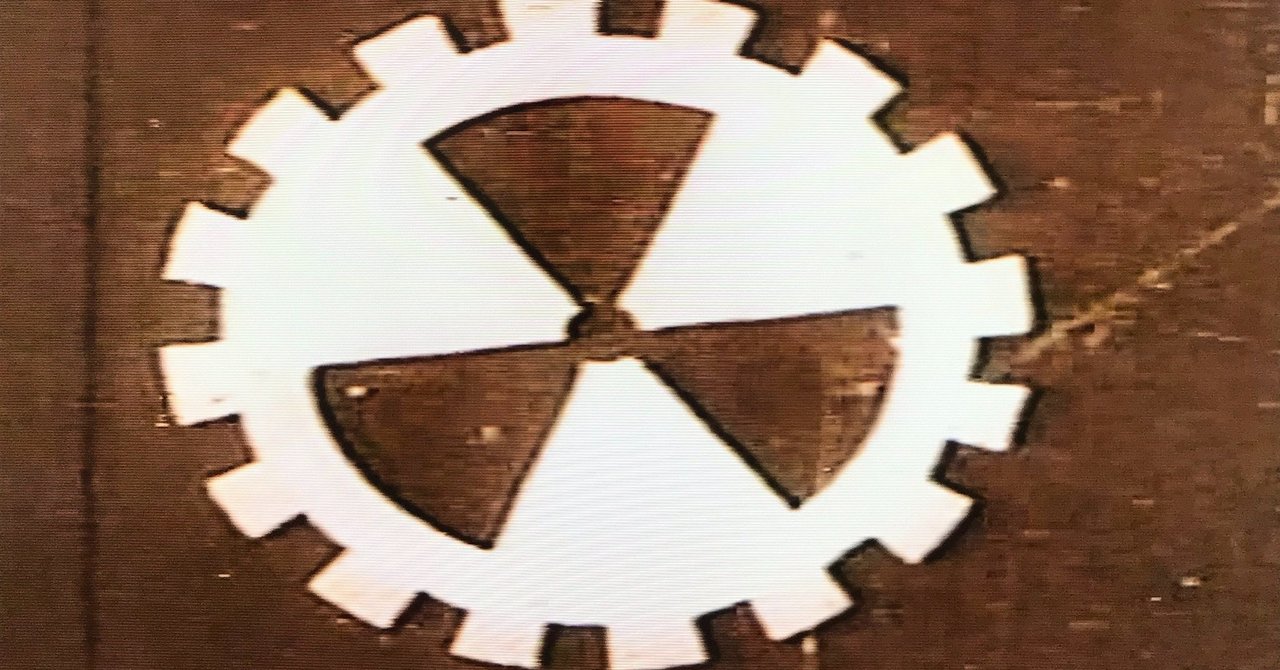【再録】即興自由映画「ハリウッド征伐」──瑞西、萬國自由映畫會議餘談──(肥後博,1929)
[序]この文章は「キネマ旬報」348号(昭和4[1929]年11月11日号)p.54 に掲載された肥後博の記事の再録である。肥後博は"松竹本社のキレ者"(徳川夢声)から邦楽座支配人を経て新宿武蔵野館支配人となった人物で(1929-30年当時は神田淡路町の"異端の映画小劇場" シネマ・パレス経営者・支配人で配給会社「前衛映画社」も経営)、当時買付け等で渡欧していた(仏独伊を歴訪)。
1929年スイスのラ・サラ(サラズ)城で開催された「国際独立映画会議」(前記事「ラ・サラ城での出会い」参照)に参加した日本人の一人であり、その会議中に撮影され未完・紛失とされる『ラ・サラの嵐』(Tempête sur La Sarraz, 英題The Storming on La Sarraz)なる作品の具体的詳細を本稿は記録していて貴重な証言といえる。同作品には"Le Combat de la cinématographie indépendante contre le commerce"[商業に対する独立映画の戦い]という別題もあり、表題の「ハリウッド征伐」はこれを意訳したものと思われる。
なお、さらに貴重な情報として「第2回プロレタリア映画の夕」(1930.6)において、肥後博がシネコダック(16mmカメラ)で断片的に再撮影した同作が上映されたという不確かな情報があり、断片的な映像が日本で上映された可能性がある(予告されたが実際は上映されなかった可能性も)。
*再録にあたって旧字旧仮名はすべて現代表記に改めた。また文中の[ ]内は西嶋の注または原文の人名表記である。
スイス・ラ・サラズにおける「万国自由映画会議」[国際独立映画会議 Congrès International du Cinéma Indepandent de La Sarraz]、これは[1929年]9月2日から6日までの5日間に行われた。
参加国は、ドイツ(4名)フランス(5名)オランダ(1名)イギリス(2名)アメリカ(1名)イタリア(2名)スイス(4名)スペイン(2名)ロシア(3名)オーストリア(1名)それに日本(槌谷茂一郎君と小生の2名)の11カ国で、出席人数は以上の数であった。で、会議の内容、決議事項、それから当時の模様などについては、槌谷君が詳しく旬報誌上に発表することになっているから[キネ旬349号,351号に掲載の槌谷氏の特別寄稿「国際独立映画会議の記」,当ブログに再録]、小生は全然それには触れないことにして、その余談として、会議中の暇を愉しんで一同が考え上げた「即興自由映画」について語ることにしよう。
それは9月4日のこと、晩餐の食卓で──
「ねえ、エイゼンスタイン、どうだね、折角これだけの古城のバックを持って、これだけの珍品古物を持って、そしてこれだけの珍しい顔ぶれを持って、何か面白い一、二巻物の自由映画は出来ないものかね、作りたいもんだね」
とは、ドイツの監督ハンス・リヒタアの提言であった。
「ウン、それは僕だって考えないじゃないんだがね、生フィルムは持っているし、キャメラはあるしだが、でもあのマダム[ド・マンドロ]がそれを承諾してくれるかナ」
「ナァーにそれなら僕から一つ掛け合って見よう、大分マダム、話に興が乗って面白そうに喋っているから、そこをつけ込んでね」
と言ってツイと立ち上って行ったのは、フランスの評論家レオン・ムウシナックである。
「大丈夫……だが弱ったね、マダムは明日昼には町の御歴々を招待しているから、この連中が来ている時に、色んなものを持ち出したりなんかされては困るから、それまでにやってくれるなら差支えないというのだが、どうだね、それでやれるかね」
「よし、何とかやっつけよう」
話は早くまとまった。ドイツ評論家ベラ・バラージュ[原文バラズ]、それに例の「伯林[大都会交響楽]」の製作者ルットマン、それからエイゼンスタインの名キャメラマンのティッセ[チッセ]、アシスタントのアレクサンドロフ[アレキサンドルフ]、轡を並べて一同がでっち上げたのは、即ち、自由映画「ハリウッド征伐」なる一篇である。
勿論これがどんなにカッティングされて、どんな傑作が出来るかは到って疑問だ、が、兎に角エイゼンスタインとリヒタアの合作、監督はエイゼンスタインが七分通りを受け持って、あとはリヒタア、ルットマン、ムウシナック、バラージュなどとウルさ方が、やれそこはどうの、あそこはこうのと駄目やら何やらが出たことであるから、ヒョッとしたら痛快なものが現れ出さないとも限らない。キャメラは名に高きティッセの腕、主演俳優といっては別にないが、フランスの女流批評家として、そしてカヴァルカンティ[キャバルカンティ]の「港町にて」の助監督を勤めたブイスヌーズ[ブュスニューズ]女史が映画の女神を演じ、英国から来たアイザックス[イザック]がセシル・B・デミル[ドミューユ]に適められて商業映画の敵役に当てられ、エイゼンスタインが自由映画軍の総帥となって、映写機に跨って商業映画の敵地へ突進するというような筋のあらましで、何れも鎧甲を身につけた大時代の装束の中に、現代の器械や道具が混って、実に何んといっていいか、想像もつかぬ自由映画となるのであろう。だから、何れも様の扮装たるや、ソクラテスもいればナポレオンもいる、アントニーや仙人や、スパルタの武士どもが、互いに敵となり味方となり合って、ラ・サラズの城を戦禍の巷と化しているというのだから、いとも凄絶悲絶なお話である。
[注 ジャニーヌ・ブイスヌーズは後に小説家・歴史家となり日本では『コンドルセー 大革命の中の啓蒙哲学者』が翻訳されている]
映写機に跨るドンキホーテ将軍(エイゼンシュテイン)
映画の女神を演じるブイスヌーズ嬢
タイプライターで戦うオリオール(従軍記者か)
独立映画騎士団のハンス・リヒター、"独立映画のために"の文字
ここに哀れを止めたるは、我が槌谷茂一郎の君、天晴れ商業映画の武卒となって、得意気に胸撫で廻し「我こそは日本のコムマーシャル・フィルムの精也」と何処からどうして持って来たか、エタイの知れないメイセンのタテジマの着物を身につけていい気持になっていると、後ろから抜き足さし足忍び足で窺い寄った怪し気なる曲者、黒の頭巾に左右両脇は黒タテ縞のツツ袖「ヤアヤア汝、よくも商業映画などと人を偽り世を誤魔化し、愚にもつかぬ迷画をば名画なんどとぬかしたり、今こそ汝の武運も尽きたるぞ、いでジンジョウに勝負勝負」「何を、この期に臨み、命だけはオタ、オタとはいよいよ以って卑怯千萬、立派に腹かき切って申訳せい」と詰めよれば「ああ、俺はナシャケない」と云って彼は、歯を食いしばり両眼閉じ、或は右にまた左に目玉をクルクルさせて──この所クローズ・アップ──くたばるのであった。
この時、後ろに控えた曲者は、グーと見得を切る。「君、首を少し廻し加減に、白目玉を出してグルグルと廻してグーッと下のハラキリを睨むんだ……ソレ、ソレその通り」ここでまたクローズ・アップ、何れもエイゼンスタインの監督演出である。噫、止んぬる哉、小生はこの曲者であった。自由映画の精兵となってめでたや彼をやっつけるという、役どころだけは悪くはないが、その扮装を思い出すと、我乍らゾーッとする。生れて始めて活動役者を勤めた。昼前の強い太陽の下で、鏡のレフレクターを向けられて、大見得を切った時は、旅の恥はかき捨てとは申し乍ら、いや辛かったぜ。(何んと、S君よ、このフィルム出来上がったら、旬報あたりで買ったらどうだね)
黒頭巾の曲者のアップと思われるカット
あとで、エイゼンスタインは、盛んに日本の歌舞伎について語った。勿論、それは先年、左團次がモスクワ入りをした時、絶えず注意して見聞し得た智識からである。だからこの日の撮影でも、日本人の芝居は全部歌舞伎の態で、目玉をムクものと考えているところから、あんな演出をしたのかも知れない。
こんな具合で兎に角、撮影は終った。マダムのお客様方に、この醜態を見られることもなく、正午までには、俳優の芝居の夫々は完了した。そして、午後になってティッセとアレクサンドロフは、公然と皆の前で、キャメラを城の廻りのあちらこちらに置き替えて、城壁やら、景色やらの写真を撮していた。
思えばナヤマシイ、また愉快な仕事ではあった。
瑞西(スイス)ラ・サラズに於ける楽しい思い出。
一九二九、秋九月巴里にて
附記──
さて、これからベルリンへ行って、約一ヶ月ばかり滞在して再びパリーに戻って来る。
十月二十八日伊太利ナポリで乗船して十二月七日横浜着の予定。船は伏見丸。
今度土産に、フランスの前衛映画を買って帰る。持参する荷物は次の通り。
アルベルト・カヴァルカンティ[キャヴァルキャンティ]作品
「時の外なにものもなし」 四巻
「港町にて」 五巻
A・シルカ作品
「あひるの悲しい死」[公開題「家鴨の惨死」] 二巻
既に、日本で誰方が買いつけた「秋の霧」「ひとで」「坊主と貝殻」「地帯」これは「坊主と貝殻」だけが二巻である他、他は一巻物だと思う。何れも面白い映画だ。
僕の輸入した前記の四作品は、是非旬報の人達に見て頂きたいと思う。 [再録了]
[補記] 肥後博が持ち帰った3本の作品、カヴァルカンティ『時の外何物もなし』26(3巻)と『港町にて(En Rade)』27(7巻)およびA・シルカ『家鴨の惨死(La Malemort du Canard)』28は肥後の前衛映画社配給で、1930年2月9日、市政会館(日比谷公会堂と一体の会館)で上映された(キネマ旬報355号, p.142に広告あり)。これがフランス前衛映画の最初の上映と思われる。徳川夢声らの解説(活動弁士)、村山知義らの講演予定とあるが、官憲が中止したとされる。
上映に先立ち試写評が矢野目源一「前衛映画を正しく批判せよ」としてキネ旬353号pp.52-53に紹介されている。「自体前衛映画とは、因習的なものから蝉脱解放を目的とする映画という意図を持つものであり、映画芸術の法則とその可能性の研究であり、将来の映画芸術の発見をその目標とするものである。」云々。
この前衛映画上映会は、大阪朝日会館(2/20,21)、名古屋千歳劇場(2/27)、静岡と続き、弁士の夢声も同行した。また『時の外何物もなし』は2/20から芝園館で『王様萬歳』『母』の併映作品として上映された(飯島正の評がキネ旬359号p.38にあり)。『港町にて』は2/27から芝園館、道玄坂キネマ、南明座にて『大飛行艦隊』『飛行士になるまで』の併映作品として上映された。
肥後博は当時のキネマ旬報にしばしば寄稿、1930(昭5)年には「小劇場と経営難」、553-4号(昭10年)あたりで「洋画興行論」を連載、554号ではトーキー初期の吹替版(日本語版)を論じている(昭6年のフォックス『再生の港』が最初、昭9年JOの『空飛ぶ悪魔』は失敗など)。
また、鈴木重吉が輸入したキルサノフ『秋の霧』27,マン・レイ『ひとで』28,デュラック『貝殻と坊主』28,ラコンブ『ラ・ゾーヌ(あの界隈)』28も公開されたが、『ひとで』と『貝殻と坊主』は検閲に引っかかりかなり公開が遅れた。矢野目源一が358, 360号(1930年3月)の「再び前衛映画に就て」で3作品の試写評を論じているので、この年に公開されたことは疑いない。『ひとで』『貝殻と坊主』は「映画検閲時報」によれば1933年1月21日にかなりカットされて通過(この検閲通過・上映に尽力したのがのちの映画史家・田中純一郎[当時,キネマ週報編集部]だったという。cf.広瀬愛「田中純一郎における実験映画への視点」『映画への思い 日本映画史探訪3』2000)。1933年2月8,9日に大阪朝日会館でカール・ドライヤー『吸血鬼』と共に上映(講演「前衛映画に就いて」牛原虚彦)、2月16-22日に邦楽座で『イグルウ』(米,32,アーウィン・スコット)と併映で封切、その後各地で併映上映。
『ひとで』の1933-37年の上映についてはマン・レイ研究家の石原輝雄が「ときの忘れもの」HPのエッセイで触れている。 http://blog.livedoor.jp/tokinowasuremono/archives/53477880.html