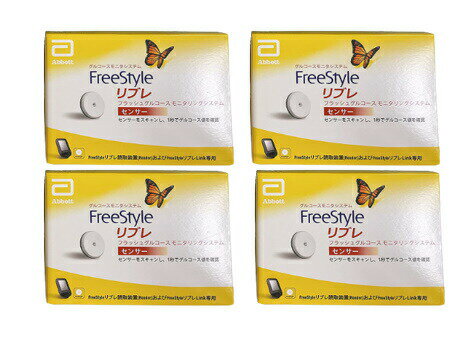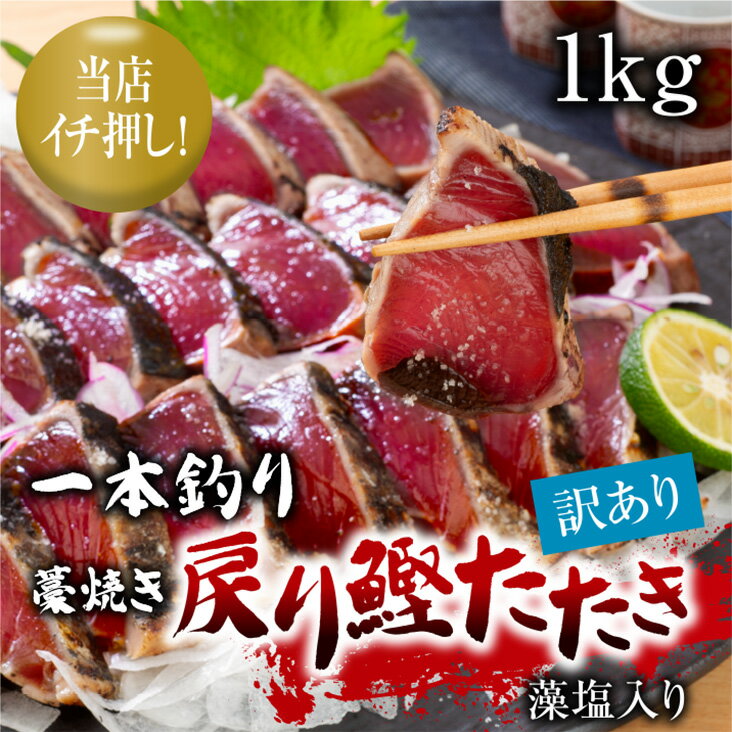伊勢白山道さんの昭和天皇が表神事をやり裏神事を高松宮様がなさり昭和の日本を支えていた…
しかし高松宮様が亡くなったあと裏神事の代わりを務めたのは何と茶道だった。
私から視る茶道とは、「慰霊」と「鎮魂」の作法であり行為だと感じます。
その「場所」に集まる霊たちへ御茶を献上することで、忘れ去られた霊たちを慰めて供養する行為が茶道に感じます。
その場所に掲げられる掛け軸は、霊の「依り代」として機能します。
そこで御茶を頂く人々は、飲みたい霊たちの代わりとして頂き、鎮魂を手伝っていることに成ると感じます。
では、茶室の入口が小さくて、窓明かりも障子で閉じられた空間の茶室とは何なのか?
私は、「神棚の中」に居ることに成ると感じます。
私は、神棚はトビラで閉じるタイプが良い、その中の閉じた空間が神棚には大切だと説明して来ました。
古い神社ほど、社殿の奥に在るのは閉じられた部屋、「空の間」であると感得します。
出雲大社の神殿の中にも、何も無い閉じられた「空の間」を御神体として祭るのが古代の方法だったと私は想像しています。
・ 神様は、閉じられた部屋の空間に宿る。
ここにミニ宇宙を表すウズを巻くことを、神気の動きとして感じます。
「茶室とは、神棚の中の空間だった」、これを感じた時に次に浮かんだことは、
・ 茶道の本質は、野点(のだて)に有り。
と感じます。
本来の茶道は、荷車に5枚ほどの大きな細工をされた建具の板垣を野外に運び、そこで簡易的な即席のハメ込むだけの茶室を作ります。
その閉じられた空間の中で御茶を点(た)てることは、その場所を、地域を、浄化すると感じます。
千利休を家元として広がった古い家系の茶道の家元は、どの流派も大徳寺と皇室との関係を通じて「言うに言えない」子供たちとの関係が深かったと想像します。
そういう男系男子と深い御縁がある家柄の茶人が点てる御茶には、国を鎮魂する意味が有ると感じます。
でも、時代を経た今からの国家存亡の危機には、特別な方々だけが行う鎮魂(ちんこん:恨みを持つ霊たちを慰めて、平和を呼び寄せる行為)
では間に合わないとも感じます。
そこで、日本に住む多くの方々が、外国人の方々も含めて霊を鎮魂する意識を持つことが、子供や孫たちに住む国を残す縁に繋がると私は感じます。
では、どうすれば良いのか?
大きめの湯呑みに熱い御茶を、心を込めて入れて、キッチン台の隅か、食卓テーブルの上に置いて上げることを参考にしてください。
家の中だから、閉じられた空間にも成っています。
そして、日本の大地(プレート)に住める感謝と、
言いたいことも言えずに忘れ去られた人々の霊へ、
「どうぞ御茶を召し上がってください」
という感じの内容を、自分なりの言葉で思って御茶を置くことを参考にしてください。
この御茶は、30分〜1時間が経てば、流し台に廃棄をしてください。
絶対に飲んでは生けません。霊に捧げた物は、最後まで霊の物です。
湯呑みは洗浄すれば、家族が使用しても問題はないです。
もし気になれば、専用の湯呑みの用意を参考にしてください。
こういう気持ちの蓄積が、日本と海外を、様々な災難を鎮魂して収めることに成ると感じます。
でも、「そんな自分などがしてもムダなことだ」と思う人が多いかも知れません。
ところが、そうでは無いのです。
その根拠を説明します。
これは戦前の話ですが、九州の長洲という地域に親神様と呼ばれた松下松蔵という、一瞬でどんな病気も治す人物が居ました。
その評判を聞いてウソだと思った新聞記者や、東京の医師たちが、九州まで出向いて確認した結果、その全員が感服して応援者に変わり、九州の新聞社の社長までが信奉者に変わったという御方でした。
私の父親は、九州から遠く離れた場所に住んで居ました。父が幼稚園児の頃に重い熱射病に罹り、多臓器不全まで起こし始めて医師から命の危険が有ると告げられます。
もう時間経過を見るしかないと言われた時に、昔に近所に住んで居た人から週刊誌でも見たと言って、九州の長洲の親神さんに電報を打つだけもして見ればと言われ、親はその通りに子供の名前と危篤だと電報を打ちました。
(知人も電報を打ち、計2度の電報と成った。このへんの詳しい事情は「昭和の話 その5」参照)
すると、郵便局の人が長洲の住所に電報が届くと言った時間帯に、父は急に熱が下がり始めて一命を取り留めました。
何の御礼も出来ないまま父は健康に育ち、当時の全国で数が限定された第(数字)高等学校(その時代の旧制高等学校は、今とは格も教育内容も違うそうです)を無事に卒業して、大学入学が決まった記念に、九州の長洲まで松下松蔵氏に会いに行ったそうです。