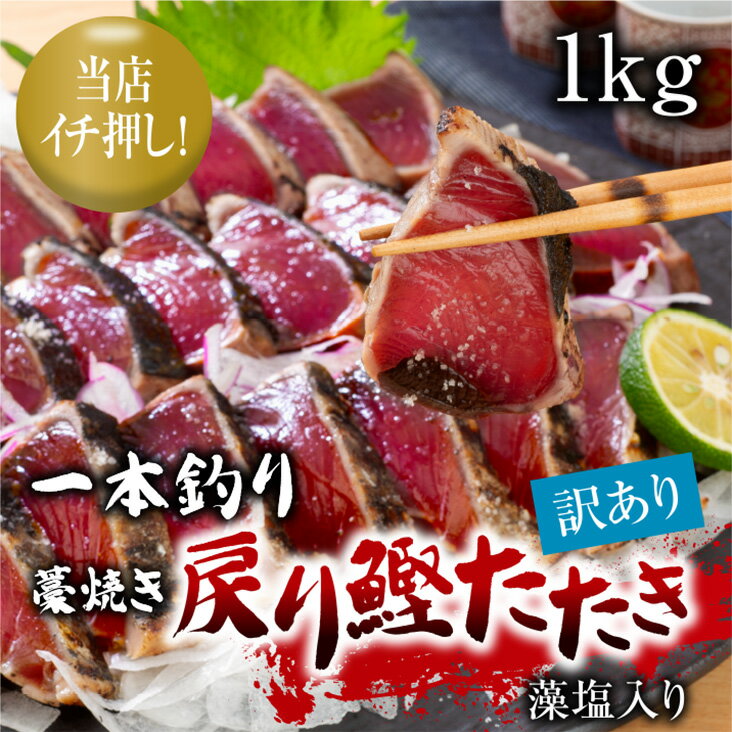日本の歴史の悪い習慣は、都合の悪いことは、
・ まるで何も無かったかのように。
・ 無念を持った存在たちを忘れ去ること。
・ 過去には触れないこと。
有名な聖徳太子にしても、蘇我氏と皇位継承を巡って敗れたその死後に、聖徳太子の家族全員が自殺したり殺害されており、その範囲は普通は免除して残される女性親族と女系の親族までの全員がその痕跡を消されています。
これが近年でも、聖徳太子という名前は歴史書には存在しないという理由で、教科書から削除されて厩戸王(うまやどおう:庶民からの尊称は聖徳太子)に修正がされています。いずれは聖徳太子という名前は教科書から消えるという指摘も有ります。
これが更に進んでおり、「聖徳太子は存在しなかった説」が学説として上がり始めています。
つまり、聖徳太子が行ったとされる憲法制定や事業が短期間に膨大過ぎて、それぞれの事業を行った人物が別に存在したという学説が出始めています。
皇位継承で敗れた一族は、いかに日本の歴史から不遇な対応を受けたかと言うことです。
聖徳太子と同じようなことが、崇徳天皇にも起こります。
崇徳天皇の場合は、天皇の地位についていたのに、無理やりに皇位から引きずり降ろされて配流(はいる:流罪)までされています。天皇だった御方が、です。
でも、崇徳天皇は、実際は皇室を恨むことは無くて、
・「憂き世のあまりにや、御病ひも年に添へて重らせ給ひければ」
意味は、寂しい生活の中で、悲しさの余り、病気も年々重くなっていってしまった。
・「思ひやれ 都はるかに おきつ波 立ちへだてたる こころぼそさを」
京都の都を懐かしく思い、海に隔てられた遠い場所で、心細く生きています。
という謙虚な心情を歌に残されています。優しい御方だったと感じます。
しかし、崇徳天皇の優しさを見るほどに、崇徳天皇に命を捧げるつもりで見守って来た側近たちは違いました。
側近たちが世間に広げた歌は、
「願わくは、大魔王となりて天下を悩乱せん。五部大乗経をもって廻向す。
皇を取って民となし、
民を皇となさん。
人の福をみては禍とし、世の治まるをみては乱をおこさしむ」
つまり、
* 私は大魔王に成って復讐するぞ。
* 社会に混乱と悲劇が発生するように、仏教の呪詛をもってしてでも遣り遂げるぞ。
* 天皇を民間に落とし、代わりに下の下の平民を天皇にすえ変えてやる。
* 幸福な人間には災いをもたらし、平和な社会を見れば混乱させてやる。
つまり、崇徳天皇の退位・配流に伴い、朝廷から追放された多数の元側近たちの怒りと怨念は、
・ 「日本国の天魔王となり、皇を取って民とし、民を皇となさん」
(皇室を無くして民間人に落としめて、その代わりに民間人を天皇にして見せようぞ)
という思いの下(もと)に団結し、その中には自害した元側近も多かったと感じます。
これが崇徳天皇の御名(ぎょめい)の下(もと)に、怨霊集団を日本に形成しています。この怨霊集団は、その後に皇室を二分した南北朝の動乱を引き起こしてもいます。宮中の政治に熟知していた怨霊たちには、内部で争いを起こすことが可能でした。
更には、近代には怨霊集団の第3世代が、革命家・北一輝を陰で誘導したり、三島由紀夫氏の皇室への傾倒と自害にも影響を与えたと私は夢想します。
更には、昭和天皇が靖国神社の参拝を止めた理由に関することです。
元侍従が記した手記に残されていた、第二次世界大戦時の3名の元側近たちが靖国神社に祭られた時に、それを反対していた昭和天皇が非常に怒った様子が残されています。
第二次世界大戦が始まる切っ掛けとなった、元海外留学組が居たということです。
どうして、そういう人物が日本から出たのか?
これにも日本の怨霊集団の影響を夢想します。
崇徳天皇を供養するだけでは無くて、元側近たちも手厚く供養する必要が日本には有ったということです。
当時の元側近たちも、やはり選ばれた家系であると共に、男系男子との縁が深い者たちでした。その思いの力が強かったのです。
以上は、第二次世界大戦で日本が迷惑を掛けた、中国や、朝鮮半島、東南アジアの方々、南方の島々などの方々に対しても言えることです。
当時の海外の庶民の犠牲者たちを供養することが大切です。
戦後に日本で、その国ごとの心良く賛同して頂ける在日の方々を集めて、国別に日を分けて(半日ずつでも)、日本の方法で良いから慰霊の供養をする行事を毎年に行っていれば、現在の状況はかなり変わっていたと感じます。
やはり当時の無念の怨霊が、日本を含むそれぞれの国の今の現職の方々の心情に影響をするのです。
これの有無が、大違いであり、最後の最後に日本の存亡を決める決断をさせることにも成りかねません。
・ まるで何も無かったかのように。
・ 無念を持った存在たちを忘れ去ること。
・ 過去には触れないこと。
これが、怨霊を生みます。
生きる人々にも、その気持ちと判断に影響します。
以上のすべてを、茶道のおもてなしの心で、縁ある子孫の方々を招き、柔和にして行くことが大切です。
そして、一般人も、各家庭で過去の忘れ去られた、言いたいことも言えなかった人々に、「まあ御茶をどうぞ」という習慣で故人たちを「忘れない」ことが大きな供養となり、未来の日本を助けることでしょう。