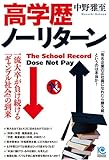
皆様こんばんは!
さて、本日は学歴は必ずしも幸せにつながるのか?というテーマについて考えさせてくれる
この一冊をご紹介致します。
学歴ってホントに役に立つのでしょうか?
少なくとも言えるのは、
これをあまり深く考えずに、子供に「いい大学に行け!」と言って、一生懸命塾に通わせたり、稼いだお金を何の疑問も持たずに「良い学校に入れば幸せになれる」と信じて投資する親は多いということです。
私は思いますが、これは頭をクリアにして今一度考えてみるべき問題だと思います。
学歴コンプレックスがある親ほど、何も疑問を持たずにこの考え方を信じて疑わない傾向にあると感じています。
何故ならば?
「自分が苦労しているのは学歴のせいだ」
と思い込んでいるから。
因に私は親のお陰でそれなりの学校へ行くことが出来ましたが、
学生時代からずっと疑問に思っていたことです。
勉強は好きでしたけどね。
それなりの学歴を手に入れて、社会人10年を過ぎた私は、
相変わらず学歴に対して懐疑的です。
いや、むしろ更に斜めに見るようになりました。
因に、私の学歴情報はFacebookやmixiでは公開していますので。
大学で学問を学ぶこと自体は、全く賛成です。
学問は心を豊かにし、視野を広げてくれる尊いものです。
問題は、「良い大学に入るだけで一生安泰」と考える発想。
果たしてそうなのでしょうか?
私と同じように疑問をお持ちの方は、少しお時間を頂き考えて欲しいと思います。
それでは、いつものように解説して参ります。
著者は、元キャリア官僚の中野 雅至さんです。
官僚だけあって、とても文章がお上手でボリュームがあります。
正直、サマリーするのも今回はしんどかったですが、なるべく要点が伝わるようにまとめてみます。
◎誰が損をしているのか
①正社員=勝ち組か?
賢明な方は疑問を抱くフレーズだと思いますが、結構常識的に考えられていることでしょう。
でもそれは、
「フリーターやニートに比べればまし」というレベルだと、著者は警告を発しています。
それは「下には下がいる」という、何とも気持ちの悪い論法であると思いますね。
そもそも、私はこの「勝ち組」「負け組」という発想自体が嫌いですが。
ともかく、一昔前に比べて正社員である価値は下落しているのは間違いないでしょう。
何せ、一生勤められる保証も無いのだから。
②格差とは、誰と誰の格差か?
「格差社会」を語るとき、少し前提条件に気をつけなければならないと著者は言います。
一流サラリーマンと貧乏サラリーマンの違いのことを指しているように捉えられることが多いですが、
実際に格差が問題なのは、サラリーマンとセレブです。
元々、サラリーマンはいくら稼いでもたかが知れています。
少なくとも、一流企業に入れるための学歴を手にする努力への報酬としては、
決して見合うものでは無いと感じるのは、著者や私だけでは無いはず。
最近、少し役員報酬が多くなって来ている傾向はありますが、事業やスポーツで成功する方が
遥かに儲かります。
また、金持ちは金持ち同士、貧乏は貧乏同士と結婚する確率が高いのは事実です。
つまり、世帯としての格差もどんどん広がっていくわけですね。
③東大生の親は年収1000万以上が多い
東大のような一流大学に入るような家庭は、基本的に裕福であることが多いのです。
つまり、学歴エリートは再分配されているに過ぎません。
この点については、後ほど詳述します。
④自営業が多いのが日本の特徴だった
元々日本社会は、「お店」などの自営業が多いのが特徴でした。
今の若い世代には感覚的に分かりづらいかも知れませんが、私が子供の頃は今よりもたくさんの
個人商店があったものです。
そこには勿論、「雇用」も発生していたわけで、雇用問題の一翼はこの自営業の没落が影響している、
と著者は分析しています。
⑤日本人は情報を金で買う感覚が乏しい
日本は、貴重な情報が無料で手に入る「おいしい」国です。
政府や官庁からは、官僚達が寝ないでまとめた経済資料などが無料で手に入るようになっています。
でも、例えばアメリカでは政府からそのような貴重なデータは入手出来ません。
作成しているのは、民間のシンクタンクなどの機関です。
当然それは、無料では手に入りません。
だからアメリカでは、知識労働にはそれなりの報酬が払われています。
要するに、日本では知識労働のマーケットが育たない、と著者は指摘します。
◎彼らは何故怒らないのか(中央官庁編)
中央官庁こそ、学歴エリートの象徴とも言える場所でしょう。
東大卒の人間など、ざらにいます。
でも、彼らほど報われない仕事も無いと、官僚出身の著者は嘆きを語っています。
基本的に、役人はまじめな人が多いのです。
マスコミが悪いイメージを喧伝していますが、それは一部の人のこと。
私も何人か友人がいますが、極めてまともでまじめに働いている人が多いという印象を受けます。
だから、自殺が多いのです。
もはや世間にも広く知られるところとなっていますが、あまりの長時間労働で鬱病になったり自殺する
人が多いことで、中央官庁は有名です。
単に仕事が激務なのは民間もさほど変わらないところもありますが、
申し訳ありませんが、あれほど退屈な仕事をやり続けることが出来るのは、
まじめな人間であることの証左だと私は考えています。
因に本書でも強調されていますが、役人は資料作りの仕事が多いため、
民間企業とは比べ物にならないほど事務処理能力の高い人材は多いです。
決して、「できない人」の集まりではありません。
でも、それを食い物にしている人たちがいる。
詳細は本書に書かれていますが、民間に比べて「どうでも良いこと」に忙殺されている、
とても報われない仕事なのです。
でも、彼らはそれでも怒らない。
理由は、金持ちの息子が多いからだと、著者は言います。
つまり、自分が積極的にのし上がる必要は無く、安定しているだけで良いのです。
人脈は親からも引き継がれますので、出世を急がない限りはそのうちそれなりのポストに就ける
仕組みになっています。
◎彼らは何故怒らないのか(一流企業編)
民間企業に話を移しますが、基本的に一流企業に勤めるサラリーマンの属性も、
官僚のそれと大きくは変わりません。
ただ、昨今のグローバル化と業務効率化の影響によって、
長く密度の濃い業務になってきています。
要するに、短時間で結果を求められるようになった。
少なくとも、お気楽リーマンはもはや殆どいません。
民間企業の実態については、他の書評にも書いているので省略しますが、
ここでも言えるのは、決して給料に見合った仕事では無いということです。
少なくとも学歴エリートにとっては。
それでも、彼らも怒らない。
やっぱり金持ちの子供が多いから。
◎中流受験秀才の悲劇
①一番損をしているのは、中流受験秀才
これまでの説明のとおり、金持ちの子供は不満があっても特に心配は要りません。
でも、一番危機感を持たなければならないのは、中流で育った学歴エリート達です。
本当に怒らなくてはならないのは、彼らです。
彼らのアドバンテージは、もはや殆ど無いに等しいのですから。
僅かに残ったアドバンテージを、以下にピックアップします。
②こんな時代でも学歴で買えるもの
1.中間層にとどまれる
流石に、下流までは落ちる可能性は低いということですね。
一流の学歴を持っていれば、少なくとも「入り口」はまだまだあります。
2.少しだけ安定した雇用機会
これは、非正規雇用やフリーターに比べて、というレベルです。
今までさんざん国産正社員は守られて来ていますが、いつまでもそうとは限りません。
その証拠に、外国人採用は年々増え続けています。
今の新卒学生のライバルは、既に同世代の日本人だけではありません。
3.二者択一時の有利さ
例えば、こういうことです。
同じレベルだったとしたら、二流大卒と一流大卒のどちらを採用するか。
言わなくても分かるでしょう。
でも、飽くまで「まし」というレベルです。
積極的に選択しているわけではないので、積極的な理由が出来ればどうなるか保証されるものでは
ありません。
他にも、以下のような内容について、非常に深く突っ込んだ議論をしていますので、
ビジネス書のヘビーユーザーにも、読み応えのある満足いく内容であることを保証致します。
◎学歴社会の崩壊
◎新・学歴社会を構築せよ
如何でしょうか?
これを読んでも、まだ学歴を追い求めますか?
因に、私の属するカテゴリーは、「中流受験秀才」です。
この本を読んで、どれだけ当時危機感を抱いたか、察して頂けるかと思います。
この本は、2005年出版。
あれから5年。
私は今、会社に頼らずとも生きていける人材になるための努力を日々行っています。
その一環が、この書評だと思って読んで頂けますと、少し私という人間の本質に近づくのでは
ないかと思います。
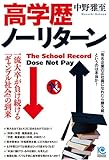
本日も最後までお読み頂き、
誠に有り難うございました!
【新ブログ】気軽に相談に乗れるITコンサルタント

【神保町ビジネス書評会】◎神保町ビジネス書評会
【神保町Facebook講習会】◎神保町Facebook講習会