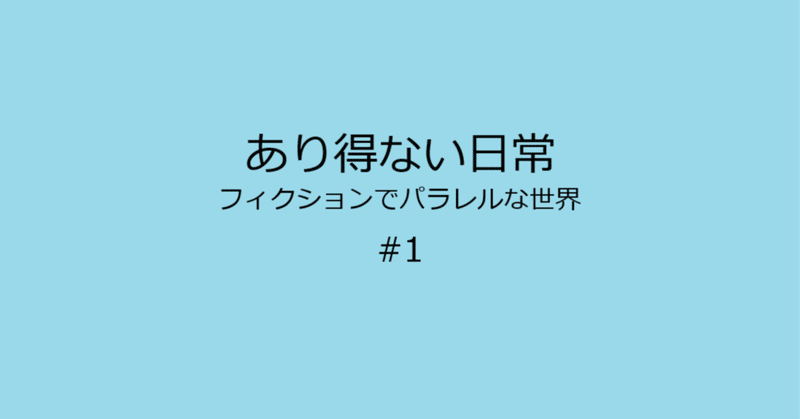この作品はフィクションです。架空の創作物語ですが、例えば銃にまつわるなどの極端な表現が含まれます。苦手な方はご注意ください。
1
学生を卒業して幾年月、もうすぐ年度替わりという事もあって年末とはまた違った慌ただしさを感じる。
田舎ならまだ少し違うのだろうか。
ラッシュ時は乗り遅れることをあまり心配する必要のない路線の駅近に住む身としては、寝に帰っているようなものだけとはいえ、便利なもので気に入っている。
休みの平日にはたまに足を延ばして、大きな駅の本屋に立ち寄るのが最近の楽しみになっている。
旅行になんて、思えばいつ行っただろうか。
男の独り身だから、時間を気にせずふらっと出かければいい。
そう思いつつも休日といえば午前中はほぼ寝て過ごしてしまう人間なので、そんな贅沢な時間を過ごしたいと妄想するのは、ある意味で自由を拘束されている勤務中くらいだ。
実際の独身男の休日なんてそんなもんだろう。
ちょっと歩けばスーパーはあるが、目の前のコンビニには敵わない。
ただでさえ貴重なプライベートタイム。
できるだけ有効に時間を活用したいものだ。
さて、明日は出勤か…。
いつの間にか消化してしまった、ひと時の解放された時間を惜しみつつ、固い寝床に入る。
2
同じ職場でも出勤時間は人によって異なる。僕の場合は来訪者の対応のためであり、窓口の受付時間に合わせた時間帯勤務なので恵まれている方だ。
ただ、土日祝日関係のない当番制なので、予定が立てづらいというのが難点ではある。あるが、独り身を極めている僕の場合はさほど困ってはいない。
あれ、急に視界がおかしいな。目にゴミでも入ったか。
さて、予約はと…。
今日は特に無いようだ。
ホッとため息をつく。
隣の部署の書類仕事くらいは手伝えるので、その仕事をこなしつつ来るか来ないかわからない来訪者を待つ。
3
入り口近くの部署には来訪者が多い。
理由は様々だが、そのため多くの人員が配置されている。
僕はというと入口から一番遠い、奥のトイレすぐ近くのこじんまりと設けられた受付スペースに詰めている。
あきらかに忙しさが違うからと言って、特別妬まれたりすることはない。
いい職場といえばいい職場だろう。
「どうかな。今日は予約入ってる?」
ふと、上司から尋ねられる。
いや、今日は無いようですねと答える。
「そうか」
予約は余程のことが無い限り入ることはない。
ないが、いつだったか、夜中にどうしてもと押し掛けてきた人はいるらしい。気持ちはわかるが規則は規則なので致し方ない。
それを担当者から聞いたのは翌日で、身構えていたが結局姿を現すことはなかった。
後日何人か訪れたものの、そのうちの誰がその人なのかはわかることは終ぞなかった。
すこし感じる花の香、時たま吹く北風に鼻をすすりながら、その日は家路につく。
花粉症ではないのが幸いだ。
そして、今日も平穏に終わった。
慣れて来てはいるが、不器用さも相まって慣れることはないだろうなと、しかしまあ、しっかりしなければと、ポケットから手のひらサイズに折りたたまれた少し重いプラスチックの塊を取り出す。
パカッと開くと緑色に輝くスクリーンの上に、黒のドット文字でメールの受信通知が2件とあった。
1件はこの携帯電話を買った店からの機種変更がお得だというお知らせメール。もう1件は実家の母親から連休の予定を尋ねる内容だった。
父も場所は違うが同じ職業についているので、大体の終業のタイミングはわかるらしい。
父は先日、永年勤続表彰を受けたばかりだ。
同じ職に就いてわかるが、よく続けられたものだと心から尊敬する。
好きなのか、性に合っているのか、自分という子供が生まれたからなのかは知らないが、父からそういう話を何ひとつ聞いたことはない。
何時かその胸の内を語ってくれるのだろうか。
父を追いかけるように同じ職に就き、僕が自分の意思ではなく、ただ配属されただけと知っているとはいえ、実際どう思っているのかも。
4
もうすぐ年度替わり、新卒の社員は早ければもう上京している頃だ。
引っ越し業者もさぞ大変だろう。
スカート丈がやたら短い茶髪の高校生もいない、反対側のホームの様子が立ち客の合間から見える窓より窺える。
普段より軽そうな電車がけたたましいブレーキの音とともに目の前に滑り込んでくると、もう春休みかとつぶやく。
座席に座れたことなど一度もないが、6駅程度だから大したことはない。
座ることができるのは始発の特権とはいえ、その分車内で時間を過ごさなければならないから大変だ。
事故が多かった頃はもっと大変だったらしい。都内に住んでみて驚いたが、田舎だと2時間は停まることも珍しくない。
対応は早いとはいえ、それはそれで複雑である。
しかし長い事、車内で過ごす人にとっては迷惑以外の何物でもない。
乗り換え、乗り継ぎなどあろうものなら、いくら慣れていても大変だろう。
声か文字を送り合うしかない携帯電話では、どこにぶつけようもない怒りと、手持無沙汰と、この後の移動経路をどうしたもんかという不安をスッキリ解消させるにはとても足りない。
バッテリーも尽きたら最後、近くの公衆電話から連絡を取るほかない。
となればもう運が悪かったと割り切るしかなく、せめて大きな事故に巻き込まれず、命があるだけでもよかったと感謝するしかないだろう。
5
数年前に政府が打ち出した法案を怒号が飛び交う中ではあったが、国会が通したことにより驚くほど混乱が減った。
渦中に行われた国政選挙でも与党に大きな支持が集まり、争点として掲げた選挙の結果でもあったため、その後は特に滞ることもなく仕組みとして整ったのである。
当時は号外が出たくらいだ。
今思えば、反対をしていた彼らは何を訴えていたのかと少し考えてみる。
まずは制度の悪用を危惧しての事だろう。
確かに悪用されたらたまったものではない。
今の慎重な手続きで行うからこそ悪用を防ぐことができる。
そうでなければ僕は間違いなく辞める。父も反対しないはずで、むしろ賛成してくれる自信すらあるくらいだ。
しかし、どうやら政府が意図したとおりに制度は運用されているらしい。
それだけがせめてもの救いだろう。
6
いつものように受付の椅子に腰をかける。もうあと一日やれば片付くであろう年度末で提出すべき書類を進める。
1時間ほど経ったろうか。
何やら視線を感じたので顔をあげると、1人の女性が立っていた。
歳は五十台くらいだろうか。
お手洗いは奥ですよ?そう案内する。
すると、いやそうじゃなくて、、、。とか細く答えが返ってきた。
あっと察し、窓口に「離席中につき他の職員にお声掛けください」と書かれた札を下げ、女性を奥の予備の小さな会議室へ案内する。
おかけくださいとパイプ椅子に手をかける女性を横目に対面に座る。
いずれにせよ決まりですので、まずは受付票にご住所とお名前とご家族など該当する項目を埋めて頂いてよろしいですかと促す。
すると女性は言いづらそうに「元の旦那もでしょうか」と聞く。
連絡先なので差し支えがあるようでしたら書かなくて結構ですよと答える。
では義理宅への電話番号を書いておきますとつぶやいた。
不思議に思ったが、規則でそこは尊重しなければならないので、特に言及することは控えた。
7
女性に規則通り説明を始める。
まず、この会議室からの様子は終始ビデオに録画されている事。会話も録音がなされている事。
そのビデオは、のちに裁判所に証拠として提出されること。
その最中にもう一人、女性同僚が入室してきた。
あ、今説明しているところです。とそっと一言。
同僚は静かにうなずくと女性の隣に座った。
では、こちらに自筆の署名と拇印をお願いします。そう伝えると、同僚の目を見て、ではここからはこちらの職員が案内しますので、と伝えて席を立つ。
また、あの窓口の席に帰るわけだ。
男性であれば自分がそのまま案内することもあるが、女性の場合は女性の職員が案内する決まりになっている。
そして、出来るだけ複数の職員で対応するようにしなければならない。
これは、来訪者だけではなく、自分たちの身を守るためでもある。
ただ、わかっていても慣れないな。そのまま席にまっすぐ戻る気にもなれず途中で自動販売機に寄り、ブラックコーヒーを胃に流し込んだ。
8
すこし前、僕がさいごまで案内した話をしよう。
あの小さな会議室から、地下へ続く順路をたどる。その間は若干画質は悪いがちゃんと監視カメラで録画されている。
職員は決して、案内する人に手を触れてはいけない。あくまで促すだけだ。本人が、帰ると言えば当然帰宅することができる。
ここまで来た人はもうほどんど引き返すことはない。
勢いで来る人もいるが、たいていは会議室で説明しているときに正気に戻るか、恐ろしくなったか、ひたすら頭を下げて帰るからだ。
地下室は空間こそ広いが、ずらりとボックスが並ぶ。
1つ1つのボックスの大きさは半畳ほど、人間一人が入れるくらいの広さで、高さ2メートルほどの特殊な加工がなされた、まるで電話ボックスのような箱が壁際に4台と、間の空間を挟んでまた壁際に4台と、設置されている。
地下は特有の湿度があるものだが、どうもそれだけではないというのが誰にでもわかるだろう。
9
もちろんすべて録画されるようになっている。
制度上、2台の録画装置で記録をとることになっていて、一人が守衛室の監視担当に内線で確認を取ると、詳しい話を始める。
ボックスの中には、ワイヤーでつながれた拳銃がぽつんと置いてあって、弾が1発だけ入っている。
安全装置の外し方は、さっきの会議室で説明をしてある。
後は銃口を顎の下に当てるように両手で持ち、引き金を引くだけだ。
設備の貸し出し時間は30分。
中の様子は防弾のガラス張りでよくわかるし、監視カメラもある。
場合によっては上の階から数人の機動隊員を呼ぶ。乾いた音がした後に火薬が燃えたような香りがすると、刑事と鑑識も呼ぶ。
そう、ここは警察署の地下だ。
10
20世紀後半、自ら命を絶つ人間の増加が問題となった。
なかでも、鉄道で自らを処す者が後を絶たず、度々公共交通機関としての機能がマヒすることに批判の声が高まっていったのである。
また、体の自由が効かず高齢で身寄りもないという者からの相談も相次いだため、安楽死に対する議論が一気に浮上した。
日本国家としては、憲法で保障されている基本的人権と矛盾することから、安楽死を認めるわけにはいかない。
しかし、鉄道などの公共交通機関だけでなく、賃貸住宅などの不動産、自殺か他殺かわからない状況での発見など、一般社会への影響も大きく、一個人の権利が国民全体の権利を侵害しているのではないかという主張もあり、政府はやむなく国民に信を問う形である法案を出したのである。
それは、現在の警察署でしかるべき整備をした設備内の限定された場所内でのみ、拳銃とその銃弾1発を貸与する。そしてこの貸し出しを受ける権利を国民個人に認めることにしたのである。
ただし、人間に対してこれら貸与物を使用してはならないとした。
注意すべきは、あくまで警察は貸し出すだけであって、貸し出すものの説明をしただけに過ぎない。
どう使うかは個人に委ねたのである。
結果、貸与された人物が自身に対して使用した場合は、当然、現行の法律が適用される仕組みだ。
現場は鑑識によって調べられ、録画物もすべて証拠として検察や裁判所へ提出される。
管理された中ではあるが、事件になるわけだ。
設備も当然汚れるから、そのことも責任の一端として追加される。
ただ、本人はもうこの世にはいない。
そこで、設備自体も貸し出しにすることで、この複雑な制度はなんとか運用を続けている。
どういう結末を遂げるかは人それぞれで、設備に入るや否やすぐに事を遂げる者もいれば、さんざんむせび泣きながら時間ギリギリになっていく者もいる。
それでも時間切れともなれば、マイクとスピーカーを使って声をかける。
「続けますか?」と。
出来れば、人生の方を続けてもらいたいものだ。
コーヒーの苦さが余計に沁みる気がした。
僕は受付へ戻る。

この作品は2024年1月27日にnote.comに原作者として掲載した作品です。
この物語はフィクションです。実際の人物や団体とは一切関係がありません。架空の創作物語です。