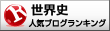この記事の内容は、様々な資料をもとに書かれています。
内容の中には一部ないしは全体を通して、資料に基づく偏見や誤りがある可能性があります。また、筆者自身による偏見や誤りがある可能性も当然否定できません。
できる限り公平かつ事実に基づいて記事を書きたいと考えていますが、この点を踏まえていただけましたら幸いです。
今回のテーマはユダヤ教の宗派についてです。
はじめに
日本以外の主要な先進国で、ユダヤ人が社会における重要な地位を占めているというのは知られている話ですが、私たちは、このユダヤ人社会というものについて、あまり注意を払ってこなかった部分があります。
ユダヤ人が何を考え、何を人生の目的として生きているのでしょうか。
もし私たちが何も知らずにいたら、世界中の人はきっと私たちとそれほど変わらない考えで、ちょっと悪い人が多いコミュニティや国、またはいい人が多いコミュニティや国があるくらいの感覚で、あまり深くは考えないものです。
そもそも、知らなければ考えようもありません。ここではユダヤ人が信じるユダヤ教について少し触れていきたいと思います。
ユダヤ教についての一般的なイメージ
一般的な日本人にとってみると、ユダヤ教というのはキリスト教の元となった宗教という印象からユダヤ教というものを捉えるのではないかと思います。
ですから、ユダヤ教徒というのは旧約聖書を信じている人達というざっくりとしたイメージが、私たちの中心にあるのだろうと思います。
振り返ってみて、外国人が日本人をどのようにとらえているのかを見てみますと、外国人の日本人のイメージは、寿司やてんぷらといった食べ物だったり、芸者や富士山といった、外国人にとってアイコンとなっているもの、また最近では、日本のテレビ番組やアニメといったものから日本をイメージする人も多いでしょう。
すべての外国人がこのように考えているわけではありませんが、入り口としてこういった単純なイメージを持つことが多いわけです。
これは恐らくユダヤ人やユダヤ教についてのイメージも同じことでしょう。外国人が日本を寿司や芸者やアニメのイメージとして捉えるように、最も単純な入口として、ユダヤは旧約聖書くらいなイメージを持つということです。
そしてすべての日本人が実際はそう思っているのではなく、ユダヤ教に詳しい人は、このようなイメージに対して、何もユダヤ教について知らない人と感じるかもしれません。
ユダヤ教というものを捉えるためには、ある程度情報を集める必要があります。その入口となるような情報についてここでは触れていくことにしましょう。
旧約聖書・タナハ
ユダヤ人は旧約聖書を信じている人だというざっくりとした印象は、世界の大多数の人がキリスト教徒であり彼らが新約聖書を信じているという知識が前提となって、このように考えている部分があります。
ユダヤ人にとって新約聖書は旧約聖書とは異なり、信仰の対象とはなりません。従って自らが信じる聖書に対して新旧の旧という表現をするわけもなく、当然、別の呼び方がされています。
ユダヤ人にとって旧約聖書はタナハと呼ばれています。
タナハの語源は、聖書を三つの部分に分けたそれぞれの頭文字をとったものです。
それぞれ、トーラー、ネイビーム、クトビームなどと呼び、トーラーはモーセ五書、ネイビームは預言者、クトビームは諸書を指します。
トーラーはしばしば、日ユ同祖論などで、「虎の巻」の虎はこのトーラーではないかと言われています。詳しいことは解りませんが、日ユ同祖論ではない元々の解釈は『六韜』の虎韜が「虎の巻」の語源ではないかとされているようです。
ではユダヤ人というのはタナハを信じている人たちなのかといえば、一概にそれだけとは言えないでしょう。
日本人で仏教を信じているとしても、仏陀の教えを信じていると単純にとらえることはできません。必ずしも仏教とユダヤ教の歴史は違いますので単純な比較はできませんが、日本の仏教も平安時代に伝来した密教や、鎌倉仏教など、宗派が様々あります。
これと同じように、ユダヤ教の中にも様々な宗派があり、もちろんそれと同じように、様々な解釈や信仰のスタイルがある見るのが妥当でしょう。
決して彼らの信仰のスタイルは一様ではないと考えることが重要だと思います。
ファリサイ派
最も古いモーセ五書についての議論は後に譲るとして古代イスラエルの時代に視点を持っていきましょう。
この時代はユダヤ教は神殿祭儀の宗教だったと言われています。ユダヤ人はエルサレム神殿での祭儀を行うのが重要な役割を担っていましたが、この時代イスラエルは、ローマの属州でしたが、次第にローマの総督とユダヤ人の間で激しい対立が生まれました。
ユダヤ人の暴動や反乱は、激しさを増し、この時の皇帝ネロは軍団を派遣して、反乱の鎮圧へ向かわせました。
この結果、エルサレムは陥落し、神殿は焼き払われ、ユダヤ人は神殿祭儀というスタイルを失うことになります。
この結果、ユダヤ教の主流となったのが、タナハの解釈を行い、人々を導くラビたちによるスタイルでした。このラビたちによるユダヤ教をそのまま、ラビ的ユダヤ教といい、新約聖書などでもファリサイ派やパリサイ派、パリサイ人とし呼ばれるようになり、現在のユダヤ教に大きな影響を与えました。
現在のユダヤ教においてラビの存在は絶大で、現代ユダヤ教をほぼすべてがこのファリサイ派に属しているとも言われています。
現在の主な宗派
現在のユダヤ教における主な宗派の中で、押さえておく必要があるのが、正統派と改革派ではないかと思います。大きく分けるとこのような分類がされることが多いと思います。
ただし、ユダヤ人がこの正統派か改革派の二つの派閥に分類できるというものでも、おそらくはなく、日本と同じように、人それぞれに様々な傾向があると考えるべきでしょう。
正統派も様々な派閥があると思いますが、超正統派のハレーディーやその中でもより強固なナートーレー・カルタのような組織もあります。
ナートーレー・カルタは徹底した反シオニズム、反イスラエルのユダヤ人組織です。
一方で、改革派は現在のシオニズムに代表されるような立場であり、シャブタイ・ツヴィという自称救世主のシャブタイ派またはサバタイ派の影響を強く受けていると言われています。
改革派はトーラーの註解書のゾーハル書、いわゆるユダヤ教神秘主義のカバラの影響を強く受けていると言われています。現在のアメリカのディープステートがカバールと呼ばれるのは、この改革派ユダヤ人勢力のことを指しています。
トランプの娘婿であるジャレッド・クシュナーは正統派のユダヤ人に属し、ナートーレー・カルタとは異なり徹底した反シオニズム、反イスラエルではありませんが、カバールとは必ずしも同じ立場ではないと考えられています。
まとめ
現在のトランプ政権を考える上で、クシュナーの位置づけとその解釈によって、この政権の捉え方が変わってくると思います。
わたしも含めて一般的な日本人の立場では、厳密な宗派の違いや考えの違いなどは肌で感じることは難しいと思われますが、ただしある程度現在の政治的な現象を考える上で、ユダヤ教が具体的にどういった考えの広がりを見せているのかを調べてみる、そしてそれを分析してみることが重要ではないかと思われます。
さいごの一言
最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご感想などありましたら、気軽にコメントください。
お手数ですが、もしよろしければバナーのクリックお願いいたします。