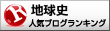今回のテーマは地球の歴史です。ここではあまり細かな話をせずに、大まかな地球の歴史の流れなどについて触れていきたいと思います。
私個人の考えですが、これらの内容は政治や経済、思想などの話をする上で外せない問題だと思っています。普通は誰もそんなことは思わないとは思っています。
それでは見ていきましょう。
地質年代
私たちが生きているこの地上、地球が誕生しておよそ46億年が経過していると言われています。ここでは地球が誕生してからの大まかな流れについて説明したいと思います。
46億年の物語(自転速度の変化と大気中の成分、大気の平均温度も記載)
46億年という歳月の数字は非常に長いようにも思えますし、場合によっては非常に短いようにも感じられるかもしれません。
地球が誕生してから人類が誕生するまで、数千年前に作られた一部の神話の物語のように短い日数だったわけではありません。また数学や経済学の単位などに用いられる兆や京といった途方もない歳月でもありません(46億年も十分に途方もありませんが)。
この46億年という歳月ですが、現在の地質学では、大きく分類して、四つの区分に分けられています。この区分を累代といいます。また地質学から時代を区分した年代のことを地質年代といいます。

地質年代の区分表(地質学会は視覚的な効果から年代のカラーコードを指定している)
地球の誕生から40億年前までの期間を冥王代といいます。
次の時代が40億年前から25億年前までで、これを太古代といいます。この時代は少し前までは始生代と呼ばれていましたが、最近太古代という呼び方が一般化されました。
次に25億年前から5億4100万年前までの時代を原生代といいます。年代が古い時代は年代を大まかに区切りますが、時代が下るに従って年代の区分も細かくなってきます。
最後の時代、5億4100万年前から現代までの時代を顕生代といいます。顕生代は「生物が顕れる」という表記に見られるように、生物が肉眼で確認できる大きさになった時代と言えます。
地質年代のタイムスケール(赤が冥王代、赤紫が太古代、紫が原生代、それ以降が顕生代)
海外ではよく541Maという表記が見られますが、これは5億4100万年前を意味します。Maは百万年を単位としています。それ以外にもMyaという単位も用いられますが、意味は同じです。
先カンブリア時代
四つの累代の中で最も事細かくよく分かってきている時代が顕生代ですが、この顕生代以前の3つの累代をひとまとめに先カンブリア時代と呼ばれます。
累代をさらに区分した年代を代といい、その代をさらに区分した年代を紀といいます。顕生代の最初の紀がカンブリア紀という時代であり、それより以前の時代という意味で先カンブリア紀と呼ばれることになりました。
原始の太陽系はガスや塵で構成されていました。このガスや塵が互いの寄り集まり、次第に直径数kmの多数の微惑星が形成されました。この微惑星がさらに衝突と合体を繰り返し、惑星の材料となる惑星胚と呼ばれる惑星が形成されていきました。
地球の誕生までのストーリー
数十個の惑星胚がさらに衝突を繰り返し、地球の軌道上には二つの惑星が残りました。一つは原始地球と呼ばれる地球の母体であり、もう一つがテイアと名付けられた仮説上の惑星です。
この二つの惑星が衝突することによって、現在の地球と月が形成されたという仮説をジャイアント・インパクト説といいます。これには異論もありますが、現在広く支持されている仮説でもあります。

NASAが作成したジャイアント・インパクトの想像図
この地球誕生から40億年前までの期間が冥王代ですが、累代を区分する40億年前を前後して地球上に生命が誕生したといわれています。生命誕生の年代には諸説ありますが、この頃に原始的な細菌が光合成をおこなった痕跡がいくつかの地域で発見されています。
太古代は細菌や古細菌が誕生し、活動していた時代です。この時代の地球の大気には酸素はほとんどなく、窒素と二酸化炭素で構成されていました。原核生物による光合成によって形成された酸素は海洋中の鉄イオンと反応して海底に蓄積し、縞状鉄鉱鉱床を形成しました。
アメリカやオーストラリアをはじめ世界各地に大規模な鉱床があります。この鉱床は19億年前以前に堆積したもので、それ以後は生成されていません。
原生代には、原始的な真核生物が誕生しました。真核生物は、細菌や古細菌などの原核生物が別の原核生物の細胞内に取り込まれることで誕生したとされています。このような説を細胞内共生説といいます。
細胞内共生
生物は、細菌と古細菌、そして真核生物という三つの分類、ドメインによって区分されています。原生代の後期には真核生物が多細胞生物となりました。この時代の末期には2度も地球全土が氷で覆われたとされています。この仮説をスノーボールアース説と言います。
スノーボールアース
顕生代
顕生代は3つの区分でさらに分けられます。古いものから順に、古生代、中生代、新生代といいます。
顕生代の大陸の移り変わり
この3つの区分の境界は顕生代最大の生物の絶滅があった時期を境に分けれらます。
初めの境界を古生代最後のペルム紀と中生代最初の三畳紀の頭文字をとってP-T境界といいます。この大絶滅は古生物学上最大の大量絶滅であったことで知られています。
次に大きかった大量絶滅が、中生代最後の白亜紀と新生代最初の古第三紀の間に起こりました。これもそれぞれの頭文字をとってK-Pg境界といいます。恐竜が絶滅したことで有名です。
この二つの絶滅の原因はおおよそ定説化しており、ペルム紀末期のP-T境界はシベリアにあるシベリア・トラップが原因とされており、白亜紀末期のK-Pg境界はメキシコのユカタン半島付近で衝突した隕石が原因とされています。
シベリア・トラップには過去6億年の歴史の中で最大の火山噴火が原因とされています。巨大なプルームが原因ではないかという説が有力ですが、最近では隕石が原因ではないかという説もでているようです。
生物の進化という視点で見ると顕生代の最初の時代カンブリア紀にはカンブリア爆発という生物の多様化が爆発的に起こった時代でした。このカンブリア紀を境にして弱肉強食の生物の生存競争が爆発的に進んだともいえるでしょう。
カンブリア爆発
カンブリア紀には生物は感覚器官を発達させました。この時代に感覚器官の中で最も複雑な構造をもち、ダーウィンをしてその進化の過程を全く説明できないと言わしめた、眼が誕生した時代でもあります。
チャールズ・ダーウィン(1809 - 1882)
世界との対話
地球がどのような変遷を辿ってきたのか、また地球上の生命がどのような進化を辿ってきたのか、科学の進歩によって見えてきたところもありますし、いまだによくわからないこともあります。
また科学的に常識だと思っていることも、今後も引き続き幾度となく覆るに違いありません。
私は地球の歴史と生命の歴史の研究が、一見かかわりのない社会の問題に様々な言葉を投げかけてくれると思っています。社会がどのようにあるべきなのかを考える上で非常に重大な役割を果たすだろうと信じています。
私の個人的な意見ですが、現代社会の倫理観や価値観は、多くの人々が感じているように、小さな社会のなかで想像された小さな世界観の中に規定されている部分があると思います。
なぜ、小さな世界観から生まれた法律や道徳に私たちが縛られて生きていかなければならないのだろうと感じることがあるかもしれません。そしてその世界観に従わなければならないと、多くの現代人は嫌々ながら諦めてしたがっているのかもしれません。もしかすると、中にはそうではない人もいるでしょう。きっとそれに従うことによって利益があるからでしょう。
人の身体も、精神も、感情も、また社会システムも、膨大な歳月を費やして形成されてきました。そして、それは世界中で広く信じられてきた神話の世界での物語よりも遥かに長い歳月をかけて形成されたものでした。
私たちは、私たちが私たちについて論じあうほどには単純な存在ではありません。政治家や宗教家、財界人や教育者が私たちが何者なのかを語るその内容は、必ずしも私たちの本質を表現するものではないのかもしれません。
私は、そういった言論よりもずっと、私にはそれを完全に読み解くことはできませんが、空に輝く太陽や、道に転がっている石や、木々にとまっている野鳥が語り掛けてくるものにこそ、意味を追い求めます。
こういった観点からも、今後も地球や生命の歴史について繰り返し記事に挙げていきたいと思っています。
こういうことを言うと偏屈な人間だと思われるかもしれませんが、ある意味で、地球の歴史や生命の歴史の科学的研究による知識は現代版の創世記と言えるかもしれません。
最後に
最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご感想などありましたら、気軽にコメントください。
お手数ですが、もしよろしければバナーのクリックお願いいたします。