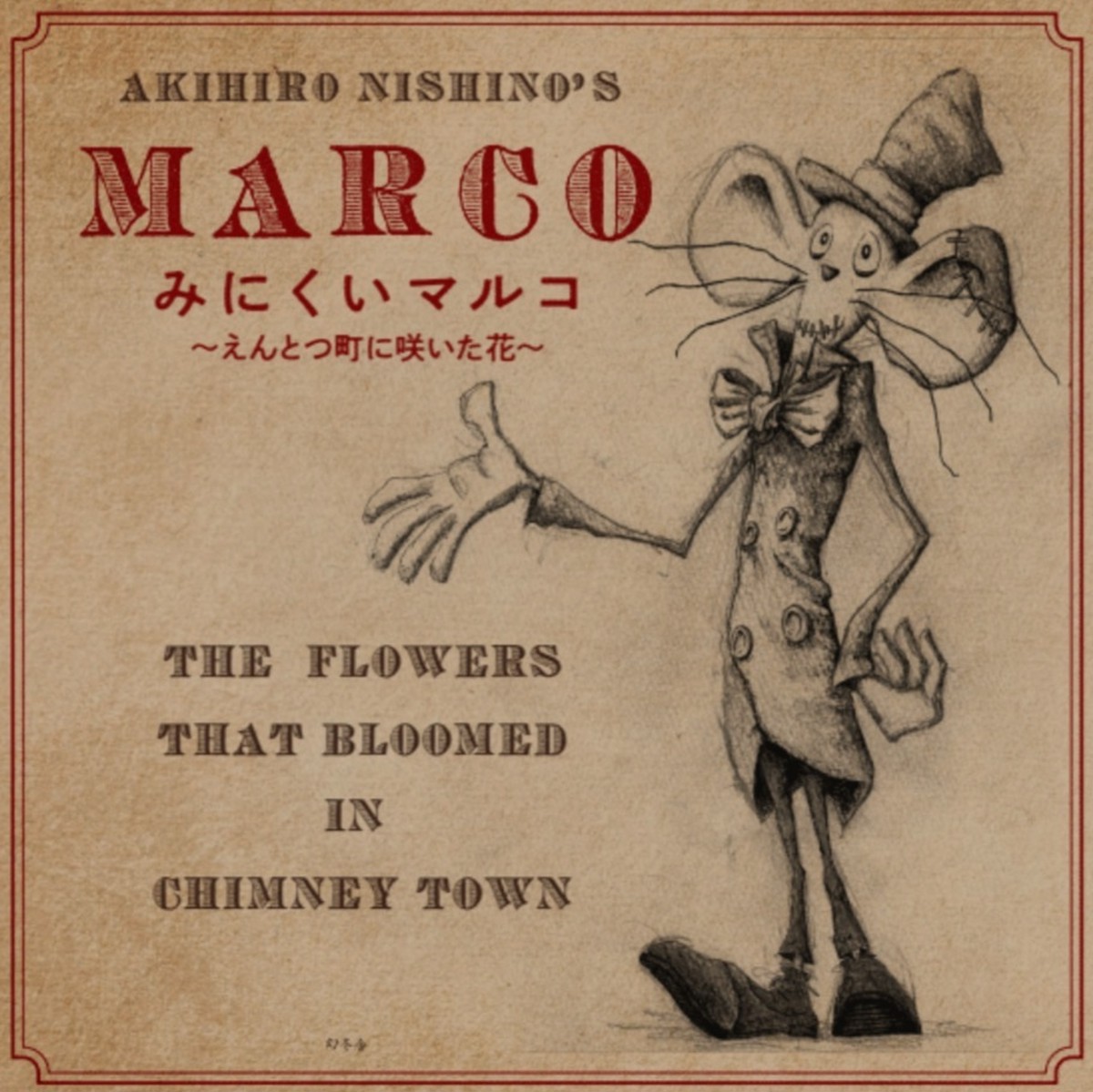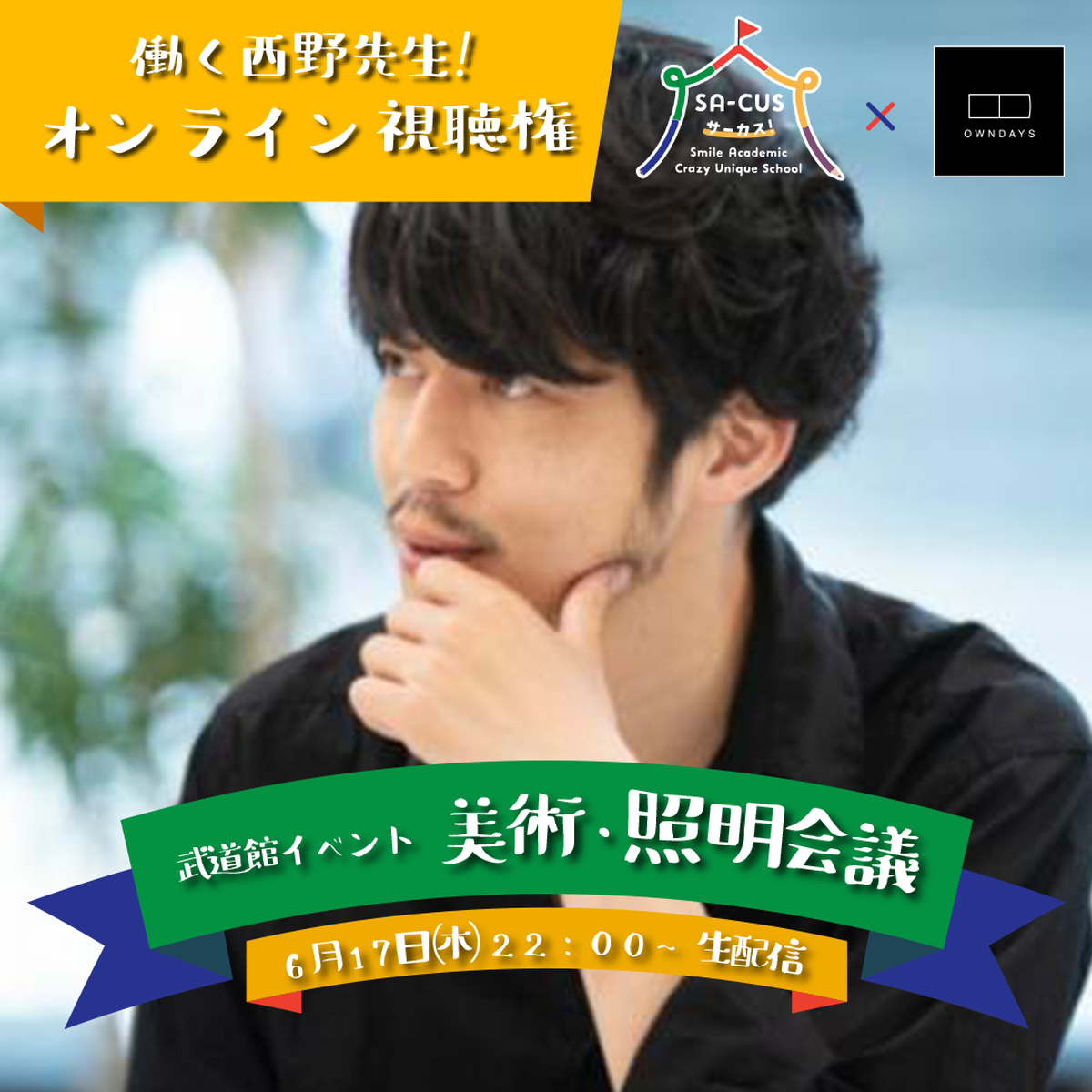今日は『「生むこと」と「育てること」は、どっちが大事?』というテーマでお話ししたいと思います。
本題に入る前に、お知らせをさせてください。
僕の絵本最新作『みにくいマルコ 〜えんとつ町に咲いた花〜』が発売となりました。
今回の物語は『映画 えんとつ町のプペル』から3年後の「えんとつ町」が舞台です。
時代が大きく変わって、職を失った主人公のマルコが、次の仕事場に選んだのが見世物小屋なのですが、そこで、ある女性と出会い、これがもう、大変なことになっちゃいます。
恋物語がベースになっていますが、今の僕の気持ちを反映させていて、ラストシーンは僕の本音でもあります。
その辺りの事情も踏まえて読んでいただけると嬉しいです。
是非、手にとって読んでみてください。
そして、こちらの作品はサイン本のご予約も承っておりまして、お求めの方は『キンコン西野のサイン本屋さん』で検索してみてください。
よろしくお願いします。
そして、お知らせがもう一つあります。
11月8日に日本武道館で「サーカス!」という学校イベントがあります。
イベントの内容に関しては、またお話しさせていただくとして、なんか、このイベントができるまでのドタバタも共有していきたいなぁと思って、6月17日22時から『【働く西野先生!】11月の武道館イベントの美術会議』をオンライン配信させていただくことになりました。
タイトルそのまま、武道館の舞台セットと照明を作る美術会議の模様を生配信するというものです。
武道館のセットが作られる現場を見ることってなかなかないだろうし、なにより、僕らの普段のガチンコ会議の様子をお楽しみオタだけたらな、と。
参考になるかどうか分かりませんが、「ウチの会社の会議の雰囲気と全然違うじゃ〜ん」となると思います(笑)
参加ご希望される方は、「11月の武道館イベントの美術会議」で検索してみてください。
チケットは400円です。
6月17日の22時からですが、1週間ほどアーカイブも残りますので、時間の都合が合わない方も是非、ご参加ください。
よろしくお願いいたします。
そんな、こんなで本題です。
今日は『「生むこと」と「育てること」は、どっちが大事?』というお話しをしたいと思います。
ちなみに「1対5の法則」ってご存知ですか?
「イチゴの法則」と言ったりもするのですが、これは、どこぞのコンサル会社のデジレクターが提唱した経営戦略における法則で、
ザックリと説明すると「新規顧客に商品やサービスを販売するのにかかるコストは、既存顧客に商品やサービスを販売する場合にかかるコストの5倍だよ」というお話です。
新規顧客を獲得することも、既存顧客を維持することもどっちも大切なのですが、そこにかかるコストに5倍もの違いがあるんです。
どの計算式で「5倍」という数字が出たのかは知りませんが、でも、言わんとしていることは分かりますよね?
たとえば、あなたがお店を出したとして、お店から半径100mに住んでいる人達にチラシを配って集客をしたとする。
それで、お客さんが来てくれたけど、リピーターにはならない。
そうすると、今度はお店から半径200mに住んでいる人達にチラシを配って集客をしなきゃいかない。
そして、なんとかお客さんが来てくれたけど、リピーターにはならない。
というわけで、今度はお店から半径300mの…となってきて、要するに集客がどんどんしんどくなってくる。
だけど、お店から半径100mに住んでいる人達が繰り返し来てくれたら、そんな集客がしなくてもいいわけじゃないですか?
新規顧客を獲得し続けることよりも、既存顧客を維持することにコストを割いた方が、よっぽど効率が良いんです。
これと、似たような話なのですが…
2019年だったか、2020年だったか忘れたので、テキトーに調べていただきたいのですが、ビジネス書の年間売り上げランキングTOP10の、ほとんどが、その年に出版された新刊ではなくて、過去に出版された定番本だったんです。
5年後がどうなっているかは分かりませんが、なんとなく今の流れとして、アタリかどうか分からない新刊よりも、アタリが約束されている定番本の方が買われる傾向にあるんですね。
つまり、本を出す側からすると「売る」ということを目的にするのであれば、新刊を出して、そこに広告コストをかけるよりも、定番本に広告コストをかけた方がコスパが良いんです。
さっきの話に戻りますが、だからと言って「新刊なんて要らない」という話をしているわけじゃないですよ。
広告のコストパフォーマンスの話をしています。
広告のコスパを軸に考えたら、定番本を持っているのであれば、定番本を宣伝した方がいいんですよ。
ご存知の方も多いとは思いますが、絵本業界なんかは、もう完全にこの世界観で、年間ベストセラーのほとんどが、ロングセラー作品です。
いまだに『はらぺこあおむし』だし、『ぐりとぐら』だし…ここ、誰も話題にしていないのですが、恐ろしいことに、2020年に売り上げ700万部を突破した『いないいないばあ』が世に出たのは50年以上前で、半世紀かけてコツコツと700万部(つまり、700万部÷50年=年間14万部)をコツコツと売ってきたのかと思いきや、違うんです。
2020年に700万部を突破した『いないいないばあ』が、600万部を突破したのは2016年なんです。
この4年で100万部。つまり、売れるペースが上がってるんです。
ご存知のとおり、日本の子供の数はメチャクチャ減っていっているのに、『いないいないあばあ』は売り上げペースを伸ばしているんです。
それぐらい「定番」は強いという話です。
当たり前の話ですが、国民にお金の余裕が無くなれば無くなるほど、一か八かの冒険をするデメリットが大きくなってしまうから、安パイたる「定番作品(定番商品)」が強くなるんです。
きっと、このラジオをお聴きのあなたも、作品か商品かサービスをお持ちだと思うのですが、「定番を作る」ということがメチャクチャ重要で、「定番を宣伝する」ということがメチャクチャ重要なんです。
その際、邪魔になってくるのは「新作を生み出さないといけない」という固定観念、もしくは「いつまで、その商品にしがみついとんねん」という外野の声です。
「定番」を手に入れたのであれば、そんなものは無視してください。
「赤福餅」に何年しがみついていると思ってるんですか?
あれ、ずっと売れてますよ。
僕、昔、名古屋から大阪に帰る時に、名古屋駅のホームでお土産で「赤福餅」を買ったら、落ちたった新大阪駅のホームでも「赤福餅」を売ってましたよ。
あいつ、めちゃくちゃ「お土産ヅラ」してますけど、どこにでもいますよ。
そして今日も売れている。
50年前に出た絵本『いないいないあばあ』は今、毎年20万部売れてるんですよ。
2016年〜2020年が急激に盛り上がっただけかもしれませんが、それでも、毎年20万部近くはコンスタントに売っているわけで…そんな作家、どこの世界にいるんですか?
だから、いいんですよ。
『赤福餅』という定番商品を持ったら、胸を張って、『赤福餅』を宣伝した方がいいし、
『いないいないばあ』という定番商品を持ったら、胸を張って、『いないいないばあ』を宣伝した方がいい。
新作というのは、定番を生み出すまでの旅だと思っておいた方がいいと思います。
「生むことも大事だけど、育てることもすっごく大事だよ」というお話しでございました。
▼西野亮廣の最新のエンタメビジネスに関する記事(1記事=2000~3000文字)が毎朝読めるのはオンラインサロン(ほぼメルマガ)はコチラ↓
▼Instagram版はコチラ↓