『鎌倉殿の13人』~後追いじゃない先走りコラム その106
第26回 悲しむ前に
今回は、鎌倉北条氏の分派繁栄について。あえて「鎌倉北条氏」と書いたのは、戦国時代に北条早雲から始まる小田原北条氏(後北条(ごほうじょう)とも言う)と区別するため。以後、北条氏とする。
頼朝(大泉洋)が鎌倉に幕府を開くまでの北条氏は、伊豆国田方郡北条(現、伊豆の国市)を本拠とする小豪族だった。時政以前の北条氏に関しては、さまざまな説があり、判然としない。
『鏡』1180(治承四)年4月27日条に「(時政は)上総介平直方の五代の孫で、伊豆国の豪傑」と記されているが、これは直方の娘を頼朝の先祖頼義が娶り、義家が生まれたことに託けて、北条と源氏ははるか昔から固い縁で結ばれていることを周知させるため、と言う『鏡』編纂者の強い意図を感じさせるものだ。※以降、系図参照。
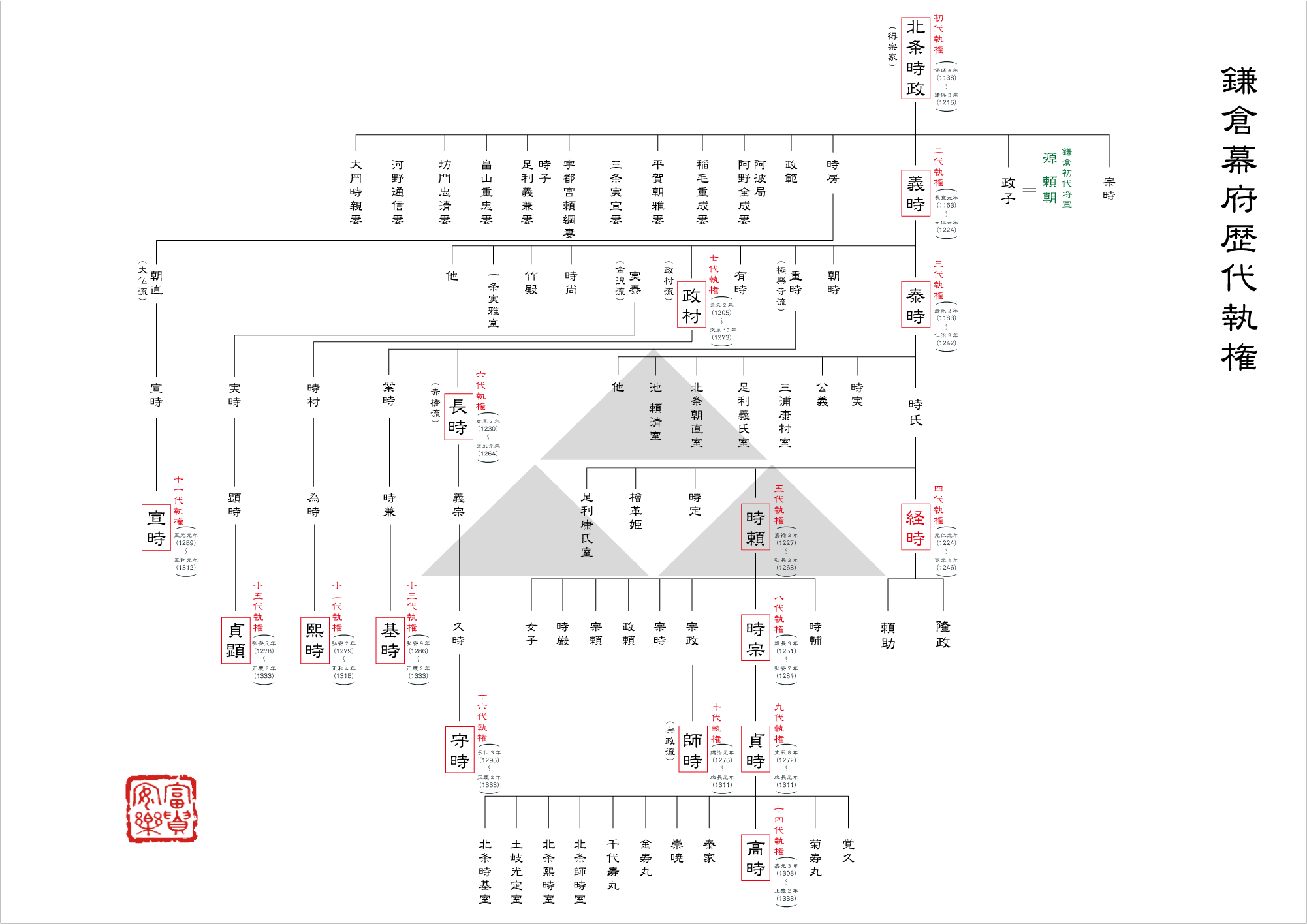
時政の時代、北条氏繁栄の端緒となったのは、周知の通り、娘政子(小池栄子)が頼朝の正妻となったことだ。時政は鎌倉殿の舅の立場を利用し、自らが幕政の中心にいただけでなく、娘たちを有力者に嫁がせて権力基盤を強化していく。時政自信は、ライバルの御家人たちを蹴落としていくが、後妻牧の方にそそのかされ、頼朝の猶子となっていた平賀朝雅(ひらがともまさ)を将軍に就けようとして失敗。失脚して伊豆に隠棲する(1205年)。しかし、頼朝からの信任の厚かった息子義時がその跡を受け、北条氏を確固たる地位に押し上げていく。この過程がこれからの『鎌倉殿の13人』の最も大きなテーマだ。

義時の子供の時代になると、北条氏は分派していく。つまり、本家と分家という形がどんどんと広がっていく。長男泰時(坂口健太郎)は本家を継ぎ三代執権に就き、次男朝時(ともとき)は名越にあった祖父時政の館を受け継ぎ名越流北条となり、三男重時は極楽寺流北条、四男有時は陸奥国伊具郡を領有し伊具流北条、五男で後に七代執権となる政村は政村流北条、六男実泰(さねやす)は六浦金沢郷を拠点として金沢流北条と言ったように。ちなみに、武士として最古の書庫金沢文庫を開いた実時は、実泰の息子だ。

同様に時房(瀬戸康史)の子朝直(ともなお)は、大仏流(おさらぎりゅう)北条を、先ほどの重時の子長時(後の六代執権)は赤橋流北条を興す。

北条は義時に時代に最も分派したことが系図からもわかるが、こうした本家、分家の間には初めさまざまな確執があった。詳細はいつか書こうと思うが、北条氏の場合、こうした確執は本家つまり嫡流家の勢力拡大という結果に帰結し、北条の本家(嫡流家)は『得宗(とくそう)』と呼ばれる特別な存在となる。義時の諡が『徳崇(とくそう)』だったことに因んでいると言われる。
やがて、同じ北条の血筋でも得宗家とそれ以外では雲泥の差が出てくる。平安時代の藤原氏もさまざまに分派し、やがて藤原北家の血筋だけが摂政関白になったことと同じだ。得宗家の力が大きくなればなるほど、その得宗家に仕える家人たちもまた特別視される。得宗家の家人たちは、『得宗被官(とくそうひかん)』と言われ、将軍と主従関係を結んだ御家人よりも力を持つようになっていく。
1285年に起こった霜月騒動がその好例だ。この事件は、当時最有力御家人だった安達泰盛(盛長(野添義弘)の曾孫)が内管領(うちかんれい:ないかんれい:得宗被官の最有力者)平頼綱とが対立し、頼綱の先制攻撃によって泰盛一族が滅ぼされてしまった事件。
(右:安達泰盛、中央:竹崎季長、右???:蒙古襲来絵詞:泰盛は恩賞奉行を勤めていた)
こうして鎌倉幕府は、将軍と主従関係を結んだ御家人が動かす本来の姿から、北条氏、それも嫡流である得宗家とその家人得宗被官たちが動かす組織へと変質していく。以前にも書いたように、『御家人の御家人による御家人のための政治』から『北条氏(それも得宗家)の得宗家による得宗家のための政治』となり、御家人たちの不満は、元寇による恩賞不足の不満と重なり、幕府を揺るがすほどになっていく。そして1333年、それをうまく利用した後醍醐天皇、護良親王らによって鎌倉幕府は滅亡へと追い込まれていく。