『鎌倉殿の13人』~後追いじゃない先走りコラム その101
第24回 変わらぬ人
今回は、頼朝(大泉洋)の遺言について
『承久記』という軍記物がある。題名通り、承久の乱について詳述した書。作者は不詳で、鎌倉時代中期に成立したとされる。この『承久記』に頼朝の遺言が残されている。次回第25回『天に望まれた者』で描かれるかどうか不明だが、もし描かれるとしたら、大泉洋が出演していた民放ドラマ『元彼の遺言状』がオーバーラップする方もいるかもしれない。遺言だけに笑。このドラマには、伊東祐親役の浅野和之も弁護士役として出演し、大泉演じる篠田とのコミカルな絡みのシーンがたくさんあった。ちなみに、綾瀬はるかと大泉洋のダブル主演のドラマ。

(6月20日が最終回)
閑話休題
慈光寺本(じこうじぼん※1)『承久記』に記された頼朝の遺言は、次の通り。いつものように私のチョー適当口語訳で笑。
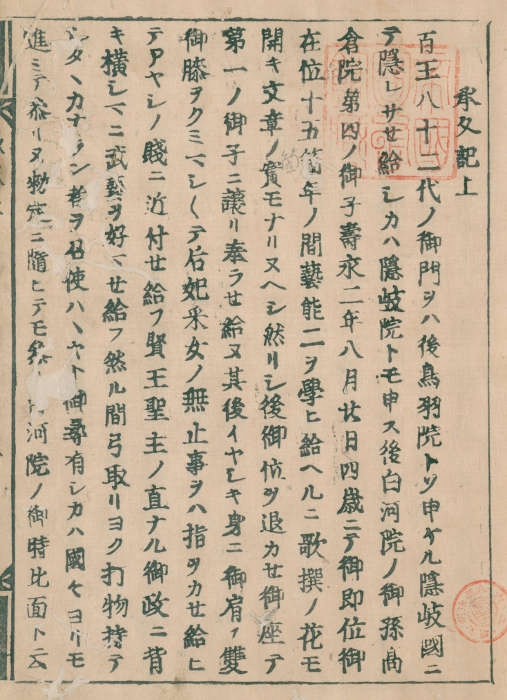
頼朝は半月もの間、病に臥し、心身ともに疲れ果て、命も尽きるだろうと思われた。病床にいた政子(小池栄子:原文では『孟光』※2)は頼朝に「半月も病に臥せって目も覚さない。これまで長年仲睦まじく暮らしてきたが、今私はあなたと同じように死に臨んでおります」と声をかけた。頼朝は頼家(金子大地)を呼び出し、「自分の命運はすでに尽きた。もし死んだ時には、千幡(せんまん:頼家の弟実朝の幼名:柿澤勇人)を愛おしく労りなさい。坂東の武士たちの悪い企み(讒言など?)を受け入れてはならない。畠山重忠(中川大志)を頼りにして、日本を守ってくれ。」と遺言を残した。
病で目も覚さないと言われた頼朝が、突然、頼家に遺言を残すというのは、ちょっとね・・・という感じだが、以上が頼朝の遺言とされるものだ。
その100で少し頼朝の死因について紹介したが、私自身は、乗馬中に高血圧からくる脳卒中や脳梗塞などによって意識を失い落馬。もしかしたら、落馬の衝撃でさらに脳にダメージを受けたかもしれないが、意識を取り戻すことなく病死したと思っている。当時の貴人の食事は、干物や塩漬けなど塩分たっぷりの保存食が多かった。また酒盛りも日常的であったことから、血圧が上がって当然の状況。武士は体力勝負なので、貴族と誓って米も玄米を好んで食べ(※3)、魚や肉なども食べていたが、頼朝は京への憧れもあったので、平和の訪れと共に、食事も徐々に貴人化したことも要因としてあったと推測している。また、当時の武士は3,000kcalほど摂取していたというデータもあるので、塩分取りすぎ、食べ過ぎ(現在一般男性の1日の摂取カロリーは2,300kcal)が様々な病の原因となったとも考えられる。

(鎌倉 御代川で現在提供されている武士祝い膳:お店の説明では、「鎌倉時代の武士の食事は、おかず類は味付けされておらず、玄米と肉・魚や,野菜に調味三種(塩・味噌・ひしお)で、自ら調味して食していたようです。このお膳は、中世鎌倉時代の武士祝いの膳を鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」など中世の文献資料を元に再現。」ということなので、しょっぱい物好きにとってはたまらないですね。醤・塩・味噌をジャンジャンと使うことも可能ですから・・・笑)
ある貴族の日記に頼朝は「飲水の病」つまり糖尿病が原因で死んだと書かれているが、塩分たっぷりの食事を摂ると、喉が渇いて水を飲むことになるのは、皆さんも経験していることだろう。そうした食生活が頼朝の体を少しずつ蝕んでいったと考えている。何の根拠もない推論ですが。
あぁ、日曜日が待ち遠しい!
※1 『承久記』には、『承久兵乱記』『承久軍物語』など異本が多い。その中でもここで紹
介した『慈光寺本承久記』は最も古く、様々な異本の元になったと言われているもの。
※2 『孟光』については、荻原さかえ氏が『慈光寺本承久記における政子呼称に関する一考
察』という論文の中で、「夫一途に、ただひたすら『内助の功』に徹した生き方をした
政子、この生き方に慈光寺本作者は、『孟光』という中国における理想的妻の名を美称
の代名詞として献上した。頼朝最期のことばの記述は、作者からの政子に対する賛辞と
読解する次第である。」と述べている。様々な文学作品で絶世の美女を中国のあの楊貴
妃に例えるのと同じように、中国の史書に出てくる孟光という女性と政子を重ね合わせ
た。さらに、荻原氏は「政子は『良妻』ではあった。しかし、『賢母』ではなかっ
た。」と論文を締めくくっている。
※3 当時の貴族たちは、玄米ではなく白米を多食したので『脚気』を患うことが多かったと
いう。栄養価の高い胚芽が取り除かれ、ビタミンB1が不足するのが原因だ。今も精米さ
れた米を食べることが多いが、副食で栄養を補うことができるので、バランス良く食事
をすれば問題はない。