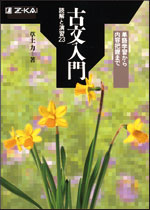「古文入門」を読んでいます。
https://www.zkai.co.jp/books/guide/id-1205/
近世編の2つ目は
本居宣長「玉勝間」
作品名はお初。
本居宣長の名前は教科書で見た。
幕末の志士たちへの影響も大きかった人。
玉勝間の名前は
「捨てるには惜しい物を籠に集めておく」という意味で付けられたそうです。
「玉勝間」の原本(写本?)Google booksから
この方がどんな方かをチェックしてみました。
1730年6月 伊勢国松坂(三重県松阪市)生まれ。江戸時代中期の人。
商家に生まれたけど、幼い頃から地理や歴史に興味を持ち、文学や医学の勉学に励み、家業は継がずに町医者となり、強い関心のある古典(古事記、源氏物語など)の研究をする、学者としての人生を歩んだ。
教科書で習った、江戸時代の「士農工商」のイメージでは推し量れない職業人生。
もしかしたら、こういう経歴の方は意外といたのかも?
玉勝間を読むにあたって、本居宣長を調べていたら、結構な沼にハマってしまいました![]()
それはともかく、この作品の「物まなぶともがら」の章。
よく聞こえたりと思ひて
心も止めぬことに、
思いの外なる
ひが心得の
多かるものなれば、
まづ
たやすきことを
幾度も返さひ考へ
問ひも明らめて、
よく得たらん後にこそ
難きふしをば
思ひ懸くべきわざなれ(一部)
ぶっちゃけこういうことかな。
「知ったかしたりマウンティングする学者が多いけど、そういう奴ほど基本が疎かだ。
そんな奴が背伸びして難解な事を人に聞こうなんて、キショいにもほどがある!!
難解な事を考えたいなら、簡単な事を何度も何度も繰り返して考え、疑問も明らかにして、それをよくよく理解してからだ。(一昨日来やがれ!!)」(全体)
今もこういう人いますよね。
自分が周りから抜きん出てやろうという欲と、お師匠様への承認欲求とを拗らせてる人。
宣長はこういう人をたくさん見てきたのでしょう。
そして彼自身が、
「簡単な事を何度も何度も繰り返して考え、疑問も明らかにして、それをよくよく理解」しながら
勉強や研究をして来た。
学ぶことに対して、
素直に
誠実に
真剣に
取り組んできた。
どうです?
古文の内容や文法は正直、まだまだ理解できてないけど、宣長は学者の鑑のような人ですね!
感激しました![]()
そして、この短い文は、今でも何かを学ぶにあたって、誰もが心得るべきことが綴られています。
古典はその長い年月の間に多くの人に読み継がれて風化することなく、伝えられて残っている。
それだけの価値があると聞いたことがあります。
まさに200年の時を経て今に伝えられるほどの文!
この文章を解説している動画があって、
大いに参考にさせてもらいました。
この先生は、古語の文法の説明もしてくれてるし、内容も詳しく話してくれてるので、とてもわかりやすかった。
宣長の世界はとても広くて深いようです。
この「玉勝間」のほかの文章でも
興味深いものがいくつかあり、宣長のお人柄を感じました。
書きたいことはほかにもあるので、この本を少し離れて、宣長のことをまた書いてみようと思います。